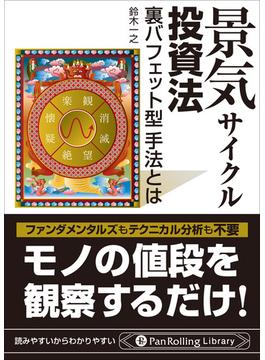- みんなの評価
 1件
1件
景気サイクル投資法 ──裏バフェット型手法とは
著者 鈴木一之
(ファンダメンタルズもテクニカル分析も不要)
モノの値段を観察するだけのシンプル手法!
「歴史は繰り返す」――
景気サイクル投資法(シクリカル投資法)は、景気循環・連動を活用した戦略で ある。これは、過去の事象は繰り返し起こるということ。好景気がいつまでも続 くことがないのと同様に、不況の闇が永遠に続くわけではない。投資において大 切なのは、その変化の転換ポイントをいかに敏感に感じ取って、「上昇」「下 落」を泳いでいくかである。シクリカル投資法では、ファンダメンダルズもテク ニカル分析も要しない。ただ単純に、モノの値段を追うだけで、景気の変化を読 み取るのだ。重要なのは、モノの値段。シ
ンプルに、株価を見る前にモノの値段 を見ていこう!
著者コメント
シクリカル投資法はとても、地味な手法です。
歴史は繰り返す――
それは、「世の中に新しいことは何も無い」というベースからスタートしていま す。本書でも軽く触れているように、2大投資法であるグロース(成長)株ほど の“ドラマチックな展開”もなければ、バリュー(割安)株のような“自分だけ が見出した光”も、そこには存在しません。 あるのはただ、経済学的な景気循環の理屈をもとにモノの値段をとおして景気を 見る―ひいては、機械的に株式売買を行うという一見すると面白みにかける投資 行動だけ。 それでも、どのセクター(業種群)よりも先行性を発揮するシクリカルセクター をもって、上昇局面、下落局面の転換を見抜きいち早く対応していくことによ り、経済のダイナミズムを天底含めて体感できる喜びがあるのです。
シクリカル投資法は、景気の流れを待つだけの手法と思われるかもしれません。 しかし、信用取引の空売りや、つなぎ売り、さらに裁定取引を使えば、より強力 な戦略を取ることができるでしょう。本書では、それらの活用法を具体的事例で 検証しています。 好景気も不景気もチャンスに変える「シクリカル投資法」で、利益が生まれる局 面と損失を出しやすい局面を知り、損小利大のトレードを目指してください。
目次
はじめに
第1章 シクリカル投資法・理論編
(1)クリカル投資法とは?
景気を相手にする/景気は循環する/シクリカル株とは/バフェットの投資対象/アンチ・バフェット型投資/シクリカルセクターの分類/セクターで考えるクセ/個人投資家に見る銘柄スクリーニング/「~関連銘柄」が儲からない理由/シクリカル投資法の有効性
(2)シクリカルセクターの収益構造
景気転換の兆し/収益は「売上高=数量×単価」である/不景気からの反転/景気の底入れは事後的に分かる/景気拡大は「単価」の上昇/コストも「数量×単価」で追いかけてくる/コストの伸びが売上高の伸びを上回りだす/価格の変化に存在する二面性/売上高が変化する8つの局面
(3)株式市場の2大原則
株式投資は難しい/景気サイクルが見える期間/株式市場に存在する大原則/2大原則で見る株価と景気のサイクル/4つの局面で見る売買のタイミング/IIIとIVの見極めが運命を分ける/投資家の死命を決するポイント/シクリカル銘柄の変動特性/売上高の変化イコール株価の上昇/価格動向の注意点/小さく取ることを繰り返す/大きく狙うと次の下落でほぼやられる/相場予測を避け観察に徹する
第2章 シクリカル投資法・実践編
(1)価格は何を見るべきか
対象となる価格/価格とは何か/ニッケルの価格/値段の位置づけ/株式投資での「一村一品運動」/代替品の景気/景気の代用品と株価の連動性/現材料の価格/価格データの収集/情報収集のコツと活用/完璧な対応関係を求めない
(2)何をもって価格の上昇・下落とみなすか?
投資家の決定事項/「買い」のポイント/ニッケル市況で見る買いのポイント/順張りと逆張り/ニッケル市況と株式市場/底値で買うことの意味/目指す利幅は小さめ/トレイリングストップ/手仕舞いのポイント/年間アノマリー/シクリカル実践レポート (3)シクリカル投資法の長所と短所
シクリカル投資法の特徴/2大投資法(グロース(成長)株/バリュー(割安)株)/シクリカル投資法との比較
(4)信用取引を活用する
空売りに適した局面/信用取引の活用(ヘッジ〔つなぎ売り〕/レバレッジ/アービトラージ〔ペアトレード〕)
第3章 ケーススタディ
BRICsの台頭(鉄鋼/非鉄/海運)
あとがき
景気サイクル投資法 ──裏バフェット型手法とは
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
景気サイクル投資法 裏バフェット型手法とは
2008/11/23 12:19
100年に一度のことは、10年に一度、起こる。
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ヂャリや - この投稿者のレビュー一覧を見る
感覚的に10年に一度のことは、実際は1年に一度起こる。
”感覚の現在性”が人をそう感じさせる。
どんなことも、今がとても重要なことに思えるのは、それが今、現在の感覚として認識されざるをえないからである。
大きく下がって、さらに下げる途中で、ビックプレーヤーの退場が明らかになる。バーゲン価格と勘違いした個人が、売りの買戻しを見て反転と思い込み、買いにはいる。個人の集合体では大して押上げ圧力にならず、機転の利くものから、売り逃げる。さらに下がって、前回の下値を下回る。さらに投げが加速した頃、書店に個人向けに空売り本が並び、初心者が空売りをしだした頃、相場が反転する。これが、私の見るサイクルだが、今回もそうなるかどうかはわからない。
しかし、予測はしないに越したことはない。
著者のいうとおり「相場予測を避けて、相場の観測に徹する」のが投資のコツだからだ。
「予測をしてしまうと、その後の自分の心と行動を縛ってしまい」「自尊心がハズレを認めず、正しい現実認識が先送りされてしまう」こうなると”感覚の現在性”までマヒしてしまうと読み解くことができ、導き出される行く末は、幻想と現実のギャップに苦しんだ挙句、強制退場というありがちなシナリオだ。
このシナリオを避ける投資法の一つが本書の「景気サイクル投資法」だ。
この手法の大前提として「株価は景気の鏡である」「株価は景気に先行する」という二つの原則が紹介されている。今後もこの原則が成り立つのかどうか、私には知る由もないが、今まではそうであったらしい。「人間の行動が今までと全く異なるこということはないので、歴史は繰り返す」というのが著者の主張です。
この意味で、初心者にとっては基礎の習得と歴史の勉強になる。また中級者にとっては、暴落時のコーヒーブレイク。上級者にとっては、手法の再確認として、本書は最適だ。
著者のいう「景気敏感株と先行指標」はたして今回もそうなるのか、じっくり観察したい。
あるときは「グロース株」またあるときは「バリュー株」ととられる景気敏感セクターの謎もわかりやすく解説されているので大変参考になる。
面白かったのは「アマノリー」の説明。よく言われる年間循環を整理してくれているのがありがたい。実際は、それで収益を狙うのは”甘いなりー”だが。
もう一つ「将来の予測を用いず、昨日まで上がっていて今日下がったら、昨日と今日とで世の中の流れが変わっただけと判断する。」さらに「”今日は非鉄の価格が値上がりした、だから景気がいいんだ”、あくる日は”値下がりした、だから景気は悪いんだ”というように、日々、景気の基調が変わるということは、現実にはありえないが、そのように”みなす”のです。」にいたっては、チョット、メチャクチャな感じもするが、感情を入れない判断手法の考え方としてはかなり有効だなと感心した。
本書は2008年10月に完成している。まさにライブと理論の検証にはもってこいのタイミングだ。一年に一度のことは一ヶ月に一度起こるという私自身の仮説の検証も兼ねながら、再読を決意させられた一冊でした。