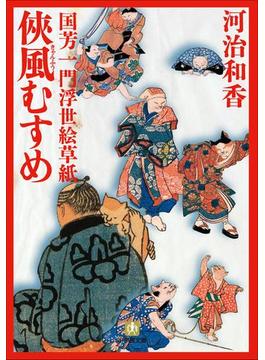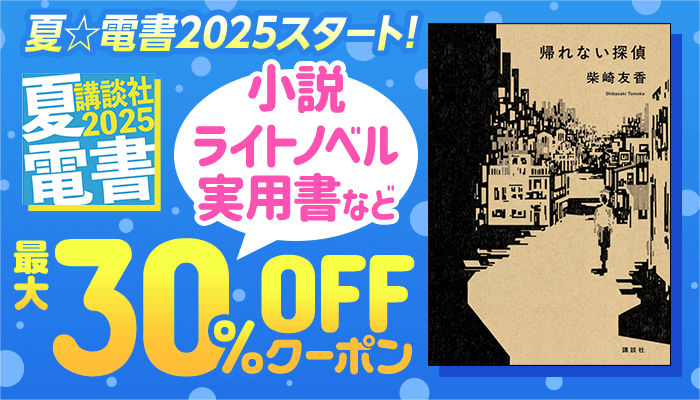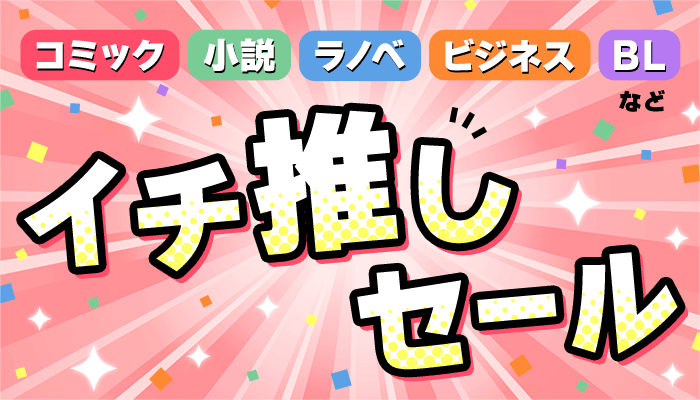- みんなの評価
 4件
4件
国芳一門浮世絵草紙
浮世絵師歌川国芳と娘登鯉をめぐる人間模様
『笹色の紅』で評論家の絶賛を浴びた新鋭作家の、ほのぼのおかしくて、ちょっとせつない書き下ろしシリーズ第1作。 天保の改革で、贅沢なものが次々と禁止になるさなか、見事な戯画で大人気を博した歌川国芳。ついには国芳も奉行所に呼び出され、顔見知りらしかった遠山の金さんと全面対決へ。さて、その顛末はいかなることに? 国芳と妙ちきりんな弟子たちとが織りなす浮世模様を、国芳の娘の絵師・登鯉の目から格調高く描く。
ニッポンチ! 国芳一門明治浮世絵草紙
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
浮世袋
2010/12/02 14:39
藤の香の浮世袋
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:saihikarunogo - この投稿者のレビュー一覧を見る
登鯉が、九紋龍史進を演じる坂東しうかのために「四紋龍」の絵を背中に描く話から始まり、登鯉が、坂東しうかから藤の香の浮世袋を貰って一緒に藤の花を見に行く約束をしたが、彼が亡くなったのでひとりで見に行く話で終わる。
それらの話の間に、登鯉は結核にかかったことがわかり、高野長英が潜伏先で役人に踏み込まれて連行される途中で不慮の死を遂げ、背中に鯉の彫りもののある夜鷹が評判になって、国芳と「御奉行」が探し回る。
この『国芳一門浮世絵草紙』シリーズは、登鯉が「御奉行」に送られて賭場から帰って来る場面から始まった。そして、この『浮世袋』でも、「御奉行」は、いつかのように、登鯉を賭場から国芳の家に送ってくれる。登鯉は「御奉行」に結核になったと打ち明け、国芳が聞けば大泣きするから内緒に、と言う。すると横笛を取り出して奏で始めた「御奉行」……
大泣きするかわりだったのかしら……と、私は思う。
登鯉は、聞き出したいことがあるような、聞きたくないような気がしたけれど、「御奉行」とお互いに、何も言わない。内緒にする約束で指きりげんまんするとき、「御奉行」のさしだした小指は震えていた。
国芳のもとには、幾次郎、米次郎、小円太という、三人の少年が弟子入りした。この小説には明治以後のことは書かれていないけど、幾次郎は落合芳幾に、米次郎は月岡芳年に、小円太は三遊亭円朝になるのですね……すごいね、みんな、お化けの絵とか話とかで有名になる人ばっかり。
国芳一門の年長の弟子たちが見ている「辻君細見」で、五十七才の、背中に鯉の彫りものがある夜鷹が、「上」とされていると聞き、それまで夜鷹の絵を描いたことのない国芳が奪い取って食い入るように見つめる。
おりしも、不忍池の鯉を取って食おうとした男たちが、背中に鯉の彫りものがある夜鷹に頼まれて鯉を逃がしたものの、傷を負った鯉は死んでしまい、そのたたりで彼らが死んだ、という怪談が広まっていた。
そして、国芳一家一門皆が、たたりで死んだ連中と同じ症状で病の床に!からだの節々が痛い、頭痛と鼻水が止まらない……って、これ、インフルエンザじゃん。
国芳たちも、これはたたりじゃなくて、流行病(はやりやまい)だと気づいた。国芳から先に治っていった。
ある夜、お使いに出た米次郎と小円太が、鯉の彫りもののある夜鷹に会ったと話した。国芳は飛び出していき、登鯉も追いかけていき、探し回ったけれど、会えなかった。登鯉に向かって、そして暗闇に向かって、国芳は、昔の話をした。
翌朝、鯉の彫りものがある夜鷹の死体が川で見つかった。死体はそのまま流された。
なんて寂しい話だろう。登鯉も、国芳も、「御奉行」も、そんな寂しいことにしたくなかったのに。どうしてそんな寂しい最期にならなくちゃならないの。いくら潔いったって、寂しすぎるよ。
浦賀に黒船がやってきた。この小説のなかにペリーの名は出てこないけれど、ペリーの艦隊である。押し寄せる見物人を乗せて漁船が出払ってしまって、魚河岸が困った。ここで新場の若親分の小安が大活躍、かっこいい。
登鯉は、小安に、国芳は実の父親ではなく、おとっつぁんが一番好きだから、一生、嫁には行かない、と話す。そして、病気を悟られないように急いで離れる。ひとりで立ち向かっていけるように、孤独に負けないように、と願いながら。
彼女は、背中に彫りもののある夜鷹のように潔く寂しく、死ぬつもりなんだろうか?
国芳は「七浦大漁繁昌之図」という、三枚続きの大鯨の絵を描いた。鯨に群がる捕鯨船の小舟を、娘たちが見物しているようすが、まるで黒船見物のように見える絵であった。
> 日本近海に黒船という異国の船が出没するようになって、それを人々は迷い込んだ鯨のような呑気さで見物に出かけたが、なにかがねじれていくような不安を……国芳の絵を求める人々は感じはじめていたのかもしれない。
黒船が去った後、国芳は「七つ伊呂波東都不二尽」という続き物の役者絵を描き、登鯉に、富士の絵を描けと言った。そのうちの一枚の「ろ」の絵が、この『浮世袋』の最後の章の『兵端』の扉に載っている。それも含めて「七つ伊呂波東都不二尽」は、["立命館大学の浮世絵検索システム","http://www.dh-jac.net/db/arcnishikie/default.htm
"]で見ることができる。検索画面で所蔵機関を「国会図書館」とし、絵師を「国芳、登里女」とするとヒットする。画題は、「七ツ」「七津」などいろいろなので、記入しないほうがいい。
当代の人気役者、九代目団十郎が亡くなり、続いて、坂東しうかも亡くなった。登鯉の描いた役者の死絵(しにえ)は評判が良かった。登鯉は絵ばかり描くようになる。その瞬間はつらいことを忘れられる。ふと、しうかとの約束を思い出して、ひとりで藤の花を見に行った。探しに来た小安が、ずっとおとっつぁんのそばで絵を描いていていいから、と言ってくれた。国芳たちも探しに来た。皆で楽しく騒ぎながら帰っていく。
ひとりじゃないよ、登鯉。寂しくなんかなるもんか。
鬼振袖
2010/11/30 11:53
振袖よりも半纏を
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:saihikarunogo - この投稿者のレビュー一覧を見る
本人は娘盛りのつもりなのに、まわりの目は厳しくなってきた、きょうこのごろ、今一度、昔の恋の名残りに、ほんとうの結末が訪れる。
登鯉が初めて好きになったひとは、小さな彼女を舟に乗せて、いい声で唄いながら櫓を漕いだ。登鯉は、男の背中の菊慈童に胸をときめかせた。十九になった登鯉が久しぶりに会ったときもまた、みごとな菊慈童のほりものを見せて、橋の欄干にもたれていた。その菊慈童を斬り裂くようにして死んでいった彼は、手拭いと、一枚の絵を残してくれた。
> 芳雪の描いた深川八幡の洗い髪の女は、無垢な可愛い顔で、夢見るようにいつまでも黒髪を風になびかせている。
> 開け放たれた楼の窓からは、咽ぶような櫓の音が聞こえていた。
火事見物に行くたびに、誰かに会っている。葛飾北斎の娘お栄は、病が重くなって床についた北斎の世話を抜け出して来ていた。ひょっとしたら、昔、いい仲だった渓斎英泉のことを心配していたのかもしれない、と、登鯉は思う。渓斎英泉はこの五ヶ月の間に四回も焼け出されたという話である。北斎の死後、お栄は登鯉に櫛と笄をくれて、江戸の人々の前から姿を消した。
また火事を見に行ったときに、乃げんに会う。邪慳に腕を振り払われる。国芳も弟子達もみんな、乃げんが恩赦で戻ってきた事を隠していたのだ。三宅島から妻と娘が後を追ってくることを知っていて、乃げんと体を重ねた登鯉。余計に寂しくなって、新場の小安と喧嘩してしまう。乃げんの妻は、たまたま、目の前で、小安が登鯉の名を呼ぶのを聞いて、乃げんが娘に同じ名を付けたことを悟る。登鯉も同時に。
登鯉は、乃げんのことを忘れることにした。新場の小安は背中に彫りものを入れるため、登鯉に、鯉の滝登りの絵を描いてくれと頼んだ。ふたりの心は、喧嘩をしながらも、徐々に、確かに、一つになっていっているようだが……
国芳一門のために梅屋鶴寿が揃いの芳桐印のある刺子半纏を誂えてくれた。裏にはひとりひとり、別の絵を描いた。国芳は地獄変相図である。火事を見物に行った帰りに、国芳が登鯉に着せかけてくれた。登鯉には振袖が誂えられたが、登鯉は、自分も刺子半纏がほしかった。国芳が留守のとき、登鯉はそっと、半纏を羽織ってみる。
振袖よりも、一門の印の付いた半纏が着たい。できれば、おとっつぁんと同じ絵の。結局、それが、登鯉の心なのだ。
国芳は、弟子や娘の個性を尊重し、彫師や刷師にも細かい注文をつけずに、彼らの腕に任せる。なかなか、彫師刷師のなまえは残らないが、河治和香のこの小説は、浮世絵が、絵師・彫師・刷師の三者によって創り上げられる作品であることを、個性豊かな人々の姿を通して教えてくれる。
浮世絵師は提灯や凧や菓子袋やおもちゃ絵など、何でも描いて稼いだ。尾張藩では二代続けて、将軍家から押し付けられた養子が藩主となっては、夭折してきた。十歳で、誰にも望まれない三人目の押し付け養子とされた藩主は、夜、寝る前に、そっと、おもちゃ絵で遊ぶのだけが、唯一の息抜きだった。彼は亡くなる前の年、お忍びで江戸の町に出て迷子になって国芳一家に紛れ込んで、「市芳」の名を貰った。
> 「国芳、今日(こんにち)は、楽しかった。恐らくもう生きては会わぬ。達者で暮らせ」
後で市芳が亡くなったときに、持っていたおもちゃ絵が全部一緒に棺に入れられたと聞いて、国芳たちがみんな泣くけれど、読んでいる私も泣けてしまった。
国芳のまわりを、怪しい者共がうろつく。泥棒?奉行所の隠密?「御奉行」は、市中見回りの途中、トイレを借りに来て、痔で馬に乗るのがつらいとか言うし、水野忠邦の後に老中首座になった阿部正弘は近眼だとか目先のことで手一杯で先のことまで見るゆとりがないとか言うし……それをもとに、国芳が、「きたいな名医 難病療治」という絵を出すと、いろいろ深読みする人々がいたために、国芳は、鍋島家の御隠居から呼び出しを受け、代わりに登鯉が行かされて、おとっつぁんの笠の土台が飛ばないように注意しろとか言われてくるし、でも実は……愉快な大団円!
登鯉も含め、国芳と弟子達一同が昼夜兼行で描きあげた「誠忠義士伝」が大売れに売れた。すごいお金がもうかって、国芳は、登鯉のお嫁入りの支度金にしようという。それじゃそのお金はもらった、と横取りした登鯉は、きょうは自分のおごりでみんなを吉原に連れて行くと叫んで、国芳の半纏も横取りして、颯爽と羽織って飛び出した。やっぱり、登鯉は、今が娘盛りだ!
あだ惚れ
2010/11/28 14:42
「だいたい二十歳前には、ふん捕まって獄門さ」
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:saihikarunogo - この投稿者のレビュー一覧を見る
> 「狙った侍の懐からサイフを掴んだとたん、バラリズーン……と、一瞬のうちに首と胴が宙で生き別れになっちまった」
『国芳一門浮世絵草紙』の第一作『侠風娘』は、国芳の弟子の周三郎少年が河原で拾ってきた生首を皆で写生する話から始まったが、第二作『あだ惚れ』もまた、人が首を切られる話が最初に来る。といっても、冒頭は、国芳や娘の登鯉が仲良くしていた髑髏太夫が死んだので、その供養に登鯉が「髑髏太夫の極楽めぐり」という絵を描くことになるのだ。その絵を注文したのは、髑髏太夫と馴染みの客で、そして、江戸三大スリのひとり、トンボの春を「バラリズーン……と」やっつけてしまったのも、その客なのだった。
登鯉は幼いときから国芳の絵を手伝っていて、今では、登鯉の描く春画がよく売れている。でも、それは国芳の娘でしかも十七歳という若さだという付加価値があって、もてはやされているのである。女が絵師として一本立ちするのは男以上にむずかしい。それは、国芳の弟子たちのなかで一番優れているとされる芳玉こと、お玉の場合も、また、国芳が私淑している葛飾北斎の娘、お栄であってさえも、同様であった。
お玉には、「天狗にさらわれた」という過去があった。最近になって、幼い女の子が次々とさらわれる事件が起こり、お玉の天狗体験の瑕が呼び覚まされる。お玉は登鯉に、ずっと誰にも話せなかった天狗との暮らしを打ち明けた。その天狗に、偶然、何年かぶりに会って、話しかけると、彼は、お玉のことを知らない、という。お玉は怒った。それで、天狗の化けの皮がはがれた。
天狗が捕えられる前に、国芳の弟子のひとりで、ちょっとぼんやりしていて子供と同じ様に遊んでしまう芳藤が、悪者にまちがえられて町の人たちになぐられたのがかわいそうだった。そして、連続少女誘拐殺人事件の犯人は、天狗でも、もちろん芳藤でもない、別の男だった。
現代にもよくある犯罪で、つらい話だ。少女たちもかわいそうだし、ちょっとぼんやりした、こども好きの若い男が疑われてしまうのも、よくある話で、これも悲しい。よく似た話が、宇江佐真理の『甘露梅』にもある。
葛飾北斎の娘は、火事が好きで、「夜中といへども十町二十町の場へ見物に行く事しばしば」で、登鯉とふたり、火事を眺めながら、しみじみと話をする。
> 「女ひとり老いさらばえてゆくのは、世間の人が思うほど寂しくはないけどね」
> 「自分のことばかり考えて生きていくのは、気楽なようで、結構めんどうなものサ」
登鯉の描く春画を大名たちへの贈答品にしていた、あの「御奉行」が、登鯉に、田辺定輔との縁談を勧める。定輔は、いずれ、同じ年頃の矢田堀景蔵などとともに、国を背負って立つ男だ、という。
来る時には同時に来るもので、新肴場の御隠居からも若親分小安との縁談を勧められるし、登鯉は登鯉で、なんと、江戸三大スリのひとり、若衆の勘太といい仲になってしまう。
スリはやめとけ、だいたい二十歳前にはふん捕まって獄門だ、と「御奉行」がいう。でも、登鯉は、定輔と結婚すると、絵をやめなければいけない、ということが、気にかかっている。国芳は、新場の小安との縁談に乗り気でいる。そして、定輔は、登鯉に長い手紙を書いてきた。難しい漢字が多くて読めない手紙を、登鯉は、「御奉行」に読んで貰った。
優しいけれど、きっぱりと断りの手紙を書いてきた定輔。天下国家のために身を捧げるつもりで、甲府に行く、という。
定輔が甲府に発った日、国芳の家の庭に、ひとかかえもあるほどの、満開の桜の大枝が置いてあった。
この桜の大枝には、登鯉と同様、私も、じいん、ときた。
田辺定輔とは、あの、明治初期に活躍した外交官田辺太一だ、ということは作品中には述べられていない。
時代は、天保十四年から十五年にかけてで、まだペリーは来ていないが、西洋諸国の船が日本に来て開国を求めたり、水野忠邦が老中を罷免されたり、また返り咲いて、報復人事で鳥居耀蔵を飛ばしたり、その合間に、高野長英が脱獄したりしている。
高野長英が、いろいろな人と人との関わりの縁から、国芳一家に飛び込んでくる。居候の癖にいばっていて酒飲みで……でも、根は、人見知りで、悪い奴ではないらしい。国芳と、登鯉と、そして、あの「御奉行」が、高野長英を、別の場所に逃がすことになる。
屋形船で行く四人。どこまでも付いてくる、怪しい船。どっちが怪しいか、という気もするが……
あれは自分を狙っているんだ、という、「御奉行」。船が目的地に着いたとき、高野長英たちを先に行かせて、ひとりで敵に立ち向かう。
> 「てめぇら人違いもてぇげぇにしやがれ! 首と別れの道楽に、腕からなり、足からなり、斬るとも突くとも勝手にするがいいや!」
そんな、ひとりでおもしろいことするなよ、とばかりに、国芳も加勢し、挙句の果てに、高野長英までが……
この小説は、ほとんど実在の人物ばかりが登場して、絵師も学者も役人も、それぞれ、皆が、史料を忠実に再現しつつも、しかも作者の想像力を十二分にふくらませて、生き生き、有り有り、手に触れ、匂いをかぐように、表わされている。そしてまた、少女たち、女たちの、悲しくて、なお、したたかでたくましい日々を描いて、笑いも涙も、海の水のように尽きることがない。何よりも文章が完璧に美しい。悲しいのに、明るくて、楽しいのに、切ない。登鯉の恋模様は、まだまだ、続くのか?