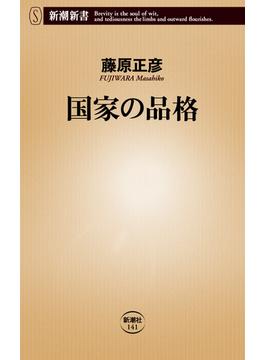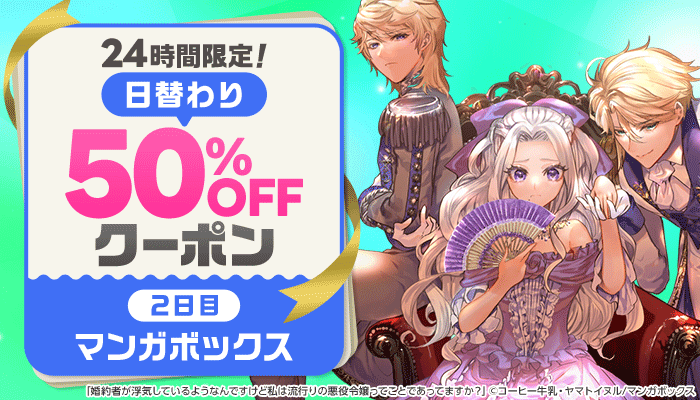- みんなの評価
 21件
21件
国家の品格
著者 藤原正彦
「品格」で流行語大賞も受賞した大ベストセラー。虫の音が美しいと思う心、説明無用「駄目なものは駄目」、「卑怯」はいけない――日本人は生まれながらにして善徳や品性を持っている。国際化という名のアメリカ化に踊らされてきた日本人は、この誇るべき「国柄」を長らく忘れてきてしまった。いま日本に必要なのは何か? それは論理よりも情緒、英語よりも国語、民主主義よりも武士道精神であり、「国家の品格」を取り戻すことである! すべての日本人に誇りと自信を与える画期的日本論。
国家の品格
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
国家の品格
2006/03/12 23:51
亡国の民に語りかける数学者の声
29人中、28人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:佐伯洋一 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「論理より情緒」。情緒を普段から優先しているような人がそれを言っても誰も信用しない。しかし、著者は数学者藤原正彦氏。この世で最も論理を探求している職業人である。我々凡人が、いかに騒ごうと、論理では数学の博士号を取得するような人には万が一にも勝てはしない。
世の中全て論理で割り切れば、市場原理主義は徹底され、累進課税もなくなり、悪平等が跋扈することになる。そうした形式的平等は既に近代法学によって否定され今に至っている。著者は、市場原理主義を卑怯だと断ずるが、既にそのことは平等概念の変質とともに市場に了承されていることである。現代日本の法律は実質的平等を定めた憲法14条というフィルターを通すことにより、累進課税を初め多くの国民は利益を得ているのである。そのことからすれば、著者の「卑怯」という指摘は、まさにその常識を追認したに過ぎず、なんら新鮮ではない。しかし、その常識を多くの人は忘れていたということだろう。
著者さらに武士道精神の復活を主張する。私は「葉隠」や「武士道」といった大名著を精読しているうち、日本という国家の中核は武士道にあると確信するようになった。日本的なものを追いかけていくと、必ず武士道という倫理体系に衝突するのである。武士道が体系的に発展したのは江戸以降だが、なぜそれをなし得たかといえば、「鎖国」の影響であろう。もちろん、そのベースは聖徳太子の中華圏離脱宣言にまで遡るが、そうしてわが国は大中華圏から距離を置いた。そこで外国から断絶した文明が誕生した。それこそまさに武士道である。
かつて日露戦争において、日本は世界で始めて有色人として陸軍大国ロシアを粉砕した。ロシアは南下政策として日本を準植民地かする腹積もりであった。まさにロシアは骨肉まで怨むべき敵であった。しかし、日本は日本兵よりもまずロシア兵戦没者慰霊塔を真っ先に案子山に立てた。ロシア皇帝ニコライ2世は泣きに泣いたという。まさに武士道が成せる業である。
その武士道を「韓国が起源」として世界中にネットを通じて英語で喧伝している韓国は日本の破壊者である。事態は相当逼迫しており、オリンピックには「剣道」ではなく「クムド」と登録される可能性が高い。そのとき、日本は滅びを加速させるだろう。
太平洋戦争は情緒、論理とは全く無関係である。ハルノートを読んで欲しい。あれは日本に死ねといっているのと等しい(パル判事はモナコでも戦う以外ないと断言している)。そこには既に情緒も論理もない。論理的には死ぬならば戦う。戦う以上勝たねば植民地。ならば勝つために最善の手を打つというのが論理である。大体、軍部では米内、山本はおろか東条英機も戦争反対であり、陛下も反対であられた。戦争とは基本的に負けたほうが悪になる。もしアメリカがまけたら、日本に原爆を面白半分に2個も落としたトルーマンは最大の戦犯だろう。でもトルーマンは英雄なのである。その理由は、戦争に勝ったからという以外に何もない。
国家とは日本人みんなで作った共同の家である。家を愛するのは当然のことなのに、日本ではそれが出来ない。日教組や社会の隅々にまで入り込んだ共産分子に朝鮮総連の影響で、学校では君が代を歌うことも出ない。これが異常でなくてなんなのだ。
日教組や共産党、社民、在日朝鮮人や中韓はこういう日本が強力になるだろう本が大嫌いである。そういう一部のダボが狂ったように本書を中傷している。しかし、やはり良識ある国民の目は騙せぬもの。88万部という売れっぷりは「どうもなにか大切なものが手中から消えていく感じがする」と嗅ぎ取った証拠であり、まだ日本は生きている証左であろう。
国家の品格
2006/04/02 17:34
新書という形態の功罪
21人中、21人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:そら - この投稿者のレビュー一覧を見る
藤原正彦さんは今とても売れているらしい。
歯に衣着せぬ発言で、その言動に快哉!を叫ぶ人も多いだろう。
一方、短時間の講演や薄い新書などでは、その論点も要約を述べるにとどまるため、誤読されたり、細部の説明不足をあげつらわれる嫌いもあるようだ。
現在、新書という形態が隆盛だそうだ。
内容も含め軽い、低価格ということから、手に取りやすいということだろう。
しかし、新書には自ずと限界があり、重いテーマを論ずるには紙数が不足である。
読書人口が減り、より軽い書物が求められる昨今、出版社が「新書」という形態に注目する理由はよく分かる。
「国家の品格」は、「文化防衛」という国家にとって、また国民にとって、存続をかけた重大なテーマについて述べられた本である(と、言い切ってしまってよいと思う)。
(従って、実は「新書」という形態に相応しくない重い内容を持っている。しかし「新書」であることで新たな読書人口を開拓できるというメリットもあるが)
また近代国家の成立にかかわる「自由、平等、国民主権」という理念が、封建的権威を覆すために創作されたフィクションであることを再確認させる。
今日の世界史の教科書の内容については全く疎いのだけれど、五十代の私が高校で学んだ世界史は、実は西洋史であった。
その「蒙を啓く」ために、この書物は大いに有効であると思う。
「国家の品格」を読んでも、マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を読んだ人は少ないだろう。
非常に薄い文庫本でも、巻末に膨大な原註を含む社会科学者の気の遠くなるような仕事を逐語的に読む余裕のある学生(これは皮肉)、或は意欲のある学生がどれくらいいるだろうか(だからこそ、新書というスタイルで易しく解説してくれる人が必要なのだろう。その実、新書では批判的に読むことは不可能だし、著者は必然的にアジテーターにならざるを得ないのではないだろうか。それがこの本に対する毀誉褒貶をもたらしているのだろう)。
プロテスタンティズム、それも特にカルヴィニズムが市場経済を促進させた。
カルヴィニズムに限らず、遡ってキリスト教が出現した当時のローマ及びヨーロッパ社会のひずみについて考察することなしに、宗教・思想は理解できない。
革命的思想が一つの仕事をし終えた後で、その「虚構」を冷静に見つめ、著者の言葉で言えば「惻隠」の情という不確かだけれど強固な感情に立ち戻ってみることが今必要なのだろう。
因みに現在50代の人間が学生時代に読む社会科学者と言えば、政治の季節であったことの影響として文科系理数系を問わずまず「マルクス」であったのではないだろうか。
放置すれば残酷さをむき出しにする市場原理は、人間性の麗しい側面を破壊するだろう。
マルクスによる革命思想が潰えた今、資本主義は覆すものではなく、制御すべきものとして、理性的に付き合ってゆくべき対象となった(この本には現政権の政策に対しても批判的である)。
エレガントな論理では割り切れないもの、時代を通じてあまり変わらない人間感情の機微について、それを最も抽象的な数学を研究する人によって「諭される」と、えらく説得力があるものである。
国家の品格
2006/03/19 16:36
見つめなおしてみましょう。---「国家の品格」書評
17人中、17人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:hiro-tom - この投稿者のレビュー一覧を見る
ここまで断言口調で説明されれば気持ちよい。著者の勢いは、
数学者の論理というよりは、どちらかというと体育会系ののり、
といったほうが近いような気がしながら読んでいたが、読後は、実は難しい内容を論理的に説明しようとしていたんだな
と感じ方が変わってきた。
本書の一番のメッセージは「論理は万能ではない」ということ
だと思う。特にビジネスの世界では、この論理が幅を利かせる
ことが多く、グローバリゼーションという波がアメリカから
流れてくるような業界は特にこの「論理」一辺倒である。
さらに、最近では、ビジネスだけでなく、人と人との会話・
つながりの基本的生活部分にまでこの論理「だけ」が
はびこってきており、大切な日本特有の「情緒」と「形」が
失われている、と指摘している。
さらにこれだけに留まらず、「武士道」の復活を提案。
日本人の美学としてだけでなく、これからの日本人生き残り
の武器である、という。愛国主義という単純なものでなく、
人間として備えていたいものをもう一度思い出そう、
というものかもしれない。
もうひとつは、「国」というものを再認識させようと、
必死である。国際人という民族は存在しない、出身地を誇り、
自国を誇れない人間がどうして国際人になれよう、と英語だけ
しゃべれ自国について語れない日本人が海外で幅を利かせる
ことを憂いている。自分の立っている場所を誇り、自分の
場所を愛し、説明できない人間は、確かに尊敬できないだろう。
それは、外国人が日本人を見るときも同じだろう。
これまで日本人とは他民族と比べてどうなのか、
日本人は近年どう変わってきたのか、それは良いことなのか、
悪いことなのか、見つめなおしてみよう、という方にお勧め
します。