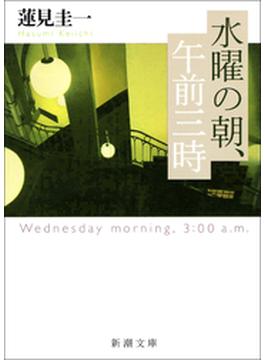- みんなの評価
 3件
3件
水曜の朝、午前三時
著者 蓮見圭一 (著)
児玉清氏絶賛のベストセラー。45歳の若さで逝った翻訳家で詩人の四条直美が、娘のために遺した4巻のテープ。そこに語られていたのは、大阪万博のホステスとして働いていた23歳の直美と、外交官としての将来を嘱望される理想の恋人・臼井礼との燃えるような恋物語だった。「もし、あのとき、あの人との人生を選んでいたら……」。失われたものはあまりにも大きい。愛のせつなさと歓びが心にしみるラブストーリー。
水曜の朝、午前三時
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
水曜の朝、午前三時
2006/10/15 02:55
書いてある内容は、かなり濃いものですが、文章自体は、淡々としているというか、凛としているというか。
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:T.O. - この投稿者のレビュー一覧を見る
Bk1の書評で興味を引かれて手にしました。45歳で脳腫瘍で亡くなった女性が、自分の死ぬ前に一人娘にテープを遺し、そのテープを起こしたもの、というお話です。ヒロインの女性は、自分がかつてとても好きだった人がいたこと、でも、ある事情でその人とは結婚できなかったこと、そんなことを死ぬ前に娘にテープに吹き込んで遺したというものです。
その女性は、1970年に万博のコンパニオンを勤め、そこで件の彼と出逢ったという設定です。1970年という時代、まだ今よりはずっとコンサーバティヴな時代で、世間の目とか、そんなものもあった時代のお話で、これは「オールド・ファッションド・ラブソング」「古風で床しい恋愛小説」だという触れ込みでした。
読み終えて、なかなか心に残る作品でした。設定が1970年ということですから、話はたしかに古風といえば古風です。1970年に23歳ということは、私よりは少し上の世代の話です。でも、この時代の20歳代の女の人の気持ちは、分かるな、と思って読みました。とにかく早くしかるべき人と結婚するように、という周りからの無言の圧力とか、それに抗って、何かをしたいという気持ちとか、それでいて、実はさほどのことも出来ないという現実とか。ヒロインはとても有能で頭の切れる女性ということですから、周囲の状況がよく見えて、自分にそれなりの自信もあって、それだけに、そのギャップも人一倍強く感じたのだろうと思います。
そんな中で出あった、理想の人、その人との熱い恋、そして別れ。コンサーバティヴな時代のことですから、今風に言えば、「ポリティカリー・コレクト」ではない話が出てきます。でも、この話の中では、それはひとつの「道具」あるいは「舞台設定」なのだろうと思います。そこに重点を置いて書かれたのではなくて、自分の取った選択は、最後は自分の意思、決断によるものだったのだということが、この話の本旨なのではないかと思うのです。
その舞台設定のひとつとして、万博がうまく使われていたようにも思いました。万博に何を見に来たかと問われて、「万博を見に来た」と答える人が多かったというエピソードも交えて、あんなふうに単純に国中が熱狂的になる、言ってみればいい意味でも悪い意味でも「純な気持ち」が支配していたときに、そういう「単純なものの考え方」を否定し、反抗しながら、ある種、そういう世間に取り込まれてもいく状態、が描かれていたのではないかと思います。
書いてある内容は、かなり濃いものですが、文章自体は、淡々としているというか、凛としているというか。それは、ヒロインの女性が、それまでの自分の選択を、恋人との別れの事も、その後の事も、自分の選択を全て、自分の身に引き受けて、逃げないで、ごまかさないで最期を迎えたからでしょうか。
心に残る作品でした。
水曜の朝、午前三時
2007/02/10 09:50
大切なものは、失って分かる
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:よし - この投稿者のレビュー一覧を見る
45歳の若さでガンに冒され、余命いくばくも無いと悟った女性翻訳家直美は、娘のために四巻のテープを残す。そこに語られるのは1970年の大阪万博での身を焦がすような恋と無残な結末、許されぬ過去。切なさとやりきれない過去の思いを45年という生涯を閉じるとき、告白することになる。
この作品の欠点というか気になったところから。文体は美しいのですが、テープに収めている内容を告白する形にしたため、少々粗さも目立ちます。(…でしたから突然…だに変わる)
娘婿がテープを興すことになるのだが、娘婿の設定は不要のような気もします。
結末がいまいちはっきりしない。気持ちが宙ぶらりんの状態にさせられます。
などなど、欠点もあることはあります。
しかし、デビュー作のこの作品は欠点を補って、おつりがくるほど素晴らしい内容です。何より切ない。無残すぎるほどの別れ。そして、胸に残りつづける深い思いを抱えた女性の思い。大阪万博という当時のイベントを背景に語られる恋は、若さゆえのものとはいえ、とっても健気でもあります。
万博の会場の描写。一人の男性を追いかけて京都まで追いかけるシーン。琵琶湖疎水のほとりを二人で歩くシーン。そして、許婚を断り、両親に話すシーン。どれも涙があふれてきます。それほど情熱的な恋。
物語半ばから急展開します。恋する人の秘密を知ったことから。わたしだったらどうするのかはわかりませんが…悲しすぎます。そしてもう一つの別れ。この主人公直美のやり切れない思いと過去への償いは年に1回京都に向かう事になります。
その思いを死を前にテープに詰め込んでいくのですが…。切ないです。病院の中で死を前にこの主人公は生きることを悟っていきます。自分勝手と思われようとこの思いを誰かに伝えることが生きることだったのですね。
当時のミュージシャンが出てきます。ジミ・ヘンドリックス、ジョニス・ジョップリン他にも多数。当時の音楽も隠し味になっています。そして、この作品名は70年代を代表するアーチスト。サイモン&ガーファンクルの楽曲名とデビューアルバム名です。それを作品名にするあたりがこの作家の手の込んだところなのでは。
恋のひたむきさと大切なものは、失って初めてわかるものだと教えてくれる作品です。粗さもありますが、涙する所多々ありの切ないラブストーリーに生きる意味を考えること間違いなし。
水曜の朝、午前三時
2015/03/23 17:56
生きていく人
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみ - この投稿者のレビュー一覧を見る
死んだ人を通して、生きていく人を書いた本だと思いました。恋愛のお話ですが、恋愛小説が苦手な人にもオススメです。
小説の設定として2人だけでは完結しえない話のため、恋愛を書くことで生きていく人の描写に成功したお話だと思います。
かつて逃げたことを誰にも言えずに生きてきたとしても、自分の選択である今のこの生活を生き抜こうと、諦めながら背筋を伸ばすことのできるお話です。