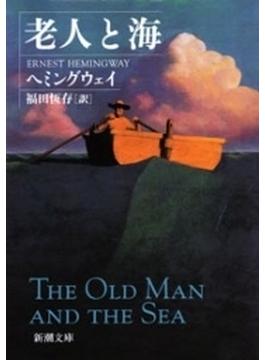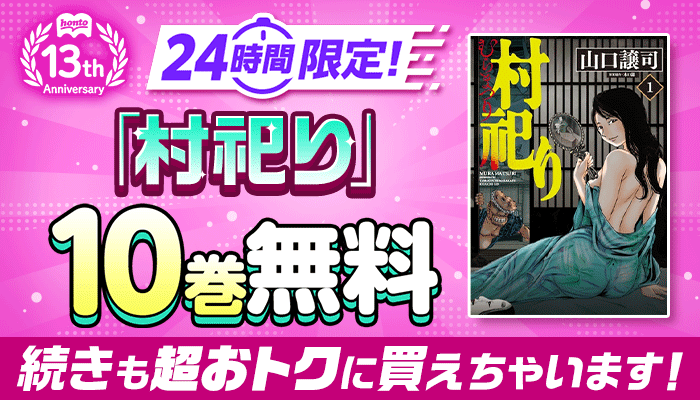この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
老人と海 改版
2008/01/06 20:13
単純な話と簡単な話とは 似ていて非なること
13人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くにたち蟄居日記 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この作品の筋は実に単純だ。老漁師が一人でカジキを釣り上げるが 帰港の間に魚をサメに食べられてしまう。それだけだ。
「単純」な話と「簡単」な話は似ていて非なるものだ。この作品が その良い例だと思う。
この話は漁師の「敗北」を描いているのか、「勝利」を描いているのか。それすらはっきりと断言できない。それほど 難しい話なのである。
カジキを持って帰れなかったという筋だけを見ると「敗北」の話だ。但し 老人はカジキを釣り上げた点を見ると これは紛れも無く「勝利」と言える。特に 老人は 既に漁師としての盛りを過ぎたと言われていた環境を考えると「大勝利」であると言ってよいと思う。
但し、と思う。
但し この話は やはり「敗北」の話なのではないか。そう読む方が 味わいにぐっとコクが出てくるような気がしてならない。
「敗北」には ある種の甘美さがつきまとう。負けっぷりの良さ という言葉もあるが 僕らは どこか敗北の中に美を見る部分があると思う。「老人と海」という シンプルな話が美しく煌くとしたら その漁師の敗北の美学ではないだろうか。
繰り返すが この話は単純で 難しい話なのだ。色々な読み方が出来る。そんな本は余り多くない。
老人と海 改版
2004/08/01 22:59
夏休み不良少年読書日記8月2日
8人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:脇博道 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ぼくのおとうさんは高校生のとき、夏休みにこの本を読んで読書感想文
として提出したら全国なんとかコンクールで佳作をもらったそうです。
めずらしくぼくにそのはなしををしたあとで読んでみなさいといった
ので、読みました。おとうさんはどんな感想文を書いたのか聞いたら
もう遠い遠い昔のことでおぼえていないといいました。そしてたとえ
おぼえていたとしても読むまえに話さないほうがいいだろうとも言い
ました。それっておとうさんが、いつもいっている一冊の本を読んだ
人が百人いたら百通りのかんじかたがあるのだから、ということなの
かなーと思いました。老人はひとりで何日も何日もさかなを待ちます。
とても孤独です。ひとりぼっちです。でもぼくはこの老人となにかが
きっとつながっていてけっしてひとりぼっちじゃないんだと強く感じ
ました。強いこころをもったひとだなーとも感じました。海は無限に
ひろがっています。こわいくらいです。ぼくも舟に乗ったことがある
のですが、自分がいまどこにいるのかわからない気がしてとてもこわ
かったです。でもこの老人はひろいひろい海のまんなかで、いま自分
がどこにいてなにをしようとしているのかはっきりとわかっていると
ころがすごいと思いました。最後のほうはあんまりハッピーエンドで
はありません。でもこれでいいのだと思いました。理由はありません。
ただそうかんじただけです。この本を読んで、すこしおとなに近づいた
気分になりました。いっぱいひとがいてみんなちがうことを考えていて
孤独で悲しいけれど、どこかでつながっているような気もしたし、つな
がっていなくても自分はこころを強くもつことがひつような、そんな
感じです。この本を読んでいたときは、不良になることはぜんぜんわす
れていました。おとうさんにこんな感じの感想をはなしたら、すこし
笑ってくれたのでぼくはとてもうれしかったです。夏休みのあいだに
もういちど読んでみようかなと思いました。ヘミングウェイというひと
のちがう本も読もうかなっていったら、別に読んでもいいけれどほかの
はもうすこしむずかしいかもしれないぞって言われました。いま迷って
いるところです。
老人と海 改版
2010/02/22 08:59
ボヴァリー夫人は私だ、サンチャゴ老人も私だ
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:風紋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
メキシコ湾流の流れる海の漁師、サンチャゴ老人は84日間一匹も釣れない日々が続いていた。最初の40日間はマノーリン少年が同行していたが、両親は老人に見切りをつけ、少年を別の舟に乗りこませた。
不漁85日目の正午の頃、ついに大魚が餌にかかった。老人の舟よりも2フィートは長い。体重は1,500ポンドを超える。老人との闘いがはじまった。一日たったが、マカジキはへばらない。老人の闘いは、自分の肉体の限界との闘いともなった。海へ乗りだしてから三度目の太陽が昇った。ついに仕とめ、舟の脇にくくりつけた。老人は疲労困憊していたが、意気は高かった。あとは家路につくのみ。
好事魔多し。新たな敵が出現した。苦闘の果てに得た獲物を横からかっさらおうとする盗人、鮫である。「いま、老人の頭は澄みきっていた。全身に決意がみなぎっている。が、希望はほとんど持っていなかった」
死にもの狂いで防ぐ。銛で一匹屠った。オールに付けたナイフで、また一匹たおした。だが、鮫は次から次に際限もなく、執拗に襲いかかってくる。午後10時頃、ハバナの灯が見えた。老人の手に武器は残っていなかったが、襲撃はまだ続く。夜中を過ぎて、舟は小さな港に着いた・・・・。
日本近海にイワシが減少し、世界的にマグロが絶滅危機に面している。不漁に直面する老人の嘆きは世界各国の漁民の嘆きでもある。ここに本書の普遍性がある。
しかし、老人の属性を漁師に限定しなくともよい。本書には、固有名詞がほとんど出てこない。主人公も終始老人と呼ばれるのみで、その名サンチャゴは付け足しのように二度ほど記されるにすぎない。老人が住まう土地の名すら、定かではない。主人公の所属が具体的でない反面、その行動は即物的であり、目にあざやかに見えるようだ。ここから、事が漁業にとどまらない広がり、ふくらみ、象徴性が生じる。
たとえば、老人をヘミングウェイ、マカジキをヘミングウェイの作品、鮫を批評家と見立てる。老人(ヘミングウェイ)が釣り上げた獲物(作品)を、寄ってたかって鮫(批評家)が喰い荒らすのだ。
あるいは、読者は読者で、自分の体験と照合させることができる。老人に味方しない海、すなわち自分の志に味方しない状況、そこに生じる孤独感と無力感・・・・誰しも人生の一時期にこうした体験があるのではないか。本書を読みながら、雄々しく闘いつづける老人を自分に重ね合わせることもできるだろうし、あるいは闘いたかった思いを老人に仮託することもできる。
本書は、ある状況を細かく描くことによって別の状況を想起させる、という点で、アルベール・カミュ『ペスト』や大岡昇平『俘虜記』に通じる。