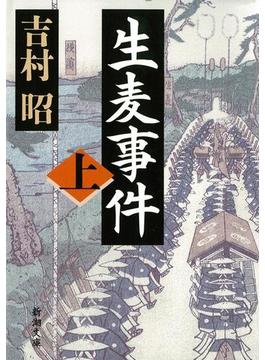生麦事件
文久2(1862)年9月14日、横浜郊外の生麦村でその事件は起こった。薩摩藩主島津久光の大名行列に騎馬のイギリス人四人が遭遇し、このうち一名を薩摩藩士が斬殺したのである。イギリス、幕府、薩摩藩三者の思惑が複雑に絡む賠償交渉は難航を窮めた──。幕末に起きた前代未聞の事件を軸に、明治維新に至る激動の六年を、追随を許さぬ圧倒的なダイナミズムで描いた歴史小説の最高峰。
生麦事件(下)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
評価内訳
- 星 5 (0件)
- 星 4 (0件)
- 星 3 (0件)
- 星 2 (0件)
- 星 1 (0件)
生麦事件 上巻
2007/10/04 18:08
歴史書と小説の間
7人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ばんろく - この投稿者のレビュー一覧を見る
「歴史小説」を読んだことがない、と言う人はいないと思うので、試しに今まで読んだ物をざっと思い出してみてほしい。それはどんなタイプの小説だっただろうか。歴史上のある一点に焦点を絞って人間ドラマや政治的策謀を描き出すものか、それとも幾多の事件を有機的に結びつけていくことで歴史の流れを浮かび上がらせるものであっただろうか。前者は歴史を舞台としているが小説に近く逆に後者は歴史書に寄っているといったように、歴史小説は歴史と小説との間にあってその位置取りが作品の一つの重要な性格となる。さらには人物に魅せられてこの両立を図ろうするとこれがたちまち大長編に編み上がってしまうようでもある。勿論これは一つの見方であって、またこれには括られないものもあるかもしれないが、今回はこの観点で紹介していきたいと思う。
ペリー初来航から9年、日米修好通商条約締結から4年後、神奈川の生麦で起こった薩摩藩士による外国人商人殺傷事件すなわち生麦事件から明治維新までを詳細に綴る。英国・幕府・薩摩藩の三角関係を生む生麦事件を発端に据えることが幕末期各人がいかに対等に交渉を繰り広げたか、言い換えれば幕府がいかに権威を失っていたかを象徴し、時代に追随できない幕府を尻目に薩長をはじめとした雄藩が、列国との直接接触を通して攘夷から開国へと世論を変化させていく姿が見事に描かれている。
年数にすれば約6年であるが、この濃密な時期を俯瞰する形で描ききる本作は、緊迫や狼狽、安堵といった雰囲気を文学的な表現でよりも書き込む事象の密度や配列、つまり構成によって生み出している点が大きな特徴である。各人の思惑がぶつかり合う中での苦悩、葛藤といった時代転換期の熱気は確かに伝わってくるのに、心理的な描写はと見てみるといたってシンプルで、淡々とした形容詞を用いるのみのことが多い。場の緊迫感をひしひしと感じさせるのは次から次へと舞い込んでくる情報によってで、例えば事件の直後や英国への賠償問題の回答期限が迫る場面などでメモなぞ取ろうとすれば、ノートには全てのページ番号が振られてしまうなんて事になりかねない。
これだけの収集され整理された情報を目の当たりにするだけで著者の執着力を感じさせるが、これを冷静に並べていく事の出来る事が驚異である。これだけの材料が揃えればその一部だけでも十分にものを書くことができるはずだが、もし一つ一つを自分の言葉で表せば最終的な全体像は膨れあがったうどんのようになってしまうだろう。自国商人の憤怒を押さえながら冷徹な外交を繰り出す英外交官、薩摩藩の横柄な態度とそれに厳然とした態度で臨む現場職の神奈川奉行、挟まれた幕府の閣僚の狼狽、押し黙る閣議の空気といった、もとより我々が想像・共感しうることは書かないという程の姿勢が、この作品を洗練されたものにしている。別の言い方をすれば日本人はこの作品を読んで満足するが、思考の異なる外国人は行間が読めず全く面白くないのでは、と思わせるような書き方である。
歴史という非常に長いスパンのものを書くに当たって個々の事象よりその繋がりで興奮を呼び起こせるというのは、まさにその手法としてふさわしいように思える。歴史を生で小説にする構成力はすばらしい。