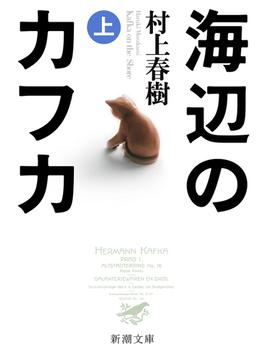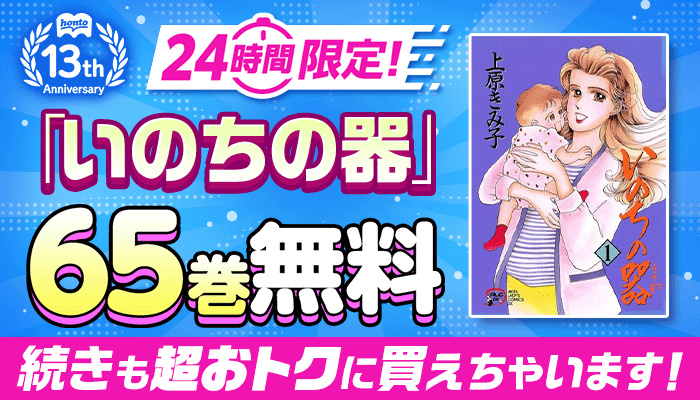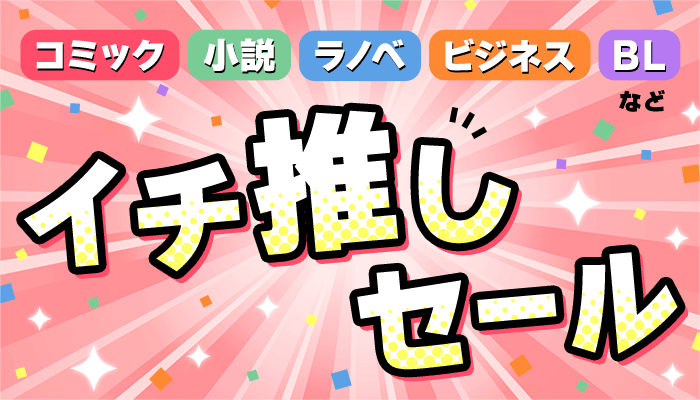- みんなの評価
 38件
38件
海辺のカフカ
著者 村上春樹
「君はこれから世界でいちばんタフな15歳の少年になる」――15歳の誕生日がやってきたとき、僕は家を出て遠くの知らない街に行き、小さな図書館の片隅で暮らすようになった。家を出るときに父の書斎から持ちだしたのは、現金だけじゃない。古いライター、折り畳み式のナイフ、ポケット・ライト、濃いスカイブルーのレヴォのサングラス。小さいころの姉と僕が二人並んでうつった写真……。
海辺のカフカ(下)(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
海辺のカフカ 上
2005/04/11 08:46
春樹の「んだ」語尾と猫の客観性
11人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:吉田照彦 - この投稿者のレビュー一覧を見る
たぶん多くの人が感じていることだと思うのだけれど、村上春樹の小説というのはどれもたいへんに読みやすい。読んでいると、なにか静かな山奥の小川のせせらぎに身をひたしているような、とても快い気分になれる。本書を読みながら、それはなんでかな、ということをずっと考えていたのだけれども、少なくとも僕個人が彼の小説において最も心地よく感じるのは、作中の登場人物たちがしばしば口にする「んだ」という、科白の語尾であるということに気付いた。
「君は絵の中の少年に嫉妬しているんだ」
「(略)自分でも信じられないくらいなんだ」
「いつそれを言ってくれるか、ずっと待っていたんだ」
「(略)君はなにかとくべつな部屋を探しているんだけど、その部屋はぜんぜん見つからないんだ。(略)私は叫んで、君に注意を与えようとするんだけど、私の声はうまく届かないんだ。(略)それで君のことがとても気になっていたんだ」
「君は正しいことをしたんだ」
実際、こうしてざっと抜き出してみただけでも語尾が「んだ」になっている科白(ここでは仮に「んだ」語尾の科白と名づける)というのが結構ある。もちろん、「んだ」語尾でない科白もたくさんあるし、他の作家の小説にも「んだ」語尾の科白というのはたくさんあるはずなのだろうけれども、僕にはなぜかこの著者の小説の中の「んだ」語尾だけが非常に強く印象に残り、特に好ましく感じられるのである。
言語学的に言って、「んだ」語尾というものに何か普遍的な意味合いがあるのかどうかは僕の知るところではないけれども、少なくとも僕が村上作品における「んだ」語尾から感じるのは、非常に夢見がちな口調であるなあという感覚である。たとえば上記の例でいうと、「君は正しいことをしたんだ」なんという科白は、本来、それを口にする人物による「君は正しいことをした」というひとつの「宣言」であると思うのだけれども、これが「んだ」語尾になっていることによって、その宣言性とでもいうようなものがうまいこと和らげられて、なんというか、夢見るような、歌うような口ぶりに変化しているような気がする。単に「した」でもない、「したんだよ」でも「したんだぜ」でもなく「したのだ」でもない、「したんだ」というまさにその語尾が、一切の押しつけがましさを排して、水のようにすうっと心の中に染み入ってくるような心地よさを感じさせるのである。
このことはもしかするともうすでにどこかで誰かが指摘していることかもしれないし、あるいは逆に僕だけにしか感じられない極度に個人的な印象の問題に過ぎないのかもしれないけれども、ともかく僕が村上作品に感じる好ましさの最大の要因がこの「んだ」語尾であるということはどうも間違いないことのような気がする。
ところで、本書には猫と会話が出来る人間というのがいて、猫が人間の言葉でいろいろとしゃべる(というか、その人間が「猫語」を解する)のだけれども、これが猫であって犬ではないというのは、僕にはとても重要にというか、面白く感じられる。話は違うけれども、たとえば夏目漱石の『吾輩は猫である』が『吾輩は犬である』であったとしたら、ちっとも面白くなかったろうと僕は個人的に思うのだけれども、どうも猫というのは人間にとって客観的な存在であり、犬は逆に主観的な存在であると、これは漱石や村上氏にとってだけではなくて、一般的にそのように捉えられているのではないかという気が僕にはする。それはおそらく、彼ら動物自体が人間に対して取っている(と人間が感じる)スタンスを反映しているのだろうと思う。
海辺のカフカ 上
2005/05/10 21:01
ずっと敬遠していました。
8人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しぃ - この投稿者のレビュー一覧を見る
読み始めてまず感じたのが、詩の様だということ。文章が詩的と言うわけでなく。一章一章が詩の一節で、本まるごと一冊がひとつの詩を成している。(上下巻で2冊だけど)
だから、この作品を楽しむには意味を考えてはいけない。1ページ1ページ、目に入った文章を素直に楽しむ。瞬間瞬間のストーリーを単純に楽しむ。
ドロドロに引き落とされたと思ったら、整然としたリズム感あふれる文章で引き戻される。ズタズタに引き裂かれたと思ったら、軽い文章で心が和む。
読み終えた時、心が揺さぶられすぎたせいか体が震えていた。しばらく何もできなかった。
今まで食わず嫌いで、村上春樹氏の作品を読まなかったことが悔やまれます。空想小説?というかたちをとっていますが、恐ろしく現実的な作品です。「現実」ってものをここまでリアルに描き出せる作家を私は知りません。海外では評価が高いそうですが、日本では、あまり評価は高くないらしいですね。もったいない話です。
海辺のカフカ 下
2007/11/21 23:40
やっぱりすごい!!
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トマト館 - この投稿者のレビュー一覧を見る
上巻からかけられたなぞかけが、
どんどん結末にむかって
つながっていく。
このさまがさすが、という感じです。
上巻で、わたしは、
「この田村カフカという少年は、15歳にしてはあまりにも言葉をもちすぎている。」
と感じたが、
それもだんだん腑に落ちてくる。
あまりにも言葉をもっている田村カフカと、
あまりにも言葉をもっていないナカタさんの話なのである。
村上春樹にしては、
すごく明るい作品だという印象が、
ひたすら残った。
これだけの大きな展開を組み立てられるというのは、
やはり作者の腕だと思う。