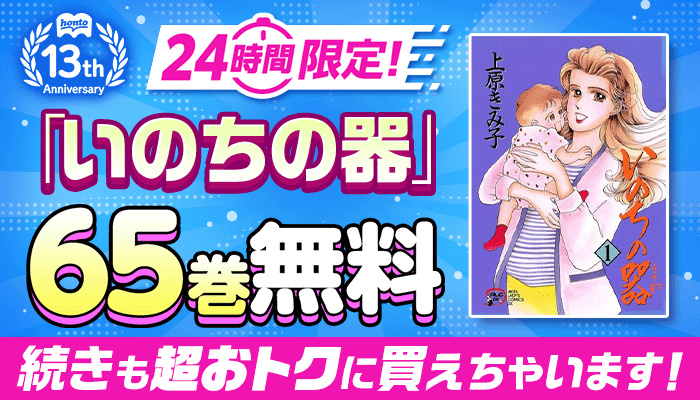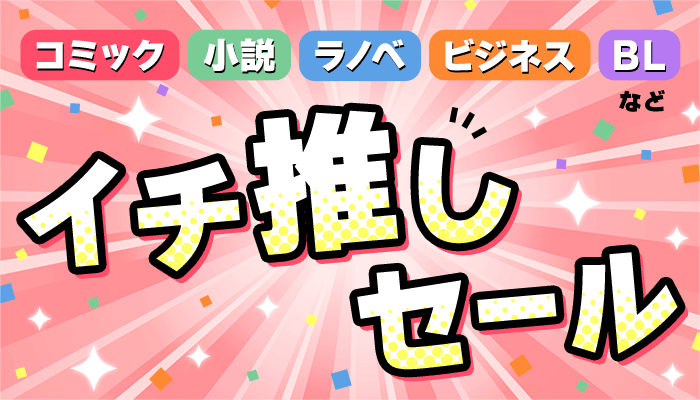- みんなの評価
 3件
3件
安田講堂1968-1969
著者 著:島泰三
一九六九年一月、全共闘と機動隊との間で東大安田講堂の攻防戦が繰り広げられた。その記憶はいまもなお鮮烈である。青年たちはなぜ戦ったのだろうか。必至の敗北とその後の人生における不利益を覚悟して、なぜ彼らは最後まで安田講堂に留まったのか。何を求め、伝え、残そうとしたのか。本書は「本郷学生隊長」として安田講堂に立てこもった当事者によって、三七年を経て、はじめて語られる証言である。
安田講堂1968-1969
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
安田講堂 1968−1969
2006/07/11 02:50
”あの頃”の学生たちの心情を想う
14人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:良泉 - この投稿者のレビュー一覧を見る
どのような歴史にも、必ずなんらかの「転換点」と呼べる出来事がある。しかし、学生運動の歴史における東大安田講堂攻防戦ほど、顕著なターニングポイントとして示されるものはない。安田行動攻防戦を境に、学生運動の歴史は大きく転換した。
安田講堂攻防戦以前の学生運動は、学生本来の純粋な正義感の発露であり、多くの一般市民からもかなりの程度、共感を持たれ、受け入れられていたものであった。
これに対し、安田講堂攻防戦以降の学生運動は、衰退・退廃の一途をたどることになる。一般市民の眼にも、以降の学生運動は、「内ゲバ」、「同士粛清」、「テロリズム」といった暗く納得し難いイメージにうつることが多くなる。
東大安田行動は、まちがいなく、ある時代のシンボルであった。そして、多くの者たちが、この時点を境に燃え尽きた。
学問を志し、大学の自治を唱えるまじめな学徒たちが、なぜ、ヘルメットをかぶり、こん棒を握り締めたか。
人並みに遊び、普通の人と同じように恋愛もしたかったであろう若い少年・青年たちが、なぜ、投石し火炎瓶を投げるに至ったのか。
当事者たちの思いや行動は、もっともっと記録され、次世代の若者にも継承されていくべきだ。長い沈黙の中にこもっていた当事者たちの声が、この本のような形で少しずつ知られることは、とても貴重なことである。
そして、本書を読んであらためて思う。いまの“沈黙”は何だ。
あきらかに歪んだ方向に向かっていると言わざるを得ない現代の政治経済情勢。これに対する学生・一般市民側の“沈黙”が気持ち悪くて怖い。
かつて、アメリカのベトナム戦争に巨大なパワーで反対を表明した多くの人達がいた。現代では、日本の自衛隊が直接、アメリカの世界戦略の下働きに、海外に“出兵”してさえも、そんな声は起こらない。
かつて、大学の管理強化に猛烈に反対した多くの学生がいた。現代では、管理を受け入れる、いや、さらに進んで自ら強者の管理下に従属することにしか居場所を見つけられない学生が多くいる。
あらためて、この落差に愕然とする。
安田講堂 1968−1969
2006/10/02 22:45
感動した!
12人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:GTO - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本を読んで最初に思い浮かんだ言葉は、[義を見てせざるは勇無きなり」である。彼らは単なる暴力学生ではなかった、少なくとも安田講堂までは。大学教育の在り方自体に問題があったわけだから、象牙の塔に籠もる人たちとはどこまでも平行線だったが、三島とはコミュニケーションが成立したのだ。そして、共産党にほんの少しでも庶民性があったならば、他の野党が少しでも学生の声に真摯に耳を傾けていれば、この闘いも、今の日本も違っていたと思う。
その日、1968年1月18日は土曜日で、学校から帰ると翌日の陥落までテレビに釘付けであった。小学校5年生であった私は、父親の買ってくる「朝日ジャーナル」や「中央公論」、「文芸春秋」で大学生たちが、なにかに苛立ち怒りをぶつけようとしていることは知っていた。上記の雑誌を読んでも、学生たちの主張は小学生には難しくて理解できなかったが、大学生の真剣さは分かった。多勢に無勢、そのうえ武器、装備すべての面で機動隊が優位なことも小学生にさえ明白だった。
佐々の『東大落城』の書評でも書いたが、安田講堂攻防戦ごろまでの全共闘を一般市民は、佐々が言うような「幼稚で甘えた暴力学生」などと思っていなかったし、多分に同情的(シンパ)であったと思う。現在、あの時代を語る時、「暴力学生」という表現で片付けられることがあるのは、その後に内ゲバ、同志殺害、テロ、ハイジャックを起こした分子がいたからにすぎない。
たとえば、大学生の親がマイクを握らされ、「〜ちゃん。馬鹿なことは止めて、出てきなさい。」と叫んでいた時の私の父が言ったのは「自分が正しいと信じるなら、『最後まで闘え!』と言ってやるから安心しろ。」だったと記憶している。共産主義も社会主義も信じていない彼がである。(父が小学生の私にした共産主義の説明は「能力に応じて働き、必要の応じて使う理想の社会」で、「そんなことができる人間が周りに何人いる?そんな社会はありえないだろ。」だった。)
この本を読めば、どちらが暴力的だったのか分かる。大学当局や政府は学生を挑発し、先に暴力を振るい、学生たちを武装させたのだ。いまの若い人は信じないかもしれないが、警察機動隊も全共闘側の人間だけを検挙する。だから、彼らだけが暴力を振るっていたような印象が残ってしまっているが、当時の雑誌を見るだけでもそれが嘘だと分かる。公式記録だけを見れば、話し合いで解決しようとする権力側と暴力に訴える学生に見えるかもしれないが、宮崎学の『突破者』を読めば、それが体制側のポーズにすぎなかったことは明らかだ。
全共闘の学生たちは、大学当局、それに雇われた右翼・暴力団・体育会系学生、警察機動隊、そして日本共産党(その下部組織である民青)を敵に四面楚歌の状態で闘い抜かねばならなかった。また、全共闘運動はもともとは共産革命を目指した左翼思想から出発したのではなく、ごく普通の当然な要求から始まったことが分かる。社会主義や共産主義というようなイデオロギー闘争ではない面があったので、一般市民も共感する部分があったと思う。
私がポスト団塊の世代として、全共闘世代に批判的になのは、最近、自己弁護の書としか思えない団塊の世代の本が目につくからかもしれない。しかし、この本は気持ち良く読めた。私は全共闘の敗北は第二の敗戦だと考えているが、作者には闘いはまだ終わっていないのだ。この本によって、時計台放送は再開された。もうすぐ40年、真に時代を裏切り得たか?心ある団塊の世代は、作者のもとに結集されたし!今だからできることがあるはず。
他の世代にとっては、教育、医療、戦争、環境、経済一つ一つの問題について、明日の日本を考えていくためにも、全共闘運動の失敗を教訓とするためにも、貴重な本だと思った。
安田講堂 1968−1969
2006/10/22 12:44
馬鹿は死ななきゃ直らない
18人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:塩津計 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者は「親指はなぜ太いのか」という非常に面白い本を書いたサル学の専門家である。この本を読んだ当時は「面白い本を書く人だな」と好意的にみていたが、そいつがまさか東大に立てこもったオオバカヤロウで、しかも今日に至るまで、あの暴力事件・騒擾事件について反省も悔悟もしていない阿呆だったとは思わなかった。かつて「反省するならサルでも出来る」という言葉が流行ったが、反省とは無縁の島君は「サル以下」いや「サル未満」と言い切っていいだろう。著者が本書をあらわす契機となたのは、我らが英雄・佐々淳行さんの名著「東大落城」http://www.bk1.co.jp/product/934344にあるようだ。とにかく本書には、やたらと佐々さんの著作が引用されては「そうではない」という否定が入る。あきれ果てるのは、あれだけ東京大学を壊し、東大教授陣に迷惑をかけ、日本政府に迷惑をかけ、警察にも迷惑をかけ、かわいそうな警察官に死者さえ出しているくせに、日本政府・警察関係者・東京大学関係者に「悪いことをしました。すみませんでした」の一言もないことだ。著者が羅列するのは、ただただ暴力学生(加害者)側の蒙った被害の話ばかりで、被害者(日本政府、大学当局、学生、及び昭和44年に東大受験を予定していた受験生達など)への配慮は微塵もない。著者は今でも「正義は我が頭上にあり」と確信している模様で、機会があれば、今からでも再び東大安田講堂に立てこもり警察官に火炎瓶と投石を再開しそうな筆致なんである。島という野郎は、本当にどういう人間なのか。何度でも書くが、現代の民主主義社会では、如何なるご不満があろうとも、その不満を暴力によって表現してはならないし、不満を暴力という手段を用いて晴らしてはならないのである。そもそも正義は我が頭上にありという思い込みが、彼ら彼女らの思い上がりなのである。正義なぞ人の数だけあるのだ。不満なら口頭で文書で抗議すればいい。埒が明かなければ大学なんか辞めればいいのである。それとも何か。東大生は別格で何をしても許されるとでもいいたいのか。笑わずにはいられないのは、東大生は入学後も学内での順位に汲々とし、やれあいつは秀才だの、オレは頭が悪いだのと他者との比較に余念がないことだ。東大理学部では数学科がトップの秀才が集うところで、筆者の所属していた人間学は最低の馬鹿が回されるところだというのだ。そんなの東大に入学できなかった人から見れば同じだって。みんあ超秀才なんだよ。この構図は理科系に限らない。文系でも財務省に就職しても、最初に配属されるのが大臣官房文書課に配属されるのがトップの証で、主税局だの理財局は落ちこぼれだみたいな迷信がある。島君は、さぞ口惜しかったのだろう。その口惜しさを今日まで鬱々と抱き続けていたのだろう。それを一気に吐き出したんだろう。それでお里が知れてしまうということなぞ、思いもしなかったのだろう。ほとんど嫌悪感しか催さないひどい本だったが、唯一共感できたのは大学の教養課程を「まったくの無駄、まったくの浪費、専門能力を身につけるためには、まったくゴミのようなもの」(81ページ)と切って捨てている点だ。立花隆なる阿呆が「大学の4年間はリベラルアーツを教える教養課程に特化して専門教育は大学院に任せよ」などという妄言を吐き散らかしている昨今、この点だけは私も共感できた。