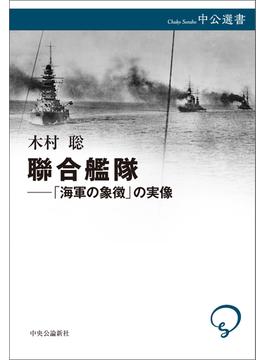- みんなの評価
 2件
2件
聯合艦隊――「海軍の象徴」の実像
著者 木村聡 著
誰もが知る「聯合艦隊」初の通史。
東郷平八郎や山本五十六ら聯合艦隊司令長官は、ともすると海軍大臣よりも一般に名の通った存在である。
では、聯合艦隊とはどのような「組織」で、どのような役割を果たしていたのか。
本書は、本来、戦時や演習時に必要に応じて編成される臨時の組織に過ぎなかった聯合艦隊が平時に常設されるようになり、海軍の象徴として政治的にも大きな存在となりながら、次第に戦争の現場に合致しない組織となっていく過程を、鍵となる司令長官の事例を軸に説き起こす。
聯合艦隊――「海軍の象徴」の実像
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
聯合艦隊 「海軍の象徴」の実像
2022/05/12 00:36
博士論文の一般書化
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オタク。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者は平成5年生まれとあるので、今までの帝国海軍の研究者と違って、多少は海軍関係者に取材はしていると思うが、基本的に文献類や映像・音声資料を基にして接しているだろう。博士論文を元にした一般書化との事。
確かに「栄光の聯合艦隊」を批判的に論じた本は少なそうだ。「陸軍悪玉論」に反比例した帝国海軍讃歌(これは学徒出陣の際に内務班生活がない海軍予備学生になった人の海軍びいきもあるだろう)、聯合艦隊讃歌と違って、常設化した聯合艦隊が帝国海軍の中で1つの権威、この本で言うところの「第二の軍令部」となった聯合艦隊司令部が自律していった過程を関東軍になぞらえている。
聯合艦隊を維持する為に必要な予算の記述が見当たらないのは担当するのが海軍省の役割だからだろうか。
ただし、聯合艦隊が常設ではなかった時代の記述が歴代司令長官の表ぐらいしかない。山屋他人海軍大将のような常設ではなかった時代の聯合艦隊司令長官がある日突然、有名になったのは著者にとっては生まれた年の話しだ。
昭和初年の美保関事件の記述に海軍士官が海軍大佐に名誉昇進した上で「除隊」とあるが、水兵さんの除隊じゃないのだから、ここは予備役編入ではないのか。
今時、「クニャージ・スヴォーロフ」を「スワロフ」と表記するとは思わなかったが、「アレクサンドロス3世」ではツァーリ・アレクサンドル3世ではなく、マケドニア王アレクサンドロス3世を連想してしまった。アレクセーエフを「アレキセーエフ」だから、当時の表記をそのまま使っているようだ。
最近はやりの「皇族軍人」という言葉は、当時の皇族王公族は基本的に軍人となる事が義務づけられているので、ことさら「軍人」と強調する必要がない気がする。もっとも帝国海軍は昭和18年まで朝鮮人・台湾人には門戸を開いていなかったから、帝国海軍に軍籍があった王公族はいない。「英親王李垠伝」にあるように海兵への入校が予定されていた王世子李玖が実際に入校したら、色々と制度を手直しする必要が出て来ただろう。
勲章を佩用した帝国海軍の提督達の写真を見ていると、レジオン・ド・ヌール勲章を貰っていたら必ず佩用するのか、と思えてくる。それだけナポレオンが制定した勲章が憧れだったのか。
聯合艦隊 「海軍の象徴」の実像
2023/02/23 16:39
「海の関東軍」
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mt - この投稿者のレビュー一覧を見る
組織としての「連合艦隊」に着目した一冊。戦時に臨時で置かれる編成が、大正期の軍縮の余波から常設化され、海軍の栄光を一身に背負うことに。しかし、それは軍令部との指揮系統の混乱を招き、ましてや陸海の共同が必要な島嶼戦では、陸軍との軋轢を増す要因となる。現場の出先機関の暴走という点から、連合艦隊を「海の関東軍」と評する著者の主張は刺激的。陸軍が大陸での泥沼という高い代償を払って、中央の統制を回復したのに対し、最後まで改善しなかった海軍という見方も強烈である。海軍に対するスマートなイメージを破壊する内容。