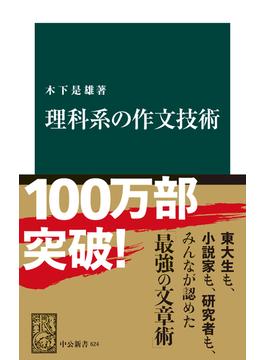- みんなの評価
 6件
6件
理科系の作文技術(リフロー版)
著者 木下是雄 著
物理学者で、独自の発想で知られる著者が、理科系の研究者・技術者・学生のために、論文・レポート・説明書・仕事の手紙の書き方、学会講演のコツを具体的にコーチする。盛りこむべき内容をどう取捨し、それをどう組み立てるかが勝負だ、と著者は説く。文のうまさに主眼を置いた従来の文章読本とは一線を劃し、ひたすら「明快・簡潔な表現」を追求したこの本は、文科系の人たちにも新鮮な刺激を与え、「本当に役に立った」と絶賛された。2016年には紙の書籍がついに100万部を突破した、不朽の文章入門。
理科系の作文技術(リフロー版)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
理科系の作文技術
2004/05/29 20:15
論理的文書力が向上する本
10人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:さにお - この投稿者のレビュー一覧を見る
私は自分のホームページを通して、年に数回取材を受けます。簡単な取材の場合は、メールで私が書いた原稿を送ります。その原稿はライターがきちんと読ませる文書にまとめ、雑誌に掲載されます。ライターが書いた原稿と私が最初に書いた原稿を見比べると、自分の文章力の低さを思い知ります。素人とプロの差は歴然でした。
社会人になって中堅にもなると、多数の第三者に向けた文書を書く機会が増えてきます。また、自分のホームページでも、たくさんの人が私の文書を読んでいます。自分の文書力を向上させる必要性を感じる機会が増えるようになりました。そんな時、続「超」整理法・時間編(野口悠紀雄著)を読んでいて、本書を知りました。野口氏はかなり強く本書の一読をすすめていました。
本書の目標は理科系の若い研究者・技術者、学生に表現技術(作文技術)のテキストを提供することです。視点として、「さきに結論を出してから本文をかく、トピックセンテンスはパラグラフの最初に書く、事実と意見との区別する」の3つが特に感じ入りました。内容の的確さに、版を重ね20年以上も読まれている理由がわかります。
理科系でなくても、論理的な文書を書く能力は必要です。仕事でもプライベートでもその場面はあります。本書を読んで、作文技術を理解し実践すれば、文書力がもう一段アップすると思いました。
こちらに要旨をまとめてあるので購入する前にぜひ読んでみて下さい。他にもビジネス関係の本の要旨がありますので、参考にして下さい。
理科系の作文技術
2003/05/12 23:53
研究者としてやっていくノウハウの全て
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:KAZU - この投稿者のレビュー一覧を見る
作文が苦手な理科系の方は意外に多いように思う。それは、普段の実験で実践している思考方法、ロジスティックな頭の中身を文章にするときに、ついつい見せかけを良くしようという下心が芽生え、文学的表現を試みるために起こる悲劇だと思う。何の事はない、普段の思考をそのまま簡単に、わかりやすく、着飾らない言葉で短く表現すれば、それが最上の作文になるのである。
研究者の文章作成のノウハウ本としてはバイブルと言われている本書を、私自身は職業研究者になってのちに読んだ。大学卒業後2年してからのことである。その後、本書は文字通り私にとっての文書作成のバイブルとなった。大学時代に読んでおけばよかった、願わくば授業で本書を使った「理科系の作文技術」なる講義があればよかったのに、とずっと感じている。
本書に足りないもの。それはインターネットに関連した事項、たとえば、e-mailやPowerPointを利用したプレゼンの仕方の類である。しかし、その基礎となる事項はすでに本書の中に、手紙の書き方や学会講演の要領として詳しく書かれており、それを現代風に応用すれば済むことである。
まさにこの一冊で、職業研究者としてやっていくノウハウの全て −研究立案から論文発表まで− を得ることが出来る。1981年に出版された噂のバイブルはその版を重ねて現在も出版されている。その事実が本書が「本物」であることの証明となると思う。
理科系の作文技術
2021/09/17 21:19
古い本だが一読の価値あり。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:さんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
初版が1981年と約40年前なので、部分的に何分古めかしいところがあるのは否めない。しかし、文章を書く際の本質的な心得としては、まったく古びていない。とくに、事実と意見を区別すること、パラグラフごとに内容を分けて、トピック・センテンスを付けるということは、一般に日本人の苦手とするところで、大いに学びたい。理科系と銘打っているが、事実や意見を的確に読み手に伝えることを目的とする人々全般にとって役立つ内容と信じる。