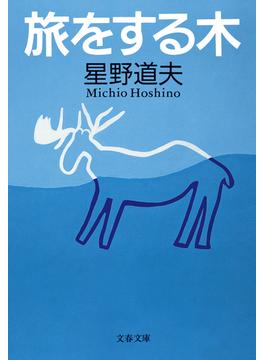- みんなの評価
 13件
13件
旅をする木
著者 星野道夫
広大な大地と海に囲まれ、正確に季節がめぐるアラスカで暮すエスキモーや白人たちの生活を独特の味わい深い文章で描くエッセイ集。
解説・池澤夏樹。
※この電子書籍は1995年8月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
旅をする木
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
旅をする木
2008/07/22 10:55
写真とはこう眺めるものであったか。
20人中、20人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ばんろく - この投稿者のレビュー一覧を見る
●1952年生まれ、20代にアラスカに渡り、その広大な自然を撮り続けた写真家・星野道夫のエッセイ。初版は1995年、40歳頃の作品で、「母の友」に連載した文章および書き下ろしである●
短編の中でも、夜ふとんにくるまって読み始めて次々と章を追ううち、気がつくと枕元の明かりを煌々と照らしたまま眠り込んでいた、なんてのはいい本だと思っている。そのままずるずるといくうちに、空がしらみはじめてしまった、というのもまたいい。
しかし今回のこの本は、そういうものとはちょっと違った。一つ一つからにじみ出る雰囲気を存分に味わいたいと思うと、一度に幾つもというわけにはいかない。もちろんつぎに読みすすみたい気持ちがないわけではないのだけれど、それよりも、いま読み終えた箇所を、電気を消して目をつぶって反芻することのほうをとりたくなる。そのせいでというか、本の厚さのわりには読みきるのにずいぶんと時間がかかってしまった。できるだけ多くの量を読むことが吉と、ふだん格別に意識しているわけではないが、習慣づいてしまっていた自分に、ほんの数ページを大切に抱えて眠るというスタイルをとらせたこの本は、とても特別なもののように思える。そしておかげさまで本書を読んでいる間は寝不足が解消されたようでもある。
実は星野道夫という名前はこれまで全く知らなくて、ただ友人に勧められるがままに読んだ。96年に亡くなったときにはそれなりにニュースになったそうなのだが、当時僕はまだ小学生だったから、写真家という人について何か思うような年頃ではなかったのだ。星野道夫は52年という生まれにして、20代には早くもアラスカに渡っているという一風変わった経歴の持ち主である。アラスカの自然相手に写真を撮るという道に入っていった経緯については、幼少期に映画の中に見た大自然に圧倒されたこと、学生時代古本でみつけたアラスカの写真集、その中の一枚の写真を発端とするアラスカへの第一歩など、本書の中にもいくつか語られているが、それらのきっかけの上でなおその原動力となったのは、大学時代に経験した友人の死であるようだ。中学からの親友で、登山をする仲間であった友人が妙高連山の登山中に噴火に巻き込まれて亡くなる。この出来事に対して、一年後ふと見つけた答えが「好きなことをやっていこう」という強い思いであったという。彼の生き方はこんな背景を持っている。
さて中身はといえば、アラスカの風景やその生活の中で感じたことを書き綴った、と、言ってしまえば何でもないものである。しかし、その一つ一つが、読んでいるものを自然と落ちつかせるようで、我々のものとは比べられないほどゆったりと、大きなスケールで流れている彼らの時間が、じんわり滲み出てくるようなそんな語り口である。アラスカに身を置くことは、広大な自然という空間的な意味だけでなく、時間的な意味で我々の世界とかけ離れた体験であるようで、変わらぬ営みが続く土地で培われた氏の一つの単位は、最後の氷河期が去ってからの一万年前という時間であるという。
写真家の書いたエッセイを、これはまさに写真集である、と評するのではまったく芸がないと思うが、やはりそういうべきなのだろう。読むと言うよりは細部までじっくりと味わうように眺め、目をつぶってその風景を頭の中に思い描いてみる、そんな読み方を自然とさせるような本である。といっても実は僕自身は、未だかつて写真集というものに何か刺激されたことがあまりないものであるから、正直に白状すればこの表現はちょっとかっこつけである。むしろ写真集の読み方は本来こうであろうかと、本書から教わったような次第である。したがってもっと実感に乗っ取った感覚を持ち出すとすれば、(ちょっとなさけないかもしれないが)素敵なカレンダーを手に入れたときの、次の月までのあの我慢の気持ち、というのが一番近いと思う。
どうしても頭から離れない言葉があった。狩猟民について語る『カリブーのスープ』の章、春の渡り鳥の編隊に感動する彼の脇で、土地の人達が鉄砲を片手に舌なめずりをするというようなエピソードを交えながら、「僕たちが生きていくということは、誰を犠牲にして自分自身が生きのびるのかという、終わりのない選択」。という、その言葉である。日常で聞いたなら相手にもしないようなこの言葉は、星野氏のこの本の中では全く違和感がない。大げさでもなく、軽々しくもない。その重みの計り知れないことを理解しているから、これほど素直に語れるのかもしれない。
本書には「悲しみ」という言葉が多く出てくる。彼がアラスカで出会う人は、みな悲しみを湛えた目をしている。我々はといえば、ヒト同士での奪い合いに突入しつつあるなかで、狩猟という犠牲の概念などとっくに通り越してしまっているようにも思える。我々は、彼の言うところの「悲しみ」をいつか思いだすことがあるのだろうか。それともその代わりに、体に取り込まない血の匂いに対して「悲しみ」を感じるようになるのだろうか。さらにはその「悲しみ」まで忘れるようになるのだろうか。しばし時間をおいて再読したい本である。
旅をする木
2009/05/08 21:18
記憶のアルバムをめくるように、アラスカでの著者の旅の軌跡が語られてゆく。胸にひたひたと満ちてくるものがあるエッセイ集です。
10人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:東の風 - この投稿者のレビュー一覧を見る
1978年にアラスカ大学に入り、アラスカに移り住んでから十五年。この地の自然と人々の暮らしにすっかり魅せられ、旅を続けてきて、いつしかここに根を下ろそうとしている著者が、アラスカでの思い出を振り返り、自分とアラスカとを結ぶ強い絆を歌い上げたエッセイ集。静けさをたたえた文章の中から、ふつふつと湧き上がり、立ち上がってくるアラスカへの熱い思い。文章の隅々まで、森と氷河の自然に包まれたアラスカの大地の息吹が浸透していて、胸にひたひたと満ちてくる素晴らしい味わいがありました。
十五年前、アラスカという未知の土地にやって来て、暮らし始めた頃の自分のひたむきな姿を、アルバムの一頁目を開くようにして綴った「新しい旅」。本書の冒頭に収められた、1993年6月1日の日付のあるエッセイから、アラスカをめぐる著者の旅の軌跡に引き込まれましたねぇ。なかでも、次の文章の底に流れる著者の思い。静かに、豊かに胸に沁みる思いの深さ、澄んだ眼差しの美しさが忘れられません。
<頬を撫でる極北の風の感触、夏のツンドラの甘い匂い、白夜の淡い光、見過ごしそうな小さなワスレナグサのたたずまい・・・・・・ふと立ち止まり、少し気持ちを込めて、五感の記憶の中にそんな風景を残してゆきたい。何も生み出すことのない、ただ流れてゆく時を、大切にしたい。あわただしい、人間の日々の営みと並行して、もうひとつの時間が流れていることを、いつも心のどこかで感じていたい。> p.231 「ワスレナグサ」より
著者・星野道夫という人間への思いのこもった巻末解説、池澤夏樹の「いささか私的すぎる解説」と題した文章がいい。本文庫の表紙カバーの絵、ほんめ つとむの「およぐシカ」の装画も、とてもいい。
旅をする木
2012/06/13 11:20
何かあると開く本
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:rie - この投稿者のレビュー一覧を見る
なんとなく、もやもやした気分の時や、
いろんなことが上手くいかないなぁと思う時に、
ふと、読みたくなる本です。