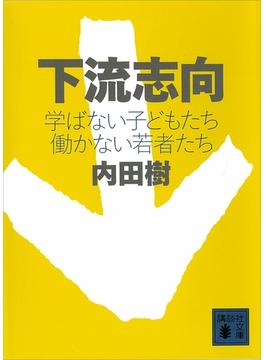- みんなの評価
 10件
10件
下流志向 学ばない子どもたち 働かない若者たち
著者 内田樹 (著)
なぜ日本の子どもたちは勉強を、若者は仕事をしなくなったのか。だれもが目を背けたいこの事実を、真っ向から受け止めて、鮮やかに解き明かす怪書。「自己決定論」はどこが間違いなのか? 「格差」の正体とは何か? 目からウロコの教育論、ついに文庫化。「勉強って何に役立つの?」とはもう言わせない。(講談社文庫)
下流志向 学ばない子どもたち 働かない若者たち
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは


この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
下流志向 学ばない子どもたち働かない若者たち
2011/01/16 09:36
設定された読者と 設定されていない読者
16人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くにたち蟄居日記 - この投稿者のレビュー一覧を見る
数時間で楽しく読み切った。
この本を読むに際しては、自分の立ち位置を良く考えないと行けないと感じる。もっと言うと、著者が本書の読者として設定しているのは副題の「学ばない子どもたち 働かない若者たち」本人ではなく、彼らの親や上司であると僕は理解した。従い、本書の読者が、著者の設定した立場にいるか、いないかで本書の読み方も多分全く変わってくるはずだ。
僕自身は幸か不幸か著者の設定した読者の範疇にいると思う。中年を迎えて、子供の勉強が気になったり、会社においても部下のモチベーションを考えることが多くなっている。その立場から本書を読むと、誠に快刀乱麻であり非常に説得された。但し、「学ばない子どもたち 働かない若者たち」が本書を読んだ場合にどのような反応を示すのだろうか?
「設定されていない読者」として、彼らが本書をどのように読むのかを考えることは中々難しい。そもそも、彼らが本書を手に取るかどうかすら分からない。「学ばない子どもたち 働かない若者たち」という表現には、著者が彼らとの間に取っている一種の「距離感」が有る。その「距離感」に彼らが耐えつつ、本書を読破することが出来るかどうかということは僕の疑問だ。
それにしても内田という方の論にはいつも感嘆する。内田の本の魅力は、読んでいて その全く新しい独創的な論に魅了されるという点にあるわけではない。むしろ「そうそう、僕もそう思っていた」という、一種の既視感に囚われることが多い。自分で考えていたことをすらりと纏めてくれる味方のような印象を受けてしまう。
勿論、そこに内田という方のたぐいまれな話術がある。内田の論を「前からそう僕も思っていた」と思わされてしまった段階で、強烈な説得力になる。なぜなら、その段階で内田の論を「自分の意見」と勘違いしてしまっているからだ。人間は常に「自分の意見」だと思っていることに固執することも確かだ。
2015/05/01 17:56
一気に読みました。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:eri - この投稿者のレビュー一覧を見る
読むきっかけがあってよかった、と感じた本です。また、もう少し早く読みたかった、とも思う本でした。はっとさせられると同時にどこか深く納得できました。そして反省もしました。著者の指摘に当てはまるような授業の取り方をしていたように思ったからです。わかりにくい授業や説明に対して感じていた苛立ちの理由もより明白になりました。時折読み直して確認したいと思いました。
下流志向 学ばない子どもたち働かない若者たち
2010/08/09 09:31
スーパーモラトリアム人間の勘違い
13人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゆきはじめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
社会構造的問題、特に高度な格差の影響が子どもたち若者たちの世代に、文字どおり意思としての「下流志向」という形で現れている、という現状認識と問題提起がされています。
30年ほど前の高度成長時代に現われた「モラトリアム」人間は、社会に対して責任ある言動を取る自信が無いため少し猶予が欲しい、という従属関係を求める存在だったと思いますが、この「下流志向」人間は、自分にとって責任を果たしてくれそうにない社会は無視する、という独立関係を決め込む存在のようです。
若い人たちに、「下流」でも「貧困」までは陥らないだろう、「貧困」といっても「飢餓」にはならないだろうという幻想や、勉強しなくても上手くやれば何とか成るだろうと思っている節を感じるのも、一億総中流世代の保護者を持つという社会構造の裏付けがあるからでしょう。
それもこれも高度格差社会に仕組まれた風潮なのかも知れませんが、変化するのは社会の常ですから、「下流志向」のスーパーモラトリアム人間にも新たな構造変化の波が押し寄せることに、早く気が付いて欲しいものです。
となると、保護者や教育機関の側には「気付き」に導く方策が求められるでしょうか。

実施中のおすすめキャンペーン