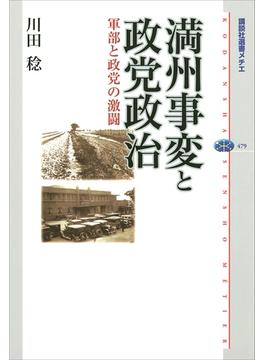- みんなの評価
 1件
1件
満州事変と政党政治 軍部と政党の激闘
著者 川田稔
激闘86日。万策尽き政党政治は終焉した。従来考えられていた以上に堅固だった戦前政党政治が、なぜ軍部に打破されたのか。そこには陸軍革新派による綿密な国家改造・実権奪取構想があった。最後の政党政治内閣首班、若槻礼次郎の「弱腰」との評価を覆し、満州事変を画期とする内閣と軍部の暗闘が若槻内閣総辞職=軍の勝利に至る86日間を、綿密な史料分析に基づき活写する。(講談社選書メチエ)
満州事変と政党政治 軍部と政党の激闘
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
満州事変と政党政治 軍部と政党の激闘
2011/01/06 05:53
いまだからこそ、習うべき歴史がここにある
11人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:良泉 - この投稿者のレビュー一覧を見る
関東軍の謀略により満州事変が勃発した後も、国内では天皇以下、首相・陸相・参謀総長までもが戦局不拡大の方針に賛同した。
しかし、それなのに、歴史は軌道修正されることはなかった。その後の日本の歴史の行方はご存じの通り。満州傀儡国家建設、国際連盟脱退、日中全面戦争、そして第二次世界大戦突入。敗戦。
多くの犠牲と悲劇を生んだ。
なぜ、こんなことになってしまったのか。満州事変以降の内閣と軍部の暗闘、若槻内閣総辞職に至る86日間の攻防を検証する作業が本書である。
戦前政党政治の流れを引き、政党主体の政治を押し進めようとした浜口雄幸の流れを引く若槻礼次郎首相。一方、満州関東軍の石原・板垣ら首脳と国内で彼らと意気を通じる永田鉄山軍務局長ら。両者の持つ戦争観、そして日本の行く末に対する思いは、結果として大きく方向を違えたわけであるが、その発想の出発点はどちらもが、第一次世界大戦であった。
戦車、航空機など機械化兵器が本格的に使われた第一次世界大戦は、それを経験した者に衝撃を与えた。それまでの戦争観を一変させた。もし次に戦争が起こった場合は、必ず国家総力戦になる。兵員だけでなく兵器・機械工業とそれをささえる人的物的資源を総動員し、国の総力をあげて戦うことが求められる。では、そのために国としてどのような準備をしておくべきか。
原敬や浜口雄幸などの政党政治家は、戦争抑止の観点から、次期対戦の防止を主要目的として創設された国際連盟の存在とその役割を重視した。自国の軍事力のみならず、国際連盟の存在と、軍縮や平和維持に関連する多層的多重的な条約網の形成による平和維持システム、戦争抑止システムの構築に期待した。応戦能力と国力が一定のレベルに達していれば、それが対外的に戦争抑止の効果があるものと考え、一定程度の戦力保持で十分であると考えた。
一方、永田鉄山軍務局長らはどのように考えたか。「戦争力化し得べき一国の人的物的有形無形一切の要素を統合組織運用」「国家総動員の準備計画なくしては、現代の国防は完全に成立しない」総力戦に向けての国力強化と、そのために国内だけでは不足する物的資源を求めての満州進出を目論んだ。
どちらが正しかったか。歴史は明確に物語る。しかし、過去の歴史は変えることはできない。日本は進む道を誤り、破滅への進路をとった。
その過ちの道筋を本書でじっくりたどることができる。本書に示されるストーリーは、まるで小説でも読むかのように軽快に読み進めることができる。しかし、ここに書かれていることはまぎれもない現実なのだ。
賢者は歴史に学ぶという言葉がある。歴史が偉大な教師であることがあらためて認識される。
民政党・政友会という二大政党が拮抗し、政党政治の確立期と考えられていた当時においても、あっさりと彼らは軍部に屈することとなった。あっけなく大政翼賛的体制に移行させられてしまった。この歴史は、まさに現代こそ学ばなければならないところであるはず。
誤った歴史は、決して繰り返させてはならない。