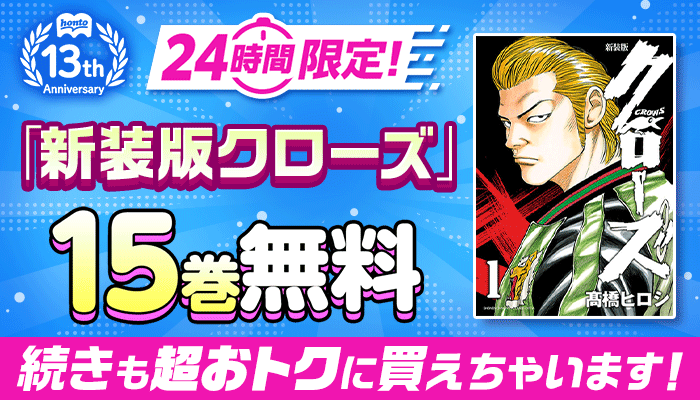- みんなの評価
 1件
1件
日本文化の核心 「ジャパン・スタイル」を読み解く
著者 松岡 正剛
「わび・さび」「数寄」「まねび」……この国の<深い魅力>を解読する!
独自の方法論で日本文化の本質を見通す「松岡日本論」の集大成!
お米のこと、客神、仮名の役割、神仏習合の秘密、「すさび」や「粋」の感覚のこと、「まねび」と日本の教育……断言しますが、日本文化は廃コンテキストで、一見、わかりにくいと見える文脈や表現にこそ真骨頂があるのです。(「はじめに」より)
<本書のおもな内容>
・なぜ日本はヤマトと呼ばれるのか
・神さまをカミと呼ぶようになった理由
・日本人のコメ信仰にひそむ背景
・日本人が「都落ち」にダンディズムを感じる理由
・日本人が七五調の拍子を好むわけ
・世阿弥が必要と考えた「物学」の心
・今の時代に求められる「バサラ」と「かぶき者」
・「伊達」「粋」「通」はなぜ生まれたのか ほか
<本書の構成>
第一講:柱を立てる
第二講:和漢の境をまたぐ
第三講:イノリとミノリ
第四講:神と仏の習合
第五講:和する/荒ぶる
第六講:漂泊と辺境
第七講:型・間・拍子
第八講:小さきもの
第九講:まねび/まなび
第一〇講:或るおおもと
第一一講:かぶいて候
第一二講:市と庭
第一三講:ナリフリかまう
第一四講:ニュースとお笑い
第一五講:経世済民
第一六講:面影を編集する
日本文化の核心 「ジャパン・スタイル」を読み解く
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
日本文化の核心 「ジャパン・スタイル」を読み解く
2022/01/16 13:41
日本文化とは・・・
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:だい - この投稿者のレビュー一覧を見る
○柱を立てる
大和朝廷の国造り、それは“柱の国”づくり
日本の神社では柱そのものが神々(心の御柱)であった
○和漢の境をまたぐ
漢と和の交流が融合し、日本独自の価値観をつくった
中国伝来の鏡は創造上の花や鳥だが、和鏡は身近な松や鶴に置き換えられた
○イノリとミノリ
常民は農作物が無事に育つことを祈って、“ミノリ”を願い“イノリ”の文化をつくった
その中心は“稲(お米)”
その年の五穀を祝するのが“新嘗祭”
新天皇が即位後の最初の新嘗祭が“大嘗祭”
○神仏の習合
日本人はもともと神仏習合的な宗教観を持っていた
仏教や仏像を愛し、伊勢や出雲や鎮守の八幡さんなどの神祇神道に親しんできた
○和する/荒ぶる
和御魂(にぎみたま)柔らかく優しいアマテラス
荒御魂(あらみたま)強くて荒々しいスサノオ
○漂泊と辺境
日本には流された神こそ、かえって恵みをもたらす信仰がある
これは“負け犬”感覚ではなく、“負い目”を許容する感覚である
○型・間・拍子
型のひとつは“形木”(木型か金型)
もうひとつは体の動作が関わる型
日本の型には拍子の“間”がある
○小さきもの
日本人はスクナヒコナに見られるように、小さい事に“みごとさ”“かけがえのないこと”を感じ、思いと想像力をめぐらしてきた
○まなび/まねび
日本において学ぶことの基本は“写す”ことであり、お手本を写す“まねび”に基づいている
世阿弥は芸能としての“ものまね”を通して、“まなび”こそが“まねび”であり、“まねび”がどうすれば“まなび”になるかを追求した
○或るおおもと(ブランドとしての家)
かつての日本は“家柄”“家格”がブランドであった
家がブランドでなくなった原因は、財閥解体であり、家柄の歴史が軽視、反発されてきたからだと思われる
家名を持った家は、永らく“公家”と“武家”が代表してきた
公家のトップは“摂家”次は“清華家”
武家は“平氏”と“源氏”
家のブランドを意匠化したものが“家紋”である
○かぶいて候
歌舞伎は“傾く(かぶく)”という言葉から生まれた
バランスがとれていない者を“かぶき者”と言った
一方、華美で大胆なことをする武士を“婆娑羅”と呼んだ
バサラやカブキモノは斬新な動きと派手な装いで魅せる“歌舞伎”となった
○市と庭
日本の庭の3つの原型
いずれも公の出来事や人が出会う所である
神庭
神が告知や人々の心を鎮めるところ
斎庭
人々を清めたり裁いたりするところ
人庭
市場のこと
○ナリフリかまう
日本文化の非合理的なプロセス
・根まわし
・埒をあける
・さま(様式)
・ナリフリ
“身なり”の“なり”
“振り付け”の“ふり”
日本人はナリフリを磨き、ナリフリを重視することで“様”を作り上げてきた
○ニュースと笑い
日本の情報文化の始まりとして古代日本では、重要な情報は天皇が発し、“ミコトモチ(御言持ち)”が運んでいた
笑いの起源も神々と共にあり、世間にふるまうものであった
○経世済民
経済という言葉は“経世済民”の略
世を経め、民を済う意味であり、国が国を保ち、国が世を治めるコンセプトそのものである
ある時期から、経済となりエコノミーと訳されるようになった
○面影を編集する
面影はそこに居続けるものではなく、何かのきっかけにより現前するもの
日本人は面影を論理で組み立てることはせず、編集により価値観格として発展させた