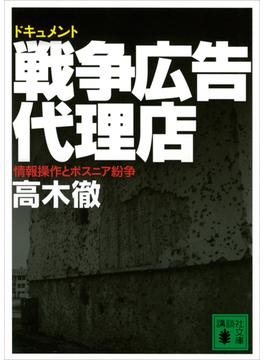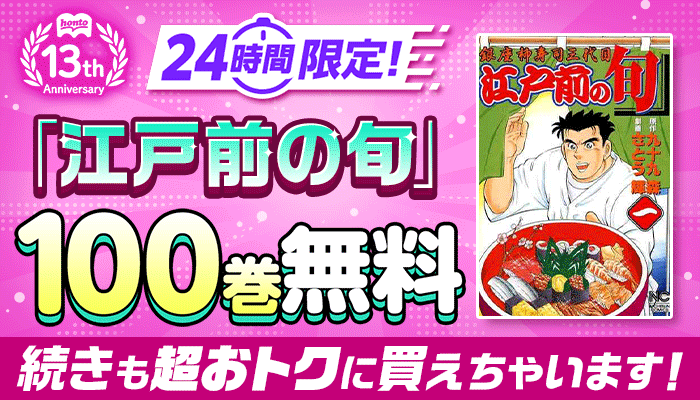- みんなの評価
 10件
10件
ドキュメント 戦争広告代理店 情報操作とボスニア紛争
著者 高木徹
「情報を制する国が勝つ」とはどういうことか――。世界中に衝撃を与え、セルビア非難に向かわせた「民族浄化」報道は、実はアメリカの凄腕PRマンの情報操作によるものだった。国際世論をつくり、誘導する情報戦の実態を圧倒的迫力で描き、講談社ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞をW受賞した傑作! (講談社文庫)
ドキュメント 戦争広告代理店 情報操作とボスニア紛争
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ドキュメント戦争広告代理店 情報操作とボスニア紛争
2007/04/09 10:09
ドキュメント・ボスニア紛争の情報戦、その明暗を分けたもの
15人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:としりん - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本が情報戦を仕掛けられている。米議会における慰安婦謝罪決議問題だ。決議案はこれまでにも何度か提出の動きがあったのだが、今回は議会決議される可能性大だという。安倍総理発言について米メディアの不可思議な歪曲報道が拍車をかけている。
これだけでも大変な問題なのだが、カナダ議会にも飛び火しているということだ。
さらには、南京大虐殺をテーマとする映画が各地で十本以上も制作上映される。
こうした日本を標的とする同時多発的な事件が偶然とは思えない。米メディアの歪曲報道も単にメディア側の認識不足によるものではないのだろう。早急に反転攻勢をかけなければ日本の国際的イメージは低下するばかりであり、深刻な事態にもなりかねない。
このような状況だからこそ、国際舞台での情報戦の凄まじさについて再確認しておきたい。
本書はボスニア紛争が舞台である。ボスニアのモスレム人とセルビア人との内戦であり、どちらが善玉でどちらが悪玉というものではなかった。
それが、米国PR専門会社の支援を受けたモスレム人側のPR戦術により、情報戦でセルビア人側を圧倒、国際世論を味方に付ける大勝利を収めるのである。情報戦で敗れたセルビア側は、のちのコソボ紛争においても、悪玉という先入観により、NATOの空爆を受けるという惨禍をも招くのだ。実にショッキングである。
モスレム人側についたPR専門会社の情報操作、PR戦術の巧みさはさすがに見事なものだ。日本の情報担当者も大いに学ぶべきところがあるのではないか。なにしろ、ありもしない「強制収容所」までデッチ上げることに成功しているのだから。
一方のセルビア側は情報戦にあまりに鈍感だったことが、そもそも敗北の原因だったと言えよう。
先述の「慰安婦」「南京大虐殺」にしても、仕掛けは米国の中国系団体などが噂されている。しかし、その背後にどのような組織が暗躍しているのか明らかでない。
かつての大東亜戦争も、情報戦で敗れ国際世論を敵に回したことが、日本の悲劇の一因になった。そうした過去と重ね合わせてみるにつけても、本書は極めてショッキングであり貴重な書であると言えるだろう。
ドキュメント戦争広告代理店 情報操作とボスニア紛争
2005/07/28 05:22
情報の持つパワーを思い知らされる
10人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:良泉 - この投稿者のレビュー一覧を見る
“国際化”“高齢化”などと並び,“情報化”という言葉は,近未来を語る際のお決まりのキーワードとなっている。
しかし,本書によりあらためて知らされる。「情報」という言葉の持つ幅の広さと,それを有効に活用した場合の底知れぬパワーを。驚愕のドキュメントである。
ヨーロッパの火薬庫と呼ばれたバルカン半島を発信し,世界中に波紋を起した,旧ユーゴスラビア内戦であるが,その勝敗の帰趨(そのすべてとは言わないが)を握っていたのが,「情報」にあったとは。そして,その情報の多くは,アメリカの一民間PR企業によりつくられたイメージであったとは。
当時,誰もが信じた「セルビア人は悪」のレッテル。旧ユーゴスラビア分裂に際し,セルビア人が一方的にクロアチア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,コソボに武力侵攻する構図。「民族浄化(エスニック・クレンジング (ethnic cleansing))」という台所のクレンザーを連想させるようなそのさらりとした言い回しにより,セルビア人による他民族殺戮の様を一層不気味に映し出していた。
しかし,その言葉さえ,ボスニア・ヘルツェゴビナが雇ったPR会社により考えられ,国際世論が持たされた戦争イメージの多くが,PR会社のイメージ戦略にのせられた作り上げられたものであったとは。
(もちろん,戦争そのものが嘘であったというわけではない。客観的に見れば,各民族それぞれに責任がある内戦であったのだ。)
情報戦略が国際世論まで操作し,戦争の行方を左右する。情報戦略により多くの人が戦争で死んでいく。恐ろしい話である。
しかし,筆者はあとがきで言う。
「紛争に介入するPR企業は「情報の死の商人」ということもできるだろう。銃弾が飛び交う戦場からはるかに離れたワシントンで,ファックスや電話(現在ならインターネットや電子メール)を使って国際世論を誘導するそのやり方には,倫理上の疑問が残る。・・・しかし,このような情報戦争という事態を完全に規制しようとすれば,結局のところ政府などの権力が情報を統制支配する社会にするしかない。それを私たちが望んでいないのは自明のことである。」
近未来社会は情報を受け取る側の能力がこれまで以上に問われる社会となるようである。
ドキュメント戦争広告代理店 情報操作とボスニア紛争
2010/01/05 11:42
現代情報戦の最前線
8人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yjisan - この投稿者のレビュー一覧を見る
1991年10月、ムスリム主体のボスニア・ヘルツェゴビナ政府は主権国家宣言を行い、1992年2月29日から3月1日にかけて独立の賛否を問う住民投票を行なった。住民投票は、セルビア人の多くが投票をボイコットしたため、90%以上が独立賛成という結果に終わる。これに基づいて、3月、ボスニア・ヘルツェゴビナはユーゴスラビア連邦からの独立を宣言した。これに反発したセルビア人住民は4月には「ボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア人共和国(スルプスカ共和国)」を樹立、ボスニア・ヘルツェゴビナからの分離を宣言した。このセルビア人勢力が隣のセルビア共和国の支援を受けて軍事行動を開始したため、ボスニア・ヘルツェゴビナは窮地に追い込まれた。
ボスニア・ヘルツェゴビナにとって唯一の活路は、西側先進諸国を主体とした国際社会をこの紛争に巻き込み、更には味方につけることしかない。だが鉱物資源に乏しく地政学的にも特に重要でないバルカンの小国の紛争に、欧米諸国が介入する可能性は低い。そもそも、できたばかりのボスニア・ヘルツェゴビナ政府は外交のイロハも知らない素人集団にすぎず、国際社会における人脈も皆無であった。
そこでボスニア・ヘルツェゴビナ政府外相ハリス・シライジッチは、5月にアメリカの大手広告代理店ルーダー・フィン社を雇い、セルビアの非道性・ボスニアの正当性を世界に伝える「広報活動」を一任する。
国際紛争におけるPR戦略の専門家として作戦の総指揮を執ったワシントン支社のジム・ハーフは、ルーダー・フィン社の人脈と情報網を活かして、膨大な情報を収集し、また発信した。そして傲岸不遜で好色なシライジッチをTV映えのする「ボスニア内戦という悲劇に直面し奔走するヒーロー」へと改造して人々の同情と共感を集め、更にはセルビアの蛮行を「民族浄化」と名付けて人権問題へと押し上げる。このようにルーダー・フィン社は巧みなメディア戦略と周到なロビイングを通じて、アメリカ世論、ひいては国際世論をセルビア非難へと誘導し、やがてボスニア紛争の帰趨を決定づけていく・・・・・・
刻一刻と変わる国際情勢の中で、ジム・ハーフはどのようにPR作戦を展開したか。そしてセルビア側はどう逆襲に出たのか。銃弾飛び交う戦場から遠く離れた国際政治の舞台で行われた「もう1つの戦争」、すなわち「言葉」を武器とした苛烈な情報戦の実相を生々しく描く迫真のドキュメンタリー。張り巡らされる複雑な策謀を、時系列に沿って、平易な文体で、分かりやすく叙述している。
ジム・ハーフらルーダー・フィン社のスタッフは、捏造や隠蔽といった露骨な謀略は使わない。彼等の情報操作の手口はもっと洗練されている。事実の一部を切り取り、微妙に誇張し歪曲し、受け取り手が喜ぶような単純明快でインパクトのある形に加工して与える。大手メディア社や政治家たちは、ジム・ハーフの提供する勧善懲悪のストーリーにいつの間にか絡め取られ、知らず知らずのうちにボスニアに肩入れしていく。世論誘導に邪魔な存在はネガティブ・キャンペーンによって政治的に抹殺する。
ジムらの仕事はキャッチコピーやテーマ設定による「方向付け」であり、勘所を押さえた脚色と演出によって世論を制御していけば、わざわざ捏造や隠蔽を行わなくても、後は人々が勝手に、ジムたちにとって都合の良い「真実」を創出し増幅してくれ、結果的には捏造や隠蔽と同様、いや、それ以上の効果が得られる。嘘をついたり隠したりするよりも、特定の事実をピックアップしクローズアップし「情報」として大量に流してメディアや政治機関に「自発的に」協力者になってもらう方が、望ましい世論を作る上で有用なのである。
本書はジム・ハーフらのプロパガンダの悪辣さを糾弾し、陰謀を企てて戦争を呼び込む「情報の死の商人」としてPR企業を断罪するものではない。それでは「セルビア=加害者、ボスニア=被害者」という従来の図式を反転させただけでしかない。実際ジムが、純粋なビジネスとしては必ずしも割が良いとは言い難い貧乏小国からの依頼を引き受けたのは、「ボスニアを救いたい」という彼なりの正義感も作用している。そして顧客の利益を最優先するのは、民間企業としては当然のことだ。事が戦争である以上、勝つためにはあらゆる手段が用いられるべきであり、宣伝戦の重要性を理解しようとしなかったミロシェビッチがその責めを負うのは、不公平ではあっても不合理ではない。
我々が生きる世界は善玉と悪玉の二項対立で理解できるほど、簡単なものではない。倫理的な善悪はさておき、PR活動を怠れば、セルビアのように国際社会の孤児となり、不当なまでに懲罰されてしまうのが国際社会の冷厳な現実であり、生き残るためには好むと好まざるにかかわらず情報戦略に真剣に取り組むしかない。それが本書の極めて現実的な主張なのである。南京大虐殺や従軍慰安婦問題など宣伝戦で常に後手に回り続けている日本にとって、セルビアの悲劇は決して他人事ではない。
最後に、本書からの引用。
日本政府も、アメリカのPR企業を雇うことはある。だが、PR企業の社員を首脳会談に同席させるなど絶対にありえない。日本の場合は、国際政治の舞台でPR戦略を担当しているのは役人だ。それはどこの先進国もそうである。だが、問題なのは、そのPRの能力において、ハーフが日本外務省の官僚よりはるかに優れていることだ。その結果、皮肉なことに、自前のスタッフを持たないボスニア・ヘルツェゴビナという小国に世界の注目が集まり、国際政治において日本などより格段に大きい存在をもつに至る、という現象が起きた。