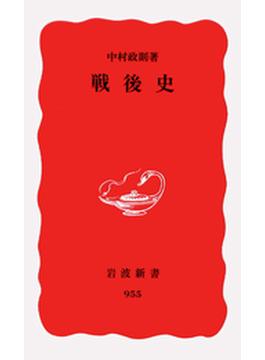- みんなの評価
 3件
3件
戦後史
著者 中村政則 (著)
1945年8月15日の敗戦から60年.戦後を否定的にとらえる論調や歴史意識が強まり,いま戦後最大の岐路に立っている.戦後とはいったい何だったのか.戦争とグローバルな視点を重視する貫戦史という方法を用い,アジアとの関係や戦争の記憶の問題に留意しながら,戦後60年の歴史を総括する.
戦後史
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
戦後史
2005/09/26 00:12
戦後は終わっていない。
13人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:jis - この投稿者のレビュー一覧を見る
戦後60年も過ぎたのに、戦後史と名のつく書物が少ない。通史として激動期を記録しているこの本は、新書でありながら一級の資料ともなっている。まず、参考文献が多い。後書きにもあるように、先行研究及び著者の生活体験をベースに叙述、さらに「聞き書き」を挿入することによって、重層感を出している。
時期区分を4つに分けている。①敗戦と占領(1945〜1960)②高度成長時代・ベトナム戦争の時代(1960〜1973)③第一次石油危機・バブル崩壊(1973〜1990)④湾岸戦争、9.11同時テロ、イラク戦争(1990〜現在)各区分がほぼ15年になっている。
この時期区分を、出来事の項目を追って解説している。それにしても、戦前の戦争、侵略、専制、貧困に対して、戦後の反戦、平和、民主主義、貧困からの脱出と考えるなら、なんとこの60年の慌ただしい時代であることか。
戦後生まれで、時代が混乱している頃に生まれた世代として、この通史はまるで自分たちが生きてきた時代を再確認させ、今ある世界の成り立ちを見せてくれるようである。特に印象深いのは、天皇崩御の1989年がベルリン崩壊と軌を一にしており、これが冷戦の終わりに繋がり、一国主義のアメリカが湾岸戦争に突入していくという時代の回転である。
あのバブル期の異常さも思い出される。土地の投機にうつつを抜かし、アメリカ本土を買い占めない勢いを示していた愚かな日本が、傲慢ゆえの転落を見るほど歴史の因果応報はない。そこには、銀行の思惑と政府の政策の失敗というオマケが付いているが、国民の大多数は、これは異常だと気づいていた。
さて、戦後はいつ終わったのか。敗戦国である日本の戦後は終わっていない。対米従属的関係の解消、アジア諸国に対する、過去の清算が終了するまで終わらない。先の選挙で小泉自民党の圧勝を受けて、またぞろ胡散臭い動きが出ている。
それは、憲法の改正、改悪の動きである。戦後の終わらせ方の問題にもなるが、「戦争への道」か「平和への道」か、ということである。憲法9条の扱われ方で、この国の進路が重大な岐路に立つことになる。と著者の歴史認識が、われわれに警鐘をならす。
若い人達からお年寄りまで、今こそ読むべき良書である。
戦後史
2016/12/30 10:41
戦後史はまだ終わらない
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゴジラ - この投稿者のレビュー一覧を見る
かつて「もはや戦後ではない」といわれたことがありましたが、果たして本当にそうなのでしょうか。
私はまだ対米従属の状態が続いているところをみてそう思っているのですが、タイトルどおり「戦後史」をまとめた本書は戦後とは何か、戦後は終わったのかを考えるうえで重要な一冊だと思います。
戦後史
2006/06/23 05:46
歴史から未来への展望を考えよう
12人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:未来自由 - この投稿者のレビュー一覧を見る
新書版一冊で「戦後史」を語ることなどできるのだろうか。断片的な内容に事件の羅列、そんな本なのかと思いながら読んだが、予想外に濃い内容をともなった書になっている。
「歴史を描くとは、過去を語ると同時に、それが現在に生きる人々にとってもつ意味を問うことであり、できうれば未来への展望を示すことである」と著者はいう。そして、それを示すために戦後を語るうえで、「貫戦史」という視点を提起する。
最初「貫戦史」という説明を読んでも、ピンとこなかったが、読み進めるうちに、現在から未来への視点を示そうとする著者の意図に興味をもった。
戦後を語ろうとすれば、終戦を語ることが必要であろう。著者は言う。「昭和天皇が退位もせず、また自らの戦争責任について何も語らずに終わったことは戦後日本史、とくに日本人の精神史にはかりしれないマイナスの影響を与えた」「アジアで2000万人、日本で310万人の死者を出しておきながら、大元帥天皇に何の責任もないなどということがありえるだろうか」
戦後の出発そのものが誤っていた。そこに「貫戦史」という著者の戦後への視点があると私は読んだのだが、どうだろうか。
歴史教科書問題や「靖国史観」など、今日の一部のイデオロギーがあらわれるのも、戦後の出発点で曖昧にされたがゆえにおこっている問題と読み解いた時、今日の問題が見えてくるのではなかろうか。
著者は、日本の戦後史を日本の経済や政治だけでとらえるのではなく、国際関係のなかでもとらえている。これは重要な視点であり、著者の意図は成功していると思う。
著者の視点の所々に、違和感を感じたり「異見」もあるが、著者の意図を読み取ったうえで読み進めれば、頷ける点が多い。
著者は、最後に「戦後60年にして、いまわれわれは戦後最大の岐路に立っている」と力説する。それは、憲法改悪に反対し、憲法九条の意義をこそ世界に発信する日本を実現することである。