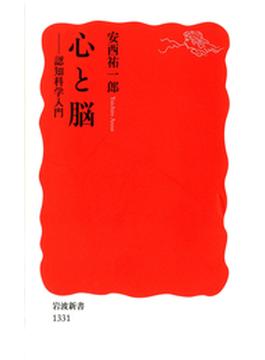- みんなの評価
 2件
2件
心と脳
著者 安西祐一郎 (著)
人間とは何か? 社会や環境の中で,何かを感じ,知り,考える心のはたらきとはどのような仕組みか? それは脳の中でどのようにできているのか? 20世紀半ば,情報という概念を軸にして芽吹いた認知科学は,人間の思考や言語などを解き明かし,社会性や創造性の核心に迫っている.その全体像を描く,またとない入門書.
心と脳
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
心と脳 認知科学入門
2012/02/12 22:03
認知科学という「知的営み」の歩みと成果を、一望のもとにわかりやすくおさめる新書
7人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:拾得 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「新書らしい新書」といってよいだろう。その拠って立つ人間観から認知科学のあゆみ、そして現在の研究の広がりまで、コンパクトに1冊にまとめたものである。広い領域に目を配りつつ、読みやすいストーリーにまとめてくれている。一定水準以上の知識を、門外漢のような私にもすらすら読めるように提示されている。新書の鑑である。
「認知科学」と「学」を付けてしまうと、ひとつの学問領域に見えてしまうが,著者が再三強調するように「完成した学問分野」ではない。著者の表現を借りれば、さまざまな学問領域における「知的営み」である。心と脳の働きへの関心をもつさまざまな学問領域に対し、情報学のインパクトが加わって成立した営みである。近年はこれに脳科学という強力な道具が加わっている。
さらりと読めてしまうが、認知科学すなわち本書が対象とする学問分野は、心理学、神経科学、言語学、人類学などにもおよび、それを一つのストーリーにまとめることは、たいへんな労力であっただろう。新書ゆえのスペースの制約から直接に明示されている文献は限られているが(参考文献は著者のサイトに掲載)、本文そのものに手抜きはない。限られたスペースでも、丁寧な紹介ときちんとしたコメントが添えられている。サブタイトルで「入門」とは謳っているが、それ以上の「認知科学小辞典」といった趣さえある。特に、認知科学の研究史を扱った第2部は、膨大な研究史を手際よくまとめあげている。コミュニケーションも認知科学の重要なテーマと言うが、こうした「まとめあげる力」そのものも、著者が認知科学研究で培ってきたものなのであろうか。
認知科学という知的営みが、人間の心とは何かという根源的なテーマをもとに、いかに大きな流れをつくりだしたのかがよくわかる。ここで得られた成果を、個別の研究領域がどう受け継いでいくのか、それとも新たな「知的営み」の大きな流れが見られるのか,それももまた楽しみである。
心と脳 認知科学入門
2023/03/26 03:00
日本の教育を骨抜きにした罪は重い
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:名無し - この投稿者のレビュー一覧を見る
中教審会長の地位を濫用し、自身の出身で塾長も務めた慶應義塾大学への露骨な利益誘導は、早稲田大学総長の鎌田薫や早稲田大卒で元文部科学大臣の下村博文と結託しての所業。国立大学の体制破壊は日本の学術・社会を破壊したものであり、万死に値する。