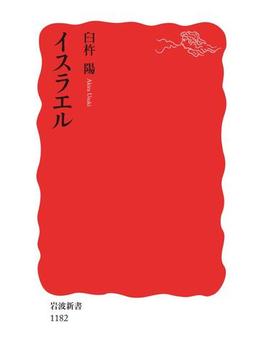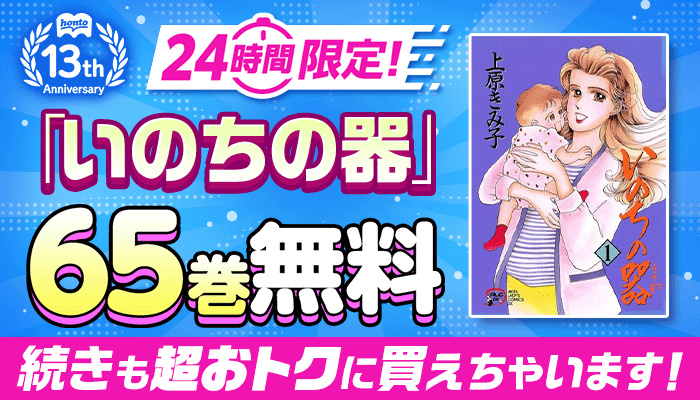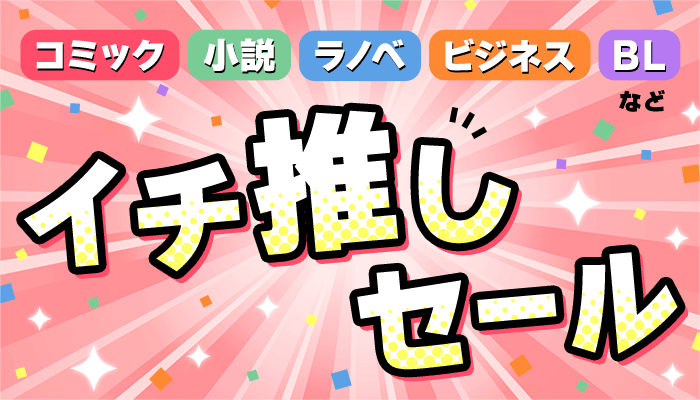- みんなの評価
 2件
2件
イスラエル
著者 臼杵陽(著)
イスラエル国家の暴力性には,いかなる歴史的背景や国内要因が横たわっているのか.統合と分裂のはざまに揺れ動く多文化社会は,これからどこへ向かうのか.シオニズムの論理,建国へと至る力学,アラブ諸国との戦争,新しい移民の波,宗教勢力の伸張など,現代史の諸局面を考察.「ユダヤ国家」の光と影を見つめる.
イスラエル
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
イスラエル
2009/12/06 23:15
ミズラヒーム(=中東イスラーム世界出身のユダヤ人)という視点からみたイスラエル現代史
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サトケン - この投稿者のレビュー一覧を見る
政治史を中心に新書版一冊にまとめた、1948年の建国以前から建国60年を過ぎた現在にいたるイスラエル現代史。
イスラエルにかんする本は無数に出版されているが、本書における著者の最大の功績は、イスラエル社会の現在の実態に即し、従来から日本でも知られている枠組みである、アシュケナジーム(=中東欧系ユダヤ人)とスファルディーム(=1492年のスペイン追放後、地中海沿岸地方に離散したユダヤ人)の違いよりも、アシュケナジームとミズラヒーム(=中東イスラーム世界出身のユダヤ人)の違いという視点からイスラエルを考察していることであろう。
ミズラヒームは、モロッコ、イラク、トルコ、イエメンなどから、イスラエル建国後移民してきたユダヤ教徒である。彼らは、シオニズムという世俗国家の理念とも西欧流のライフスタイルとも関係なく、現在にいたるまでイスラエル社会の下層としての生活を余儀なくされてきた存在だ。
本書は、一言でいってしまえば、ミズラヒームとパレスチナ人を含めたアラブ系イスラエル人という視点からみたイスラエル史である。
イスラエル現代史とは、主流派であったアシュケナジーム中心の世俗国家から、多文化社会への変容によって、きわめて宗教色の濃い国家に変貌させてきた歴史である。
これは、『見えざるユダヤ人』(平凡社、1998)で、ミズラヒームの存在を日本語でははじめて読める形として読者に提示した著者ならではの特色である。移民国家で、多文化社会であるイスラエルは、どのカテゴリーに焦点をあてるかで、まったく異なる像が描かれることになるからだ。
イスラエル建国の中心となった、アシュケナジーム系のシオニストが主流派であった労働党が凋落し、ミズラヒームに加え、エチオピアやソ連崩壊後のロシア系移民も含めた出身地と、宗教的姿勢から複雑にカテゴライズされている現在のイスラエル社会は、著者がいうように、多文化主義性格をもつがゆえに、その反動として逆説的にナショナリズム的な行動をとらざるをえない傾向が強まっている。そうでないと国民がバラバラになってしまうという懸念につきまとわれているためだ。
イスラエルという国家のアイデンティティはいったい何なのか。周囲を外敵に囲まれているという意識から、安全保障以外に国民の共通利害がないのか。
また、還暦をすぎたイスラエルという国家は、今後どういう方向に進もうとしているのか。
多様性と、ユダヤ性強化というナショナリズムとのあいだに存在するジレンマに引き裂かれる状況、これはイスラエルだけでなく、中国も含め、戦後独立した新国家にみな共通する難題であろう。
本書は、一冊の新書本に情報を詰め込んでいるので、ちょっと読みにくいのは否定できないが、じっくり腰をすえて読めば、必ずや得るところは大きいはずだ。読む価値のある労作である。
イスラエル
2009/04/21 21:51
左翼はスターリン主義的な反ユダヤ主義を奉じがちだが。
9人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オタク。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「見えざるユダヤ人」以来注目してきた人が書いたイスラエル論。一番読み応えがあるのは、あとがきだ。イスラエル留学時代にお世話になった防衛大の立川良司氏の「エルサレム」と「揺れるユダヤ人国家」に似た視点でイスラエルが論じられている。左翼によくある第三次中東戦争以来、イスラエル国家そのものを「悪の国家」、ソ連東欧圏から来た反シオニズム=反ユダヤ主義的な論調とは一線を画しているから、読みやすい。
「見えざるユダヤ人」にも書かれているが、共産主義者がユダヤ人とパレスチナ人の共存を唱えていたのだから、皮肉なものだ。ヨーロッパと中東では違いがあるのだろうか?
ただ、1930年代にドイツとユダヤ機関の間に結ばれたハアヴァラ協定によるドイツ・ユダヤ人の持っている資本をパレスチナへ輸出した事は事細かに書かれているが、戦後のルクセンブルク協定から始まるドイツとイスラエルとの関係は素っ気ない。
第三帝国がユダヤ人のドイツからの「追放」から「最終的解決」に転じた戦時中にエルサレムのムフティーがドイツに亡命したのを考えると、何か異様な気がする。別の本で著者はアミン・アル・フセイニーを歴史上の犠牲者視していたが、それは如何なものだろうか?よりにもよって反英闘争でドイツと共闘しようとしたレヒ=シュテルン・ギャングにしても考えものだが、ムフティーを犠牲者視するには抵抗を感じる。
それにしてもユダヤ人がマサダを聖地視するようになったのは、シオニスト達がヨセフスの「ユダヤ戦記」を読むようになってからだろうが、ローマ軍に投降した歴史家が書いた本に書かれたエレアザル・ベン・ヤイルの演説からだから、この本は、そこまで書かれていないが、ある意味では皮肉なものだ。バル・コホバを愛国者扱いするようになったのも含めて。そこまで書いてくれればシオニズム論にも深みが出るのだが。