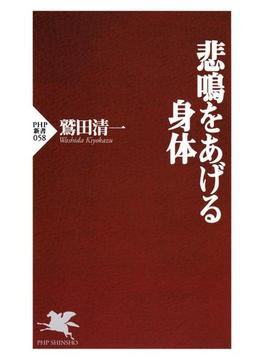- みんなの評価
 3件
3件
悲鳴をあげる身体
著者 鷲田清一
ボディ・ピアシング、拒食・過食、ゆがめられ萎縮する性。本来なら、ひとを癒し、快くするはずの行為が、身体への攻撃として現象している現在。本書では、専門の現象学研究に加え、モード批評などで活発な言論活動を展開し、最近では臨床の知としての「臨床哲学」を提唱する著者が、このような身体状況を濃やかに描写する。 ●第1章 パニック・ボディ ●第2章 からだの経験 ●第3章 からだの幸福 ●第4章 生の交換、死の交換 ●第5章 からだのコモンセンス ●第6章 〈ゆるみ〉と〈すきま〉 著者は、私たちの身体は、今、一方では〈私〉という個の中に閉じ込められ、また、一方では〈私〉という存在から遠く隔てられているという、引き裂かれた状態にあるという。では、そもそも身体に深く浸透しているはずの〈智恵〉や〈想像力〉、そして〈他者との関わり〉の中にある身体性の回復はいかにして可能か。リアルな問いを投げかける一冊。
悲鳴をあげる身体
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
悲鳴をあげる身体
2006/03/12 21:18
「お箸をちゃんともてる、肘をついて食べない、顔をまっすぐに見て話す、脱いだ靴を揃えるなどということができていれば、あまり心配はない」
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:GTO - この投稿者のレビュー一覧を見る
第1章から第3章の身体や食をめぐる論は、さすが鷲田清一、読みがいがある。「身体が悲鳴をあげている」(p.22)と聞くと、内科的疾患や食品の安全性の問題を扱っているのかと思うかもしれないが、健康を気にし過ぎる清潔症候群や摂食障害などの症状を指した表現である。
第3章の「みんなよく似た服装をしているが(していないと不安だが)同じ服装は絶対にいやなのだ。人間というのはまったくの孤立に耐えられるほど強くはないが、共通性のなかに埋没して安心するほど無神経でもないのだ。」(p.69)の指摘は鋭い。制服も流行もその意味では同じである。そして、それは服装だけの問題ではない。
著者は、村上龍の作品が好きなようで、この本でも何カ所かに引用されている。第3章では『イン ザ・ミソスープ』から「普通に生きていくのは簡単ではない。親も教師も国も奴隷みたいな退屈な生き方は教えてくれるが、普通に生き方というのがどういうものなのかは教えてくれない」(p.75)を引用しているが、勢古浩爾の『ああ、自己嫌悪』を読んでみたら、では答えにならないだろうか。若くして分かるべきかは疑問だが。
第4章で登場するカニバリズムに関する論は、本人も「カニバリズムについてくわしく語る資格はわたしにはない。」(p.100)と認めているように、知識が正確でないため、説得力に欠ける。自説を補強するために歪めて解釈していると思われるところがある。4章も終わりの「もつ」「ある」「いる」の議論になるとまた分かりやすくなり、第5章へとつながっていく。
第5章は、鷲田の真骨頂であるファッションの話を経由して、第6章の「間身体性」へ、そして「家族・家庭」が最後に登場する。ここから先は、実際に拒食症や潔癖性の患者と接してきた斎藤学(『「家族」という名の孤独』など)の出番かなと思う。
この本を読んで、これからの社会では確固たる柔軟性と身体に染みつけた勘やコツこそ必要になるだろうと感じた。まずは、大きな声で挨拶してみることだ。「おはようございます。」「いただきます。」…「さようなら。」「ごちそうさまでした。」と。
悲鳴をあげる身体
2001/03/05 11:43
身体に備わる深い能力をムダにしていませんか。
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中村びわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
「からだで憶える規範や原理が確実にある、そんな時代があったのだ。いま、わたしたちのまわりでは世代の交替ということがうまくなりたたなくなっている」
「なにか身体の深い能力、とりわけ身体に深く浸透している知恵や想像力、それが伝わらなくなっているのではないか。あるいは、そういう身体のセンスがうまくはたらかないような状況が現れてきているのではないか」
−−プロローグの問題意識から、「我が意を得たり」と嬉しくなってしまった。
我が意といっても大したことでないのが恥ずかしいのだけれど…。通算して15年以上サラリーマンとして勤めてきて、首都圏のラッシュアワーをいやというほど体験してきた。
すし詰めの列車の中では、ある程度力を抜いていれば人波の動きに力がうまく吸収されて怪我をしにくい。
あらゆる方角へ向けて人が行き交う駅構内では、スロー&クイックで、ダンスやサッカーのように緩急をつけながら、対向者をひょいひょいよけて縫って歩くというコツがある。
私だけの思い込みかもしれないが、ここ数年、そういった体の反応に頼った行動をうまくこなせない人が、特に10代、20代の間に急速に増えてきたような気がしていたのである。
こちらがひょいとよけたのに反応して、反対によけてくれればいい。だのに、反応がトロいというか無いからぶつかってしまう。口が悪いし頭に血がのぼりやすいので、思わず「トロくさい!」と体力のありそうな男の子に言ってしまいそうになり、慌てて言葉を呑みこんでいると、「チッ!」という舌打ちが聞こえてくる。
道端にすわりこんでしまうとか、靴をどったばったさせて階段を下りていくのも「ダサい」「どんくさァー」と思うけれど、価値観が違うので、向こうにしてみれば、こっちの方がよっぽど…なのかなあ。(おばさんの愚痴になってしもうた)
西洋風に「スタイリッシュ」「エレガント」でも、和風に「粋」でもいいけれど、美意識に根ざした所作を身につける意識は、確実に失われつつあると実感する。
「段取り」を失った食事で食事時間を意識できなくなった女性が「過食」に走る。
交感により快楽を得るべきセックスが、マニュアル本により特定部位の性能の問題にずらされてしまい、萎縮していく。
入浴や排泄の「存在の世話」を無条件にしてあげることで人生の肯定感情を育てていくべき幼年時代の危機。
現代社会をとりまく問題があれこれ分析されていきながら、著者の本質的な哲学のテーマ「身体とは何か」「わたしとは何か」「わたしの死とは何か」にまで導かれる。
医療や臓器移植、ファッション、身体のラインをつくる産業にまで論考は広がりを見せながら、「ゆるみ」「すきま」「あそび」を身体の内部に抱合させることの大切さを説いている。
他者との関り合い、つまり社会的な機能を果たして始めて存在する個人の身体ということについて、いろいろな発見をもたらしてくれる、考えるヒントがいっぱいの本で、実に面白かった。
悲鳴をあげる身体
2002/06/26 16:04
ゆるやかな病院化社会への批判
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:森亜夫 - この投稿者のレビュー一覧を見る
幸せを感じることの、第一に、著者は「食」の問題をあげる。なるほど、生まれ落ちて、「食べさせてもらう」ことの満足は一番根源的で深い。その「食」が外部化されていく過程で、家族という共同体が揺らいでいるというのである。
話は「食」に限らない。現代社会において、身体をもっとも管理しているのは、医療である。医療は、身体に関する情報を数値化し、人々の身体に関する技法の共同性を分断する。そのような見方で、医療を語るかたりくちは、決して大げさでないし、攻撃的でもない。しかし、医療への本質的な批判たりえていることには、読者は注意を払うべきである。
医療をトピックとして取り上げるのだが、その各論としては、日常の病院という空間から、脳死移植、体外受精や代理母などの生殖技術にまで及ぶ。しかし、著者の語り口は従来の生命倫理といった堅苦しいものではない(生命倫理にも、堅苦しくない本はあることはあるが、一般的に倫理というものは、堅苦しいものだと私は思う)。
身体が<ゆるみ>と、<すきま>を生きるとき、遊びが生まれ、現実世界のリアテリティが支えられる。<ゆるみ>と<すきま>を失った身体で、現代人はいったいどこにいくのか。
医療によって、ある意味の「身体の共同性」を失ったことが記述されているが、医療そのものへの批判にはならない。しかし、心ある人は、彼のこの本を正しく「病院化社会への批判」として受け止めるだろう。
各章扉の石内都さんの写真が本書の内容と響あって、とても心地よい。