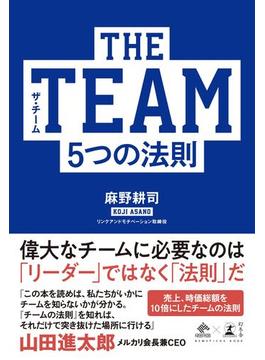- みんなの評価
 4件
4件
THE TEAM 5つの法則
著者 麻野耕司
・・偉大なチームに必要なのは「リーダー」ではなく『法則』だ
「個」の重要性が叫ばれている今。そこからさらなる成長・脱却を遂げるためには、個と個をつなぐ「チームワーク」が重要だ。
しかし、私たちは正しいチームづくりを教わったことがあっただろうか――。
本書は経営コンサルタントとして数多くの組織変革に関わってきた著者が、Aim(目標設定)、Boarding(人員選定)、Communication(意思疎通)、Decision(意思決定)、Engagement(共感創造)という 5つの法則をもとに、成功するチームとはなにかを科学的に解明した、チームづくりの決定版だ!
「『THE TEAM』というタイトルには、チームの法則の決定版を届けたいという思いと共に、読んでいただいたすべての読者の方が「あなたのチーム」をつくれますようにという願いを込めました。 今こそ「チームの法則」によって、ドラマや映画の中では当たり前のように起こる「チームの軌跡」を自らのチームで起こせるようになることを祈っています。 」
(本文「はじめに」より)
・・各界から絶賛の声
「この本を読めば、私たちがいかにチームを知らないかがわかる。
『チームの法則』を知れば、それだけで突き抜けた場所に行ける」
(山田進太郎 : メルカリ会長兼CEO)
「自分のチームづくりがいかに整理されていなかったか、情けなくなった。
もっと早くこの本に出会えていたら」
(岡田武史 : 元サッカー日本代表監督・FC今治オーナー)
「この本は、チームに関する知の結晶だ。
この一冊に何冊もの学術書の知見が詰まっている」
(中原淳 : 立教大学経営学部教授)
・・目次
はじめに 売上、時価総額を10倍にした「チームの法則」
チームを科学する
誰もがチームを誤解している
この国に必要なのは、チームという武器
チームの法則がもたらせた奇跡 他
第1章 Aim(目標設定)の法則~目指す旗を立てろ! ~
「共通の目的がない集団」は「チーム」ではなく「グループ」
「目標を確実に達成するのが良いチームだ」 という誤解
意義目標がなければ作業と数字の奴隷になる 他
第2章 Boarding(人員選定)の法則~ 戦える仲間を選べ~
チームで最も大切なメンバー選びとメンバー変え
チームは必ず4つのタイプに当てはまる
人が入れ替わるチームは本当に駄目なのか?
チームには多様性が必要だという誤解
「ゴットファーザー」より「オーシャンズ11」型のチームが強い 他
第3章 Communication(意思疎通)の法則~最高の空間をつくれ~
実はチームのコミュニケーションは少ない方がいい
ルール設定の4つのポイント
コミュニケーションを阻むのはいつだって感情
「理解してから理解される」 という人間関係の真実
「どうせ・しょせん・やっぱり」がアイデアを殺す
己をさらして心理的安全をつくり出す 他
第4章 Decision(意思決定)の法則~進むべき道を示せ~
誰も教えてくれない意思決定の正しい方法
「独裁」vs「多数決」vs「合議」
「正しい独裁」はチームを幸せにする
独裁者が持つべき「影響力の源泉」
第5章 Engagement(共感創造)の法則 ~力を出しきれ~
超一流でもモチベーションに左右される
モチベーションを科学する~気合いで人は動かない~
チームのどこに共感させるか
エンゲージメントを生み出す方程式
[特別収録]チームの落とし穴~あなたのチームは足し算か、掛け算か、割り算か?~
[最終章]私たちの運命を変えた「チームの法則」
THE TEAM 5つの法則
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2020/08/16 00:08
組織でなく、チームづくりのための一冊
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:本野 - この投稿者のレビュー一覧を見る
Goodpatch代表と著者の対談「離職率40%から8%への道のり、組織崩壊の状態からグッドパッチが立ち直れた理由」から興味が出て、本書を読みました。
チームの状況(目的)に合わせてどのようなチームを作ればよいか、説明してあります。
これまで組織論やマネジメントの本は何冊か読んできたのですが、組織やマネージャーでなく「チーム」にフォーカスした本には初めて出会いました。
そのため経営者、マネージャー、一社員という目線でなく、チームを支えるメンバーという目線で読むことができます。もちろんマネージャーにもおすすめですが。
タイトルにある「5つの法則」は1章につき1法則が書かれており、必要なところだけ読むこともできるため、手軽に読めます。
【5つの法則】
・Aim(目標設定)の法則[旗を立てろ!]
・Boarding(人員選定)の法則[戦える仲間を選べ]
・Communication(意思疎通)の法則[最高の空間をつくれ]
・Decision(意思決定)の法則[進むべき道を示せ]
・Engagement(共感創造)の法則[力を出しきれ]
斬新な内容はないですが、学術的根拠に基づいたVUCA時代のチームづくりに必要な一冊です。
2021/05/13 07:22
チームには
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
共通の目的、というのが当たり前なようで、その目的意識を持たせることが重要なのですね。単なるグループとチームの違い……納得です。第四章の野球や駅伝、サッカー等四つのスポーツ競技に分けての解説は、大変よかったです
THE TEAM5つの法則
2020/06/21 11:40
まずは法則を知るべし
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:じょんたま - この投稿者のレビュー一覧を見る
私も一応部下がいる立場ですので、このチームをいかによい状態で保つかということには、日々悩まされていますし、なかなかこれはという解決法が見つかるわけではありません。というわけで、この本を読んでみたわけです。
本書が提唱する5つの法則は、章ごとに具体例とともに説明されていて、とても読みやすいです。構成としては以下のとおりです。
第1章 Aim(目標設定)の法則〜目指す旗を立てろ! 〜
第2章 Boarding(人員選定)の法則〜 戦える仲間を選べ〜
第3章 Communication(意思疎通)の法則〜最高の空間をつくれ〜
第4章 Decision(意思決定)の法則〜進むべき道を示せ〜
第5章 Engagement(共感創造)の法則 〜力を出しきれ〜
チームによっては、自分たちで人員を選定できないとか、なかなか本に書いてあるとおりにはいきませんが、私なりに気になったところをいくつか紹介します。
まず、チームには共通の目的が必要だということが書かれていました。当たり前のようですが、これは意外と難しいですね。昔であれば、プライベートより仕事優先みたいな前提があって、誰もが仕事上の目的意識を共有していましたが、今はプライベート重視の人も多く、あくまでも仕事は仕事と割り切っています。もちろん、割り切っていても、仕事上の目的くらいはもってもバチは当たりませんが、そこまでのモチベーションがない人が増えているように思います。
次に、3つの目標について説明されています。行動目標、成果目標、意義目標。正直、私の場合は成果目標で終わっていますが、意義目標がもてるといいですね。ここは参考にしなければいけません。
そして、チームタイプという考え方もユニークです。サッカー型、野球型、駅伝型、柔道団体戦型。環境の変化度合いを縦軸に、人材の連携度合いを横軸に考えています。さて、我がチームはどれに当たるのか。意外と駅伝型かも知れません。
誰もが難しいと感じているのが、コミュニーション。「どうせ」「しょせん」「やっぱり」という言葉が出てこないチームを目指したいものです。
この本を読んだら何かが変わるのか、それは分かりませんが、リーダーという立場の人も、あるいは、何らかのチームに所属している人も、基礎知識としてもっておいた方がよいことが書かれていることは間違いありません。参考文献なども丁寧に紹介されているので、この本を羅針盤にして、さらに興味のある分野を開拓していけるといいかも知れません。