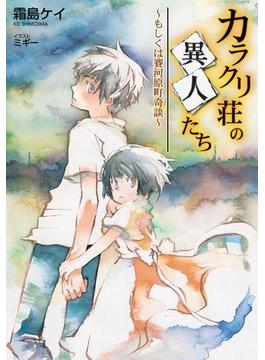- みんなの評価
 3件
3件
「カラクリ荘の異人たち」シリーズ
父の頼みで下宿することとなった賽河原町にある「空栗荘」。一見なんの変哲もない古いだけの建物だと思っていたら、そこは妖怪の住む「あちら側」の賽河原町との境目にある建物だったのだ。勝手に歩き回る市松人形に、喋るカラス、ろくろっ首……。不思議がしぜんとそこに「居る」世界が、扉の向こうに広がっていた。そんな不思議を「不思議」とは思わない、空栗荘の住人達も癖のある人ばかり。――太一のちょっとかわった下宿生活が始まった。 ※電子版は文庫版と一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください
カラクリ荘の異人たち4 ~春来るあやかし~
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
カラクリ荘の異人たち もしくは賽河原町奇談
2008/10/30 20:58
バスをおりたら、妖怪の町でした。
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:紅葉雪 - この投稿者のレビュー一覧を見る
以前より、この作者は『人間以外のモノ』を書いたら抜群で、さらには『人間』と『人間以外のモノ』の関係や、『人間』を描くのが上手いと感じていた。
今回のこの作品も同様である。
家庭の事情から下宿することになった高校生の太一。ところがその下宿先、カラクリ荘に向かう途中、何と妖怪の町へ……? カラクリ荘は『人間の世界』と『妖怪の世界』の接点に建てられていたのだ。
そこの大家を始め、住んでいるのも、一癖二癖どころか、三癖も四癖もあるつわものばかり。さらには人間だけでなく、人形の『付喪』(つくも)アカネを筆頭に、愛敬(?)たっぷりの妖怪たちも登場する。
他人と上手くコミュニケーションがとれない太一も次第にそのペースにまきこまれ、ついでに不思議な事件に巻き込まれ……。
と書くと、最近のYAに多くみられる何ともありふれた話のようだが、これはあくまで「あらすじ」を纏めている自分の力量が不足しているため。
話は申し分なく楽しめる。
一番の魅力は活き活きとした、個性的なキャラクターたちだろう。
一昔前の古き良き時代(?)の日本にあるような、決して他人を放っておかない、親密で世話好き、言い換えればお節介な人間や妖怪たちを描きながらも、作者はまた同時に不思議な距離も保っている。
強いて言うのであれば、誰もが心の底に持っている痛みや傷、他人には触れてほしくない所には登場人物たちにも触れさせず、でも放っておくのでもなく、少しだけ距離をとって気にかけている……そんな優しいスタンス。
この作者の本は、デビュー当時の絶版になってしまっているものを除き、ほぼ全て読破している。自分にとっては、中身やあらすじを確認しなくても、
「霜島ケイ」という名前だけで安心して本を購入できる、数少ない作家の一人でもある。
今年8月に、続編「カラクリ荘の異人たち2」
も出版されているので、この本を読んで気に入ったという方には、そちらもお勧めしたい。
カラクリ荘の異人たち 4 春来るあやかし
2010/04/29 11:16
もっとカラクリ荘の話を楽しみたかったです。シリーズ完結が、少し寂しいです。
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:紅葉雪 - この投稿者のレビュー一覧を見る
カラクリ荘の異人たちの完結編。
自分の感情すらよく掴めず、人間関係にも難がある太一が、ゆっくりゆっくりとだが成長していく物語は、この巻で完結した。
今回は、太一のクラスメートが巻き込まれた話をはじめとする中編が3作。
季節は春。
今までほとんど話をしたことがなかったクラスメートに、太一は突然声をかけられる。
しかも彼から言われた台詞が。
「幽霊って、みたことあるか?」
結局、詳しい話は聞けないまま会話は終わってしまう。
しかし相手は「カラクリ荘」を知っていた。
だからこそ、そこに住む自分に助けを求めてきたのでは? とも思う太一。普段なら「自分には関係ない」と放ってもおく。
だが、なぜか放っておけなくなってしまう。
そして再び『ヒトではないもの』との騒動に巻き込まれてしまうことに。
今回は、三作とも太一の成長を感じさせる話だった。
カラクリ荘のオーナーが、彼の部屋番号を0144(「おひとよし」と読む)号室と決めた理由も判るような。
表紙のカバー絵からもわかるように、太一が柔らかい笑顔を浮かべている。……そんな話だ。
私ごとになってしまうが、このほぼ二か月、自分は「本が読めない状態」になってしまっていた。時間的制約やら何やらというより、精神的なものが大きすぎたように思える。
難題が山積みし、細胞分裂をしているのではと思える量の仕事、さらに様々な人間関係のストレスは頂点、……ついに本を読む気力すらなくなったというべきか。
『本を読むこと』でストレス発散をしていた自分が、その道をふさがれ、余計に精神状態が悪くなる悪循環のスパイラルに完璧に巻き込まれた。そしてそれに気が付いてもいなかった。
だから今まで読んでいて、発売日には必ず手にしていたシリーズの幾つかも、まだ手にしてないものもある。この本もそうだった。
ただこのシリーズは友人が非常に楽しみにもしていて、そちらから「新刊でたけど、まだ?」コールにさらされ、買った次第。
だが表紙に魅かれ、ふとページをめくったとたんに、すっと再び話に入り込めてしまった。
今まで忘れかけていた「カラクリ荘」の世界に、ぐっと引きこまれてしまった。
本当に久々に『読むことができた』本になった。そしてこの本をたった一冊『読めた』ことによって、再び他の本にも目を向ける余裕ができてきたのだ。……やっと。
寝ることや食べる事、いやむしろ無意識のうちに呼吸をしているのと同じように、何も考えなくても、ごく自然に本を読むことが自分の生活のリズムになっていた。
あまり本を読まない友人から、『本を読むには気力がいる』と言われた事もあり、『そうかもしれない』と思った事もあるにはあるが、その意味が自分には全く判っていなかったと、今ならば思う。
あまりにも、自然に読書をしてきたために。
だが今ならばそう振り返れるこの二カ月であったし、さらにその事に気がつかせてくれた貴重な一冊になったとも思う。
カラクリ荘の異人たち 3 帰り花と忘れ音の時
2009/04/29 22:13
あと一冊で終わるのが、もったいないです。
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:紅葉雪 - この投稿者のレビュー一覧を見る
カラクリ荘の異人たち、シリーズ3作目。
あいもかわらず「人外のモノ」たちと不思議な接点を持ち続ける、カラクリ荘。
今回は中編が3作。
そのうち2作が、傷ついた心を持ち、どこか他人を拒絶する太一の内面に深く関わっていくことになる。
季節は冬。
「人間でないモノ」と顔を突き合わせる毎日にもすっかり慣れた太一の元に、義母の「鈴子さん」から手作りクッキーが送られてきたことから、彼はさまざまな心の葛藤を抱くことに。
なにより太一は「鈴子さん」が苦手。
もちろん彼女だけでなく、「人間」が苦手なのは変わりがないのだが……。
まず一作目(第1章)。
「探している『本』を見つけてほしい」と、ヒトではない『モノ』に頼まれたカラクリ荘の大家。
その『モノ』を、うっかりカラクリ荘に招き入れてしまったのが太一だったため、彼もその『本探し』に関わる事に。
太一と大家が見つけた『本』とは。
そしてその『本探し』を依頼してきた『モノ』の正体とは。
それが、鈴子さんからのクッキーと同様、太一の心を揺らす、小さな伏線になっていく。
そして第二作(第2章)。
冬休みを控え、太一が頭を痛めているのが、『正月に里帰りするべきか』という問題。
正直、彼は帰ることに乗り気でないのだ。
カラクリ荘の面々が正月も残ることをこれ幸い、自分もそうしようとするが。
普段は穏やかな、同じ下宿人のレンから、「家に帰るべきだ」と言われ、動揺する太一。彼はレンからきつい言葉を投げつけられる。
「なんか言い訳してたけど、本当は君は、ここに逃げていたいだけだから」
さらに。
「君は他の人の事なんか、何も見てないよ。見てないくせに、都合のいいようにばかり考えている。それで何かうまくいかなくなると、全然考えようともしないで仕方がないどうでもいいって投げだすんだ。(……略)」
それは太一に対して真摯に向き合おうとしている人々に対して、すごく失礼だと。
ちなみに補足するなら、レンは植物と意思疎通を図ることが出来る。それだけでなく、他人の心の痛みまでもダイレクトに感じてしまい、だからこそ太一とは違う意味で人ごみにはいられない。カラクリ荘の大家にかけられた「暗示」で、かろうじて今の生活をしていられるのだ。
そのレンに対し猛反発する太一。
そんなとき、太一は「ろくろっ首」から「決して開けてはいけない」と念をおされて、蓋をした徳利を預かることに。
カラクリ荘の大家へ渡して欲しいと頼まれたのだが、ひょんなことから徳利が壊れてしまい、さらにその中に閉じ込められていた「身体が溶けてしまった雪女」に取りつかれてしまう。
だが逆にその雪女「六花」と会話する内に、太一は自分に欠けていたものや、レンが言いたかった事に気付いていく。そして正月に家に戻ることを決心して……。
その後にも一波乱というか、もう一捻りを加えた展開を迎えるのが、この作者の巧いところだと思う。太一が里帰りする第3章は、それこそ太一でなくとも「目が点」状態になってしまうだろう。
実際に自分も「おっと!」だった。
登場人物の心の内を丹念に、だが冷静に綴っていく筆力には脱帽。そしてそれに合わせた登場人物たちの設定も見事だと思う。
この作者の別のシリーズ(そちらもライトノベルだったが)でも感心していたのだが、本当に読み応えがあり、ライトノベルは敬遠しがちと言う方たちにも、自信を持ってお勧めできる。
あとがきによると、あと一作でシリーズは完結予定だとか。
もう少しカラクリ荘の話を楽しみたかったのも本音なのだが。