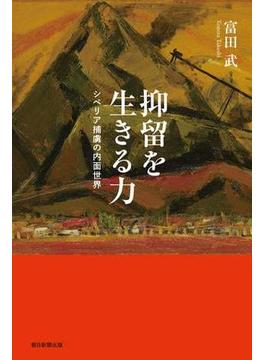- みんなの評価
 1件
1件
抑留を生きる力 シベリア捕虜の内面世界
著者 富田 武
飢え、酷寒、重労働という「三重苦」に耐え、シベリア捕虜たちが生き抜いた強さはどこから生まれたのか。残された絵画、俳句・川柳・短歌のほか沿海地方などの楽劇団の活動から、苦難の体験を「生きる力」に変えた芸術表現や精神性をたどる。
抑留を生きる力 シベリア捕虜の内面世界
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
抑留を生きる力 シベリア捕虜の内面世界
2022/07/06 07:57
シベリア抑留の研究とは
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オタク。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
保阪正康に将校達の振る舞いを語ると怒ると書かれた若槻泰雄もそうだが、この著者が一緒に仕事をしているがイデオロギー的に対極な長瀬了治といい、何故シベリア抑留の研究書を書く人は書き方が極端なのだろう。「内面世界」というけれど、「反動」と見なすか、それとも「サムライ」と見なすかで揺れるソ連当局に物申す将校と特権の上であぐらをかくが吊し上げられるとだらしない将校や下士官、「民主運動」のアクチーブと見なすか、それともソ連に追随する事しか出来ない元共産党員や元共青員と「反ファシスト」の間にいる普通の日本兵がほとんど見えてこない。
いくら何でも赤軍やモンゴル人民軍に日本では19歳で召集されるから、それ以下の年齢の少年飛行兵や少年戦車兵を見分けてくれ、だなんて無理だろう。それに元山空のように海軍の部隊もあるから、予科練出身者などがいるわけだし。それでいて何故か「男狩り」が出て来ない。若槻泰雄の「シベリア捕虜収容所」にパナマ帽と背広という、どう見ても民間人にしか見えない身なりの人が兵隊達と一緒に映っている写真が掲載されているのを見ているはずなのに。それと何故か南樺太で参戦した国民義勇戦闘隊を見落としている。
日本軍の敵の捕虜になった将兵の取り扱いについて、昭和16年の戦陣訓を前面に出したら、昭和14年のノモンハン事件での赤軍とモンゴル人民軍の捕虜になった将兵についてはどうなるのか?それにここにもあるように戦陣訓は東條英機陸軍大臣が制定したのだから、海軍や「地方」人には呪縛されなかったのか?
昭和25年に共産党が非合法化されたかのような記述はレッド・パージと混同しているのだろうけれど、若槻泰雄が袴田里見除名の頃に原稿を書いているのに、袴田里見自身が実弟だと書いている袴田陸奧男を「袴田里見の実弟と称した男」と書いているみたい。
ドイツ軍将兵の「反ファシスト」は食べる為に「ソ連の手先」になったと書いているが、中公新書の「シベリア抑留」で言及しているハインリヒ・フォン・アインジーデル伯爵は必ずしもそう言えないではないか。それでは産経の「20世紀特派員」2で書くところの「カシスト」という侮蔑的な言い方と変わらない。著者は気がついていないが、「日本新聞」が「反動」歌謡の「異国の丘」を批判した時に「内地」からやって来た「パンパン」という言葉を使った事を批判しているが、食べる為に「反ファシスト」になったドイツ軍将兵をこき下ろすのは同じ「論理」だ。