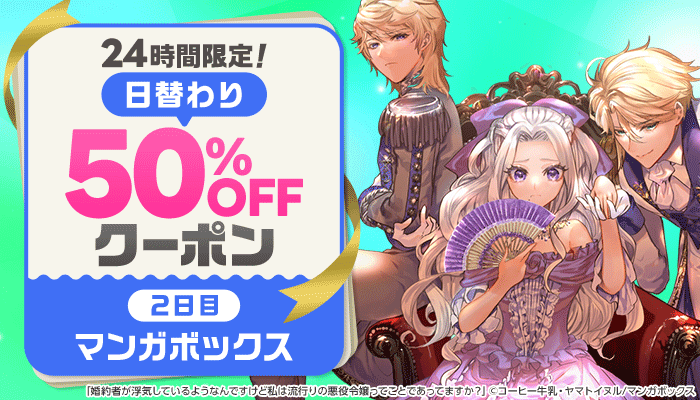- みんなの評価
 1件
1件
マイノリティデザインー弱さを生かせる社会をつくろう(ライツ社)
著者 澤田 智洋
「澤田さんには、目の見えない息子がいる。僕はそれを、うらやましいとさえ思った。」
佐渡島 庸平氏(コルク代表)
日本テレビ「シューイチ」、NHK「おはよう日本」などにたびたび出演。
本書の著書は、SDGsクリエイティブ総責任者ヤーコブ・トロールベック氏との対談をはじめ、
各界が注目する「福祉の世界で活躍するコピーライター」澤田智洋。
こんな話があります。
「ライター」は、もともと片腕の人でも火を起こせるように発明されたものでした。
「曲がるストロー」は、寝たきりの人が手を使わなくても自力で飲み物を飲めるよう作られたものです。
それが今では障害者、健常者、関係なく広く利用されています。
障害者にとって便利なものは、健常者にとっても便利だからです。
つまり、「すべての弱さは社会の伸びしろ」。
ひとりが抱える弱さを起点に、みんなが生きやすい社会をつくる方法論。
それがマイノリティデザインです。
大手広告会社で名だたる企業のCMを手がけるコピーライターだった澤田氏は、
自身の息子が目に障害を持って生まれてきたのを機に、「広告をつくらないコピーライター」となりました。
そして、活躍の舞台を広告業界という「マス」の世界から、福祉業界という「マイノリティ」の世界にスライドさせ、
「弱さ」を起点に社会課題を解決する仕掛け人となります。
その活動は多岐に渡ります。
・福祉器具である義足をファッションアイテムに捉え直した「切断ヴィーナスショー」
・視覚障害者の「足」と寝たきりの人の「目」を交換する「ボディシェアリングロボットNIN_NIN」
・過疎化地域への移住を劇的に促進させたPRプロジェクト「高知家」
・ユナイテッドアローズと立ち上げた、ひとりの悩みから新しい服をつくるレーベル「041」
・運動音痴でも日本代表選手に勝てる「ゆるスポーツ」etc……。
苦手、できないこと、障害、コンプレックス=人はみな、なにかの弱者・マイノリティ。
テレビやウェブで話題になった数々の仕事、その全貌を書き下ろした、ビジネス書としては澤田氏初の書籍となります。
マイノリティデザインー弱さを生かせる社会をつくろう(ライツ社)
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
マイノリティデザイン 「弱さ」を生かせる社会をつくろう コピーライターが福祉の世界に飛び込んでみたらできたこと
2021/09/19 00:22
見えない息子と向き合って
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:第一楽章 - この投稿者のレビュー一覧を見る
広告代理店に勤める筆者が授かった長男が、目が不自由であることがわかってからの奮闘記(活躍といってもよいかも)です。
「父親がキレイなCMをつくったところで、視覚障害のある息子は見れない」という苦悩から、「マイノリティに「広告的なやり方」で光を当てられないか?」と考え、苦手/できないこと/コンプレックス/障害といった「弱さ」を、”克服しないといけないもの”ではなく”社会が解決すべき課題、むしろ「伸びしろ」”と発想を転換し挑戦と企画を重ねていきます。
「当事者の声を聴くこと」、そして「まずはやってみること」という筆者の姿勢はとてもいいなと思いました。抽象的なターゲットやペルソナを設定するのではなく、目の前の困りごとを解決する。例えば、車椅子の車輪に巻き込まれず脱ぎ着もしやすいスカートが欲しい、そんな声に応えようとユナイテッドアローズと協働した「041(オールフォーワン)」。それが結果として、機能性もデザイン性も兼ね備えた商品の開発となります。初めからマスを相手にしようとすることの限界と、マイノリティに着目してそこから展開していくことの可能性の双方を感じました。
写真でも見えるかなと思いますが、この本のカバーには小さな凹凸があります。点字です。調べてみたら「マイノリティデザイン」と書かれていました。視覚障害を持った息子さんへの思いを感じました。わたしにとっても「なんて書いてあるのだろう?」と思って調べ、点字を読むことに挑戦するきっかけになりました。(わたしには指先の感覚だけではわからず、結局凹凸を目で確認したのですが…)
この本のメッセージを象徴すると思ったので付記します。