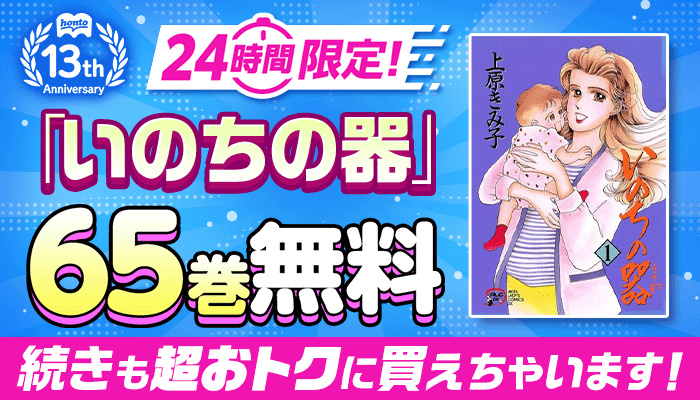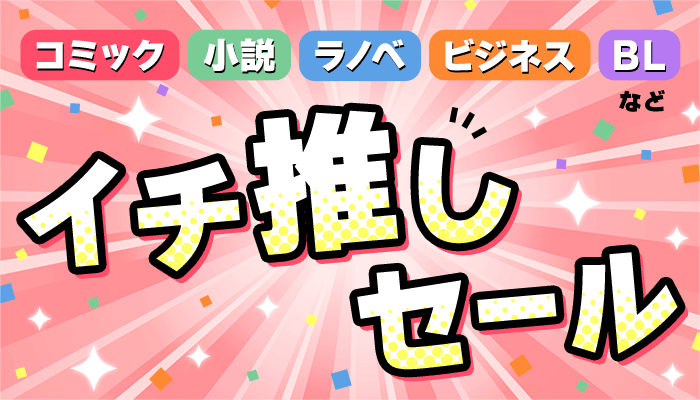私には「整理すること」が必要だった!
2008/01/25 00:24
10人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ポカ - この投稿者のレビュー一覧を見る
行き詰っていた。
色々なことに行き詰まった感があり、途方にくれていた。
なにがいけないのか、
なにからはじめればいいのか、
なにをすればいいのか、
なにも進まず、なにを進めればいいのかもわからなくなった。
そんなときこの本に出逢った。
出逢った途端、閃いた。
まだ読んでもいないのに、その白い表紙を見て思った。
わかった!と思った。
私には「整理すること」が必要だ、と。
読んでみて、やはり思った。
自分が把握しきれないものが溢れると混乱する。
机の上も、アタマの中も整理しなければならない。
まずは、モノの把握。
溢れかえる机の上のものを整理することからはじめた。
机の存在の根本は、作業すること。
たったそれだけ。当たり前のことだ。
なのに、それを見失っていた。
一番重要なこと、コトの本質を中心において整理する。
モノの用途と所在を把握すること。
そして、机の本質を取り戻すこと。
かなり苦労したけれど、机の真っ白い天板を取り戻したとき、
心のなかの霧がぱぁっと晴れたような気がした。
やりたいことが見えてきたような気がした。
ただ、机の上を整理しただけなのに、
気分が晴れやかになっている。
机の上を整理しながら、
モノの整理はもちろん、アタマの中も整理されていったのだと思う。
空間、情報、思考、全てが混沌としていてはなにも出てこない。
整理して、把握する。
自分の中で把握できることでしか、コトを進めることは出来ないと思う。
把握するためには、整理しておくことが必要なのだ。
整理するということは、その本質を見つけること。
外してはいけないものを見つけること。見失わないこと。
本質さえ中心においておけば、きっと迷うことはない。
とはいえ、モノであれ、情報であれ、思考であれ、
色々入ってくれば、また溢れて入り乱れる。
溢れて本質を見失ったのなら、また整理すればいい。
そうやって、メンテナンスしていくことが必要なのだ。
この本で、「整理する」という考え方のエキスを教えてもらえた。
だからといって、
可士和氏のようになんでもスカっと整理はできないだろう。
それでも、なんとか自分なりの整理をしていこうと思っている。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kiyo - この投稿者のレビュー一覧を見る
同じ考え方であると感じましたが
実行されている内容が高度であり、その点で非常に参考になりました。
投稿元:
レビューを見る
なぜアイデアが尽きないのか?
「デザインの答えはいつも自分ではなく相手のなかにあるから」
「デザインの整理と問題解決は、同じベクトルでつながっている。」
「他人事を自分事に出来るから」
総括:
世の中のグッドデザインは、様々な要素が整理しつくされているプロダクト。
投稿元:
レビューを見る
クリエイティブディレクターの仕事って、おもしろいですね。ノウハウ本というよりも、彼の仕事の事例本として、おもしろかったです。2007/10/10読了
投稿元:
レビューを見る
本書はクリエイティブ/アート系が好きな私の友人のブログから知った。 これまで佐藤可士和氏の活動については全く知らなかったのだが、ユニクロを始め、楽天・国立新美術館などの著名な企業・施設・商品のロゴを手がけている。
整理法の書籍に関しては野口悠紀雄氏の「超整理法」を皮切りに多数の書著が出回っている。 その多くがビジネスマンの日常業務に焦点を当てたものであり、また著者もその様なバックグラウンドを持つ方々だったりする。 しかし、本書の面白いところは、通常ならば感性が要求され、整理とは縁の薄いイメージのあるデザイナーが書いている点である。無論佐藤可士和氏自身が整理好きであるということもあるだろうが、「デザイナー」故の面白い整理法の切り口におどろかされる。
本書では
1. 「空間」の整理術
2. 「情報」の整理術
3. 「思考」の整理術
の3点を軸に整理方法を展開しているが、デザイナーでなくとも十分に一般利用できる内容である。 それに加え、可士和氏のデザインを考えるプロセスを過去の事例から説明しており、可士和氏のデザイナーとしての資質に驚嘆するばかりである。
投稿元:
レビューを見る
表紙だけでなく、中身の構成も非常にシンプルで読みやすいです.机キレイにしてます?KW:「思考の言語化」「仮説をぶつけること」
投稿元:
レビューを見る
ま、タイトルどおりのただの整理術について書かれている本ではない。如何にアイデアをまとめるか、頭の中の整理を中心に語っている。
関係は薄いが、著者が始めて自分で書いた本というのには驚いた。
投稿元:
レビューを見る
アートディレクター佐藤可士和の整理術。身の回りの整理だけではなく、情報や思考の整理といった目に見えないものの整理におけるまでの著者自身の整理術を仕事(プロジェクト)上の事例を織り交ぜつつ紹介している。クリエイティビティというのは整理をしっかりとやり現象を的確に認識すれば、おのずとその中に見つかるものだと言っている。情報が氾濫し混沌としている現代にとって、「整理」というものの重要性を語っていた。
投稿元:
レビューを見る
整理整頓ができない=仕事ができない
先輩たちにも言われ、今月に入ってずっと悩み続けてる私。なんとか打開したくて買ってみた。
結局この人はもともと整理が得意な人だったんだから…という気持ちも捨てきれてないけれど、空間の整理→情報の整理→思考の整理の順に難しくなっていく(らしい)のに思考の整理からがんばろうとしてたと気づけた。
あの狭い机はかわらないから自分で整理しながら仕事をしなければいけない。
佐藤氏は鉛筆たても置いてはいけないとゆってたけど、全部机に入れて出してしまってするのはうちの場合、引き出しすらも自分のものではないから難しい。
でも不要なものを捨てること、手放してみること、それで本当に大切なものを見つけること。これは整理するのに欠かせないし、もしかしたら人間関係でもいえてるのかもなぁと思えた。
まずはかばんにはいるものしかいれないで会社に行くことから実践したい。仕事に追われるのではなく、仕事を追いたい。来週からはこのスタンスで。
それに今治のタオルの話のところで自分と接点を持つことの大切さについて考えさせられた。他人事でやってる今の仕事、自分事に考えられるようになれたら…ちょっと難しいけど。
投稿元:
レビューを見る
超人気クリエーターが初めて自ら出版した本。タイトルからは一見、広告に関する本なのかどうか分からないが、実際に読んでみると、文字通り著者の身の回りの整理整頓術から発展し、デザインの企画を考える際の論の立て方まで発展する。また、実際にこの本の内容自体もうまく整理して書かれているので、一気に読み進めることができる。読後感としては、自分の思考も自然と整理され、不思議とクリエイティブな気持ちになってしまっていた(笑)。
投稿元:
レビューを見る
佐藤可士和がどうやってクリエイティブなアイデアを生み出しているのかを知りたかったのだが、どちらかというと問題解決手法を説明するような本になってしまっていて、ちょっと残念。彼のような仕事でも問題解決手法が重要なのがわかったのはそれはそれで良いけど、期待と内容がずれていてちょっとがっかり。本のタイトルと内容もずれを感じる・・・
投稿元:
レビューを見る
「物理的」整理術を「思考的」整理術に応用した本。「物理的」整理術に関しては耳が痛かった。本当に日々使うものは限られているので、無駄なものは捨てる勇気を持たなければならない。確かに持っていると安心なものは沢山あるが、それらの大半を捨てたとしても何の支障もなかったりする。「思考的」整理術に関しては、要はカオス状態にある事柄を整理し、何かしらの範疇に分類して行く中で物事の本質(Priority)が見えてくるという内容。それだけ。全く内容のないロジカルシンキングの本みたいだった。
投稿元:
レビューを見る
携帯電話のデザインを手がけ、UT立ち上げに携わったアートディレクター佐藤可士和がいかにしてデザインをつくっているのか、実例に則して紹介している。そこが面白い。アイディアの源泉は「整理」(「空間の整理」「情報の整理」「思考の整理」)にある。「空間の整理」は単純で、取り入れやすい。得るものはあったのだけど、整理術としては、ちょっと期待はずれな感は否めない。
投稿元:
レビューを見る
この本につられて会社の机周りの大掃除を行う。社長に「おうっ・・・すごくすっきりしたな」と言われた。
でも、たしかに机がすっきりしていると、やるべき案件1つだけに集中できる。
改めて再読してインフォノートに書きつけておかねば。
投稿元:
レビューを見る
整理することの大切さを再認識した反面当たり前のことを当たり前に書いているような気もした。しかしその「あたりまえ」を当たり前にすることが困難なのかも知れない。とりあえず部屋掃除します。