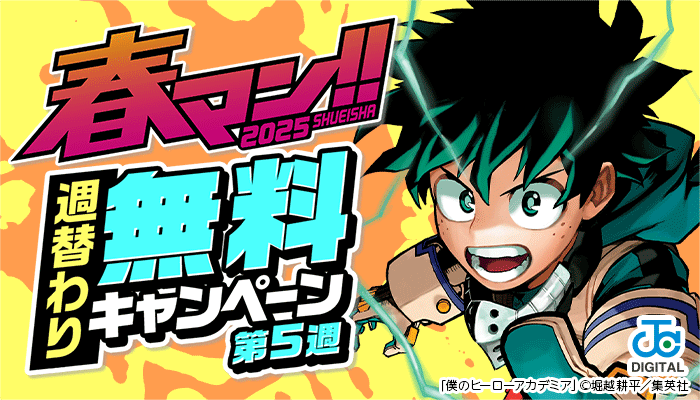1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ごまたまご - この投稿者のレビュー一覧を見る
題名通りビギナーなので知恵が欲しくて購入しました。ビギナー特有の疑問に答えてくださり、とても満足しています。
投稿元:
レビューを見る
生きてる実感のない人は自殺をしやすく、そしてそういう人は伝説になるのだなあ、と思った。
学生運動なんかどうでもよくて、彼女は単に集団のなかにある自分を客観的に見て成長したいと思ってたんだろう。
そして彼女の自殺の最たる原因は失恋だろうなあ。
自分が女であることを嫌悪して嫌悪しつづけた彼女は、結局はそれで命を落としてしまったのかもしれない。
生きていれば多分ただのおばちゃんとして普通に暮らしていたと思うのに。
そう考えれば考えるほどこの時代への興味は高まる。
投稿元:
レビューを見る
自分と作中の高野悦子は別の時代を生きているのに、深い共感を覚えた。同じ大学に通っているというのもあるのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
「独りであること、未熟であること、それが私の『二十歳の原点』である」この言葉を残して、貨物列車に飛び込んだ女子大生、高野悦子の手記です。読んでいてあまりにも純粋で、そして痛々しかったです。
「独りであること、未熟であること、それが私の『二十歳の原点』である」
高野悦子
いやぁ、やっと読み終えた。これは、有名なのでさらりとしか書かないけれど、二十歳で鉄道自殺を遂げた大学生の十四歳から亡くなる直前までのころを綴った手記である、僕がこれを知ったのは、単なる『ジャケ買い』で、彼女のことは当時何にも知らなかった。
でも、経歴を見て、『あぁ、やっぱり何か惹かれるものがあったんだなぁ。』というものがあった。やはり、僕のなかにも彼女は、いる。だけど、彼女は純粋すぎた。
僕は、年をとったので、永遠に時間をとめてしまった彼女よりは少しだけいろいろなことを知っている「つもり」である。だから、いろいろなことがあってもなんとか、生きていける。読んでいてつくづく思うことは、あそこまで自分と格闘すればその先に待っているのは「死」のみである。
ということに他ならない。彼女の手記を見て、「純粋」さと「危うさ」というのは本当に表裏一体であると感じずにはいられなかった。だけどここまで自分と向き合ったのか?ときかれると正直「ウーン」といわざるを得ない。
読んでいて非常に内容が生々しく、後半の死に向かっていく過程はあまりにも痛々しいものだった。
でも、一見の価値はあると思う。できれば十代、二十代のときに読んでほしい本である。
投稿元:
レビューを見る
今の20歳前後の読者の中で、大学紛争の時代を知っている人はほとんどいないはずだ。その意味で、この日記は「遠い世界の出来事」かもしれない。でも、この人の苦しみや孤独感は、少なからぬ若い人の共感を呼ぶと思う。
この本は、1969年6月24日、20歳で鉄道自殺をとげた高野悦子さんの日記である。書かれた順で言えば、中学~高校時代の「二十歳の原点 ノート」と、大学1・2年生の「二十歳の原点 序章」に続き、大学3年生となった1969年1月~6月までの日記が収められている。刊行順は「二十歳の原点」(71年)「序章」(74年)「ノート」(76年)だが、僕は書かれた順に読んできた。
高校時代から自分を厳しく律しようとする真面目な女の子だった著者は、大学に入って学園闘争やサークルの活動を通じて自己と社会との関係を問い続けていた。日記の前二巻は、この時期のことを書いたものだ。
この巻では、それが激流に変わる。学園闘争を背景に、著者の孤独感が強まっていく。学問や部活といった話題は後景に退き、詩や、バイト先の男性への恋愛感情や、酒、タバコといった諸々が彼女の中心になっていく。そして、五月の末には家族との「訣別」……。
こっちはもちろん結末(彼女の自殺)がわかって読んでいるんだけど、それにしてもこの展開に「そんなに焦らなくていいのに」と声をかけてしまいたくなる、痛々しい展開の日記だ。
なにが彼女をそこまで追い立てたのだろう。それは僕には最後まで実感を伴った形ではわからなかった。もしかして、この年代の人の焦りを読みとく感性を、30代の僕はもう失っているのかもしれない。だからよけいに、若い読者がどう読むのかを知りたいと思う。
なお、最後の日の日記には、「旅に出よう」という言葉から始まる詩も書かれている。この翌日に自殺するという文脈を抜きにすれば、静謐なトーンの素敵な詩だ。これもぜひ読んでみてほしい。
日記の後にある父親・高野三郎氏の文章「失格者の弁」も良い。なんとか娘の死をめぐる「物語」を編み出して一つの決着をつけたいという思いに満ちていて、解釈せずにはいられない姿が読む者の胸を打つ。僕にはむしろ、日記本編よりもこの父の痛切な手記が印象的だった。
(補記)「ノート」「序章」「原点」という三部作をまとめて読む時、「彼女は結局「書くこと」によって殺されたような気もする。書いて内省を深めることで、どんどん自分を追い詰めていったような。この点、国語教員として、どう考えればいいんだろう。
投稿元:
レビューを見る
私が全共闘時代の興味を持った時に読んだ高野悦子「二十歳の原点」は是非読んでほしい。私たちは多かれ少なかれ人との繋がりで生きています。その繋がりを断ち切り、自分の強さと信念を磨くことで孤高に生きていこうとした女子大生。彼女が鉄道自殺に追い込まれる直前までの日記を書籍にしたもの。
投稿元:
レビューを見る
「独りであること、未熟であること、これが私の二十歳の原点である」
1969年6月、立命館大学の学生であった高野悦子が自ら命を絶った。享年20歳。『二十歳の原点』は彼女が書き残した日記である。1969年1月2日、20歳の誕生日からそれは始まる。
立命館大学文学部に入学した後、彼女は読書やアルバイト、そして学生運動との狭間で、自己を確立しようと努める。考え、迷い、悩み、叫び、行動を起こす。喫茶店「シアンクレール」で思案にくれ、あるべき自分を模索し続ける日々。
時として、その終着点は「死」に向けられた。しかし多くの場合、彼女は「生」への強い想いを抱き続ける。明るさとせつなさを交錯させながら、強く生きることを切望する。
6月22日、彼女は長い長い日記を綴る。睡眠薬を大量に飲みつつも、それに打ち勝って眠らずにいられるかを試し、最後に一編の美しい詩をうたう。それが彼女の最後の日記となった。
20歳の日々。何を考え、どのように生きていただろうか。そんなことを考えさせられる本でした。
投稿元:
レビューを見る
『二十歳の原点 ノート』『二十歳の原点 序章』に続けて読んだ。死の直前まで綴られた最後の日記は、文章の密度・緊張感ともにどんどん高まってきている。
学生運動にもどこまでも真面目に取り組む著者。アルバイト労働者としての自分を見つめ、学費不払いを選び、それをきっかけに家族との訣別を選ぶ。家族には安らぎを感じつつも、自身が思想を深めれば深めるほど、食い違いが大きくなっていくところなどはよくわかる。だが当時の雰囲気や思想の内容にリアルな実感を持てない私には、距離を感じざるを得ないところがある。
しかし「四角い言葉」を操る一方で、恋人を求め、孤独感に苛まれる二十歳の女の子である。ふとした拍子に等身大の声が垣間見えることがある。もしかしたら彼女自身の中で分裂していくものがあったのかもしれない。自殺という言葉が繰り返し語られ、そもそも死への傾きを持っていたような気もするのだが。
もし彼女が日記を書いていなかったら、違った結末があり得ただろうか?
「書くこと」が人を生かす力になる例も私達はたくさん知っているが(例えば『フリーダム・ライターズ』など)、人を殺す危険な力にもなり得るのか。
三冊を通じて、最も心を揺さぶられるのは実は巻末のお父さんの手記かも知れないと思う。死後ずっとノートを読みながら対話を続け、死の理由を読み取ろうとする。ノートが残されていたのは家族にとって良かったのかどうか…。答えのない「対話」にとらわれ続けるのだとすれば辛いことのようにも思える。
ベストセラーになった当時、同年代の若者たちはどのように読んだのかな。
著者は生きていればまもなく62歳。
投稿元:
レビューを見る
3年前、浪人していた頃の自分によく似ていた。
頼るべきsomeoneの不在がいれば結果は違ったものになっただろう、それはsomeoneに限らず家族、宗教、郷土愛、なんでもよかったのかもしれない。国の大きさに対抗しうるだけの大きさを彼女の中で持ち得る依拠対象があれば。それがなかったため自分にしか頼れず、しかし拠り所たる自分の弱さに直面し。
投稿元:
レビューを見る
村上春樹の『ノルウェイの森』、その映画版を見ている時に、ふと高野悦子とこの本のことが思い出されたのだけど、この二人はどちらも同じ1949年生まれ、そしてこの2冊はどちらも同じ時代の大学の雰囲気を色濃く残している。
といっても私は彼らの子ども世代より、まだ若い。この時代の虚無と自殺の描かれ方には、どうしても共感できない部分がある。
十分なレビューとはとてもいえないけど、とりあえず今の自分には、ここまで。
投稿元:
レビューを見る
ラジオで、紹介されて読みました。
十代の今、読んで良かったなって思います。
彼女は、孤独に殺された
そのように感じました。
投稿元:
レビューを見る
わたしも14歳からノートに書いている。14歳とはそういう時期なんだと思う。生きていてほしかった。生きているものは必ずいつかは死ぬのだから。みんな変わっている。普通の人間なんていない。自殺する人が特別変わっているのではない。ただ自分らしくいたかっただけなのに。素直な人。
投稿元:
レビューを見る
著者の考えた記録がまとめられてます。日々をとてもしっかり考えて生きているなぁという印象。読書に対する意識も大学生時代の自分とは比べ物にならないくらい高い。
でも、キャッチーなコピー(と自分が思ってるだけ)をつけるとしたら「その思考の中心には、反権力という若さがあった。」って感じです。大学生らしさが随所に感じられます。
途中までの自殺しないぞという決意、最後の詩、最終的に自殺することになるまでの心境、このあたりの関係性をもっと読み取れるといいんだけど、なかなか読み取れていません。
投稿元:
レビューを見る
読後感はちょっと不思議な感じ。そもそも著名人ではない人の日記という物を読んだことがないので、書かれていることがどれくらい重みがあるのか良く分からなかった。どうでも良いような日常のつぶやきの様であり、その後主人公の運命を決める告白であるような、読んでいる時は判断がつかない。もう一つは学生運動。私が学生だった時は、学生運動が盛んであった時からそんなに年月が経っている訳ではないのだが、学内にその雰囲気はほとんどなかった。かろうじて建物の落書きがその当時を偲ばせるくらいで、全くリアリティはなかった。従って、学生運動を戦った人のリアルな話を聞いたことがなかったので、妙に新鮮というか、もっとはっきり言うと、そんな訳の分からない建て付けでやっていたのか、というのが正直なところ。そして、最も不思議なのが作者が自殺した経緯。日記を読む限りは全く分からない。確かに死をほのめかす記述は沢山出てくるのだが、死を決意したという風には感じられなかった。作者は死の直前に両親に会いに行き、決別したようであるが、娘の死に直面した両親の心の痛みはどれほどであっただろうか。娘がまさか自殺するとは思わなかった?ここに書かれているのは本人の日記であり、後記も本人の略歴のみなので、両親の思いというのは記されていない。ある意味本書全体が淡々としているのである。それが両親の狙いなのかもしれないが、作者の心の叫びを感じた読者からすれば、不思議というか、何か心の核心に届かないもどかしさに繋がっている。
投稿元:
レビューを見る
二十歳の原点三部作の最終巻。
三巻目では二巻の終わりから漂う狂気感というか,追い詰められている感じが全編にわたります。ここまで落ち着いて書けるのはすごいの一言。

![二十歳の原点 [新装版]](https://img.honto.jp/item/2/265/360/10126100_1.jpg)