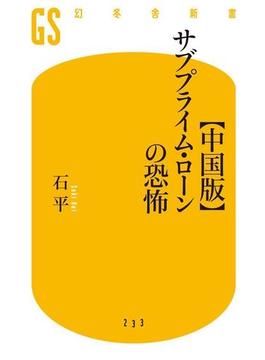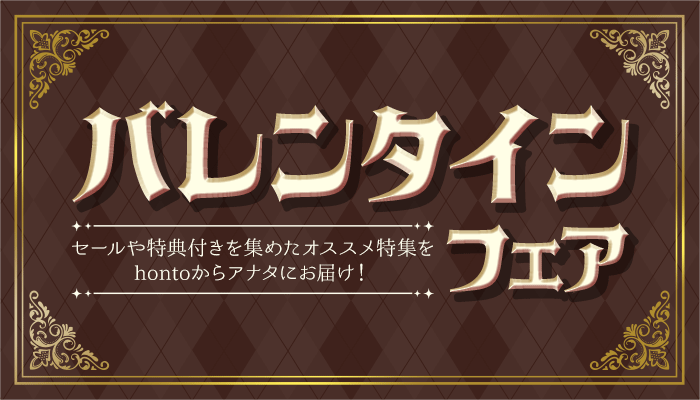指摘しているポイントは鋭い
2011/10/04 11:22
7人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:塩津計 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は産経新聞等にチャイナに対し、常に厳しい視線を投げかける石平氏が書いたチャイナ経済行き詰まり論である。なぜチャイナの経済が行き詰るのか。それは、ひとつには政府が進める強引な経済成長優先主義の結果もたらされた膨大な、あまりにも膨大な通貨の膨張の結果、不動産がバブル化し、終息の見通しの無い悪性インフレに経済が陥り、富が一部の権力者に集中する一方、大多数の庶民には年金も社会保険もなく、格差が天文学的レベルにまで拡大しているというものだ。1978年を基準にするとチャイナのGDPは92倍になったが、広義のマネーサプライは705倍に膨らんでいるという。これでインフレが起きないわけがない、不動産バブルが起きない訳がないというのが石平氏の見立てだ。
チャイナ経済の大きな特色は、チャイナという国は税金を集められない国で、本来、儲からないからこそ国が税金を投入して実施すべきインフラ整備の多くが「儲かります」という間違った前提の下、収益事業として国営企業や第三セクターによって実施されているという点だ。本来、インフラと言うものは儲からないし、基本的にタダで国民に使用させる類のものだ。だから日本ではガソリン等に高い税金を課し、道路特定財源として年間5兆4千億円を集めて、市道・国道のような一般道路の整備を行っている。これとは別に、国際的に見てもかなり高い高速道路料金を設定し、年間2兆6千億円を集めて高速道路を整備している。それでも高速道路の大半は赤字で(黒字は東名名神、中央)それが故に道路公団の借金は40兆円まで膨らんだ。日本国有鉄道の借金は民営化の直前、24兆円まで膨らんだ。日本の新幹線は昭和39年当時、世界銀行からの融資を得て実現に漕ぎ着けたものだ。こうしたモノを、チャイナは恐ろしいほど短期間に、全部、政府系金融機関からの借金で行っている。なぜチャイナは税金を国民から取らずに借金でインフラ整備を進めるのか。それはチャイナをはじめとする旧共産主義国では国民から税金を取らないのではなく取れないからなのだ。共産主義と言うのは福祉もインフラも全部政府がタダで作ってくれるもので、税金はゼロの無税国家だった。だから国民に納税意識のかけらも無く、今になって税金を取ろうにも取れない社会的風土が出来上がっている。ここが旧共産主義国の国家運営を著しく難しいものにしている。しかし儲からないものは儲からない。そもそもチャイニーズは日本人ほど豊かではない。1人当たり国民所得は日本の10分の1程度にすぎない。にもかかわらずチャイナが整備した高速道路網は2010年9月時点で65000キロ(日本は7642キロ)、高速鉄道網は6920キロ(日本の新幹線は2176キロ)。これが如何に無謀な数字であるかは、もうみただけで分かろうというものだが、このチャイナの急ぎ過ぎが先のチャイナの鉄道事故でグロテスクな形で世界中に知れ渡ってしまった。既にチャイナの鉄道省が抱える借金は24兆円を超えているという。これはもう破綻するしかない。
チャイナの経済は基本的に内需では無く輸出で成り立っている。しかもその過半は外資による組み立て工程の、いわば下請けだ。チャイナは世界の工場では無い。世界の下請け工場と呼ぶべき存在だ。100円ショップに製品を供給している東莞市周辺に軒を連ねる中小企業は労賃が伸び悩む中で塗炭の苦しみの中にあるという。なぜならチャイナの唯一のウリは「価格が安いこと」しかないので、人民元があがっても、労賃を下げてでも安い価格を維持していかないと、仕事がミャンマーやベトナム、バングラデッシュに移ってしまうからなのだ。こうして昼夜兼行のチャカポコ労働をチャイニーズは継続せざるを得ないのだ。
チャイナが貯め込んだ3兆ドルの外貨準備も、実はこうした貧しい中国のなせる技であることを我々は知るべきだ。普通、国が豊かになれば、それに見合いで輸入が増える。輸出主導で経済を拡大した我が日本も、それに見合ってどんどんどん輸入を増やしていく。外貨とは基本的に輸入代金に充てるもので、輸入を上回る外貨をため込んでも、それは使い道のない紙きれで、国民の生活にはあまり役に立たない。ところがチャイナは人民元が値上がりすると経済そのものが可笑しくなると思い込んでいるので必死になって為替介入し米国債を買いまくっている。そのグロテスクなまでのドル買いの成れの果てが3兆ドルもの外貨準備に表れている。これはチャイナ経済の強さの証明では無く、弱さの証明なのだ。
「不動産業はチャイナ経済の基幹産業だ」と言ってのけるチャイナの要人の話もお笑い草だ。既に北京の不動産を全部売ったらアメリカが買えるんだそうだ。これもどこかで聞いた話で、以前、日本を売ったらアメリカが四つ買えるといわれていたっけ。しかしこれもおかしな話で、不動産と言うのはエンドユーザーに売り抜けない限り完結しない商売で、そのエンドユーザーとは末端の庶民なのである。つまり不動産価格をあげすぎると庶民にとって住宅は高根の花となり手が出なくなる。手が出なくなると買い控えが起き、そうなると不動産は庶民でも買える水準に暴落せざるをえない。こういうメカニズムになっているのである。チャイナの不動産需要の6割は転売目的の投資需要だと本書にも書いてある。既に夜になっても全く電気のともらないゴーストタウンがチャイナのあちこちに出来ているという。目先のあぶく銭に追われ、不動産バブルに目を奪われるチャイニーズたちの終わりは近い。既にチャイニーズエコノミストは2012年にチャイナの不動産は半値になると宣言している人もいるそうだ。最近、香港とチャイナの株式が底が抜けたように大暴落しているのも、そのことを先取りしているのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
中国系帰化日本人の石平の本は2冊目だ。
石平は日本人としての感性を持っているように見えて、持ちきれていない。日本で育った人間は伊勢神宮で「日本」を感じることはないからだ。
その過剰さこそが石平が中国育ちであることを如実に表現するが、私は、石平の中国評価に関してはかなり信用している。日本評価に関しては半分ぐらいのしか信用していない。
それでも、彼のような人が日本を愛し、中国ウォッチングしてくれていることは日本人が中国を知る上で非常に高い価値があることである。これからも彼の著作は事あるあるごとに読もうと思う。
中国や韓国が崩壊するというシナリオはもうこの数十年見続け飽き飽きしているのだが、私は自分の感性を非常に重要視していて、その感性からももうそろそろだな。と感じている。それは、経済指標や経済白書からのものではない。街を見て、その建物を見て人を見て感じる普通の感性だ。
本書で語られているような中国の「先軍政治」や「暴動」や「投機」のあり方を見たとき、歴史の必然というものが顕わになる。具体的に何年何月というほど私はうぬぼれているわけではないが、必ず中国は混乱の渦に巻き込まれる。経済のソフトランディングだとかハードランディングだとか言っているレベルではないものが必ず起こる。今、正にギリシャ国債のデフォルト問題、欧州の金融・信用不安や米国のドル不信から広がる全世界的な信用不安・株安の最後の砦として中国がクローズアップされているが(ある意味日本の円高も日本がクローズアップされている証拠ではあるが)、私たちはこの30年成長し続けた中国という国を間違いなく誤解している。中国が成長しないといっているのではなく、問題は中国の偏りなのだ。偏見を取り除き、感情をかなぐり捨ててもなお中国は異常である。異常が許されるような世界ならば、私は、世界を信用しない。
私は正に今中国を信用していない。それを再認識することができる本だと思う。
投稿元:
レビューを見る
中国の経済成長の歪みについて書きます。日本経済で個人消費が弱いと言われながらGDPの60%は個人消費。それに対し中国は37%でしかもその比率は下がりつつある。大量の銀行融資を行うことで経済成長を維持してきたがその反動で設備余剰がひどい。消費も弱く設備も余剰、ということで本来ならデフレ傾向に向かうはずが過去供給したマネーサプライの過剰によりインフレが止まらない。今年6月以降各地でちょっとしたことで暴動が起きるようになっており、ネットの普及とあわせ党の高級幹部ですら批判の対象になるようになってきている。中期的に見ても急速な老化(一人っ子政策のため、若年層が少ない)に襲われるのは既定の事実であり、難しい経済運用を迫られている。
投稿元:
レビューを見る
中国の成長率の失速、不動産バブルの正体、それに対応策を見いだせずにジリ貧になってる政府の実情を描く。
消費者物価指数や各都市の不動産価格など、数字を引き合いに出しながら論じていた。
成長率を率いていた「外需」と「投資」→リーマンショック前後から外需が失速→量的緩和を際限なく進めて金余りに→内需がふるってない企業は調達資金を不動産で運用→不動産バブルの流れ。
財政出動も出尽くして、インフレとバブルの板挟みになってる様子はよくわかった。
後半4割は経済というより、それに関係する中国の社会や軍の影響力の話に進めて、若干風呂敷を広げ過ぎな印象も。
中国の経済の実情が、データとあわせてよく理解できた。
できれば、世界各国とどう連動してどう影響していくかも論じて欲しかった。
投稿元:
レビューを見る
中国経済の急激な成長の二大牽引車が輸出と不動産というかなり歪な形になっており、不動産を支えているのが政府による過剰流動性供給。過去30年で経済規模は92倍に拡大したがマネーサプライは702倍、GDPの2倍以上のマネーサプライが不動産の高騰、バブルを招いたと驚くべきデータが紹介され、バブルの崩壊とインフレは不可避というのが中国経済のジレンマだと。中国経済頼りの日本も他人事では無い。一方で、此だけ非常識な規模のマネーサプライをしたにもかかわらずインフレ率が10パーセント程度に収まっているとはある意味驚くし、ハイパーインフレの亡霊に怯える日銀はどう思うのであろうか。
投稿元:
レビューを見る
大枠はよくいわれてる不動産投機と過剰な流動性による
インフレの話。でも細かい情報は中国ウォッチャーではないので
参考になりました。以下ネタばれ。(僕にとっては備忘録)
---------------------------------------------
1978年 GDP 3645億元
M2 859億元
2007年 経済成長率 13%
2008年 第一四半期 10.6%
3月消費者物価指数 8.3%
第三四半期 9%
11月 内需拡大10項目 低所得者向け住宅/建設促進
銀行融資規制撤廃 48兆円
2009年 GDP 33兆5400億元
M2 60兆元
経済目標 保八
03月 新規融資放出額 4兆5800億元
第一四半期固定資産投資額 前年度比28.8%アップ
年間個人消費総額 12兆元=約144兆円
不動産購入額 約6兆元
年間新規融資総額 9.6兆元=約115兆円
GDP 33.5兆元=約403兆円
*日本は474兆円と30兆円。
就職率 68%
2010年09月 M2残高 約69兆元=約837兆円 (前年度比19%増)
10月 01月からの名目GDP 約29兆元=323兆円
*先進国ではマネーサプライ/GDPは50%〜70%
個人消費率/GDP 37.5% 91年 48.8%
過去10年間 経済成長率 10%
固定資産投資 25%
2011年03月 北京新築平均販売価格 前月同月比−10.9%
06月 北京売れ残り不動産時価 約1兆元=12兆円
エリートと金持ちは「西遊記」をやり高級感部は「紅楼夢」を
楽しみ、地方政府は「三国演義」を繰り広げ庶民は「水滸伝」
を演じてみせる。
暴力抗法 土下座嘆願
投稿元:
レビューを見る
外資系に勤務しているのですが、先日社内会議があり、今後のわが社の成長は中国やインドの成長にかかっていると確認したばかりです。
そんな状況にいる私にとって、中国が崩壊するとは信じたくないですが、この本を読むと不安になってしまいます。
この本の著者(石氏)は、中国の実情に詳しい方であり、彼が2012年には崩壊をし始めると警告しているのである程度の覚悟は必要なのでしょうか。
サブプライムローンの崩壊の影響は日本を含めて全世界に悪影響を及ぼした中で、中国だけは一時期からV字回復したと世間では言われていますが、それは中国政府の金融政策(異常な量的緩和)によるもので、いずれ崩壊するとのことです。
以下は気になったポイントです。
・2011年6月現在、北京市で売れ残りの不動産在庫面積は、すでに3300万平方メートルで、時価では約12兆円であり、平均的販売率からすると、在庫消化には1年半以上かかる(p16)
・中国はずっと好景気であるが、意外なことに、「需要が供給を上回ることがほとんどなく、むしろ逆」、中国経済は2006年からすでに深刻な生産過剰になっている(p23)
・中国が直面しているインフレは、普通のインフレと異なって、需要や供給と関係がなく、企業などによって提供されるモノやサービスの量を上回る形で、中央銀行によって貨幣が増やされて、貨幣価値が下がることでインフレが起きるものである(p28)
・一般に先進国では、マネーサプライとGDPの比は50から70%(バブル経済の日本は20%)であるが、現在の中国は260%である(p31)
・中国では、国民消費は経済全体に占める割合が低く(1991:48%、2010:37%)、内需の慢性的不足(米国:70%、日本:60%)になっている、そのために投資と輸出の拡大を図る必要がある(p34、37)
・中国では1回の診療で払う一人当たりの平均医療費は、月給の4分の1程度もある(p38)
・スイスUBSの試算では、現在の中国で中産階級と認定できるのは、2500万人程度で、総人口比較2%のみ(p39)
・1997から2007年までの11年間、中国のGDPに占める労働報酬の比率は、53%から40%程度に落ちた(p40)
・中国の外貨管理制度のもとでは、国内企業の稼いだ外貨は企業の手元には入らない、中国政府(中国銀行)によって買い占められて、政府の外貨準備高となる、その代り、輸出企業の稼いだ外貨に相当する額の人民元を発行して、輸出の対価として企業に渡す(p45)
・人件費、エネルギー資源の高騰がもたらす生産コストの急増、アメリカ経済の衰退が原因で、中国では輸出が伸び悩み、中国の多くの企業が「利益ゼロ」になり、多くの企業が工場や機械を売却しようと努力している(p54)
・日本では企業の生産部門が調達した資金は30兆円程度(GDP比較で6.4%)で、中国の場合は、借金の割合は28%である(p68)
・死にかけた不動産バブルが復活したのは、2009年から政府が行った放漫融資にあった(p92)
・中国人民はいまは四大古典小説を実演している、エリートと金持ちは「西遊記」、高級幹部は「紅楼夢」、地方政府は「三国演義」、庶民は「水滸伝」である(p132)
・多くの富裕層を海外移住にとりたてたのは、中国国内の環境汚染、食料・医薬品の安全問題、公共サービスの悪さ、社会的不平等、法制度の不整備等にある(p156)
・過去10年間に中国から海外への移民数は年平均45万人で、彼らが外国へ持って行った資産は2500億ドルで、中国政府と国内企業がいままでに行った直接投資の2倍(p157)
・一般の出生比率は、女100に対して、男は103-107であるが、中国(2008年)では、男が120であった、これは「一人っ子政策」による(p200)
・中国は過去30年間にわたって「一人っ子政策」により、人口を4億人減らすことができた(p203)
2011年10月29日作成
投稿元:
レビューを見る
中国の喫緊の課題が、インフレと不動産バブルの崩壊であることが繰り返し述べられていて大変参考になる。軍事面も含め中国情勢から目が離せない。石平氏の著作は始めて読んだ。活躍に注目したい。
投稿元:
レビューを見る
私は仕事の都合で中国に赴任してから2年になるが、
至るところで暴動と呼べる事件が起きているとは
知らなかった。
当然、中国人もほとんど知らないだろうと思う。
2012年の中国経済はどうなるのか。
非常に興味深い。
投稿元:
レビューを見る
中国不動産バブルは崩壊し、共産党政権は混乱に陥る、
という石平氏の希望的観測の本
四大古典小説の小話、
「西遊記」「紅楼夢」「三国演義」「水滸伝」
「3400万人余剰男」と「植民地戦略」
投稿元:
レビューを見る
中国もバブル崩壊か。
中国って、どうも怪しいんですよね。
んで、思わず手に取りました。
中国の経済繁栄は、なんと国家予算による虚構らしいんですな。
んで、元を乱発しているおかげでインフレ爆発。虚構ですから、いつかは崩壊する。
その時期とは??もうすぐらしいですよ。
おすすめ度は5点中、3点。まあまあ面白かった。
投稿元:
レビューを見る
↓を参照して下さい。
http://badboydiehard.wordpress.com/2012/03/31/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%89%88%E3%82%B5%E3%83%96%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%81%90%E6%80%96/
投稿元:
レビューを見る
中国という国の状況をわかりやすく伝えてくれる本。
なんだかすごい課題を内包していることはよくわかりました。
こんな国に投資して進出していく日本の会社ってどうなんでしょうか?
資産の投機ならまだしも投棄にならないことを祈るばかり。
でも、まわりを見渡せば、中国、北朝鮮、韓国、そして、極めつけは日本か。
なんとまあ東アジアの国々って個性的でリスク満載なんでしょうか。
投稿元:
レビューを見る
中国のバブルについて知りたくて読書。
著者の本を初めて拝見させてもらう。著者のような専門家に活躍してもらえる日本であって欲しいと個人的に願う。さすがに中国出身だけあり情報取得に長けている印章を受ける。
新しい本なので2010年4月の庄河の土下座嘆願、2011年8月の大連のデモなども取り上げられている。
日本でもデフレ解消のためにマネーサプライを増やすことを主張する専門家もいるようであるが、むしろ日本は実施して、多少インフレへ誘導してもいいのではと思ってしまう。日本が再び経済成長の道を歩み出すことで、中国にも大きな影響が与えられると思うから。
大連に住んでいてもこれだけの格差、物価上昇の中で、ある程度の治安が保たれていることは奇跡だと感じることがある。
インターネットの力が今後の中国の方向性へ影響を与える要因となりつつある。仮にバブルが崩壊して、経済成長が失速したときに正当性と存在価値を問われる可能性がある共産党政府はどうのような国策を出してくるのであろうか。
人民解放軍を統制する憲法、法律がないという事実は衝撃的。シビリアンコントロールされていない北朝鮮と同じだと初めて知る。
もし中国人と結婚しても不動産を購入する氣にはなれなくなる1冊。
読書時間:約50分
本書はお借りしています。有り難うございます。
投稿元:
レビューを見る
様々な角度から現在の中国の問題について書かれています。不動産市況の今後を読むうえでは非常に参考になる一冊です。中国のインフレの元凶も理解できました。。政治的な混乱は軍部の増強につながり、これは世界の平和にとっては大きなリスクとなりそうです。。自らの将来戦略に関しても考えさせられる1冊です。