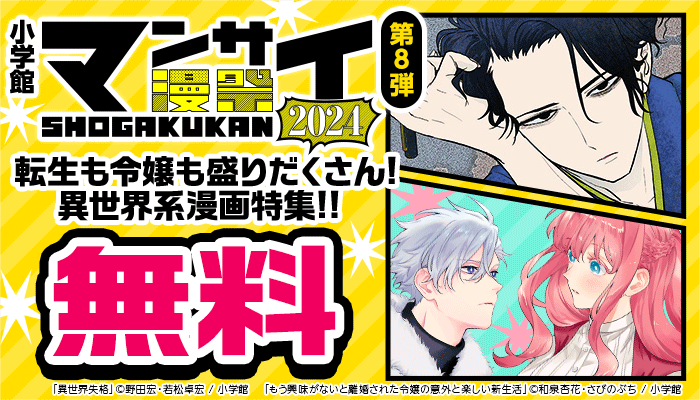0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:フランクリンプランナー - この投稿者のレビュー一覧を見る
フランクリンプランナー
投稿元:
レビューを見る
7つの習慣で有名な著書の新刊です。7つの習慣同様、著書も必読の一冊です。著書は70歳を超えているので、もはや新刊は出ないかなと思っていましたが、新刊が出て驚き、実際に読んでみて再び驚き、あまりの大作に圧倒されました。勝つか負けるかではない第3の案をキーワードにして、仕事や家庭、社会に至る世の中のあらゆる物事において解説してくれます。
7つの習慣を先月再読したきっかけのひとつが著書です。新刊を読む前に、7つの習慣を再読しようと思い、ブログにも書評をまとめました。7つの習慣を再読して初めて気付いたことがあり、実は7つの習慣の中でも第3の案というキーワードが出てきていました。以前から著者は第3の案という考えを持っていたことが分かります。7つの習慣では、数行触れているだけで詳細な説明はしてありません。その第3の案という考えを500ページに渡って説明しているのが著書になります。
著書の構成としては、まず第3の案という考えについて解説をしています。その後の章で、職場、家庭、学校、法律、社会、世界、人生とあらゆる対象に第3の案の考えを適用して、読者に第3の案の凄さを語りかけています。著書の内容が非常に充実しているので、7つの習慣同様、何回かにわけて書評をまとめようと思います。
7つの習慣との関係について、まず説明しておきます。著書と7つの習慣は補完関係にあると思います。7つの習慣は自分自身の問題、他者との関係の両方について解説していましたが、どちらかと言うと自分自身の問題に重きを置いた内容となっています。一方、第3の案は、他者との関係に特化した内容となっているので、理想的には2冊両方読む方が好ましいかもしれません。
早速、著書の解説です。1章はプロローグであり、本格的なスタートは2章からになります。2章で第3の案の説明を100ページに渡って解説しています。3章以降は各論なので、2章だけ読めば、著書の概略はまずはつかめると思います。
第3の案とは何か、著書では冒頭にこう説明されています。
私たちが直面する最も厳しい問題、とても解決できそうにない問題も解決できる方法がある。人生のあらゆるジレンマや根深い分裂を突き抜ける道がある。前に進む道がある。それはあなたのやり方でも、私のやり方でもない。それらを超えるやり方である。これまでだれも一人として思ったこともないほど効果的な方法である。私はその方法を「第3の案」と名づけている。
私の案、あなたの案のどちらかの2者択一ではない全く別の案、すなわち私たちの案が劇的に物事を解決してくれる、著書ではそのように説明されています。
第3の案を探すパラダイムは次のようになります。
①私は自分を見る
②私はあなたを見る
③私はあなたの考えを求める
④私はあなたとシナジーを起こす
このパラダイムは、第3章以降の各論でもたびたび登場します。第3の案を導くために、このパラダイムを用いて考えることができます。
このパラダイムで重要でかつ最も困難なのは、①と②だと思います。自分と相手の利害を��えず、身にまとっていた肩書き、固定観念、習慣、過去の伝統を全て取っ払って、ゼロベースで自分と向き合い、相手と向き合うことです。言わば、自分自身のアイデンティティーを全否定することになりかねないので、困難がつきまといます。しかし、そこまでさらけ出さないと、相手も親身になって心を開いて話をしてくれません。
そのハードルさえクリアすれば、あとは輝かしい道が開けます。お互い腹を割った状態で相手に意見を求め、これまで思いつかなかったようなアイデアが浮かび、2者択一では成し得なかった素晴らしい案が創造されます。
続いて、第3章です。
目次
第1章 転換点
第2章 第3の案:シナジーの原則、パラダイム、プロセス
第3章 職場での第3の案
第4章 家庭での第3の案
第5章 学校での第3の案
第6章 第3の案と法律
第7章 社会における第3の案
第8章 世界における第3の案
第9章 第3の案の人生
第10章 インサイド・アウト—内から外へ
投稿元:
レビューを見る
すごく内容が濃い本だった。
正しいのは貴方か私かの二者択一でお互いが自分が正しいと思ったときどうするか? だれでもこの状況になったことがあると思う。
夫婦間・友達との間・隣人との間など色々な関係で起こるこの状況で,喧嘩別れになるかどちらかが我慢するか,お互いに我慢しあうかになることが多いと思う。
そんな時もっと良い方法を探すという「第3の案」
すばらしいと思った。
投稿元:
レビューを見る
本書を読んでみて、自分が普段いかに二者択一型のパラダイムに捕われているのか気付かされた。想像してみると普段自分が抱えてしまう嫉妬や怒りは確かに本書のいう「シナジーのパラダイム」を持てばほとんど解決できると思う。自分の普段の行いと照らし合わせながら本書を読み進めると、どんどん内容に引き込まれていく。特にワード・クラパムのストーリーに深い感銘を受けた。
読み終わった後に何か視界が開けるような一種の爽快感が残る。訳者の表現も上手いのだろが、この人の書く文章は何か温かくて好きだ。
人によっては好き嫌いがはっきり分かれそうだが、7つの習慣と合わせて何か壁にぶち当たった時や、迷いを抱えたときに是非読み返したい。
投稿元:
レビューを見る
7つの習慣の類書。家族に関する記述も多く、考えさせられた。第3の案を考えるにあたって重要な4つのパラダイムとその順序を学び、トーキングスティックの技法を早速友人と話す際に用いてみたところ、相手と会話が重なることが減った。
この本から得られた内容はこれからも意識し続けたいし、折にふれ読み返したいと思う一冊。
投稿元:
レビューを見る
ある方に奨められて読んだ。
私が感心したのは、家族の第3の案のところである。
これまでは、二者択一の考えに陥り、自分か、嫁か、どちらが正しいかで争っていたのだが、これが一気に改善。
びっくりした
第3の案を考えたのではなく、二者択一の考えをやめただけでスムーズになったのである。
私にとっては、それだけで十分ありがたかった。
投稿元:
レビューを見る
「7つの習慣」にご縁あって始めて触れて以来早4年になろうかというタイミングで本書に出会った。
コヴィー博士に「しっかりやっとるか?しっかり聴いとるか」と激励いただいた気持ちにさせてもらえる。彼はやり続けている、本書にいうクレッシェンドな人生を実践している。
「7つの習慣」で学んだ方法論をライフワークとして昇華して行くケーススタディーを中心に本書は展開される。
自分の仕事を事業創造に繋げることを求められている私としては、多くの例示を通じて(特に第六章)シナジストであり、ピースメーカーでなければならない、というミッションを本書に明らかにしてもらえたと感じました。日常とミッションを繋いでくれるマストな一冊です。
投稿元:
レビューを見る
7つの習慣を読んで強烈に人生が変わったため、今回も絶対にいい本に違いないと思い購入。
予感のとおり。
数年に1度の大ヒット!
トーキングスティックのコミュニケーションの重要性を本当にさまざまな具体例を挙げながら説明しているので、非常に納得感がある。
また、著者自身もよく失敗しているとか、簡単なことではない、と言っていることが真実味を増している。
敵を許すか許さないかは選択できるという発想もすごい。
自分に対する攻撃は、攻撃と受け止めるかどうかも選択できる。
まずは相手の話を共感をもってきく。
ただおうむ返しでもいいから、自分の意見をはさまずにひたすらきく。
相手が理解されたと感じるまでひたすら聞き続ける。
確かにこれは難しいが、効果も絶大であろう。
思えば日本をつくる政治家たちも、ずっと二者択一的に対立を続けている。
テレビでマスコミが中国で汚泥から油を作っていると聞けば我々は、「中国人はまったく・・」
とひとくくりで見てしまう。
そういった考えからでは確かに生産的なものは生まれない。
考えが異なることが感謝できるように。
まずはつい聞き流してしまう妻の話をよく聞くことからだな。
投稿元:
レビューを見る
タイトル通りに二者択一ではなく第3の案を探しなさいということを、様々な事例を交えて説明している。職場、家庭、法律、社会などなど。
筆者が第3の案を見出す手段として推奨しているのは傾聴。言いたいことがあってもまずはぐっとこらえて相手の言いたいことを理解すること。そうすればみたが見えてくる。確かにそうだと思うがなかなか難しい。どうしても自分の意見を主張したくなってしまう。
読んでみて損はない本でした。
ちょっとだけメモ。
•私はあなたの話を聴き、あなたを理解したうえで、あなたと取引をする。私は何も隠したてず率直に、あなたと話すのである。
•すべての子供は独自の才を持った第3の案である。
投稿元:
レビューを見る
二者択一の思考から、両者にとってメリットのある、第3の(解決)案を提案しようというものである。第3の案を導きだすためには、4つのステップがある。あらゆる場面での第3の案の例示。
職場、家族、学校、社会、世界、人生。
第3の案は折衷案ばかりではなさそうだ。新たな発案により、次元の違う案を提案することが良い解釈方法として求められることがあるようだ。
トーキングスティックの話は以前にもあり。
今回は、カーターのキャンプデービットでの話が印象に残った。
シナジーに至る4つのステップ
1第3の案を探す問いかけをする
「私達がまだ考えたことのない解決策を探して見ないか?」こたえが「イエス」なら、ステップ2に進む。
2精巧基準を定義する
全員が喜ぶ解決策の特徴を下のスペースにシストアップする。どうなれば、成功なのか?本当になすべきことは何か?関係者全員の「Win-Win」は何か?
3第3の案を創造する
このスペース(または他のスペース)を利用して、モデルを作る、絵を描く、アイデアを借りてくる、自分の考えを逆さまにしてみる。スピーディに、クリエイティブに作業する。興奮が湧き起こり、シナジーに到達したと実感できる瞬間まで判断は差し控える。
4シナジーに到達する
第3の案を記述し、必要であれば実行計画を書く。
シナジーに到達するプロセス
1第3の案を探すための質問をする
対立の場面であれ、創造的な状況であれ、この質問をきっかけにして、全員が自分の固定的な立場を離れ、あるいは先入観を捨て、第3の案の創造へ向かって動き出す。
2成功基準を定義する
全員にとっての成功がどのようなものかを説明する文を書く、あるいは成功の特徴をリストアップする。以下の問いを確認する。
・基準の設定に全員が参加しているのか?出来る限り多くの人から、出来る限り多くのアイデアを得ようとしているか?
・全員が「Win」となる結果は何か?
・凝り固まった要求から、より良い何かに視線を移しているか?
3第3の案を創造する
以下のガイドラインに従う
・遊ぶ。これは「リアル」ではなく、ゲームである事を全員が踏まえる。
・閉鎖的にならない。合意やコンセンサスを急がない。
・他社のアイデアであれ、自分のアイデアであれ、是非の判断をしない。
・モデルを作る、ホワイトボードに絵を描く、図をスケッチする、模型を組み立てる、草案を書く。
・アイデアを逆さまにしてみる。世間一般の通念をひっくり返す。
・スピーディに進める。時間制限を設けて活気を維持し、アイデアがスムーズに出てくるようにする。
・多くのアイデアを出す。どんなアイデアが第3の案になりそうか予断せず、思いついたアイデアをどんどん出す。
4シナジーに到達する
室内が興奮の渦に包まれたら、第3の案が見つかった瞬間である。それまでの対立はなくなる。新しい案は成功基準を満たしている。注意:妥協とシナジーを混同してはいけない。妥協は満足を生むが、喜びは生まない。妥協では全員が何かを失う。シナジーでは全員が勝利する。
投稿元:
レビューを見る
原発反対vs原発賛成、がれき受け入れ反対vs受け入れ賛成、消費税反対vs消費税賛成、保守vsリベラル、、身の回りにはたくさんの二項対立が存在する。それは政治的な問題だけでなく、職場でも家庭でも。
筆者は「二者択一」にとらわれずにどちら側の考えをも上回る新たなアイディア(第3の案)を探求すべきと繰り返し説き、その道筋を示す。
特に身に染みたのは家庭での「第3の案」。ダメだと分かっていてもついつい子供に考えを押し付けている自分がいて、その内容というのがかつて自分が親に言われて嫌だったことだったりする。
子供の考えvs親の考えではなく、よりよい道を共に探すことができる関係を築きたい。
職場においてもついつい自分の組織を守ろうとするマインドセットに陥って、他組織との打合せに対決姿勢で臨んでしまうことがある。あぁなんと幼稚で非生産的なことか。対立を前進する絶好のチャンスと捉えなければ。この本読んで少しだけ大人になった気がする。
投稿元:
レビューを見る
これは、商談などで実践しています。
7つの習慣は内的実践ですが、これは外的実践法ですね。
しかし、3冊含めてこのシリーズは常に読み続けないといけない
投稿元:
レビューを見る
「二者択一」を超えて,第3の案へ。
シナジーを起こす!
今の職場でも!
巻末の20項目に救われる。
投稿元:
レビューを見る
Win-Winを超えた概念。Win-Winは結局の所、双方ともに妥協が入り、落としどころを見つけるやり方にすぎないが、第3の案は妥協ではなく、全く新しい解決を模索しようとする方法であり、パラダイムを変えなければそこにたどり着けないとする。考え方は非常に納得性があり、理想論的にも思えるが、実際にそのような事例も多くあり、特別なものではないことは理解できる。
しかし、シナジーを起こす第3の案を導きだすのは、当事者双方の意識改革が必要なため、非常にハードルが高いと感じる。
その為のツールとして、トーキングスティックや傾聴のスキル等が必要である。それらのツールを活用し、安心な安全な対話の「場」と「キッカケ」が設定できれば、やってみる価値はある。「対話」「多様性」、そして各個人には、自分を知ること、相手を知ること、謙虚さが求められる。読む価値のある一冊だと思う。
投稿元:
レビューを見る
七つの習慣の内容を追補している内容。
本書は、相手と自分のコンセンサスについてが中心。
七つの習慣でいうのであれば、win-winの関係が関連することでしょう。とはいえ、相手とその関係を築くために何をしましょうかっていうことが重点。
第三者の案ということで、
第一の案、私は自分自身を見る、私はあなたを見る
第二の案、私はあなたの考えを求める
これだけでは、1か0で、そこから、その先の解決案。
私はあなたとシナジーを起こす
二者択一から、第三者の案を選択しましょうというのが、本書でいいたいこと。
そうすれば、1プラス1が100にも200にもなるという建設的なコンセンサスに向かうための方向性を記した本です。
対象も章ごとにまとまっていて、
家族、職場、政策、学校などなど、あらゆる意思決定をする場で活用、応用できるようになっています。
実践は難しいですが、大切なことだと思います。