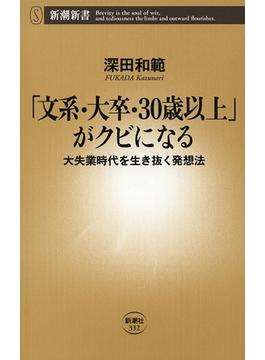紙の本
タイトルは刺激的だが説得力に欠ける
2010/01/24 15:31
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たかたか - この投稿者のレビュー一覧を見る
労働者派遣法が緩和され、一般的な製造業にも派遣が可能となった小泉政権時代、そしてその後の派遣切り問題という流れをみると、これまでの製造業の派遣切り問題の後に出てくるのは、バブル時に大量採用された30代以上大卒文系のホワイトカラーが次のリストラ対象問題であり、大失業時代が近いうちにやってくるとの「予想」が成り立つのもわからないでもない。
本書はそういう時代を受け入れ、リストラ後どのように生きていくかという心構えを持ちなさいという警告を発している。
そしてこの大失業時代は、日本が次の成長をする上での必要なプロセスであると述べている。
しかしどうであろうか。このホワイトカラーの大量失業が雇用のミスマッチの解消となるのであろうか?はたまた新たな産業への就業者移転となるのであろうか?そのあたりがよくわからない。必要以上に不安をあおりたてているだけのようにも感じるし、クビにならないような「処方箋」も見当たらない。
このタイトルから本書に興味を示した人は少なくないと思う。それはこの「文系・大卒・30歳以上」という条件に合致するホワイトカラーは少なくないからである。私見であるが、「売れるタイトルをつけたな」という印象はぬぐえない。その割に述べていることが表面的であり、週刊誌を読んでいるような、新書とは思えない説得力のなさが問題なのではないだろうか。
投稿元:
レビューを見る
私「文系・大卒・30歳以上」なんですけどw といいつつ本質は日本におけるホワイトワーカーといわれる専門性を持たない職業人たちがいかに企業の大多数を占め、結果として企業競争力・生産性を貶めるに至ったかを卑近な例示からマクロ的な日本経済分析を行ったもの。タイトル的には非常に釣られやすいです。
投稿元:
レビューを見る
自分は文系の大学生で、本書とか、「若者はなぜ3年で~」のような、これからの雇用情勢の変化について関心があり、読んでいる。
もちろん就職を控えてということもあるのだろうけど・・・・・・
本書は、内容的には、なかなかわかりやすかったように思う。だが、行き詰まる白色労働者の行き先として、安易に介護業界を挙げるのはどうかと思った(そんなものが分かれば苦労しないけど)。
投稿元:
レビューを見る
リストラが進行された事例が本当に面白い。
とはいえ、僕もリストラ対象だから笑えない。
どうすべきか。
本書の事例を踏まえて、
「子供の成長はなぜ早いか。それは出来ないことが多いから。僕はできないことをもっとやらなきゃいけない。」
投稿元:
レビューを見る
・今後、生産性を改善するためにはホワイトカラーのリストラぐらいしか方法がない
-生産や販売現場の向上はもうすでに相当向上している
・賃金が高いホワイトカラーの削減効果が一番効果が高い
-過剰気味なため、メスも入れやすい
・今回の不景気では、打開のための牽引役の商品がない
-過去の不景気では、パソコン、携帯などがあった
-次世代を担う商品がない
・コインポイッシャー(コインを磨く人)
-1円玉を磨き続けても価値は上がらない
・経費削減はリストラへの呼び水
-こんだけやっても、業績が悪いんだから最後の手段としてリストラを行う。と納得性を持たせる
・リストラされる人が「俺が何をしたっていうんだ」と言った時の切り返し
-君は何か悪いことをしたわけじゃない。しかし、特別に良いことをしてきたわけでもない
・30歳以上・文系はリストラしても日常の業務は滞らない
-20代は実務、技術職は開発がある
・基本的にホワイトカラーは過剰気味だから、落ち度がなくてもリストラはされる
☆「成長」とは、出来ないことが出来るようになること
●サッカー少年たちは日に日にサッカーが上手くなる
●人は出来ないことが出来るようになったとき、ガッツポーズをして本当に喜ぶ
タイトルに惹かれて購入しました。今まで漠然としていたリストラについての考えが、この本により明確化されました。ホワイトカラーは落ち度がなくてもリストラされる、一円玉を磨き続けるホワイトカラーが沢山いるといった事実は衝撃でした。このことは今の日本は年を取れば取るほど一つの会社にしがみつかないと生きていけないことの現れだと思います。どこに行っても通用するために、著者が述べている「成長」の気持ちを忘れないようにしたいと思います。
投稿元:
レビューを見る
生産性の低いホワイトカラーは切られる。養っておく余裕はもうないし、切れるとこはもう大分切っているから。成長できない仕事でダラダラと過ごすよりは思い切ってリスクを取ろうってことかな。
投稿元:
レビューを見る
重い。ホワイトカラーに突きつけられる過酷な問いと
正規雇用者への大リストラを予告する、深刻な一著。
投稿元:
レビューを見る
●世界大不況は「人口が減少に転じた中で発生した、日本史上初めての不況」ととらえるべき。
●ホワイトカラーは会社において存在しないほうがよい。
●最近のホワイトカラーは「コイン・ポリッシャー」になっている。
●もともと、ホワイトカラーの仕事の本質は、「社会と企業、そして従業員との間を効果的に結びつける」ということにある。
●日本企業の弱体化の一因となったのが、がん細胞と化したホワイトカラー。
●しっかりとした仕事をするためには、会社や従業員のことだけではなく、社会や家族のことまで考えなければだめだ。それが『会社人間』と『社会人』との違いだ。自分の能力が高いと思うのであれば、低いものの分まで考えて全体がうまくいくようにがんばらないといけない。会社をまとめていく仕事をする者は、そうやって他人のこと、全体のことを考えられる人間でなければならない。
●総人口が減少する中での大不況という状況下において、存在し続けることができるものは、「これまで必要とされてきたもの」ではない。「これから必要とされるもの」だけだ。
●あるものの必要性を決めるのは、あくまでも「他者」である。したがってホワイトカラーの必要性を決めることができるものは、ホワイトカラー以外の者ということになる。
●これまでのように、ホワイトカラーが大勢いて、それが高い賃金をもらっている時代の方が異常だったのだ。
●経営者にとって、従業員の雇用を維持することは、会社の業績を向上させ、株主に配当を還元することと同じくらい重要な使命である。しかし、この使命とは、会社に不必要な人材を抱え込んでおいてもよいということではない。こういう状態を続けていると、業績が下がり、株主から見放され、事業の縮小を余儀なくされて、結局は、従業員の雇用を維持することができなくなってしまう。
●『成長』とは、できなかったことができるようになる、ということです。
●将来のことを考える場合に過去のことを振り返ることは必要である。しかし、過去のことばかりを議論していても何も始まらない。
●大量失業の発生という「傷の痛み」に耐えて、環境変化への不適応という「病の苦しみ」と向き合い、その治療に取り組む覚悟があるのかが問われている。
投稿元:
レビューを見る
次のリストラの対象は、ずばり、「文系・大卒・30歳以上」。
データと論理でそれを実証する憂鬱な一書。
投稿元:
レビューを見る
まさに自分がその予備軍(文系・大卒・20代後半)であり、自ら持っていた会社に対する疑問を、論理的に述べてくれたような本。
こと生産性というキーワードで考えると、今後の自身のキャリアのあり方を、自身で再度考えて行動していかないとならないと痛感した。
正社員であるからと会社のいうがままにしていたのでは、遠からず昨今の派遣ぎりのような状況に自分自身が置かれたとしても、誰にも文句はいえまい。
投稿元:
レビューを見る
そうだよね、と思う内容。新鮮さはないが、自分の業務の無駄は再チェックしようと思った。本当にその仕事は必要なのか、顧客のためになっているのか。
投稿元:
レビューを見る
就業者総数の減少に反して増えてしまったホワイトカラー。彼らの仕事の無駄と人員数が業績を圧迫しているため、リストラで業務を正常化しようという論理。というか、近い将来そうなるであろう事を踏まえての論理。
「リストラにあっても暫くは辛い生活を送ると思うけど、新エネルギーや介護のように今伸びている業界に受け皿はあるし、ホワイトカラーのリストラで企業の業績が回復すれば雇い先も増えるよ!」とリストラされた者の行く末を前向きに論じているが、実際にそう上手くいくかどうかは疑問が残る。
業績が回復した企業が真っ先に雇い入れるのは、現在でも溢れている新卒や第二新卒のような伸び代のある若者で、中年の失業者にまで職が回ってくる事があるのだろうかと思うのは悲観的すぎだろうか。
投稿元:
レビューを見る
この不況を象徴するようなタイトル。
ホワイトカラーはする必要の無い仕事を作って人を増やして、そのつけが回ってきたと言うようなお話し。
社会構成上、相対的にもホワイトカラーの人数が増えているというところに目を向け筆者は100万人の解雇が起きると予想しております。
さてさて、どーなりますやら。
投稿元:
レビューを見る
正に自分が当てはまる本書の条件。
早速読んで見ねばと思い、手に取った。
ホワイトカラーの大失業時代が来るとの予想に立って、
自身が著者の抱く問題意識から、
特に文系・大卒・30歳以上が何故リストラに遭うのか?
こうした大失業時代、どう生き抜いていくのか?が書かれている。
著者の考え・思い込みに傾倒気味であるのは正直否めず、
やや極端な内容ではあったが、個人的には大変納得感は高い。
やる気を醸成して行動に移させる自己啓発本ではなく、
恐怖を煽るタイプの自己啓発本と言える。
個人的に印象深かったフレーズは、
「成長とは『出来ないことが出来るようになること』」
「失業は失敗ではない」
とかく楽観的に考えてしまう自身であるが、
本書を読み、気を引き締めるに至った。
分かりやすい平易な表現が徹底されており、
読んですぐに理解出来る内容であるのは良い。
投稿元:
レビューを見る
きっと自分がホワイトカラーだったらまさか大失業時代なんて来るわけないだろう、そう思っていたに違いない。
ただそれは現実をきちんと見ていようとしているのか?
確証バイアスが働いていないか?
逃げではないのか? そう自問自答したくなる。
内部の中に閉じこもっているだけでは外部のことはわからない。鳥の目を持っていつでも戦闘態勢に入れるように準備しておくべき。自分の力だけではどうしようできない、やがてくるだろう大失業時代到来のためにも。