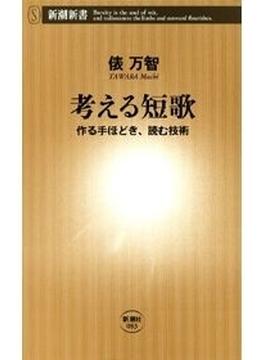読割 50
電子書籍
考える短歌―作る手ほどき、読む技術―(新潮新書)
著者 俵万智 (著)
どうすれば気持ちを正確に伝えることができるのか。短歌上達の秘訣は、優れた先人の作品に触れることと、自作を徹底的に推敲吟味すること。ちょっとした言葉遣いに注意するだけで、世...
考える短歌―作る手ほどき、読む技術―(新潮新書)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
考える短歌 作る手ほどき、読む技術 (新潮新書)
商品説明
どうすれば気持ちを正確に伝えることができるのか。短歌上達の秘訣は、優れた先人の作品に触れることと、自作を徹底的に推敲吟味すること。ちょっとした言葉遣いに注意するだけで、世界は飛躍的に広がる。今を代表する歌人・俵万智が、読者からの投稿を元に「こうすればもっと良くなる」を添削指導。この実践編にプラスし、先達の作品鑑賞の面からも、表現の可能性を追究する。短歌だけに留まらない、俵版「文章読本」。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
これは短歌をやっている人だけに通じるものではない。例えばポップスの作詞をしている人なんかにも大いに役立つはずだ。
2011/11/18 22:29
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yama-a - この投稿者のレビュー一覧を見る
世の中にテクニカルに解決できることは意外に少なくない。挨拶するとか敬語を使うなどというのもつまらない争いを避けるためのテクニックである。それを「人として当然身につけておくべきこと」とか「先輩を敬う気持ち」などと言い始めると途端にややこしくなる。
そういうことは表現という行為のなかにもある。「見たまま感じたままを表現せよ」「細部を削ぎ落して本質を描け」などと抽象的なことを言われてもどうすれば良いのか分からない。芸術というものはとかくそんな風に伝承されてきたのだが、そんな中で表現の難しさをテクニカルに解決する術を教えようとする本書は本当に良書であると思う。
僕は『サラダ記念日』の頃からの俵万智ファンである。ただ僕自身は、ごくまれに戯れに短歌らしきものを詠んでみることもないではないが、日頃から短歌に親しんでいる訳でも何でもない。しかし、それでもこの本が、表現という問題を如何に見事に解決しているかはよく解る。これは短歌をやっている人だけに通じるものではない。例えばポップスの作詞をしている人なんかにも大いに役立つはずだ。
著者は各講の冒頭にまず「公式」(例えば、「体言止めはひとつだけにする」等)を掲げ、そして実例を挙げて添削する。その「使用前」と「使用後」の短歌の出来栄えの違いは素人目にも明らかである。ああ、そんなことでこんなに良くなるのか、と感心せざるをえないのである。
中には逆に「この素敵なコスモスの歌二首を、ダメなほうに改作してみよう」(64ページ)などという試みもやっていて、これがこれまた見事にダメになる。この説得力は、やはり著者がどれだけしっかりと「公式」を把握しているかという証でもあるのである。分けても、サ変動詞のない名詞の場合は「の」で繋いで良いが、サ変動詞がある名詞の場合は「する」で繋ぐべきである(114ページ)などという明快な分析に出くわすと驚きを通り越して嬉しいくらいである。
これは職業であれ趣味であれ、ともかく何かを表現しようとする人間にとっての大きなヒントになる本である。もちろんヒントだけでは何も書けないということは言うまでもないが、そのことは言わずもがなの大前提とした上で、名人・俵万智がテクニカルな部分だけをきれいに切り取って提示してくれているのである。小気味良いほどの参考書である。いや、参考書と呼ぶには、読み物としてあまりに面白い。
ただ、この尻切れトンボみたいな終わり方は如何なものだろう。これは雑誌の連載記事ではないのである。1冊の本という体裁を取るのであれば、最悪「あとがき」という形でも良いから、何か全体のまとめめいた文章で本を締めるべきであって、そうしなければそれこそ「けり」がつかないと言うべきなのではないだろうか?
ま、不満はそこだけである。逆にどの講からでも読める辞書的なものを目指していたのかもしれない。僕にとっては辞書と言うよりむしろバイブルと言っても良いくらいなのだが。
紙の本
詩や歌を作るための「うらわざ」「技術」
2006/02/02 01:54
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Shinji - この投稿者のレビュー一覧を見る
書店でタイトルと著者の名前に惹かれて手にした本書の帯には「一文字の力 表現のうらわざ 『言葉の技術』教えます」と大書されていました。詩や歌を作るための「うらわざ」や「技術」を正面切って取り上げた本は、かなり珍しいのではないかと思います。
優れた歌人である著者は、短歌の添削という作業を通して「表現のうらわざ」「言葉の技術」を、分かりやすく提示してくれています。具体的には、助詞や副詞、形容詞を使うときの注意点や句切れや語順のことなど、まさに、「うらわざ」「技術」というに相応しいポイントが扱われています。
紙の本
客観的に添削を「考え」てください
2008/02/22 00:03
11人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トマト館 - この投稿者のレビュー一覧を見る
俵万智の短歌についての本を読んで、いつも思うのですが、
とにかく著者さん、
出典を明記しなさい。
初心者が陥りやすい表現を指摘するのも結構ですが、
前提として、
歌集が非常に流通していなくて、
初心者泣かせなのを忘れているんじゃないですか?
これじゃせっかく「鑑賞コーナー」をよんで、
「この歌人の歌もっと読みたいな」
「この歌、どんな連作に入っているのかな」
と思っても、出典が明記されていなければ、
どこにもつながりません。せっかくの興味・関心をそぐことになります。
どうか面倒くさがらないでください。
大岡信氏は「折々のうた」で毎日やっていたではないですか。
あなたの短歌から短歌をはじめたという人はたくさんいます。
そうであるならばなおさら、
読む指針として、最低限出典を示すべきではないですか?
添削は、俵万智リフォーム術と言って差し支えないのではないでしょうか。
添削には必ずこういう問題がでてきてしまいますが、
短歌を面白くする、というより、俵万智っぽくするためにはこうする、
という技術が披露されていると思います。
必ずしも面白くなっているとは、わたしは思えません。
もともとの歌のいい部分が切り落とされて、
添削者の好みの表現にかえられているものもあると思います。
そのへんを、ほんとうに短歌を面白くしたい人には、
客観的に「考え」て読んで欲しいと思います。