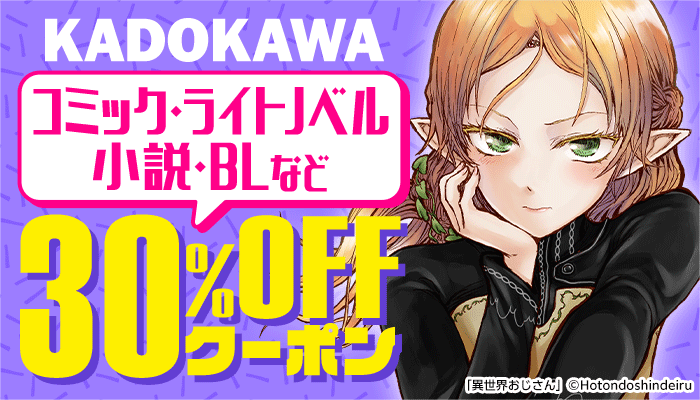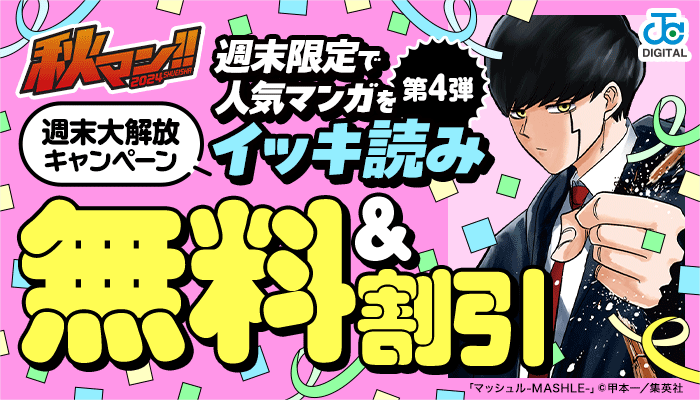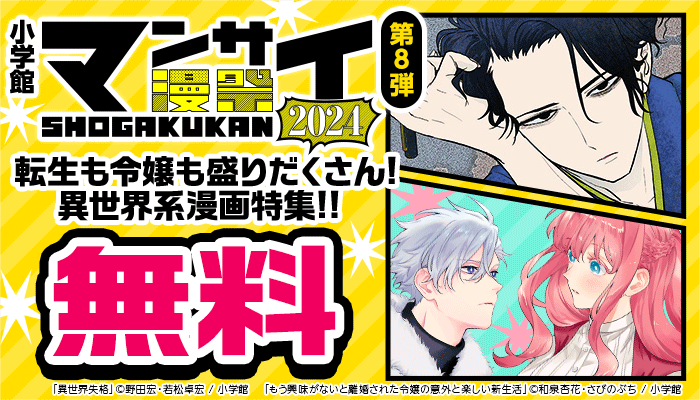投稿元:
レビューを見る
経理部門の業務は、一般的な決算書を作る作業とその作った決算書から読み取れる情報を業務へ還元する作業がある。
今回の本は主に後者に重点が置かれたものである。
多くの企業では、本業を従事する傾向にあり、管理部門の業務に対する生産性に疑問視する視点が多い。また、経理部門に存在する人間も作業が求められる中で、存在意義を見失うことが少なくない。
そんな一般業務へのメッセージ、および現在目標を見失うことの多い経理担当者へのメッセージがふんだんに含まれ、どの企業に向けても参考になるものである。
投稿元:
レビューを見る
内部監査の今後を考えるうえで、気になった会社のひとつ、ファストリ。そんな矢先にこの本をいつものうどん屋の隣の本屋(大崎ThinkPark)でめっけました。
ベーシックな会社管理(債権債務管理、棚卸資産管理、予算管理など)も含め、管理部門が会社の成長に貢献するための「数字」の使い方がわかりやすく解説されてます。
ユニクロ含む上場準備コンサルで得た経験もふんだんに織り込まれていると思われ、いわゆる準拠性監査にとどまっているところからの脱却をする際の目線を養うのにも最適な本のひとつ。
数値での事例も多いし、チェックリスト的にも監査用にまとめられそうです。
以前インタビューした会社の監査室長さんがおっしゃっていた「次の内部監査室長には、できれば子会社なりのマネジメント経験者でないと。。。」というのも、ほんとよくわかります。
これくらいを最低限の共通言語にしておかないとですね。
投稿元:
レビューを見る
面白かった。一気読み。
実務家が実例をもとに会計を中心とした経営のキモを解説してくれるから、わかりやすい。
コンプライアンス、内部統制、上場と、現課題がキーワードになっていて、有益。
価値創造→数字目標を掲げ、社員の意識を変えると会社も変わる
会計思考→損益構造「儲ける」、キャッシュフロー構造「現金が残る」
投稿元:
レビューを見る
宇部市の紳士服店、小郡商事を上場準備コンサルタントとして、監査役として、ユニクロというグローバルなプレーヤーになるまで会計面から支えた著者の一冊。会計思考経営、予算管理、強い成長企業の会計数学ケーススタディなど、興味深いテーマで読み終えるのもあっという間。「損益分岐点を低くする5つの方法」は、当たり前だけど、とっても大事!
投稿元:
レビューを見る
会計というと数字ばかりで近寄りがたく、その道のプロが知っていれば良く知っているべき分野である、という認識を持っていた。
実際には、この本を読んで、誰もが必要な知識で、そこまで難しくない分野であるという事が認識できた。認識できただけで同分野を理解は出来ていない。
おそらく軽く理解するためには同分野の本を10冊程度読まないと無理だと思う。
そういう意味では、会計的数字どっぷりだけではなく、経営的な視点も多分に取り入れているので、今後同分野を理解するためにもっと読みたい!と思わせてくれる本であった。
加えて、日々の仕事への取り組み方・視点を経営的な視点に変えさせてくれる本である。
投稿元:
レビューを見る
数字と向き合うことを多くの人が避ける傾向がある。「数字に弱い」、「見方が分からない」、「面倒くさい」、「現実を受け入れたくない」など理由は様々だが、会計数字がその会社の実態を忠実に表しているとしたら、私たちは見て見ぬふりをすべきではないだろう。
数字はその企業の健康状態を示し、問題点を提起し、目標になり、到達するまでのマイルストーンになる。そしてその数字は、今や誰もが簡単に手に入れることができる。経営者や経理部門だけが関わればいい時代ではなくなったのだ。
著書はユニクロ、アスクル、カクヤスなど、近年急成長を遂げた企業を支えてきた著者が、初心者にもわかりやすく会計数字を紐解いている。
内容は「棚卸の重要性」、「与信管理の大切さ」、「正しい経費削減の方法」など、目次を見ただけで経理部門だけではなく、物流、生産、そして営業に至るまで、会社のほとんどの部署に会計数字が関連していることに気づかされる。そしてなぜそれらが重要なのかを丁寧に説明している。読者は、義務感で行っていた仕事の重要性に触れ、きっと取り組む意識の変化を感じるだろう。
また、経営者にはユニクロ、マクドナルド、日本電産、東レなど、会計数字をもとに問題解決をし、成長を遂げてきた企業の事例が大変役立つだろう。
ロバート・キヨサキ氏が著書「金持ち父さん、貧乏父さん」の中で財務諸表が読めることの重要性を訴えたが、この本はまさに会計数字の読み方を知るための教科書である。
経営者や経理部門に携わる者のみならず、ぜひ多くの方々に一読することをお奨めしたい一冊だ。
投稿元:
レビューを見る
公認会計士かつユニクロの監査役を長年務め、会計面からユニクロの躍進を支えてきた著者が、企業経営においていかに会計思考が必要かをまとめた本。
色んな論点が出てきて雑多な印象はあるけれど、各論点は非常に具体的なレベル(実務的とも言える)まで述べられており、内容がわかりやすい点が特徴か。
また、図解の分かりやすさが非常に素晴らしい(減価償却の図説は今まで見た中で最も分かりやすく、参考にしたい)。
【個人メモ】
■第1章 会計思考経営だけが会社を成長させる
・企業活動におけるあらゆるものを定量化し、利益と現金の確保に向けて全社員が行動することが会計思考。
・組織図は、経営戦略の機能別解説書。
中小企業等のコンサルティングにおいて、組織図を作るところから始めると、人員の適性配置やチェック機能が存在するかを確認できる(内部統制の第1歩)。
・ユニクロでは、ロードサイドを想定した標準店舗と店舗当たり標準損益をモデル化。
これにより出店時及び店舗運営が統一化され、ローコストオペレーションが実現可能に。
■第2章 「月次決算」の迅速化と予算管理の徹底が強い会社の基本!
・月次決算はPDCAサイクルにおいて重要なツール。
例えば、一定のアラート基準を定めて、基準未満の場合にすぐに原因分析~対策実施できれば、問題を未然に解決できる。
・月次決算の迅速化のためには、間接部門の業務を標準化し、効率化することが大切(財務・経理部門だけでは実現できない)。
間接部門コストの低減も副次効果として得られる。
・決算作業の中でも、「実地たな卸」の効率化は非常に重要。
実施後の差異極小化を目標化すると、在庫管理の徹底等による業務効率効果も得られるため、経営者が現場を知る手段として立ち会ってみるのも有効。
■第3章 儲かる強い会社にするための会計数字の使い方
・社員1人あたり損益計算書の作成により、社員1人あたりが利益確保のために幾ら売り上げる必要があるかなど、会計数字を具体的に感じることができ、会計思考の定着に有効。
・在庫管理はキャッシュフロー・マネジメントの基本(企業の立て直しでは、在庫管理から手を着ける場合が多い)。
・与信管理は日頃から徹底すべし。
貸倒が発生すると、同じだけの利益を確保するには貸倒額の数倍もの売上が必要(損失に比べれば、多少コストをかけてでも与信管理を徹底するべき)。
■第4章 強い会社をつくるタコメーターの魔術
・企業の総合力を図る財務指標であるROEやROAの分析時には、売上高伸び率と総資産伸び率との関係にも着目をする。総資産伸び率の方が高い場合は、資産の利用効率が下がっている証拠であり、借入金による増加の場合はなお注意が必要。
・財務指標以外にも、業界特有のKPIに着目。ユニクロのような小売業では店舗面積あたりの売上を示す月坪効率を重要視している。
■第5章 強い成長企業の会計数字ケーススタディ
・ユニクロの場合は月次ベースで現金収支を管理する「資金繰り予定表」を活用している。売上目標をベースに、所定の現金売上・売掛金の割合、売掛金の回収タイミング、現金支払・買掛金の割合等を用いて現金収支に影響のある項目を予測し、実績と比較することで、中長期的で無理のない資金繰りを実現している。
・店舗における人員配置(レイバースケジューリング)は売上・利益に影響を与えるため、適正な管理が必要。作業量を人時に置き換え、定量化して計算すること。
投稿元:
レビューを見る
◯多分、初めてかなぁ?やっと読みきれる会計本に出会えたかも笑。会計に限らず経営という視点でも勉強になる本。
投稿元:
レビューを見る
信用管理のところの、まず大事なのは前始末。
東レの過去の話で、この会社はいつ潰れるのか?に、正確にいついつですと答えた経理の担当役員の話。
投稿元:
レビューを見る
知ってる人には当たり前すぎる企業会計の実際についての本。
「損益構造」(利益が出るかどうか)と「キャッシュフロー構造」(手元に現金をどれだけ残せるか)の二つの柱が、自分の会社、あるいは店、業界だと何の数字になるのか、それをいつどんな風に確認して意思決定していくべきか、という話。
雇われでもなんでも、飲食や小売の店長とかやってる人は体感で身に付けてそうなこと。
机上の財務諸表ではなく、実際の企業の事例で生々しく見ていくのは割りと参考になる。
投稿元:
レビューを見る
辛口ですが。
前半は、いかにもコンサルタントの先生が書きました!って感じの正論が並べ立てられている。どこかで読んだことあるような内容だし、「それができりゃ苦労しないわ」とツッコミを入れたくなる箇所がちらほら。
最後のユニクロのケーススタディはわかりやすかったんで、そこだけは読んで良かったかな。どっちかっていうと会計初心者向けです。
投稿元:
レビューを見る
経営者はじめ、ビジネスマンには会計思考が大切ということを具体的に教えてくれる本。
損益計算と収支計算、予算と実績の比較、一般的な経営指標に加え会社独自の経営指標を持つこと、等々。いずれも具体的なのが良かった。表やグラフの雛型みたいなものもいくつか掲載あり。
あと、企業の事例がいろいろ書かれていたのが良かった。もっと知りたいなと思わせてくれる。
投稿元:
レビューを見る
将来は会社を大きくしていきたい経営者(現在は中小企業)、マネージャー、には是非読んでほしい一冊。
株式上場支援などを行う人間が実施するであろうベーシックな「手法」が説明されている。
管理会計的手法であるが、管理会計という言葉すらしらない人間であっても、
ユニクロなどの例を基に説明されているため、リアリティーがあり理解しやすい。
特に大企業になるためだけでなく、予算導入や月次決算の速度化など、
中小零細企業にとっても当り前かつ、重要な事柄が述べられている良書である。
投稿元:
レビューを見る
経営者に必要な会計思考が過去の実例と共に書かれている。経営者もそうだが、経理担当者や経営者と触れる機会のある方にもオススメの良書。
投稿元:
レビューを見る
ユニクロやアスクルなど成長企業は会計を戦略ツールとして捉えている。その立役者となったのが著者の安本隆晴氏だ。
日次決算など著者の会計に対する考え方は非常に実践的で、「こういう動きでこう変わる」「こういう問題にはこう対処すべき」など具体的である。
会計を軽んじている中小企業はもとより、組織が硬直化して会計を報告ツールになり下がっている大企業にとっては学ぶところが多いだろう。
スタートアップ企業の取締役は必読だろう。