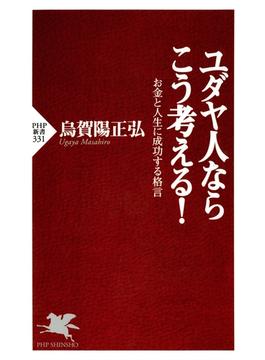投稿元:
レビューを見る
680
烏賀陽正弘
1932年マニラで生まれ、幼少期を米国で過ごす。京都大学法学部卒業後、東レ(株)に入社。国際ビジネスに従事し、訪問した国は80カ国に上る。ニューヨークと香港にも長らく駐在し、欧米や中国に多くの顧客と友人を持つ。米大手量販店シアーズ・ローバック社が、優れたビジネスマンに贈る最優秀賞「アワード・オブ・エクセレンス」を受賞した数少ない日本人。海外駐在より帰任後、同社マーケティング開発室長などを歴任。その後、独立し、国際ビジネス・コーディネーターとして活躍
「いかなる格言も、真実でないものはない」 “No proverb is untrue.”
「お金は木には 生らない」 “Money doesn't grow on tree.”
ユダヤ人は、私たちが想像する以上に、格言がとても好きです。ユダヤ人が格言を好む原点は、約3000年前にさかのぼって、見つけることができます。
彼らは「書の民」といわれています。世界各地に四散し、厳しい迫害と差別を受けながらも、ユダヤ人としてのアイデンティティーを保てたのは、「旧約聖書」、中でも「トーラ(モーセ五書)」と、離散後に編纂された聖典「タルムード」を熟読して研鑽に励み、信心深かったからだとされます。
「世界は崩れ落ちる橋のようだ」 “The world resembles a collapsing bridge.”
「家が貧乏なのは、50の疫病にかかっているよりも悪い」 “Poverty in a man's house is worse than fifty plagues.”
「どんな汚点でも、わずかな金で消せる」 “All spots can be removed with a little gold.”
「バカが沈黙している時は、賢人並みに扱われる」 “When a fool is silent, he too is counted among the wise.”
「1セントは大金だ。ただし1セントもない時にね」 “A penny is a lot of money―if you haven't got a penny.”
「金持ちと付き合うには金がいる」 “If you rub elbows with the rich, you get a hole in your sleeve.”
1 「神を信じることは、セックスと同じほど必要だ」 “To believe in God is as necessary as sex.”
2 「神は物語がとても好きだから人間をつくった」 “God made men because He loves story.”
3 「人の企てを神は笑う」 “Man plans, God laughs.”
「明日のことは、神に任せよ」 “Let God worry about tomorrow.”
4 「人にトラブルが伴うのは、あたかも鉄がさび付くように避けられない」 “Trouble is to man what is rust to iron.”
「ユダヤ人であることは難しい」 “It's hard to be a Jew.”
「ユダヤ人は他の人たちと一見よく似ている。しかし、もっと違うのだ」 “Jews are like everyone else―only more so.”
5 「トラブルは早く始まり、遅く離れる」 “Troubles arrive quickly and depart slowly.”
「人はトラブルを背負うために生まれた」 “Man was born for trouble.”
6 「解決できないトラブルは何一つない」 “There is no trouble in the world without a cure.”
「教師や本から多くのことを学んだが、それよりもトラブルからもっと多くを学んだ」 “I have learned much from my teachers and books, but most from my troubles.”
7 「苦難に耐えなければ、幸福はやってこない」 “He that cannot endure the bad, will not see the good.”
8 「活路があれば、なんら恐怖におびえることはない」 “When there is a way out, there is no need for fear.”
「飛び越えられないのなら、下をくぐれ」 “If you can't go over, go under.”
「最良の道を選ぶとしたら、まず情勢判断は悲観主義を取り、そこで行動を起こすときは楽観主義を取れ」 “The best way for a man to choose is pessimism in evaluation and optimism in action.”
9 「明日のことは心配するな。なぜなら何が起こるかは誰も分からないから」 “Don't worry about tomorrow, because no one knows what tomorrow will bring.”
このように、ユダヤ人は長年、世界各地で多くの辛酸をなめただけに、苦労や心配事に関する格言が実に多いのです。 それについて、こんな有名なジョークがあります。 汽車の中で、二人のお互いに見知らぬユダヤ人が、向かい合わせで座っていました。お互いに、ユダヤ人だと分かりながら、しばらく押し黙っていました。
苦悩は、それほどユダヤ人に一生ついて回る、一種の持病のようなものなのです。彼らは、内面的な自己批判や反省が、他民族に比べて人一倍強いのです。先に触れたように、精神分析学の開祖とされるフロイトがユダヤ人であり、アメリカにおいて精神科医にユダヤ人が非常に多いのも、当然のことと言えるかもしれません。
10 「腹が減ったら歌え、悲しかったら笑え」 “When you are hungry, sing, when you are hurt, laugh.”
「笑い声は、泣き声よりも遠くに届く」 “Laughter is heard farther than weeping.”
「笑えばみんなが注目してくれるが、泣けば誰も注目しない」 “When you laugh, everyone sees, but if you cry no one sees.”
「神の前では泣け、人前では笑え」 “Weep before God, before people laugh.”
11 「成功への扉には、『プッシュ(押)』と『プール(引)』と書いてある」 “The door of success is marked ‘push’ and ‘pull’.”
12 「世の中に、完全なものは何一つない」 “Nothing is perfect.”
「何か間違いが起こるような要因を内在している場合、それはいつか、必ず表面化する」 “Anything that can go wrong, will go wrong.”
13 「死にたいのなら、いつでも死ねる」 “For dying you always have time.”
ユダヤ人の中には、激しい迫害に遭った時、自分の命を絶つことを考えた人がいたに違いありません。しかし、たとえ、どんなに苦難に満ちた人生であっても、絶望してはいけません。 ここでは、人生をすばらしいものと肯定し、明日を信じて、懸命に生き抜くことを勧めるわけです。
「生きることを選べ!」 “Choose life!”
「死んだライオンよりも、生きている犬のほうがましだ」 “A live dog is better than a dead lion.”
14 「成功に運は欠かせない」 “Without luck, nothing will succeed.”
「不運はお互いに結びつく」 “Misfortunes bind together.”
「雨が降る時は 土砂降りだ」 “It never rains but pours.”
「幸運に恵まれない人は、死んだ人に等しい」 “A man without luck is a dead person.”
15 「運が向いてきたら、椅子を差し出せ」 “When fortune calls, offer her a chair.”
「悪運がなければ、幸運に全く恵まれないだろう」 “If it wasn't for bad luck, I wouldn't have any luck at all.”
「幸運に恵まれたら、自分の賢さが倍になる」 “When luck joins in the game, cleverness scores double.”
16 「何事も泣いているうちに終わるさ」 “Everything ends in weeping.”
「神様よ。なぜ見知らぬ人にすばらしいことをしながら、どうして私にしてくれないのですか?」 “Dear God: You do wonderful things for complete strangers, why not me?”
17 「人生は最大の掘り出しものだ。なぜなら、人生をタダでもらっているから」 “Life is the greatest bargain―you get it for nothing.”
18 「われわれは、みんな不運で 愚かなのだ」 “We are all schlemiels.”
19 「世界を支えている3本柱は、お金とお金、それにお金だ」 “The world stands on three things: money, money and money.”
20 「お金が世界を支配する!」 “Money rules the world!”
21 「車輪に潤滑油を差すと、初めて車が走る」 “If you grease the wheels, then you can ride.”
ユダヤ人は金儲けが並外れてうまい、その秘密は、一体どこから来ているのでしょうか。 それは、ユダヤ人が金儲けに巧みだということは、お金がどういうものであるか、その本質を熟知しているからだと思います。 私たちがお金について、当たり前のように考えていたり、気がつかなかったり、あるいはそれを避けたりするところに、意外とその本質があることを教えます。
「よき友は買わなければならないが、敵はタダでもできる」 “A friend you have to buy, but enemies you get for nothing.”
自分たちの運命にかかわることが多かっただけに、ユダヤ人は、お金の本質を理解し、その絶大な効果を、誰よりも一番よく知っていたのではないでしょうか。
22 「賄賂なしには、何事も成就できない」 “Without bribery, you'll get nowhere.”
「賄賂が玄関から入ってくると、正直は窓から出て行く」 “When a bribe enters through the front door, honesty departs through the window.”
「悪魔が入る戸口は広いが、出口は狭い」 “The door to evil is wide, but the gate back is small.”
23 「お金ですべてが動く」 “With money you can do everything.”
「お金がさらにお金を呼ぶ」 “Money goes to money.”
「お金を払う人が、権限を持つ」 “He who pays has the say.”
ところでユダヤ人はこのようにお金儲けが上手であり、心中ではそれを誇りにしながら、他人から、特に非ユダヤ人から、そのようにほめられることを極端に嫌がります。 というのも、先にも触れましたが、お金があったり、それに執着したりするということで、羨望やねたみを受け、差別や迫害されたからです。
24 「金の鍵は、すべての扉を開く」 “A golden key will open all the doors.”
25 「富を求めるのは、人間の本質である」 “It is the nature of man to long for wealth.”
しかしユダヤ人には、このような考え方は、まったく通用しません。ユダヤ人にとってお金を儲けることは、なんら後ろめたい行為ではなく、恥でもありません。むしろ貧乏であることのほうが、恥ずかしいことなのです。��の点が、私たち日本人の考え方と大きく異なるのではないかと思います。
26 「神様は貧乏人を愛するが、その一方で金持ちを助ける」 “God loves the poor but on the other hand helps the rich.”
27 「貧乏であることは、決して恥ではないが、といって非常な名誉ではない」 “It is no disgrace to be poor, but it is no great honor either.”
注目すべきは、ユダヤ教には、貧乏であることを美徳とする教えが見当たらないことです。前にも触れましたが、キリスト教では、お金を愛することを、悪の根源だと見なしたのと対照的なのです。
「貧乏であることは、決して恥ではない。しかし、それしか、ほめ言葉がない」 “It's no disgrace to be poor―and that is the only good thing said for it.”
「お金がすべてを、良くするのではなく、むしろお金がないことのほうが、すべてを悪くする」 “It's not that money makes everything good, it's that no money makes everything bad.”
「小麦粉がなければ、聖書も存在しない」 “Where there is no flour, there is no bible.”
「支払えなければ、神に祈りを捧げなさい」 “He that cannot pay, let him pray.”
28 「お金が人生のすべてでないと言う連中に限って、いつまでたってもお金が貯まらない」 “When someone says life is not for the sake of money, he will never earn money.”
「お金は善人にとって優れたものになるが、悪人にとっては邪悪なものとなる」 “Money is the cause of good things to a good man, and the cause of evil things to a bad man.”
29 「悩みはスープとともに腹におさまる」 “Worries go down better with soup.”
「恋愛は甘美だが、パンがあればなおいい」 “Love is sweet, but it is good with bread.”
「裕福であれば、どんな欠陥でも隠せる」 “Wealth can cover up any fault.”
30 「重い財布は、心を軽くする」 “A heavy purse makes a light heart.”
31 「身体のすべては心臓に頼る。でも心は財布に頼っている」 “All the parts of body depend on heart, and the heart depends on purse.”
たとえば、貧乏をすると、付き合いが悪くなったり、周りから敬遠されて、友人との関係が疎遠になります。そうなると、人からの刺激や指導を受けられなくなるので、精神的にも貧困になり、自己向上することが、なかなかできません。 友達や取引先との人的関係は、お金には代えられない貴重な財産なのです。したがって、それを失うことは、高価な代償を払うのに等しいのです。 日本の諺で、貧乏をすると、世俗的な苦労が多いので才知が鈍り、品性がさもしくなることを、「貧すれば鈍する」といいますが、まさしくこのような状態をいっているのです。
32 「貧乏になると、最初に顔に表れる」 “Poverty shows first on your face.”
私たちも精神状態や心理が表情に表れることを、「顔に出る」と言いますが、貧乏をすると、本人は気がつきませんが、知らず知らずのうちに、それが顔に表れるものです。 貧困からくる疲れや苦悩で、顔のつやや張りがなくなり、しわも増え、それに生気のない、よどんだ目になって顔に出ます。それが相手にそれとなく感づかれ、分かるのです。 だから貧乏をすると、損をするよということを、言外に意味しています。 この格言は、顔という比喩を巧みに使って、貧乏をしてはいけないことを教えているのです。
33 「金持ちであれば、みんなから、賢く、男前で、歌もうまいと言われるよ」 “If you are rich, people will say you are intelligent, handsome―and sing like an angel.”
「金持ちが自分の代わりに、人を雇って死んでもらえるなら、貧乏人は楽な生活を送れるに違いない」 “If people can hire people to die for them, the poor would make a nice living.”
34 「たまにしか入らない1ドルよりも、確実な10セントを取れ!」 “Better a steady dime than a rare dollar.”
「1セントを貯めないものは、いつまでたってもドルが貯まらない」 “Those who don't save pennies, don't have dollars.”
35 「きみを心底から信用するよ。だが、現金で支払ってくれ!」 “I trust you completely, but please send cash.”
「現金さえあれば、もっとも強い立場にある」 “So long you have cash, you're on the top.”
「現金が最良のブローカーである」 “The best broker is cash.”
36 「破れた袋に、いっぱい詰めることはできない」 “One can't fill a torn sack.”
靴がうまくフィットするなら、履くべし」 “If the shoe fits, wear it.”
37 「人に金を貸せば、敵を買ったことになる」 “You buy yourself an enemy when you lend a man money.”
「ビジネスは兄弟愛ではない」 “Business is not brotherhood.”
「金を借りる時は笑うかもしれないが、返済する時は泣く」 “If you laugh when you borrow,
「金持ちが貧乏人を支配し、借り手は貸し手の奴隷となる」 “The rich rule the poor, and the borrower is a slave to the lender.”
38 「お金を稼ぐより、節約することのほうが難しい」 “It is easier to make money than to keep it.”
「お金があるのは、もちろんいいことだが、それ以上に、お金を管理することのほうがもっといい」 “To have money is good, but to have control of money is still better.”
39 「ベーグルを全部食べてしまったら、穴しか残らない」 “If you eat up your bagel, you will have nothing left but the hole.”
「1セントを貯めれば、1セントを儲けたことになる」 “A penny saved is a penny earned.”
「わずかな金でも、自分の世界を太陽のように明るくする」 “Even a little money lights up your world like the sun.”
40 「アイデアには、税金がかからない」 “Ideas are exempt from duty payments.”
41 「いったん手がけたら、最後までやり通せ!」 “When you start something, finish it!”
たとえば、スポーツ分野一つを見ても、彼らは広く活躍しています。オリンピックで7個の金メダルを取った水泳のマーク・スピッツや、野球の名投手、サンディー・コーファックスや現役の強打者、ショーン・グリーン、さらにプロ・バスケットボールの名コーチ、ラリー・ブラウンは、みなユダヤ人です。
42 「仕事があれば、苦労から解放される」 “To have a trade is to be free of worry.”
「職業を持つことは、自分の王国を持つようなものだ!」 “A trade is a kingdom!”
43 「仕事が好きな人には、仕事がますます増える」 “He who likes his work, to him work comes easily.”
44 「自信を持つことは、勝利を半分手にしたようなものだ」 “Confidence is half the victory.”
「自信を持てば、人からも信用される」 “The man who has confidence gains confidence in others.”
45 「他人に頼るな、自分で実行せよ」 “Don't depend on others―do it yourself.”
「他人の歯でものは嚙めない」 “You can't chew with somebody else's teeth.”
「人の助けが要るならば、他でもない、それは自分の腕の先にある」 “If you ever need a helping hand, you'll find one at the end of your arm.”
46 「うぬぼれなければ、一体、誰がほめてくれるのか」 “If we did not flatter ourselves, nobody else could.”
ここでいう、うぬぼれとは、自信を指しています。物事を成就したり、人と折衝をしたりする際に、忍耐力や、しつこさがどうしても必要となります。自信や自尊心は、強い意志力とあいまって、その原動力となります。 これがなければ、自分の意志を貫徹させたり、達成させたりすることが、できません。つまり、適度なうぬぼれがなければ、それが実現できないのです。 逆に自信や自尊心のない人は、ねばりや執拗さがなく、えてしてその過程で気力を喪失し、それを中途で投げ出します。つまり、このような人には、物事の交渉をうまく成立、あるいは実現させる可能性が少ないのです。
「他人にアドバイスするほうが、自分にアドバイスするよりも簡単だ」 “It's easier to advise others than oneself.”
「賢人は人のアドバイスに耳を傾ける」 “A wise man listens to advice.”
「叱られて嫌がる人はバカだ」 “Whoever hates reprimand is stupid.”
「頑固の病に効く療法はない」 “There is no cure for the disease of stubbornness.”
47 「人が集まれば、お互いに話すべきだ」 “When people meet, they should speak.”
「学問は、集団を通じてのみ達成できる」 “Only through group, people can learn.”
「人はその会話で人柄が分かる」 “A person is recognized by his conversation.”
「世代は変わるとも、論議は尽きない」 “Generations come and go, but controversy lasts forever.”
「論理よりも美しいものはない」 “There is no greater beauty than that of logic.”
48 「例をいくら挙げても、立証したことにならない」 “’For instance’ is not proof.”
「自分が正しいと、あまり言い張りすぎると、かえって間違いとされる」 “If you insist too long that you are right, you are wrong.”
49 「沈黙は、知恵の周囲にめぐらした塀である」 “Silence is the fence around wisdom.”
「返答をしないのも、立派な返答である」 “No answer is also an answer.”
「しゃべりすぎると、 戯言 になる」 “If you talk too much, you talk nonsense.”
「話すことは、吠えることではない」 “Talking is not barking.”
「ぶたれた痛さは忘れるが、暴言はいつまでたっても忘れられない」 “A slap heals but a harsh word is remembered.”
50 「ビンの中に、コインが1個しかないと、音を立てるが、いっぱい詰まっていると、音を立てない」 “One coin in a bottle rattles, but the bottle filled with coins makes no sound.”
もう一つの意味は、���分の成功や幸運をやたらと自慢すると、人の羨望や恨みを買います。特にユダヤ人でない人から、それがもとで、迫害や差別されるかもしれません。したがって彼らは、お金持ちになっても、仕事がうまくいっても、それを口外することを極力避けます。 また、ユダヤ人の昔からの迷信で、物事がうまく運んでいる時や、幸運が続いた際に、これを口にしたり、自慢したりすると、不幸がやってくるといわれています。そこで自慢することに、なおさら控え目で慎重になるわけです。 ところで、ユダヤ人ビジネスマンは、幸運を口にしたり、自慢話をしたりすると、木製の机や製品を、指で、2、3回ノックする奇妙な仕草をします。 これは「ノック・オン・ウッド(knock on wood)」といって、木を叩かないと、せっかくの幸運や好事が逃げる、あるいは続かないという迷信に由来しています。
愚者は、すぐ怒るが、賢者は、頭の中身が詰まっているから、なかなか怒らない、冷静であることも意味しています。
「怒りは賢者を愚者にする」 “When a wise man is angry, he is no longer wise.”
「人が怒っている時に、なだめてはいけない」 “Never try to pacify a person when he is angry.”
51 「疑問を抱くことは、人を賢明にさせる」 “Doubts have made people wise.”
とりわけ、ユダヤ人は猜疑心が極めて強く、本能的に物事を疑う性癖が身に付いているといわれます。とくに権威や既成概念に対しては、警戒心や猜疑心をつのらせてしまいます。 これは、ユダヤ人が長年、世界各地で過酷な差別と迫害を受けてきたことと無関係ではありません。
そういうところから、彼らが絶えず物事を懐疑し、疑問を抱き、それをよく吟味し批判するようになったといわれます。これはユダヤ人にとって、本能的で体質的なものだ、とさえ極言されているほど、彼らの頭と体に深くしみ付いています。そのためユダヤ人は、会話の際に、疑問形を盛んに使うのです。
「人に好かれたいなら、その人の意見に同調するがよい」 “If you want men to like you, agree with them!”
52 「どんな返答にも、新たな疑問がわく」 “To every answer, you can find a new question.”
「知識が増えるほど、疑問も増える」 “As knowledge grows, so do doubts.”
「疑わしきは罰せず」 “Give every man the benefit of doubt.”
「バカな質問をすると、バカな答えが返ってくる」 “If you ask a foolish question, you will get a foolish answer.”
53 「人は好奇心を満たすためのみに生きるべきだ」 “A man should live if only to satisfy his curiosity.”
54 「見るのはタダ」 “It costs nothing to look at.”
私が、そのことを痛感するのは、初めての外国を訪問する時です。商売柄、これまで80カ国近く訪れましたが、どの国も、本やテレビで知っていた予備知識と、実地に行って見るのとではまるで印象が違うことです。例外なく先入観が打ち砕かれます。 たとえどんな未開発の貧しい国であっても、小さな国であっても、そこに行ってみて、やはり来てよかったと、いつも思うのです。
55 「10回尋ねるほうが、迷うよりもましだ」 “Better ask ten times than go astray.”
また、「耳学問」という言葉があります。自分で学んだのではなく、他人の話を聞いて物知りになることを意味します。これは、ともすれば、聞きかじりの知識と見なされますが、決して軽視してはいけないと思います。 というのは、相手がその分野に精通し、エキスパートであれば、その人から意見を求めたり、アドバイスを受けたりするのは、大変有益だからです。場合によっては、何にも勝る貴重な忠告ともなります。しかも、お金がかかりません。
「学ぶには、目よりも耳のほうが役に立つ」 “For learning, ear is more important than eye.”
「真理を追求しようとするなら、相手に耳を傾けよ」 “He who seeks the truth must listen to his opponent.”
私は文科系出身のせいか、技術者や医者の友人を非常に大事にします。なぜなら、彼らは私が無知で苦手な分野のことをよく知っているからです。たとえば、技術者であれば、パソコンやその部品を買う時に、どこの製品を、どこで買ったらいいかを聞きます。
56 「人は求めなければ、生きていけない」 “He that cannot ask cannot live.”
「内気な人は、いつまでも学べない」 “A shy person never learns.”
57 「神様は、どこにでもいることができないから、母親をつくった」 “God could not be everywhere―so He made mothers.”
「最良のフォークは母親の手である」 “The best fork is mother's hand.”
「母親のいない子供は、取っ手がないドアのようなものだ」 “A child without a mother is like a door without a knob.”
「母親は子供がたとえ口に出さなくても、それが何かが理解できる」 “Mothers understand what children do not say.”
58 「1人の母親は、100人の教師より勝る」 “One mother can do more than a hundred teachers.”
ユダヤ人は、何百年もの間、世界各地で厳しい迫害を受けましたから、その差別や苦難からくる経験が、この考え方をもたらしたのです。彼らは長年、離散した各地で土地や工場の所有を禁止されたので、やむなく頭を使って働く以外に手がありませんでした。その上、長年住み慣れた地から、突然、着の身着のままでいつ、追放されるとも限りません。
そこで彼らは、頭さえ良く、つまり賢ければ、どこに移り住んでも食べていけると考えていました。教育をしっかりと与えれば賢くなり、いい“頭脳”さえ持てば、どんな苦境や困難に直面しても、これを乗り越えられるというのが、ユダヤ人の、長い苦しい体験から生まれた確信と信念です。
59 「学習することは、一生涯の仕事だ」 “Learning is a lifelong occupation.”
ユダヤ人は他民族に比べて、人一倍、教育熱心です。聖典「タルムード」に、「ユダヤ民族は書物の人である」と記されているように、本を読み勉強することが、幼少の時から、一貫して日常生活や学校で徹底されてきました。中でもこの聖典「タルムード」をヘブライ語で読んで学ぶことを教えたのです。
たびたびくり返しますが、ユダヤ人は、頭さえ良く、つまり賢ければ、どこに移り住んでも食べていけると考えていました。それだけに、自分や仲間の教育について、ことさら力を入れたのです。
その地のユダヤ人集団が、たとえどんなに貧しくても、子供が読書できるように自分の���ずかな金を割き、これに重点的に振り向けたことから見ても、よく分かると思います。
「学習を怠る人はすべてに欠ける」 “The man who lacks learning lacks everything.”
「最大の貧困は無知であることだ」 “The greatest poverty is ignorance.”
「学習することは相続できない」 “Learning cannot be inherited.”
「無知な人には、老年は冬だが、学習を重ねた人には、それは収穫期だ」 “For the ignorant, old age is winter, but for the learned, it is the harvest.”
60 「学べば行動したくなる」 “Study leads to action.”
勉強をすれば知識の幅が広がります。その結果、当然のことながら好奇心や疑問が、大いにわきます。すると、なんでも見てやろう、聞いてやろうという衝動に駆り立てられます。そこで、必然的に行動に移さざるを得なくなることを意味している格言です。
「口数を少なくして行動せよ」 “Say little and do much.”
「行動を伴わない知恵は、木に果物が 生らないようなものだ」 “Wisdom without action is like a tree without fruit.”
「共同社会から自分を決して切り離してはいけない」 “Do not separate yourself from the community.”
61 「時間ができたら勉強をする、と言っていたのでは、いつまでたっても時間はできない」 “You say when I have time I will study, you may not have time.”
長らく住んでいる地を、突如、何の予告や前触れもなく、追放されることがありましたが、その際、何よりも真っ先に持ち出したのが、彼らの学習と精神のよりどころである聖典「タルムード」だったといいます。
62 「どの国の言語も、魔法のバイオリンのようなものだ」 “Ever nation's language is like a miracle violin.”
彼らは伝統的に、ことバイオリンに関しては、抜きん出た才能を持っています。たとえば、その名手を列記すると、ハイフェッツ、アイザック・スターン、メニューイン、イツァーク・パールマンなどと枚挙に 暇 がありません。
言語は、その国の文化や歴史を鏡のように反映します。どの国も、独自の美しい言語を持っています。
ユダヤ人は少なくとも数カ国語を操れます。これが当然の常識になっています。それは何も趣味からではなく、生活をする上で、つまりお金を稼ぐ必要に迫られて上達しているのです。
17世紀に入った頃には、すでに北アフリカやトルコばかりでなく、遠くインドにまでユダヤ人は住みつき、決して単独で生活することはなく、必ず共同生活体を形成していました。 その中心となったのがシナゴーグです。しかもユダヤ人はその地で、なんらかの商売を行い、持ち前の商才と勤勉さによって、ステイタスを確立していました。
63 「よく旅をする人は、知識が豊富だ」 “A person who travels knows a great deal.”
このようにユダヤ人は、旅行することの重要性を強調します。わが国のある学者が、いみじくも、「外国は自分の鏡である」と名言を吐きました。外国に行くと、何事も自分の国の実情や文化と比較するものです。世の中は相対的ですから、その長所や短所をどうしても見比べることになります。
このようにユダヤ人は、語学が得意だったことも手伝って、���際マーチャントとして頭角をあらわし、貿易に秀でる結果となりました。
つまり、ユダヤ人が語学習得に力を入れたのは、自分たちが厳しい環境の中で生計を立てるためばかりでなく、世の動きをいち早く察知して、生存するための手段としても、どうしても欠かせなかったからです。
64 「人は誰でも噓をつく」 “All men tell lies.”
約束は破られるためにある」 “Promises are made to be broken.”
「噓を1つつけば、1つの噓、2つつけば、2つの噓だが、3つつけば、それは政治だ」 “One lie is a lie, two lie are lies, but three are politics.”
65 「真実がもっとも安全な噓である」 “Truth is the safest lie.”
66 「半分が真実であっても、全部が噓となる」 “A half-truth is a whole lie.”
「噓つきが受ける罰は、本当のことを話しても、誰にも信用してもらえないことだ」 “A liar's punishment―even when he tells the truth, people don't believe him.”
67 「信用だけで生きる人は、道に迷う」 “He who lives on trust is lost.”
固い約束をしたなら、それは自分を売ったことになる」 “If you pledge yourself, you have sold yourself.”
そこでユダヤ人はうまい話があればあるほど、鵜呑みにせずにまず疑います。疑えば、頭をよく使って知恵を働かすことになります。すると、相手の言動や表情からさまざまな意図や狙いが分かってきます。特に相手が、海千山千の人物であればあるほど、彼のたくらみやだましの手段が予想でき、その対抗手段を前もって考えられるのです。
68 「人が不正直なら、それは盗みをするチャンスを失ったからに過ぎない」 “A man is not honest just because he has had no chance to steal.”
69 「すべてのサインは、人を惑わせる」 “All signs are misleading.”
この出来事以来、どんなサインでも頭から信用してはならないという貴重な教訓を、改めて二人は、いたく思い知らされたのでした。 ここでのサインとは、先の標識をばかりでなく、一般的に、「しるし」とか「兆候」も意味しています。見かけだけを信用してはいけない、まず疑うことの大切さを、諭しているのです。
70 「鍵は正直者だけを防ぐ」 “Locks keep out only the honest.”
また、鍵は比喩的な意味でも使われています。この諺の裏の意味は、大丈夫だと安心をしたつもりでも、世の中には悪知恵が働く人が多いから、念には念を入れて行動しろ、と忠告しているのです。用心深いユダヤ人ならではの金言といえます。
「木の葉が怖いなら、森の中に入るな」 “If you are afraid of the leaves, do not enter the forest.”
71 「泥棒にキスされたら、自分の歯の数を数えろ」 “When a thief kisses you, count your teeth.”
72 「豚に椅子を差し出したら、今度はテーブルに乗りたがる」 “Give a pig a chair, then he will want to get on a table.”
豚はユダヤ人が、もっとも忌避する動物ではないでしょうか。というのも、豚は昔から不浄とされ、ユダヤ教の教えでは、豚肉を一切口にしてはいけないからです。
つまり、そのような「無神経で欲張りな男の求めに気安く応じると、際限なく要求を増やしてくる」から用心しろ、と警告しているのです。
73 「歯のない犬は、それでも骨にかじりつく」 “A dog without teeth, will still attack a bone.”
ところが、そのような犬でも、意外な隠れた力を持っており、いざという時に牙をむいて凶暴性をあらわにします。 そのことを、人を犬に喩えて警告しているのです。つまり、一見、おとなしく無力と思われる人でも、思わぬ潜在力を秘めているものです。
日本でも、「 窮鼠 猫を嚙む」と言います。追い詰められたねずみが、死力を出して猫に嚙み付くように、弱者も窮地に追い込まれると、強者に必死の反撃を試みます。 そこでどんな人でも見下したり、なめたりしてはいけないのです。決して油断せずに、見かけだけで過小評価してはいけないことを忠告しています。
「歯のない犬は、違った生き物になる」 “A dog without teeth is a different creature.”
「猫が寝ている間に、ねずみは走り回る」 “When the cat is asleep, mice dance around.”
74 「穏やかな流れと穏やかな犬、それに穏やかな敵に気をつけろ」 “Beware of still water, still dog, and still enemy.”
「川面が静かなほど、川底の流れは速い」 “Still waters run deep.”
表面では穏やかに見える人物ほど、意外と腹黒く、あるいは激情を秘めているものです。 人を見かけだけで判断してはならないことを意味します。
「梯子を上る前に、段の数を数えろ!」 “Before you start to climb a ladder, count the rungs.”
75 「勝手に決め込むと、だまされることになる」 “To assume is to be deceived.”
「用心をする基本原則は、用心しすぎないことだ」 “A basic rule of caution: Don't be overly cautious.”
「悪友よりも、良き敵を選べ」 “Better a good enemy than a bad friend.”
「ラビのように尊敬しても、彼を盗人と疑ってかかれ」 “Treat him like a rabbi, but watch him as a thief.”
76 「真のビジネスとは、自分が取り扱っていない商品を見つけてきて、それを欲しがっていない人に売ることだ」 “To sell what you don't have to one who doesn't want, that is business.”
自分がつくっている製品を欲しがっている買い手を見つけて、なるべく高く、しかも多く売るのが、ビジネスの真髄とでも考えているなら、それは間違いだ。真のビジネスとは、自分が取り扱っていない商品を見つけてきて、それを欲しがっていない人に売ることだ」 “To sell what you have to one who wants it, is not business. But to sell what you don't have to one who doesn't want, that is business.”
77 「お金がないなら、駆け引きをするな!」 “Don't bargain if you don't have any money.”
78 「タダにすれば、お客がたくさん集まる」 “Charge nothing and you will get a lot of customers.”
「どの売り手も、自分の商品をほめたたえる」 “Every seller praises his goods.”
79 「人が何かをくれたら、すぐにもらえ、人が何かを取ろうとしたら、わめけ」 “If they give you―take, but if they take from you―yell.”
80 「しつこく戸をノックする人こそが、いつかはそこに入れる」 “The man who persists in knocking the door will succeed in entering.”
81 「忍耐力を持てば、金持ちであることよりも勝ることがある」 “To be patient can be better than being rich.”
82 「忍耐強ければ、それは知識と知恵の源泉となる」 “To be patient is the source of intelligence and wisdom.”
また、相手の話が長くなると、いらいらさせられて、ろくろく聞かないことが、よくあります。しかし業を煮やさずに我慢をすれば、相手の話を傾聴することになります。すると、今まで知らなかったことや、思いも及ばなかった事柄を、違った角度から教えられることが多々あるのです。 このように我慢強くなれば、さまざまな知識と知恵が得られます。それによって忍耐力が増し、どんな逆境に遭っても、立ち直れるだけの回復力が付いて、耐えられるようになるのです。その結果、人間は、たくましく成長していきます。ユダヤ人は、そのメリットを次のように的確に言います。
「人は、我慢さえすれば、自分の欠陥を美徳に変えられる」 “A man can transform faults into virtue, if he only perseveres.”
ところで、ユダヤ人と付き合って感じるのは、彼らが、物事、こと金銭問題に関して、大変、粘り強いことです。私たちが、総じて何事もあっさりとしていて、淡白なのと対照的です。
83 「『ありがとう』という言葉は、ポケットにしまってはいけません」 “You can't put ‘thank you’ in your pocket.”
84 「楽しい心は、良薬に匹敵する」 “A merry heart does good like medicine.”
このように聖書に記されていますが、たしかにユーモアがもたらす笑いは、気分や精神を和ませ、幸福感を呼びます。さらに困難や逆境に直面しても、それを乗り越えるための気力をつけてくれるのです。
ユーモアは、欧米社会、中でもアメリカ人の社会生活上、不可欠のものとされています。これは、わが国の実態とずいぶん違うようです。日本では社会人として行動する上で、ユーモア感覚があるかどうかは、必ずしも不可欠の要素ではありません。これに欠けても、アメリカのように、その人間の全人格的な評価にまでつながることは、まずないのです。
そこで、人物に対するほめ言葉や賛辞として、しばしば使われるのが、「立派なユーモア感覚を持っている」です。人を紹介する際や、追悼演説などで、よく耳にする言葉です。
85 「雪からチーズケーキはつくれない」 “Out of snow, you can't make cheesecake.”
これと同じことを、また具体的な比喩を使って、教えているのです。チーズケーキは、ユダヤ人の好物です。もちろん、いくらがんばっても、雪からはチーズケーキはつくれません。 つまり、いくら願っても、現実がそのように実現できないのなら、どんなに努力をしても無駄骨です。理想と現実を、明確に区別して、物事を実行することの重要性を強調しているのです。
「すぐ手に入る1セントは、将来の1ドルに匹敵する」 “A nearby penny is worth a distant dollar.”
そもそも東欧時代のユダヤ人は、さまざまな職業上の制限から、行商、仕立屋、靴職人、牛乳屋などといった雑多な職業に就いていました。それらの商売の規模が小さかったとはいえ、このような職業で培った現実的で基本的な商売のノウハウとその蓄積が、彼らの多くがアメリカに渡ってから、大いに役立ったのです。 東欧からアメリカに移住した彼らは��金やコネ、それに経験もなく、当初は、縫製のためにミシンを踏んだり、仲介業や行商をしたりして生計を立てました。
しかし彼らが、やがて成功を見たのは、その同じ時期に、大量に移民してきたアイルランド人やイタリア人と違って、伝統的に飲酒になじまず、倹約家で、しかも非暴力的であったからだといわれます。
アメリカという無限の将来性を秘めた新天地で、自らの力で生活を向上させ、運命を切り開かねばならないという、現実的な考えが、ユダヤ人を成功の道へと駆り立てました。たとえ給料が安くて、長時間働かされても、それでも希望を捨てずに、努力を重ねたのです。
86 「最悪に備えれば、最善が 自ずとやってくる」 “Provide for the worst, and the best can take care of itself.”
たとえば、着の身着のままで、長年住んだ土地から強制的に追い出されても、換金性の極めて高いダイヤモンド数個だけを、ポケットに忍ばせておけばよかったのです。場合によっては、それを飲み込んだと言います。それさえあれば、次に移り住んだ町で、新たに生計を一から立てることができます。
87 「レストランに行ったら、ウェーターに一番近い席を取れ」 “When you go to a restaurant, choose a table near a waiter.”
「嚙めないなら、唸り声を出すな」 “If you can't bite, don't growl.”
88 「同情とは、弱者が考え出したものだ」 “Pity was invented by the weak.”
「同情は、他人の心の悩みを癒す、ごく少量の薬にしかならない」 “Sympathy is a little medicine to soothe the ache in another's heart.”
「1皿の食べ物をくれる友は、ため息をつく100人の友に勝る」 “Better one friend with a dish of food than a hundred with a sigh.”
「同情を受けても、それは食べ物をもらったことにならない。しかし飢えを耐えさせるのには役立つ」 “Sympathy does not give you food, but it makes hunger more endurable.”
「助けられないなら、少なくとも同情の声ぐらいはかけよ」 “If you cannot help, at least make a sound of sympathy.”
89 「腹が空になれば、頭も空になる」 “When the stomach is empty, so is the brain.”
たとえば、バイオリンさえ持ち出せれば、移住先で、結婚式や催し物で演奏をして、金が稼げます。ユダヤ人にバイオリン弾きの名手が多いのは、あながち偶然ではないのです。
90 「バカは雑草のように、雨が降らなくても、どんどん、はびこる」 “Fools like grasses flourish without rain.”
とりわけ学習を重んじるユダヤ人は、知識の習得を好まない人も、この範疇に入れます。確かに絶えず勉強をしないと、知識や知恵がつきません。 しかも、学習をすると、目先にとらわれずに、自分の視野を広げることができます。それによって、世の動きをすばやくつかんで、変わり身を早くし、時流に乗ることが可能となります。つまり、生涯学習することは、ユダヤ人にとって生存する上で義務なのです。 バカに共通して言えることは、人や書物から知識を求めようとしないことです。
「バカは知識を嫌がる」 “Fools hate knowledge.”
「バカはおぼれかかっている人に、縄を投げる。ただし、両端ともに」 “A fool will throw a drowning man a rope―both ends.”
「バカは水を計るのに、ふるいを使う」 “A fool measures water with a sieve.”
91 「バカは、誰に教えられなくても分かる」 “A fool needs no informer.”
92 「羊は正面から、馬は後ろから近づくな。そしてバカにはどこからも近づくな」 “Don't approach a goat from the front, a horse from the back, or a fool from any side.”
「バカには質問をするな。ましてや説明すらするな」 “Don't ask a fool a question, or even give him an explanation.”
「賢人には、笑みを浮かべ、バカは殴れ」 “Give a wink to the wise, and a fist to the fool.”
「一人のバカは、多くのバカをつくる」 “One fool makes a lot of fools.”
93 「バカは転んで背中を打つばかりか、鼻の先まで擦りむく」 “A fool lands on his back and bruises his nose.”
「バカは、いつも与え、賢人は、いつも取る」 “Fool gives and clever takes.”
「バカが牛の角を押さえている間に、賢人はその牛乳を搾っている」 “If a fool hold a cow by the horn, a clever man can milk her.”
「バカは何でも鵜呑みにする」 “A fool believes in everything.”
「もっともバカなのは、自分を賢いと思い込んでいるバカだ」 “The biggest foolishness of the fool is who thinks he is smart.”
94 「バカを 市場 に行かせたら、バカになって帰ってくる」 “Send a fool to the market, and a fool he will return.”
「ユダヤ人が 市 に出ると、それはあたかも魚が水を得たようなものだ」 “A Jew at a fair is like a fish in water.”
「商人のやり口は、まず屑を見せて、その後に良品を見せる」 “The merchant's way is to show you first the junk, and later the good stuff.”
「バカを市場に行かせたら、商人たちは大喜びだ」 “When you send a fool to a market, the merchants rejoice.”
95 「バカとは決して商売をするな」 “Never do business with a fool.”
96 「バカに決して腹を立ててはならない」 “Never be offended by a fool.”
「バカはいつまでたってもバカだ」 “A fool is a fool forever.”
「バカはいつまでも年を取らない、ちょうど冷水がくさらないように」 “A fool does not age and cold water does not spoil.”
バカが、いつまでたっても年を取らないということは、いつまでも変わらずに賢くならないで、そのままでいるということです。それを、冷水が悪くならないことに喩えて、救いようがないことを意味します。
「バカを直す療法はない」 “There is no remedy for a fool”
どの民族にも共通する諺があるのは、実に面白いものです。というのも、わが国にも「バカにつける薬はない」と言いますから、バカはいくら教えても賢くなることはありません。
「なぜ、バカのワイフは、概して美人なのでしょうか?」 “Why is it that fools have generally pretty wives?”
そういえば私たちの周りでも、うだつが上がらない、賢くない男が、意外と身分不相応の美人の妻を持っていることが、よくあります。ユダヤ人も、そのような経験をしているものと見えます。どうやら美人を見分ける能力と知能とは、バカの場合、別の次元の問題のようです。
97 「賢く振舞うよりも、バカになるほうが、えてして得をする」 “To be foolish can be better than pretending to be clever.”
どんなに博学な人であっても、やたらと知識をひけらかして賢ぶり、自分のことばかり主張する人は、えてして交渉が下手だといわれます。 というのは、あまり自分の賢さや偉さを誇示すると、先方に必要以上の警戒心を持たせます。その結果、相手が隙を見せなくなり、交渉がしにくくなるからです。
しかし、人にはプライドというものがありますから、バカを振舞うのは常人にとって、決してなまやさしいことではありません。
「バカに振舞えるのは、非常に賢明な人である」 “Half-fool is a very wise man.”
バカを装うばかりでなく、ユダヤ人は、相手に質問を進んですることを決して忘れません。質問をして、相手が押し黙っていることは少なく、何らかの答えが返ってくるものです。
98 「数多い医者の中で、もっとも偉大なのは時間である」 “Time is the greatest doctor.”
「時間はすべてのものを変化させる」 “Time can transform everything.”
「時間は人を傷つけ、一方でその傷を癒す」 “Time brings wounds, but time also heals wounds.”
99 「何事も時間に抵抗することはできない」 “Nothing can hold against time.”
「悲嘆に暮れる時間は、また楽しくダンスする時間でもある」 “A time is to mourn and a time is to dance.”
100 「たとえ急いでも、 巧 速 であれ」 “Make no more haste than good speed.”
この反対語は、 巧遅 です。「巧みだが遅い」ことを意味します。日本で昔から、「兵は巧遅よりも拙速を尊ぶ」と言われるように、たとえ、まずくても、早いほうが、遅いことよりもいいとするのです。 特に一刻を争うビジネス業界にあって、「機先を制する」という言葉があるように、競争相手の企業に打ち勝つために、すばやく行動を取ることが何よりも要求されます。
また新製品を市場に紹介する際に、念入りな宣伝を行っていち早く広く店頭に並べ、すばやく手を打ったところが、同業者よりも強い立場を占めます。そこで、拙速主義という言葉が生まれたわけです。
「腹が減っては、頭も空っぽになるよ」 “When the stomach is empty, so is the brain.”
「世の中に、完全なものは何一つない」 “Nothing is perfect.”
「金言をタイムリーに引用するのは、あたかも飢えた人にパンを与えるようなものだ」 “A quotation at the right moment is like bread to the hungry.”
「返答しないのも、立派な返答である」 “No answer is also an answer.”
「安いものほど高くつく」 “Cheapest is dearest.”
事実、ある有力な統計によれば、アメリカの大富豪を保有財産でランク付けした上位400家族のうち、ユダヤ人が約23%を占めたといわれます。そのうちの上位30家族に限定すれば、実に約36%もユダヤ人だということです。 また、別の最新の統計では、全米の中位の家族年間収入が約4万2000ドルであるのに対し、ユダヤ人は約5万4000ドルと、約3割も高いのです。 さらに、有産階級と目される家族年間収入7万5000ドル以上のユダヤ人は、ユダヤ人家族全体の36%であり、これは全米平均の2倍にも当たります。全米に��めるユダヤ人の割合が2%にも満たない事実を考えると、まさに驚異的な数字です。 そればかりでなく学問の世界を見渡しても、アメリカの一流大学に勤務する教授の約20%がユダヤ人です。さらにアメリカのノーベル賞の科学分野における受賞者の約30%、全受賞者の約25%までがユダヤ人といいますから、なおさら驚かされます。
その一方で、ユダヤ人ほど誤解され、偏見を持たれる民族は、他にはいないのではないでしょうか。世の中には、彼らをシェークスピアの『ヴェニスの商人』の中の高利貸し、シャイロックに代表されるような強欲な守銭奴、あるいは拝金主義者だとする先入観を持つ向きが多いのです。わが国のユダヤ人に関する書籍も、偏見に満ちた、または見当違いの皮相的なものが少なくありません。 しかも、わが国の政治家や有名人、あるいは知識人が、無知としか思えない発言によって、これまでユダヤ人団体と大きなトラブルを起こしたケースが、絶えません。その最たる例として、軽率な反ユダヤ主義の記事のために、廃刊にまで追い込まれた雑誌があったくらいです。
どの民族や人種にも、良いところもあれば悪いところもあるものです。ユダヤ人とて、その例外ではありません。たしかに、彼らの表面だけを見れば、このような強欲とか守銭奴といった極端に悪い印象を受けるかもしれません。何を隠そう、私も、かつてはその一人だったのです。
しかし、ユダヤ人と公私にわたって親しく付き合い、彼らの歴史や思想に関する書を読むうちに、ユダヤ人が、あれだけビジネスや学問の分野で大きな力を発揮している背景に、極めて長くて深い歴史と文化があることを知ったのです。
それ以来、ユダヤ人は世界各地へと離散し、約2000年にわたる、長くて苦しい流浪の旅が始まります。移住先で、ユダヤ人は独自の宗教と習慣を頑なに守ったため、異邦人として扱われました。一時的に歓迎されても、やがては激しい迫害を受け、そこから追い出されます。その繰り返しだったのです。 中世から15世紀にかけて、彼らは移り住んだ先々で共同体を形成します。スペイン、イタリア、ドイツ、フランス、東欧に、ユダヤ人の大きな社会ができたのです。 しかしそこでも、厳しい差別に見舞われました。土地所有は許されず、官公庁の役職にもつけないという、さまざまな職業上の制限を受けます。しかも、その地方の王侯や権力者によって、彼らの居住地は一定の地区に制限されたのです。
それにも耐えて、今日までユダヤ民族としてのアイデンティティーを守り、生き延びることができたのは、このような逆境から生まれた英知としたたかさによるものです。それだけに、私たちが教えられるところが少なくありません。
嫌疑をかけられた者は、激しく拷問され、自白を強いられました。罪状に応じた鞭打ちや投獄といった刑はまだいいほうで、公開で火あぶりの刑に処されることもあったほど、筆舌に尽くしがたい迫害を受けました。 その結果、何千人ものユダヤ人が殺害され、生き残った者は、すべて国外に追放されたのです。スペインを逃れたユダヤ人は10万から20万人にも上ったといわれます。スファルディは、15世紀にスペインを追放されてからは地中海沿岸やトルコ、それに中近東へと散っていきました。
1880年代から20世紀初めにかけて、その厳しい迫害を逃れるために、多数のユダヤ人がアメリカに渡りました。その数は約200万人にも達したといわれます。さらにその後、ナチスによる激しい弾圧で、多くのユダヤ人がヨーロッパを去ります。 現在、アメリカに住んでいるユダヤ人の約9割までが、この東欧系のアシュケナジだといいます。その結果、世界中でもっとも多くのユダヤ人が住んでいるのはアメリカとなりました。最新の統計によれば、祖国イスラエルよりもその数は多く、現在、アメリカに約520万人住んでいるのに対し、イスラエルは約420万人です。 それにもまして重要なのは、ヨーロッパからアメリカに渡った多くのユダヤ人にとって、無限の可能性を与え、その優れた能力を伸張させたのが、アメリカに他ならないということです。 今まで長らく束縛されてきた、秀でた才能が、自由と機会、それに豊かな富に恵まれたアメリカというすばらしい土壌を得て、はじめて見事に開花することができたのです。 どの国を見渡しても、アメリカほどユダヤ人が、あらゆる分野で広く、しかも華々しく活躍をしている国はありません。 ユダヤ人がもたらした文化や経済力が、アメリカの発展にどれほど寄与したかは、その事例に枚挙に暇がありません。たとえば学問の世界を見渡しても、特に医学と物理学、それに経済学や文学の世界で著しく寄与しています。