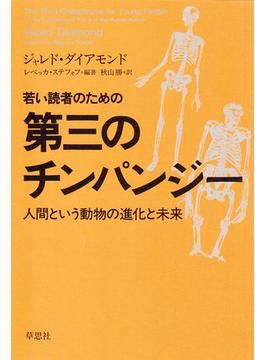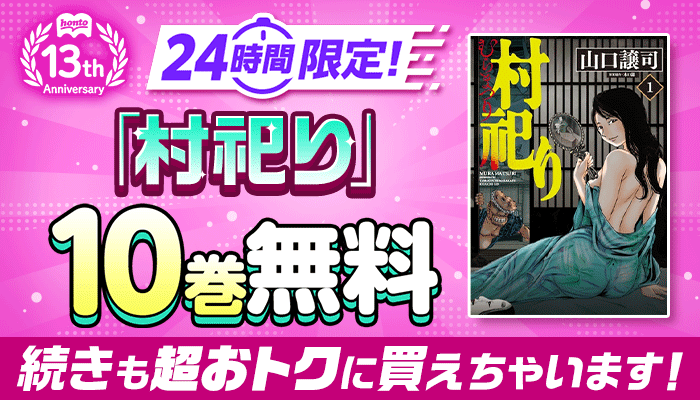若くない読者が読んだってばよ。
2015/12/20 23:26
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:朝に道を聞かば夕に死すとも。かなり。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ちっくしょー!!『銃・病原菌・鉄』を時間かけて読んだあの苦労は一体なんだったんだ!
本の扉で『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』等で展開されていくテーマが一冊に凝縮された本書とか書いてるし。理由は「おわりに」に書いています。
あ、『若い読者のための…』って書いているので、あんまりネタバレしないように書きますね。
「文明の勃興をめぐり、大陸間に現れる時間差は、ひと握りの天才によって引き起こされた偶然のようなものではない。それはまたある集団がほかの集団よりも知能に優れているとか、発明の才にまさっているというようなものでもない」というのが基本スタンス。
地理生物学、古病理学、進化生物学といった横断的ポジションから商品説明とか目次に書いている問題に取り組んでいます。
個別の領域の専門家の本ってことじゃなくて、おっきなテーマに学際的な試みをして考える人ってのが少なくてダイアモンドさんは先の著書で有名になりました。で、賛否両論あって、否って言う人は「こんなの想像で科学じゃないよ!」ってのが多いです。でも、本を読むと気づくのですが「腑に落ちる」感覚がぽろぽろと出てくるんです。
こういう本が怖いのは、科学性と本人の想像が折衷されたもの、とくに科学では再現性を強く求められるのですが、科学の特色は、現象がまず先にあって、科学ってのは現象にはこうしたことが「あてはまる」という作業をしているので、それ以外のことは触れないっていう原則があります。
でも、なんでジェノサイドが起こるの?なぜ薬物乱用が起こるの?格差問題は一体どこからはじまったの?っていう「なぜ?」に対応する言葉は哲学とかいろいろあるんですが、私たちの「なんとなく納得」度合いがダイアモンドさんの著書は多くて、読後感は「また時間が経ってみた後で読んでみたくなる」という新感覚トリプルスープのラーメンみたいなものなんです。
「あんなもん、ゲテモンだぜ。本道のラーメンじゃねーよ」って言う人がいるけど、新感覚トリプルスープのラーメンを食べた後は、誰かにそのことを話したくなる、そんな感じのお話なんですよ。ま、本屋さんで本を開いてみなはれ。
あの・・・これ、若い人に伝わりますかね?
類人猿から同時に進化した人間を、多方面の視点から詳細に分析している良書
2019/07/28 10:19
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:よっち - この投稿者のレビュー一覧を見る
700万年前に類人猿から枝分かれし、独自に進化した人間の特性を、進化生物学、地理学、比較人類学等広い視点で分析し、わかりやすく解説してくれています。
チンパンジーとは遺伝子的に98.4%同じでありながら、何故こうも違うのか。類人猿は仲間の前で公然と交尾を行うが、人間はそうではないのは何故か。人間の女性は閉経後、何十年も生きるが他の哺乳類ではまれ。芸術は人間だけの行為か。皮膚や髪の毛の色など人種の違いは何故起こったか。農業の功罪とは。人間がアルコールや薬にはまるのは何故。虐殺は何故起こる。昔から、人間は他の生物を絶滅させ、環境を破壊してきた。将来、人間は絶滅するのか。
著者は、これらの興味深いテーマを詳細に展開していいます。
読み終えると、人間という種について、人間社会のあり方について、これからの我々の未来について色々考えさせられる1冊です。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kemtarou - この投稿者のレビュー一覧を見る
DNA解析の進展により、人類に最も近い生物種はチンパンジーであり、その差異はわずか1.6%であることがわかっている。進化の過程で何が起きたか、要因になったできごととは何か、ヒトの生物学的特質と知能化などの各論で、多面的な分析を駆使しつつ、生物としての優劣ではない視点を導入した展開は斬新。幅広い学問領域の融合と開拓が示唆されている。
投稿元:
レビューを見る
『銃・病原菌・鉄』のジャレットダイアモンド氏の初期の
作品のバージョンアップ版だそうです。
大変面白い内容です。人間とはなにか?
人間特有の特性はいつ、なぜ、獲得したのか?
その後現在の人類として、大躍進をはたしたのか?
言語・芸術・農業・薬物・ジェノサイド・・・
将来的に人類はどういう末路をたどる可能性があるのか?
これから学問を目指す人たちに読んでほしい本だと思います。
投稿元:
レビューを見る
『銃・病原菌・鉄』で1998年のピュリツァー賞を受賞して一躍有名になったジャレド・ダイアモンドの第一作『人間はどこまでチンパンジーか?』(原語1992年、日本語訳1993年)を、最新の情報を取り入れて、コンパクトかつより読み易くしたもの。
前半では、私たち人間とはどのような生き物なのかを進化生物学的に解説し、後半において、人間がこの地上で行ってきた(いる)ことは何なのか、この先人間はどうなっていくのか(どうするべきなのか)を哲学的に考察する流れとなっているが、大まかな内容は以下である。
◆ヒトは、チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、テナガザルと並ぶ、霊長目5種のひとつであるが、最も近いチンパンジーとは98.4%のDNAを共有する。チンパンジー(コモンチンパンジーとボノボ)にとって遺伝的距離が最も近い種はヒトであり、ヒトはまさに第三のチンパンジーにほかならない。
◆ヒトは、700万年前にチンパンジーの系統から分れてから、常時二足歩行をする(=両手が使える)ようになったこと、恒常的に石器を使うようになったこと、また、少なくとも一度は他の猿人と分岐したこと(分岐したもう一方の猿人はその後絶滅)により、より人間らしくなったものの、“見た目がいささか立派なチンパンジー”に過ぎなかった。我々が“人間”になったのは、僅か6万年前で、当時少なくとも3種類いた人類(1.アフリカにいた解剖学的に現代人と同じ人びと、2.ネアンデルタール人、3.謎のアジア人)の中から、1のみが複雑な言葉を獲得することにより大躍進を遂げて現生人類(クロマニヨン人)となった瞬間である。
◆人間には、他の哺乳類と比較して奇妙な性行動(発情期がない等)、肌や目の色に象徴される人種の違い(これは自然淘汰ではなく、性淘汰によるものと考えられる)、一見不合理な加齢の仕方(思春期が遅い、生殖可能期間を過ぎても生きている等)などの人間性獲得のために不可欠であったライフサイクルの特徴があるが、それらはいずれも遺伝子により決定づけられたもので、人間の特異性を説明するものにはならない。
◆人間の特異性は、遺伝的基礎の上に築かれた、話し言葉、芸術、道具を操る技術、農業などの文化的特質のうちにある。但し、その特質はプラスのものばかりではなく、農業の発明は、階級の分化、栄養の偏り、伝染病などのマイナス面を生み出すことにもなった。
◆更に、人類は自らの生存を脅かす2つの文化的な性向を持っている。一つは、同じ種の異なる集団に属している相手をことごとく殺し尽くすというジェノサイド(大量虐殺)である。もう一つは、地球の温暖化や環境汚染、人口増加による食糧危機、生存に不可欠な生物の絶滅などの環境と資源基盤の破壊である。
そして、ダイアモンドは、最後半のネガティブな分析にもかかわらず、「本書がたどってきた過去から私たちが学ぼうとするのであれば、その将来はほかの二種のチンパンジーの将来より明るいものになるのではないだろうか」と結んでいる。
ダイアモンドの思考のベースが凝縮された一冊といえる。
(2015年12月了)
投稿元:
レビューを見る
人間とは何か?ジャレドダイアモンドの名著「銃・病原菌・社会」や「昨日までの世界」に加え「文明崩壊」を、わかりやすく、簡単にダイジェスト版で編集した本。
投稿元:
レビューを見る
「人間とは何か?」との問いに対し、科学的な考察をめぐらせる。
「若い読者のための」 とのタイトルに偽りなく、各章がコンパクトにまとまっている上、文章も平易で、非常に読みやすい。
例えば、
・人間とチンパンジーはDNA的には98%以上共通する
・なぜ人は「隠れて」性行動するのか、なぜ人種の差異が生まれるのか、なぜ人は老いるのか…
・言語、芸術、農業、酒タバコ薬物の乱用等からわかる人間の特質(ex.農業は「よいもの」で、「進化の道しるべ」なのか?)
・地理学が「進化の基本ルール」を決める
・ジェノサイドはなぜ起こるのか
・繰り返される環境破壊
…と、興味深いトピックを豊富に扱っており、飽きずに読み切れる。
投稿元:
レビューを見る
「どうやら私たちは、幼いころから刷り込まれた美しさの基準、愛着を覚える美の基準にしたがって、自分の配偶者を選んでいるようである。」という考えに納得がいかなかったのは、配偶者と知り合ったのが30年前であるので、その時は作者の考えのように配偶者を選んだのか今となっては知り様もないのです。だからこの本のタイトルの頭には”若い読者のための”が加えられているのかな。全体を通して目新しい情報はなかったように思いました。『銃・病原菌・鉄』の論旨と似たような印象を持ちました。
投稿元:
レビューを見る
私達が「動物」という言葉を使うとき、それはイヌ、ネコ、サル、ライオンなどをイメージする。そこに魚や鳥を含めることもあるが、あくまでも人間は含まず「人間は動物とは異なる」と認識している。確かに文明を発展させ人口を増やしてきた人間は、地球上でもっとも成功した生物種だという点で特別な存在だろう。しかし私達が「動物」の一種と見なしているチンパンジーは、人間と98.4%の遺伝子を共有しており、その違いはわずか1.6%だ。遺伝的な距離の点からすれば、人間はチンパンジー(コモンチンパンジーとボノボ)と同じ属として扱われるべきで、その点で「第三のチンパンジー」にほかならない。なぜ遺伝子のたった1.6%の差異がこれほど大きな違いとなったのだろうか。それが「人とは何か」を論じた本書のテーマだ。
著者は、ヒトの祖先が言語能力を獲得したことが進化の大躍進の引き金になった事、なぜ多様な人種が存在するのか、なぜヒトの寿命が100年程度であるのかその理由、狩猟採取民族だった人間が農業と牧畜の技術を得たことで階級格差が生じた経緯などの、人類進化と文明の発展についての考察を、進化生物学、生理学、生物地理学などの観点から明快に論じており大変説得力がある。
しかし急速に文明を発展させてきた人類は、現代も社会問題の根底にある2つの特徴を背負っていた。そのひとつが大量の人間を殺し合う残虐性で、これまでも人種、宗教、政治的立場などを理由に大量虐殺が行われてきたし現在も核兵器が存在する。もうひとつの特徴が環境と生活基盤を破壊しようとする性質だ。人間は多くの大型哺乳類を狩り尽して絶滅させてきたし森林の木を伐採しつくして砂漠に変え、栄えていた文明を滅ぼしてきた。現在も動植物の種の絶滅が進んでおり、人間の手による環境破壊が深刻な事態であることは周知の事実だ。
それでも、人間の未来には希望が無いわけではない。人間は遠隔地のことでも過去の事でも、他の仲間の経験から学べる唯一の動物だからだ。核による殺戮は広島と長崎の後は行われておらず、環境問題に対する意識も広まろうとしている。「過去を理解し、過去から学び、それを将来に役立てることができれば、人間の将来は他の2種のチンパンジーより明るいものになるのではないか」著者はこう訴えている。これからの世界を担う若い世代の人達に特に耳を傾けてもらいたい。
本書は『人間はどこまでチンパンジーか?』の内容をアップデートし、特に若い読者のために書き改めたものであるが、文明の発展や崩壊、伝統的な社会と現代社会の比較などについては、著者の『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』『昨日までの世界』にも詳しく述べられている。人間社会の営みと文明の発展、衰退の関わり合い、現代社会の問題点などについても深く考察されていて大変興味深いので、これらも是非読んでもらいたい。
投稿元:
レビューを見る
サル学.分子生物学.社会学.人種等の最新の知見を網羅している。専門書と言うには読みやすく、エッセイよりは深い内容だと思った。
後半はちょっとだれ気味だが、前半は実に面白い。
投稿元:
レビューを見る
面白い。著者のこれまでの著作を踏まえた上で、人類の歴史を振り返っている。
しかし、最後の章の環境破壊、種の絶滅に対する内容はひどくしつこく感じた。
投稿元:
レビューを見る
DNA解析の進展により、人類に最も近い生物種はチンパンジーであり、その差異はわずか1.6%であることがわかっている。進化の過程で何が起きたか、要因になったできごととは何か、ヒトの生物学的特質と知能化などの各論で、多面的な分析を駆使しつつ、生物としての優劣ではない視点を導入した展開は斬新。幅広い学問領域の融合と開拓が示唆されている。
投稿元:
レビューを見る
1991年(邦訳は1993年)に出版された『人間はどこまでチンパンジーか?』 という著作の内容を現在の知見に沿ってアップデートするとともに、若者にターゲットを絞って書き換えたものだという。元の本を読んでいないので、どこを変えたのかわからないが(※)、その後に出版され、著者ジャレッド・ダイアモンドの名声を高めた『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』『昨日までの世界』の各書で扱われた主要なテーマがこの本の中ですでに扱われている。その内容は逆にそれらの本から本書の再出版にあたっての編集においてフィードバックされたものである可能性はあるのだが。
具体的には、『銃・病原菌・鉄』で主に論じられた、特定の地域で文明が発祥し広がった理由は、その地域に住む人の遺伝的特性ではなく、地理的特性や動植物の違いによるという説について第12章「思いがけずに征服者になった人たち」にそのエッセンスが簡単にまとめて書かれている。『昨日までの世界』の内容は、第11章「最後のファーストコンタクト」に書かれた内容と一部が重なっているし、『文明崩壊』で書かれた印象的なイースター島の悲劇が環境破壊の末の滅亡の記録として第14章「黄金時代の幻想」に書かれている。
ちなみに、第三のチンパンジーとは、コモンチンパンジーとボノボに次ぐ第三のチンパンジーであるという意味だ。遺伝子レベルの差異でいうと彼らと現生人類とはわずか1.6%しか違っていない。著者は、彼らと我々現生人類との間で違いの主因となっているのは「言葉」であるとしている。思いのほか売れているユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』においても、決定的な違いは言語能力、つまり抽象的なことを伝えることを可能とする能力、であるとされており、その他多くの識者がその認識を共有するところである。そして、それが生物学的には脳の思考能力というよりも、声道に起きたいくつかの変異が原因であるかもしれないとしているのも定説になりつつある。
『サピエンス全史』やダニエル・E・リーバーマンの『人体600万年史』など最近読んだ他の著者の本とを合わせて読むと、人類史における言語の影響だけでなく、農業や疫病、都市化、芸術、環境に与えた人間の影響、などについて一般的な評価が定まってきているように思える。それらの科学的議論一般の理解において、先鞭を付けたという観点でもジャレッド・ダイアモンドが果たした役割は大きいといえるだろう。
本書は、「若い読者のための」と銘打ってあるからだろうか、最後において人類にかかる二つの暗雲として、人類が持つジェノサイドの歴史と地球規模の環境破壊について解説している。少し説教臭いのだが、将来のために考えてほしいというメッセージなのだと思う。
同じ著者の『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』『昨日までの世界』を読むのであれば、そちらの方がきちんとまとまっているので、この本を読む必要はないだろう。逆にいうと、論理が甘かったり、事例が少なかったりしているが、ジャレッド・ダイヤモンドの思想について手軽に知るには若い読者によらずよい本かと。
※ 『人間はどこまでチンパンジーか?』はAmazonで見ると590��ージ。本書は350ページと書かれているので、結構手を入れてわかりやすく短く編集しているのかもしれない。近年の研究の結果として、修正・削除をしたいところもきっとあったのかと。もちろん間違えたまま版を重ねるよりもずっとよいのだけれど。
---
『文明崩壊 滅亡と存続の命運を分けるもの(上・下)』のレビュー
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4794214642
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4794214650
『昨日までの世界―文明の源流と人類の未来(上・下)』のレビュー
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4532168600
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4532168619
『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福(上・下)』のレビュー
https://booklog.jp/edit/1/430922671X
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4309226728
『人体600万年史:科学が明かす進化・健康・疾病(上・下)』のレビュー
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4152095652
https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4152095660
投稿元:
レビューを見る
道具の使用は、動物界に明らかな起源をもつヒトの特徴にほかならない。人間のほかにもキツツキフィンチ、エジプトハゲワシ、ラッコなど、動物にも食べ物を捕らえたり、加工したりするために、同じく石や枝を道具として使うように進化してきた生き物がいる。だが、人類ほど道具に頼っている動物はほかにいない。(p.40)
人間が言葉を話す能力とは、たくさんの構成要素と筋肉が正しく機能しているおかげなのである。類人猿のように、限られた子音と母音しか出せなければ、人間の語彙はまったく限られたものになってしまう。つまり、人間を最終的に人間たらしめた不明の要素とは、人間の声道に生じたなんらかの変化—さらにきめ細かく音声をコントロールでき、もっと幅広い発声を可能にした変化だと考えられるのだ。筋肉や柔軟な組織に生じたきわめてささいな変化であるだけに、頭蓋骨の化石に現れることはなかった。(p.62)
人間の性行動の進化をめぐり、もっとも激しく交わされている議論は、なぜ私たちは排卵を隠すようになったのかであり、こうした排卵の時期を逸した性交渉にどんな利点があるのかという疑問だった。セックスは楽しいが、それは進化によってそうなったからである。(中略)
・隠された排卵と性交は、男性間の攻撃を抑制して、協力を引き出すために進化した。
・隠された排卵と性交によって、特定のカップルの絆が強まり、ヒトの家族の基礎ができていった。(p.81)
ある意味、進化とはエンジニアのようなものである。進化もまた、動物のほかの部分を切り離して個々の特質に限っていじり回すことはできない。器官、酵素、DNAなど、いずれもほかのものに使えたかもしれないエネルギーとスペースを使って作り上げたものだからである。個別にいじるかわりに、自然淘汰が選んだのは、その動物が繁殖成功度を最大化できる物質の組み合わせだった。エンジニアも進化生物学者も、なにかを増大させるなら、そこにはトレードオフ(差し引き関係)がかかわっている点を踏まえたうえで考えなければならない。(p.115)
捕らわれの身にあれば絵を描いていたチンパンジーが、どうして野生では絵を描こうとはしないのか。その答えとして私が考えるのは、野生に生きるチンパンジーの日常は、食べ物を探すこと、生き延びること、ライバルの群れを追い払うことで精一杯だからなのだ。野生のチンパンジーにもっと余裕ができ、絵具を作る能力をもちあわせていれば、おそらく彼らも絵を描きはじめるようになるだろう。(p.164)
言語が少なければ世界中の人びとが意思を交わしやすくなるので、消滅はむしろ良いことではないのかとも考えられる。そうかもしれないが、ほかの面ではまったく望ましくはないのだ。言語はそれぞれ構造や語彙が異なっている。感情や因果関係や個人的な責任をどう表現するかという点でも異なる。人間の思考をどう形づくるのかという点でも言語によって異なる。だから、この言葉こそ最善だというたったひとつの言語は存在しない。そのかわり、目的が異なればもっとそれにふさわしい言語が存在している。言語が死に絶えてしまうとは、かつて��の言葉を話していた人たちが抱いていた独自の世界観を知る手段さえ失ってしまうことになるのだ。(p.223)
旅行やテレビ、写真、インターネットに寄って、何万キロも離れて暮らす人たちも、自分たちと変わらない人間としてみることができるようになった点だ。ジェノサイドを可能にする「我ら」と「彼ら」のあいだの境界線は、技術によって曖昧になってきている。ファーストコンタクト以前の世界では、ジェノサイドは受け入れられ、賞賛さえされていたが、国際的な文化と遠隔地に住む人びとに関する私たちの知識が現代になって急速に広がり、ジェノサイドを正当化するのはますます難しくなってきた。
だが、ジェノサイドの可能性は私たちすべての人間のなかに宿っている。世界の人口が増えていくにしたがい、社会間や社会内でのせめぎあいはますます激しいものになっていくだろう。(pp.268-269)
投稿元:
レビューを見る
人間とは何か?と言う問いを哲学ではなく地球という生態学の中で深く掘り起こしたもの.「若い読者のための」とタイトルのトップについているが,まさしくこれからの地球人にこそ考えて欲しいことだと言うジャレドの想いが伝わる.
「一筋縄では解決しようのない,生態系の問題解決に失敗」した先人たちにどう学ぶのか,隣人たちとどう共生して行くのか,未来はそこにかかっている.たくさんの人に読んで欲しい本だ.