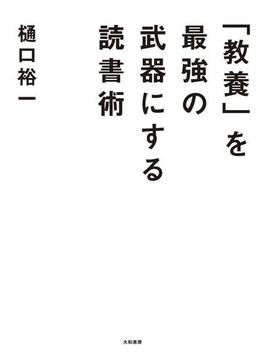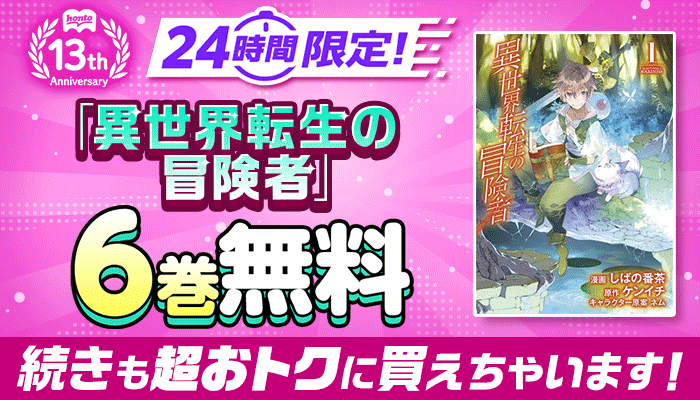0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kazu - この投稿者のレビュー一覧を見る
読書術、いうより、読書案内、というほうがしっくりする感じがします。
しかし、教養、とは一体何か、の記述部分は、なるほど、と思うことばかりで、読書をはじめ学ぶ時の指針になりそうです。
これについて学びたいけど…、文学を読んでみたいけど…、どれから読めばいいかわからない、という人におすすめです。
紹介されているのは、読んだことはないが題名は知っている、というような名作が多い印象です。手の届かない本だとあきらめていたものが、近く感じられるようになりました。
少しずつ、読んでいきたいと思います。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Y - この投稿者のレビュー一覧を見る
私が本書を読んだ理由は、特に小説の読み方について知りたかったから。12のジャンルから本を紹介していた点は魅力的。
投稿元:
レビューを見る
読書は好きだけどジャンルが偏ってしまう・・・日頃から感じていた自分の弱点に刺さった一冊。
ノンフィクションが好きな人は結果を重視した表面的なものの見方をして、過程を軽んじる傾向にある、という言葉が心に刺さりました。
もっと深く思考できる人になりたい。他の価値観を認められる人・ちょっとした情報から他人の考え方を想像できる人になりたい。そんな思いがありました。
この本では読書を12のジャンルに分けていて、各ジャンルの入門書と「なぜそのジャンルを学ぶとメリットなのか?」を説いています。
自分の持っていない知識がほしい、新しい領域に挑戦したい、そんな人にはぴったりの作品だと思います。
投稿元:
レビューを見る
マイブーム「読書とは何ぞや」を知るための読書、第五弾。
解説付きの良書のカタログ、といった感じ。
読めば読むほど、読書欲が湧いてきます。
そもそも、何で読書が必要なのかというと、本書には次のように書いてあります。
「本を読み、著者の考えを知り、小説の登場人物の価値観を知ることによって、多様な価値観を理性的に理解できるようになる。書物の中の言葉を使って、自分の考えを発信できるようにもなる。つまり、芸術、文化に触れることも大事だが、読書をすることは教養には不可欠なのだ。」(p.21)
読書に関する本を読んでいて、度々登場する言葉「教養」。
教養を身に付けることで、多様な価値観を理解できるようになる。
そして、それを元にさらに多様な考えを生み出していける。
私には、まだまだ教養が足りません。
投稿元:
レビューを見る
具体的にどんな本を読むといいかが書いてあった。
読むジャンルは、バランスが重要。
そして、フィクション、ノンフィクションをバランス良く読むことも大切。
チャートに答えて、どんなジャンル、作家を読むといいかが分かった。
確かに、普段読まないジャンル、作家だったから、これを機会に読んでみようと思う。
投稿元:
レビューを見る
最近、自分はどういう読書をしたいのか、と迷っていたが、再び読書意欲が湧いてきた。この本を参考に、興味のある分野から試しに読んでみようと思う。
投稿元:
レビューを見る
筆者の教養を深めるための読書方法の紹介。
まず、教養とはどのようなものか、読書ができることをまとめて、ノンフィクションとフィクション(小説等)にわけて書いている。ノンフィクションは、12分野に分けてあり、フィクションは世界文学か日本文学かという軸と、人間模様か思想かの2つの軸で分けてある。
巻末には参考資料もあるので、何から読み始めたらわからない人にはよい指針になるだろうし、教養の穴があると思っている人にはそれを埋める場所がわかるだろう。本書を元に、もう少し難しめの読書案内まで読めるといいかなと思った。
投稿元:
レビューを見る
“教養”、最近では“地頭”なんて言葉でも表現されますが、
具体的にはどういうことなのでしょう。
一言でいえば「価値観の多様性を認識すること」だと、個人的には思います。
“教養があるからこそ、幅広くものを考え、
他人の要望も理解したうえで判断できる。”
教養はたくさんの価値に触れることで育まれる、
それではその“多様な価値”に触れるための近道はというと、
やはり“読書”だと、思います。
多種多様に存在する“本”への触れ方を知り、
推測し、そして許容することが大事ですよと。
読書が知の座標軸を創るとは、ストンと落ちてきました。
“教養を身につける読書の基本として勧めたいのは、
ノンフィクションとフィクションの両方を読むこと”
そして、ノンフィクションから入りましょうというのが、興味深く。
「環境」「日本文化」「政治」「ポストモダン」
「歴史」「哲学」「人権」「宗教」「心理」
「日本語」「自然科学」「自己啓発」
と、12分野に分けた上で、それぞれはじまりの一冊を紹介しています。
詳細は省きますが、読みたい本が順調に増えてしまいました。
で、これを踏まえた上で、フィクション、、“文学”に突入します。
“読みたいと思ったものを、好きなように読むのが文学の醍醐味”
とされて「教訓的に読まない」のが大事だと。
心の赴くままに書き手の想いをすくい上げ、浸っていく。
この基盤になるのは、ノンフィクションから得られる知識なのだな、と。
興味深かったのは、日本と西欧の“物語”へのスタンスの比較。
“西洋の作家にとって物語を書くということは、
世界の再創造に等しい”
“(日本の作家は)自分自身の世界へ、
また、現実世界へ引きずり込むことに神経をくだいている”
西洋はトールキンやムアコックなどが、
日本であれば、漱石や太宰などが、思いつきます。
“教養を身につけたいなら、自分が好きな作品を読むのが一番”
好きこそなれの、というわけでもないでしょうが、
自分が読みたいと思ったものを読むのが印象に残るのは確かです。
ちなみにこちらは、書店をブラウジング中に出会いました。
こういった出会いがあるからこそ、書店巡りは止められません。。
投稿元:
レビューを見る
「教養」と聞くと、私は宮本輝さんの『螢川』を思い出す。息子を失った父が「教養がないがや」と喚くシーンがあって、とても印象深い。
記憶には残っているが、その意味はうまく汲み取れない。それは私に教養がないからだと思う。本書を読んでみてそれを痛感した。
ノンフィクションのところでは、自分の読書経歴の虫食いっぷりが明白になった。教養がないがや。
フィクションでも結果は酷いものだった。兎角、左下に偏りすぎている。お陰で、どうして今までミステリを避けていたのかが分かった。ああ、教養がないがや。
ピックアップされている本は、(読んだことはないけれど)尤もだな、と思うものばかりだった。推薦書リストを見るだけでも、本書を開く意味はあると思います。お薦めです。
投稿元:
レビューを見る
私の場合、読書は趣味の一貫としてやっていますが、できることならば読書を通して教養を深める・高めることができれば嬉しく思います。そのためには特定の分野や著者に偏ることなくバランスのとれた読書をしなければなりません。頭では分かっているのですが、どうしても興味のある分野が中心になっているのが現状です。
そんな私にとって、三色ボールペン等で有名になった樋口氏の書かれたこの本は、教養を武器にするための読書術として、ノンフィクション・フィクションにわけて推奨本も含めて提唱してくれています。この本で取り上げられた本を何冊か読むことで、私の人間の幅を広げていきたいです。
この本から得た素晴らしいメッセージは、フィクション・ノンフィクションをバランスさせる(p22)、および、読書をして教養を身につけることで、自分という一人の人間の経験や考えを中心にしながらも、それを絶対視せず、ものごとを相対化しつつ考えるということが可能になる(p28)ということでした。
以下は気になったポイントです。
・教養をつけるのにふさわしい本を読み、自分の読みたいものを的確に探し出して読んでいけば、必ず読書好きになり、教養が身につく(p2)
・教養を身につける読書の基本として勧めたいのは、ノンフィクションとフィクションの両方を読むこと、どちらかに偏るのではない(p22)
・読書をして教養を身につけることで、自分という一人の人間の経験や考えを中心にしながらも、それを絶対視せず、ものごとを相対化しつつ考えるということが可能になる(p28)
・複数の視点を獲得するという40代の読み方から、歴史的な視野で読み、知識を体系化させるのが、50代の読み方(p32)
・政治は戦争の歴史とは切り離して考えられない、「それでも、日本人は戦争を選んだ(加藤陽子)」は、現代人が読んでおくべき本(p54)
・文化や政治の転換期であった中世を中心にまとめられた、比較的読みやすい本として「日本の歴史をよみなおす(網野氏)」(p70)
・ニーチェの思想を体系的に知りたい人は、ニーチェの入門書として「ニーチェ入門(竹田氏)」(p75)
・日本語では状態に主体をおく、外国語では「する」(動作)に主体を置く。それが鉄道の駅名にもでてくる、日本の場合には場所の名前が普通、海外では人名のついた駅が普通に存在する。日本語の主語について分析した「日本語は敬語があって主語がない「地上の視点」の日本文化論(金谷氏)」(p101)
・動物の大きさや体重に着目して、生物の謎を解き明かす「ゾウの時間、ネズミの時間、サイズの生物学(本川氏)」(p110)
・ノンフィクションは、多読で知識の幅を広げる方法と、精読で知識を深める方法の両者を併用する(p117)
・本を読み終わったら、得た知識を発信してみる、得た内容を自分の中に蓄えておくだけではなく、他人に教えたり、ブログやツイッターで発信することで、知識を情報に転換する、これにより教養の身に付き方は大きく違ってくる(p120)
・��学の読み方の最初に挙げたいのは、そのように主人公になりきってみること(p124)
・文学の読み方のポイント、主人公と追体験・教訓的には読まない・文体や描写を味わう・よくわからない凄さを楽しむ・相性のいい作家を見つける、である(p131)
・現代のサラリーマンの意識を現代の設定でそのまま描くと、非常につまらなくなるが、時代小説(例:鬼平犯科帳(池波氏)、蝉しぐれ(藤沢氏))を現代ビジネスマンの啓発書として読む(P174,177)
・らくらく・じっくり読み、人間模様・思想読みのどの軸が自分の関心や興味の座標軸かどうかを明確にしておくと、読んだときの記憶も蘇りやすい(P201)
2013年11月17日作成
投稿元:
レビューを見る
教養がないと嘆く人→芸術,知識を語る言葉をもっていないときに感じる。→自分に足りないものを感じている。→準備ができている。
トルコ旅行にて 海外で思いやりのある人,知的に寄り添ってくれた。
読書のメリット→関心が内外に向かう。
ドストエフスキー「罪と罰」→主人公の行動,殺人,罪を体験,自分も殺人をしかねない→教養のない人ほど,自分を善人と思いこむ。
自分の中にも凶暴な精神があることを認め,だからこそ理性的に抑制している。
揺るがない知の座表軸→特定の本に感化→自分の意見が体系化
30代→このテーマならなんでも語れるくらいに突き詰める。
40代→古典的名著,経験をもとに批判精神をもちながら読む。
50代→これまで読んできたものを振り返ってみる。
①環境 1962年レイチェル・カーソン「沈黙の春」 農薬DDT,煙突の煙→きれい。環境問題を発見した。
②日本文化 日本人の奥にあるムラ社会のあり方
文化は見えないから,無意識レベルまで入り込んでいる。現代人は合理的に清潔に生きているつもり→土地や風土に根ざす前近代的な価値観に従っているにすぎない。
③政治 ざっくり全体像→各論。さまざまな問題(不景気,格差,外交,慰安婦)
マルクス「共産党宣言」「資本論」→難しい 小牧治「マルクス」
④ポストモダン 構造主義→自分が属する集団社会の価値を反映している。
近代化の思想
マルクス主義,実存主義(現実を望ましい方向へ変化させよう)→構造主義(進化だけが重要ではない。未開なものも根は同じで,構造に違いがあるだけ)
⑤歴史
⑥哲学 ニーチェ「権力への意思」
精神と物質がどう関係し合い,結びつくのかを説明するのは限界がある→養老猛司「精神とは物質である脳そのもの」
⑦人権 水俣病,部落差別
⑧宗教 「自分なんて,全宇宙の中のほんの小さな一部なんだ」
⑨心理 教養と自己コントロール能力は非常に近い関係
⑩日本語 曖昧にしか理解していない。ずっと同じ文化の中にいるためなんとなくやり過ごしている。
⑪自然科学 理解できなくても,自分の知らない世界があることを認識するきっかけ
⑫自己啓発
文学は教訓ではない。→小学校の国語は教訓的に読まされる→×「この作品の教えは?」○「作者は何を伝えようとしたのだろう?」
文学=よくわからないけど,すごい→感じる。
西洋の作家 作品の初めで世界をつくる→登場人物紹介→我慢して読み進めればよい。
鬼平犯科帳 江戸時代のサラリーマン→現代の設定ではつまらないので,江戸時代
投稿元:
レビューを見る
多様な価値観を共有できる人こそ、真の教養人と呼ぶ。
人生の悩みは若い時だけものではない。年を重ねて、経験を積むほどに、悩みが深くなるということもある。そういう時に考え方や視点を変え、自分を取り戻す方を知っているのが教養人の証。
投稿元:
レビューを見る
【超速読】
読書法というよりは、何をどのように、どの順で読んでいくか、そのとっかかりを作ってくれる本。つかみにくい教養というものを手に入れる道筋を示してくれそう。
2014.8.27
投稿元:
レビューを見る
世の中、ちょっとした「教養」ブームみたいになってますが、「教養」って何かの資格みたいにささっと勉強して身につけられるものではないと思うんですよね。
つまり、知識とかスキルのような類ではなく、その人の佇まいというか、存在そのものから立ち昇るオーラみたいなものに近いんじゃないかと。
一朝一夕で何とかなるものじゃなく、やはり日々の積み重ねそのものだと思います。
古今東西、様々な考え方に触れることで、自分自身を相対的に、客観的に見られるようになること。そういうものも教養だと言えるとすれば、本著のような読書ガイドは非常に役に立ちます。
読みたい本を読みたいように読むのがベストだと思いますが、自分の読書の傾向や偏りを把握しながら、時にはめったに手に取らないエリアに進出することでバランスを取ってみるのも、視野が広がっていいなあと思うようになりました。
投稿元:
レビューを見る
著者は仏文学、アフリカ文学の翻訳家として活動するかたわら、小学生から社会人までを対象にした小論文指導に携わり、独自の指導法を確立。通信添削による作文、小論文専門塾主宰。現在、多摩大学教授。
教養があるからこそ、幅広くものを考え、他人の要望も理解したうえで判断できる。
教養とつけるのにふさわしい本を読み、自分の読みたいものを的確に探し出して読んでいけば、必ず読書好きになり、教養が身につく。
本書は、上記の通り、読書から教養を積む方法を著者の経験をもとに以下の3項目から説明している。
①教養を人生の武器にせよ
②はじまりの1冊から教養を広げるノンフィクション読書術
③何からどう読むか?文学作品を味わう読書術
どんな本がおもしろいですか?
結構良く聞かれる質問。
そして私も常にその疑問を持ちながら選書している。
全てにおいては何を読むかというとっかかりが一番大切である。
ノンフィクション・文学作品や洋書等幅広い分野について、まずはこれから的な1冊を紹介していたり、分野ごとの切り口や次のステップの本の提示等かなり具体的に本書については紹介している。
何を読み何を学ぶかそして次に何を読むかまでが親切に紹介されている。もちろん本書で紹介されている本を全てその通りに読むというのは時間の制約もあり困難であることは確かである。
しかし、このような本のソムリエ的な良書は少ないため、何を読んだらいいのかと迷ったらまた開いて確認したいと思う。