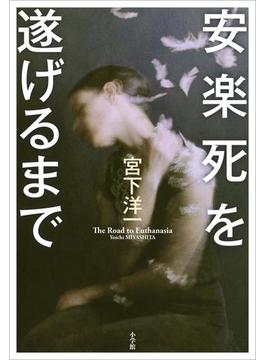電子書籍
重い内容だが目をそらせない
2018/01/23 16:43
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:AR - この投稿者のレビュー一覧を見る
実地取材で安楽死の各国事情を紹介。ここまで話は進んでいるのだなぁとしばし黙考。いろいろ考えさせられる所多し。自分も死ぬ時は自分で決めたいと思っているのでいろいろ参考になりました。個と家族とで生きる意味が違うという著者の指摘が印象的。
紙の本
正しい理解とは何か、を問う本
2022/03/23 14:22
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:BB - この投稿者のレビュー一覧を見る
ヨーロッパを拠点に活動するジャーナリストの宮下洋一さんが、安楽死/自殺幇助を合法としている国や地域を訪ね、当事者や関係者を取材している。
「安楽死」とひと言で言っても、その背景や制度はさまざまで、その選択はとても重い。
浅い知識で、賛成反対を語ることが、いかにナンセンスか。筆者が伝えたかったのはその部分である気がする。
死について議論することは重要だが、その前にぜひ、この労作に目を通して欲しい。
電子書籍
安楽死
2019/09/16 18:56
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽぽ - この投稿者のレビュー一覧を見る
一部の国や州では認められている安楽死。日本の場合は、延命治療をするかしないかしか選べず、議論も進んでいない。
投稿元:
レビューを見る
以前読んだ『「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義 日本縮約版』でも言及された、
①回復の見込みがなく
②耐えがたい苦痛を受けていて
③本人が(あるいは周囲の家族も)死を望んでいる(認めている)
場合に、自死が認められるかという問いに対し、仮に「認められる」とした場合にどのような手法がありえるのか。
その疑問に対する答えの一つとなりうるかもしれないと思い、この本を読みました。
自ら、死期を早める(自分自身で死ぬタイミングを決める)ことが認められる場合、選択できる方法としては
(1)延命処置を停止する
(2)医師による助け(薬をいれた点滴の準備など)をうけつつ、最終的には自らの手で自死する(点滴のバルブを患者自身が開けて自死する)=自殺ほう助
(3)医師による投薬などの手段で絶命する=積極的安楽死
の3点がありえるという認識に至りました。
また、各国の事情も実際の患者たちへの取材や安楽死を受ける現場に立ち会った筆者のルポを通して知ることができた点も、大きな学びになりました。
しかし、日本において(また、自分にとって近しい人において)形式はいくつかあるにせよ、この「安楽死」という死を自ら決定する制度を導入すべきかどうか、という問いについては、まだ自分自身の答えが出せていません。
個人主義の風潮が強まる昨今ですから、自分自身の人生のあり方(死に方)を個人の意思で決定することにどういった問題点があるのか、本人だけでなく周囲の同意もあるのだから問題はないのではないか、など肯定派の意見にも納得できる部分もあるのですが、「感覚的/心情的」にどうしても受け入れにくい、と拒否反応を起こしている部分があるのも事実です。
また、日本で以前問題となった「安楽死事件」のように、臨死期の緩和治療の過程で、結果として「安楽死」と言われるような事態に陥った場合の法体制(この事例では医師に法的責任が問われ、有罪判決が下されました)の整備をどこまで進めるべきか、ということについても、国民的な議論が必要だと感じます。
もちろん、すべての人が死を唯一の救いと考えることなく生を希望できる社会を作り上げることが理想なのでしょうが、現実には困難な部分もあるわけで(その実現を諦める、というのではなく)、濫用されない、また人々の支持を得られる制度を考えていかねばならないと強く感じます。
高齢化が進む社会であることに加え、個人的には90を超える祖父(幸いなことに矍鑠としており、まだ介護は必要としていませんが)がいることもあり、答えが出ない問いではありましたが、刺激的な読書体験ができました。
また、続編として『安楽死を遂げた日本人』という作品も上梓されたようです。今すぐに読む気力はちょっとありませんが、機会を見つけてチャレンジしたいと思います。
投稿元:
レビューを見る
日本でも家族とかのまわりとかじゃなくて、その人の生き方としての死を早く尊重されるといいなあ。様々な愛と葛藤と希望を感じた一冊。
投稿元:
レビューを見る
最後の方に「死に方こそその人間の生き方に直結する」とあります。祖父が「死に様が生き様」だとよく云っていたのを思い出しました。
自分が幸せだと思える死が私にも訪れると良いと思いました。
投稿元:
レビューを見る
力作だと思う。著者は日本人だが海外で育ち、欧州を拠点に活動しているジャーナリスト。欧州の幾つかの国で安楽死が合法化されていることもあり、著者の生育背景は取材にとても有利だっただろう。安楽死、というよりも自殺幇助を強く推進するスイス人医師プライシックについてその現場に臨むうちに一定程度著者だけでなく読者も安楽死への肯定感が生まれるのが序盤。ところが、安楽死そのものの持つ問題点である、「今選ぶ意志」が果たして正しいのか、という点や自己責任で選ぶのか正しいのかを疑う精神疾患患者や小児での安楽死を通じて拭い去れない疑念を抱くことになる。一方で一部の精神疾患患者にとっては「いつでも死ねる」ことが生きる希望になっていたり…。著者は取材を通じていくうちに、欧州人の個人を中心とした死生観に徐々に違和感を覚えて、「共同体の中で生きる意識の強い日本人」には安楽死がなじまないのではないかと結論付けることになる。うーん、どうだろな。私は安楽死が1つの選択肢としてあったほうが嬉しいし、私はかなり個人主義だから、著者に後半「日本人には…」という決めつけが多い点は非常に気になってしまった。もちろんそれは本書の素晴らしさを全く減じるものではない。日本で安楽死事件を起こしたといわれた3つの事件の当事者の医師への取材に長年の疑問が氷解した。ただ、いずれも「安楽死」ではなかったと知ったのは大きい。著者は医師ではないので必ずしも納得いかないようだが、3つの事件はいずれも死が間近に迫った中で瞬間的に死を早めた処置をしたといえるもの。「安楽死」とは何かが日本人には結局まだまったく啓蒙されていないということなんだろう。尊厳死への理解が進みつつある今、将来に向けて各人が考えるべきことと思う
投稿元:
レビューを見る
図書館で借りた本。安楽死を法律で認めている国に行き、安楽死の現場を取材したルポルタージュ。余命宣告を受けた人々が多いが、他に精神疾患や難病の12歳の子供や認知症など、法がどう判断するか微妙なパターンも紹介した内容。実際に安楽死を遂げた人々の写真なども掲載している。著者は最後付近で本人がどんなに安楽死を望んでも、家族などが反対なら安楽死させるべきではない。日本人は家族や村社会の繋がりが強いからと自身の結論を書いていたが、それこそ家族のエゴではないのか?と疑問。まずは本人の強い意志がこの問題の発起点であるのだから。
投稿元:
レビューを見る
安楽死と言おうか、尊厳死と言おうか、スイスで著者が目撃した死出の旅立ちやその当事者へのインタビューは、貴重なエピソードであり、それぞれが唯一無二ものもであって、ずっしりと響く。また、各国の安楽死事情や、そこで話題になった事案の当事者へのインタビューも興味深い。著者の本を読むのは初めてだが、ジャーナリストとして国際的に活躍されているようだし、インタビュアーとしてとても優秀なようだ。
他方、安楽死に関する著者の主張は、やや曖昧だ。著者が書いているように、それは読者それぞれが判断すべき問題なのかもしれないし、一つの主張を押し通すよりも良心的な態度なのかもしれない。
いずれにせよ、著者が集めたエピソード、そこには日本で起きた「事件」も含まれるが、それらの事例と、国や個人によって異なる家族観、死生観なども踏まえて、それぞれに考えを深めていく必要があるのだろう。いつか自分にも起きる死への心構えとして。
投稿元:
レビューを見る
安楽死に関して何ヵ国かを回って関係者にインタビューしたルポ。
宗教観、各国の事情・考え方、価値観の違いにより、受け取り方や法整備は様々。
メディアの報道は、スキャンダルを追うような傾向があり、背景まで追ったものは少ないことがわかる。
良いか悪いかではなく、どういう考え方があるのかを知ることができる意味で参考になったし、興味深かった。
以下は読書メモ:
安楽死は四つに分類される
1.積極的安楽死 医師が薬物を投与
2.自殺幇助 医師から与えられた致死薬で患者自身が命を絶つ 薬物入り点滴のレバーを患者が引くなら自殺幇助
3.消極的安楽死 延命治療の手控え、中止
4.セデージョン(終末期鎮静) 緩和ケア用の薬物が結果的に生命を短縮する 間接的安楽死
尊厳死の解釈は国により異なる 日本の尊厳死は3.に近い
スイス 積極的安楽死は違法、自殺幇助は黙認(法律の解釈でダメではない)。会員制クラブが自殺幇助を実施する。
オランダ 積極的安楽死も自殺幇助も合法。積極的安楽死が主流。
ベルギー 積極的安楽死は合法(殺人罪に問わないと解釈を定めた)。自殺幇助は合法ではないが黙認。
精神疾患者も安楽死できる。
アメリカ
ヨーロッパでは安楽死=尊厳死
アメリカでは安楽死や自殺幇助は違法だが、尊厳死は合法
実際には尊厳死=自殺幇助 しかし、その言い方を嫌う。
安楽死を行う人の特徴 4W. White Wealthy Worried Well-educated
スペイン
安楽死は違法 ローマカトリック教会の影響力が強い
未成年の安楽死(セデージョン)
愛
日本
積極的安楽死は刑法199条(殺人罪)違反
自殺幇助は刑法202条(嘱託殺人罪)違反
迷惑の文化
欧米との価値観の違い
投稿元:
レビューを見る
安楽死、尊厳死を認める国々と、死に纏わる問題をタブー視し続け、何も対応が進んでいない日本社会との乖離。ただ、安楽死・尊厳死を社会が受け入れる事の難しさも感じる。
高齢化社会が進む日本では、尊厳死を認めると「迷惑をかけたくない」という理由の死が多くなるような気がして恐ろしい。
投稿元:
レビューを見る
https://catalog.lib.kagoshima-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25272974
投稿元:
レビューを見る
「安楽死」とは本書では
(患者本人の自発的意志に基づく要求で)意図的に生命を絶ったり、短縮したりする行為
を指す。
本書では欧州の事例を中心に、実際に安楽死を遂げた人、その家族や近しい人、そして幇助した医師に取材し、彼らがどのような経緯で安楽死を選び、実践したのかを追う。
著者は日本人だが、欧州で20年以上、生活している。
安楽死の問題に取り組むきっかけは、スペイン人パートナーのひと言だった。看護師である彼女は、末期癌になったら躊躇わずに安楽死を選ぶだろうと言う。そして「あなたはどうしたいか」と聞いてくる。
その問いに、著者は即答はできなかった。逡巡なく答えられる問題ではなかった。
彼我の違いはなぜ生じるのか。
日本では近年、著名脚本家の安楽死を巡る発言が物議を醸したが、一般的に、安楽死を認める傾向は高いとは言えない。一方、欧米は、安楽死に関する法整備の整っている国もある。そうした国が大半とまでは言えないが、認めるべきではないかと言う主張は増えてきているようだ。
文化の違い、宗教、家族観、そうしたものが安楽死の問題にどのように関わるのかという疑問が出発点である。
本書の特色は、「個」にフォーカスし、視点が地に着いているところだろう。
いくつかの事例に関する当事者の発言、行動が詳細に記載される。著者自身が、他人の死を目の前にして自分がどう感じたか、心情的にどう揺れ動いたかも克明に記される。
「死」というものが個人に対してどういうものなのかに重点が置かれていると言ってもよい。
最初に取り上げられるのは、安楽死が合法であるスイスを拠点とする自殺幇助団体である。
その他、オランダ、ベルギー、アメリカ、スペイン、そして日本の事例が取り上げられる。
欧州ではいくつかの「安楽死」「尊厳死」に関わる協会がある。
その手法やポリシーにはいくつかの細かい、しかし厳然とした違いがある。薬物を飲むのか、医師が注射をするのか、あるいは患者自身が最後のスイッチを入れるのか。そして尊厳死の対象とされる「条件」は何であるのか。
法律との絡みはもちろんあるが、主催者それぞれの考え方によるところが大きい。
人が死を選ぶとして、それは自分だけの問題なのか。
身体的な苦痛が大きく、回復の見込みがないとすればどうか(とはいえ、本当に回復する可能性はまったくないのか)。
身体的な疾患でなく、認知症などの精神的な疾患であったらどうなのか。
自殺と殺人と尊厳死の線引きはどの程度明確にできるのか。
死に向かうそれぞれの人々は、読者にも鋭く問いを突き付けてくる。
自分であればどうするか。家族であったらどうするか。
具体的な事例と著者の内省は、読み手にも当事者の視点を持つよう促す。
個人的にはこれらの事例の多くは、自殺との線引きが困難であるように感じる。人生に絶望したから自殺することと本質的には同じなのではないか。
もちろん、読み手によって感じることは違うだろう。それだけこの問題は、「個」の視点が重要だとも言える。
本書で取り上げられた欧���の事例と日本の事例では、かなりの温度差があるように感じられる。
回復の見込みがないとされた患者が自ら死を選ぶ「権利」について、一歩二歩踏み込んだ欧州に対し、日本での事例はそこまでは至らない。家族が深くかかわっていることも特徴的だ。それが日本人のウェットな気質や社会構造のせいであるのかどうかはともかく、日本で例えばスイスのような形の「尊厳死」が法的に認められるのは、あるとしてもかなり先のことではないかと思う。
現状の欧州での尊厳死はどのようなものであるのか、そして「尊厳死」というものに対して読者がどう考えるのか、さまざまな問いを孕む点で、非常に考えさせられる労作である。
投稿元:
レビューを見る
[死は個人のものなのか、集団・社会のものか]
安楽死について、欧米各国と日本の現場を取材し安楽死の瞬間、当事者の思い、家族の思いがリアルに綴られた本。
-個人の意見としては麻痺をおって排泄食事意思表示に困難が生じ、人に助けてもらわねば生きていけない状況になったら、入院せず自然死したい
-この考えは、欧州で安楽死が認められる背景となる”死を選ぶ権利”に近い。
-死ぬ権利があることで、救われる人がいる
-よい人生を歩んでいなかったら、安楽死は選ばない
“これからは、頂点に達した人生が衰退に向かうだけ。せっかくの良き人生が、体の衰弱で奪われてしまうことを避けたい”
自殺幇助をした人の多くが、”満足のいく人生を送ってこなかったらもう少し長生きしようと思う”と言う
-オランダの年間の死因の3-4%は安楽死である
-子/親の同意を得ないまま安楽死をするケース、治療の可能性があるが耐えきれない痛みがあることを理由に死を選ぶケース。もっとも考えさせられたのは、家族の同意を得ず安楽死を選んだもの
-個人の死を尊重し、肉親の死を許すことはできるか?もしくは自分の子供の死を許せるのか?
“人間は皆個人の生き方があるんだ。死ぬ権利だってある。誰一人として、人間の生き方を他人が強要することはできない”
-アメリカで安楽死するのは4W wealthy, worried, white,well educated
-残されたものの痛みを軽減するという効用も安楽死にはあるが、家族の悲しみは軽減すべきものなのか。
-安楽死すると決めてから迷うこともある 迷いや悲しみを、よきものとする文化が日本にはある
-日本では安楽死は根付かないのは、悲しみや重荷を負うことを重んじるから?死を個人のものとしない文化
投稿元:
レビューを見る
評価の星がもっとあるなら10でも20でも、つけたい。
それくらい、読み応えのある一冊。
特に身近な人を、亡くした人には、ぜひ読んでほしい。
身内が苦しんでいた時を思い出し、なかなか読み進めることができなかった。
安楽死、尊厳死、と簡単に口に出していた自分の知識のなさに恥ずかしくなった。
簡単にできるものではない、けれど選択肢としてあることは、必要な時代になってきているのかもしれない。
筆者であるジャーナリストの宮下氏、存じ上げませんでしたが、すばらしい文章だと思った。
彼には、もっと、このような本を出してほしいと切に願います。