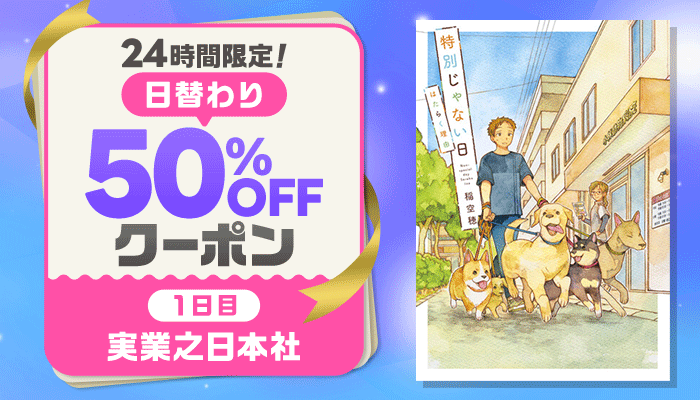投稿元:
レビューを見る
別姓訴訟で青野さんってなんかすごい人、と思い購入しました。
多様な働き方を理念だけではなく実践しているサイボウズという会社は本当に魅力的。
「払われた税金が本当に国民のためになっているのかわからない。国に任せるよりも私たちのほうがうまく社会を動かす自信がある。だから法人税を払うよりも自分たちの理念を実現するために責任をもって使う。」
この考え方が新鮮でした。働き方改革なんて確かにサイボウズのような多様な働き方を実践する会社が広まれば一番早い。別姓訴訟は会社のお金を使っているわけではないけれど、これも社会を動かすための方法。
「「掛け算」の効果。「クラウド」と「農業」どちらも100人に一人のスキルだったとしても二つを組み合わせると1万人に1人の貴重なスキルになる。」
これは私にとってもエンパワメントされる考え方。一つのところにずっといるわけではないけれどだからこそ、経験の掛け合わせで活かせる力があるのだ、と思える。
投稿元:
レビューを見る
全てにおいて途中で思考停止(まーしゃーないか。こんなもんかな。)している自分に気づいた。
もっと自分の納得がいくところまで、深く砕いて調べて考えて動こうっと。と、なりました。
投稿元:
レビューを見る
若い会社員(特に大企業)に語りかけるような調子で現状のカイシャ(文中での表現)欺瞞と不条理を解き明かし、これからのカイシャ(要するにサイボウズ社のこと)を提唱する。
言わばサイボウズ社へのリクルーティングの書とも言えますが、多くの経営者(もちろん私も)にとってはとても耳(目?)が痛くなるような厳しい提言に満ち溢れてます。
著者も自社を昔はブラック企業だったと告白しているように、少しずつ(多少はやってると自負するところもある)でも変えて行きたいと思います。
投稿元:
レビューを見る
p45
ジョブ型雇用:合意のない転勤は起きない
米国では定年制度は年齢差別に当たるため憲法違反
p92
カイシャの代表の思いと自分の思いが重なっていると仕事が楽しくなる(モチベーションが安定して高い)
p46
どんな人が代表なのか、よく見ておく
p118
自分の意見を変化させ、最初は思いもよらなかった落としどころがみつかるような瞬間こそ、交渉の面白さ
p116
相手はどんなコンセプトを望んでいるのか、自分はどんあコンセプトを望んでいるのか、その両方を満たすための手段を考える。これが交渉の基本
→仕事で感じる違和感をそのままにしていた、と反省。
交渉していかないと。☆
p102
モチベーションの高い状態とは「やりたい」「やるべき」「できる」の3つの条件が重なっている
・そのために交渉する
・どういう形でやれば喜んでもらえるか
p126
ミートアップ
自分に近い興味や問題意識を持つ人たちが集まり情報交換する場
p166、p170「すごくない雇用」をしているカイシャでは
一部の人しか楽しく働けない
・どこでも欲しがるような優秀な人を採用するのが「すごくない雇用」
・「すごい雇用」とは「他の会社では採用されない人」「制限が多い人」「採用するのに勇気がいる人」を採用すること
・「すごくない雇用」をしている会社は「実態雇用力」がない
・長い人生を考えるとリスクが高い職場
p186
外から人が集まる「ハブ・オフィス」づくり
→こんなオフィスがある会社で働きたい
p94
一人ひとりにとって、「得ることがうれしい」ものをすべて報酬であると定義するならば、他にもたくさんの種類の報酬がある
この報酬こそが自分が楽しく働く源泉になる
投稿元:
レビューを見る
サイボウズの青野さんによる働き方論。今のキャリアに悶々としている方には良い刺激になること請け合いです。
https://amzn.to/2Mjp4yA
続きはこちら↓
https://flying-bookjunkie.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
投稿元:
レビューを見る
【どんな本】
労働力を搾取して、利益を追求しまくるモンスター(会社)の支配から抜け出すために、我々サラリーマン読者に対し、今すぐ変わること、動くことを訴えている本
【内容】
モンスター(会社)から抜け出そう
【抜け出す3つの方法】
1.新しいことに挑戦し続ける
2.得意なスキルを更に伸ばす
3.希少人材になる
【主張】
変わろう、動こう!
投稿元:
レビューを見る
★メモ
利益よりも、どこにお金を配分しているのかが大切。
どちらかと言うと利益よりも従業員の給与や報酬が大切で、利益はあくまでカス。その方が少なくとも働くヒトは幸せ。
サイボウズでも利益を出さないようにしている。法人税を払っていることに喜んではいけないのではないか。むしろ、会社の利益は自分たちの理念を実現するために、徹底的に自分たちで責任をもって使っていく。
会社や代表のビジョンと、従業員ひとりひとりのビジョンを重ね合わせる。その確認作業を怠らない。
やりたいは変化する、やれるは拡大して大きくはる、やるべきは期待に答えること。
やるべきの難しいところは選択を迫られること。そのときには自分でしっかりと意思決定をして、結果がどうであれ自分で責任をとること。それをサイボウズでは「覚悟」と呼んでいる。
すごい採用とすごくない採用。
すごくない採用は優秀な人を雇うこと。これは誰でもできるし、ある意味でリスクが小さい。
すごい雇用とは他の会社では採用されない人や、制限が多い人や、採用するのに勇気がいる人を採用すること。
フラスコ理論。フラスコの中に多様な人材をいれて、振ってみると、化学反応がおこって面白いアイデアがでてくる。フラスコの口が狭まっているのは、会社にはビジョンがあるからであり、その制限こそがチームで実行可能なアイデアを引き出す。フラスコの口は明確なビジョンです。この狭い出口に向かって、全神経を集中させることで、エッジの効いた成果を出すことができる。
サイボウズでは、フラスコで化学反応が起こりやすくするための触媒として「公明正大」と「自立」がある。
サイボウズでは「みんな」という言葉を使ってはいけない。みんなと一括りにすると、多用な個性の存在を見落としがちなので。 書籍「嫌われる勇気」にも同じようなことが書かれている。
投稿元:
レビューを見る
妖怪カイシャの見極め方は、これから働く人、既に働いている人すべてのカイシャ選びに役立つと思う。またサイボウズで取り入れられているモチベーションや交渉の能力を高めるフレームワークや多様な働き方を実現する人事制度など参考になるものが多い。
投稿元:
レビューを見る
こういう人はサイボウズに来てください、という採用活動の一環だろうか。
書いていることはいちいち真っ当だと思ったが、サイボウズがどれだけこの理想を実現できているのか、というのは気になる。
あと、経営者を悪意ある個人として描き出しているのはどうかと思った。彼らも意のままに振る舞える存在ではないのだろう。どちらにしろ、我慢をしていてもしょうがないという結論は変わらないわけだけれど。
投稿元:
レビューを見る
会社ってそもそも何なんだ、どうして会社がモンスター化していくのか、そしてそんなモンスター会社への対処の仕方までをサイボウズの事例も踏まえて提言した一冊。「働き方改革」がバズワードとして叫ばれる中で、改めて会社とは何か、働くとは何なんかを考えたい人にお勧め。
・最近、日本の大企業でくすぶっている若者を見て想うことがある。君たちはね、就活に失敗したんだわ。時代についていけないサラリーマン社長が経営しているイケてない会社を選んじゃったんだわ。そして、くすぶり続けてるってことは、君たちも変化できない奴だってことになる。変わろう、動こう。
・会社とはコレだと指をさせる実態がない。法の上で人として扱えるように法人として便宜上定義したものにすぎない。
・実態の無い「カイシャのため」にというのは思考停止ワード。本来はもっと違う実態のあるもののために働いているはず。
・実態が無い上に死なない、カイシャはまさに妖怪。
・見ておくべきは、カイシャというブランドやイメージでは無く、カイシャの代理執行人である生身の経営者が信頼できるかどうか。
・イケてない人の下で偉くなった人は、たいがいイケてない。自分にとって都合の良い人を選び、都合の悪いひとは弾くから。
・我慢レースに耐え権限を手にする頃には、あたなの全盛期は終わっている。
・日本のカイシャはメンバーシップ型の雇用。社員を我慢レースに引き込む巧妙な仕掛け。我慢すればするほどお金をもらいやすい仕組み。
・カイシャが出来た時の目的≒理念は生き続けているか?あらかた当初の目的を達成し、理念をお飾りにして、ダラダラと生き長らえている妖怪がウジャウジャ。
・理念を持てない代表取締役は雇用の維持と売上・利益の拡大を目的にしてしまう。
・カイシャの理念に人を集める理由がなくなってきたなら、理念をリフレッシュさせないと、人が集まる目的が無くなってしまう。集まる理由が無い会社で働いて楽しいわけがない。
・あたなは会社の理念を言えますか?その理念にワクワク出来てますか?
・理念が失われてる中での「雇用の維持」は、人口減少社会における貴重な人材の流動性を損ね、その会社でしか通用しない社員を大量生産しているという意味で、むしろ悪でしかない。
・カイシャはバーチャルなものなので、カイシャが死んでも本当は誰も困らない。理念を軸に、もっと平易に起業廃業がなされる社会になるべき。
・売上が大きい会社を選びたくなるのは、世間体を気にしているからではないか。小さなプライドのために自分がやりたいことを遠ざけてしまってないか。売上が大きい≒お客様から多くのお金を巻き上げているとも考えられる。
・利益をあげているかどうかよりも、その利益をどのように分配しているかを見る。内
・頂いたお金を、仕入先、パートナー、従業員、社会に還元して、絞った残りカスが利益。伊那食品塚越会長。
・自分達で使い先をコントロールできない法人税を払うより���、集めたお金を自分たちの理念達成のためにつぎ込み、社会全体の幸福量を増幅させるべき。
・実態のないカイシャのために、生身のある人間が死んでしまう事態まで起きている異常事態。
・自分の夢が何なのかをよくよく自問して明らかにし、とカイシャ代表のビジョンと重なるかを見極める。
・給与以外の報酬にも目を向ける。我慢レースを強いるカイシャは給与以外の報酬は意外と少ない。
・やりたい、やれる、やるべきの3つの輪を重ねる努力をする。
・やりたいは変化する、やれるは拡大できる、やるべきは自分の意思を持って覚悟をもって選択しその結果を受け入れる。
・自分で選択して自分で責任をとる覚悟が大事。人のせいにしているうちは、主体性から生まれる楽しさを享受できない。
・言われた通りにやらないといけないと盲信しすぎ。思考停止せずに、立ち止まって考える。
・交渉はとてもクリエィティブなもの。衝突と捉えずに、より良い結果を目指す創造的な活動。A・Bどちらが正しいかではなく、両方を満たすような革新的なCというアイディアを出す。
・コンセプトワーク。その活動は誰に何と言わせたいのか。目的を確認し、手段は選択できるようにする。
・情報は発信するところに集まる。情報発信は共感してくる人を呼び込むための基本戦略。
・個性を掛け算で磨く。自分のやりたいに素直になる。
・フルタイムの人しか雇えないカイシャは今後衰退していく。制限のある人を雇えるかどうか。多様性を活かすマネジメントができるかどうか。
・フラスコ理論。ビジョンという方向性≒制約がある中で、多様な人材を混ぜる。触媒は公明正大と自立。
・みんなという言葉は使用禁止、思考停止ワード。主語はあくまで私・自分。
・カイシャは本来多様だった人材を画一的なものにしてしまう。
・複業を禁止されると、せっかくの経験が還流されない「伏業」になってしまう。
・欲しいのは気合や根性によるストレッチした数値目標ではなく、今までに無かった新しいアイディアとチャレンジ。
・カイシャが職場として提供できる楽しさとは、仲間と同じビジョンに向かう一体感、個性を活かした貢献、そしてお互いの感謝。活動が顧客の喜びを産むと共に、その先にある社会貢献への広がり。
・ディスラプターにより、今まで既得権益で利益を上げていた日本の大企業たちが、短期間で収益を大幅に悪化させることが起きる時代で、昭和時代の経営、年功序列、横並びの給与体系、残業と転勤、副業禁止、役職定年と定年退職、をいつまで続けるのか。
投稿元:
レビューを見る
青野さんの本というのと、表紙が絆創膏っぽい、
少し面白いデザインだったので読んでみました。
働くのが楽しくない、モチベーションが上がらない、
というそもそもの理由を突き詰めるにあたって、
まずは会社ってどんなところか?というところから
入って問題提起、今後について書いてあります。
参考になることや勉強になることが多かったし、
なるほど~と納得感のある内容も多かった。
【勉強になったこと】
・「カイシャ」のために働くとは正しくなくて、
正しい表現は「カイシャの代表」のために働く。
つまり就職・転職で会社を選ぶときは、
代表がどんな人なのか、共感できる人なのか、
をしっかり見極めて入らないと、
イケてない代表のために働くという事態となる。
要は会社名で選んではいけないということ。
・組織にとって最も必要な概念は、企業理念。
企業理念がしっかりしていないと、
なんのために働くのかが分からなくなる。
・人に「頼む」ことが出来る人は、
そもそも自分が何が出来て何をすべきかが
しっかり理解出来ている。
そのうえで、誰に頼むのが適任かを把握する
スキルを持っている。
・今いる「カイシャ」に違和感を感じたら、
以下の3つのどこに軸足を置くのかをしっかり考えること。
①カイシャに身をゆだねる
②自分の夢に合ったカイシャに移る
③自分でカイシャを作る
・実はスキルのコモディティ化も進んでいる。
色んなスキルを組み合わせて自分にしかない
スキルを見出さないと、その他一般と同じ扱い
となってしまう。
・給料の金額は市場性を意識して決めるべき。
・今はチャレンジして失敗することを恐れない、
否定しないカイシャしか生き残れない。
投稿元:
レビューを見る
タイトルの問題提起は素晴らしいと思うが、内容がそこまでスケールの大きいものにはなっていないように思う。
ひとつの成功例をつくられたことは画期的だが、
参考にすることのできない業種・職種・組織も多そう。
投稿元:
レビューを見る
100人いれば100通りの働き方を公式に宣言し、実践している会社の社長さんの本。
一人一人の幸せを考えるというよりも、一人一人生き抜いていくためには交渉する力が必要で、その力をつけることが楽しく生きることだと。
また、働き方の交渉をする限りは自分で折り合いをつけて決断した選択だという「覚悟」が非常に大切だと言われている。
だれかに決められた働き方をしていると感じれば、結局不満がでてきたら他人のせいにする。でも数ある選択肢の中から相手と交渉して自分自身で決めたことなら責任をもつ。
そういう風な交渉をすることこそ、大切だと言われている。
働くときに人と働くことが多いから、不満がでてくるのはつきもの。
でも、それぞれの人に覚悟を持ってもらうことが重要なことだと気づけた一冊になった。
投稿元:
レビューを見る
・いかにユニークさを出すか。
1つのカギは掛け算の発想です。
掛け合わせてスキルを作ることです。
農業をやっているひとは、クラウドサービスのことがよく分からないし、
クラウドサービスに詳しいIT業界のひとたちの中で、農業を本格的にやっている人はまずいません。
両方を理解している彼は、NKアグリと一緒に、自分の農地にセンサーを設置し、
クラウドサービスを活かした情報管理を進めました。
さらに効率よく販売するための仕組みもクラウドサービスで作り、全国に分散する農家が連携しながら、
安定した価格で販売できるネットワークを作っていきました。
これはまさに掛け算の発想です。
クラウドと農業。
どちらも100人に1人のスキルだったとしても、2つを組み合わせると、1万人に1人の貴重なスキルになります。
・掛け算が希少なユニークさを生む
イノベーションという言葉の起源は、もともと「新結合」を意味する。
これとこれを結合すると、今までになかった新しい価値になる。
いままでなかったユニークな組み合わせによって、新しい価値、可能性がうまれることがイノベーションだと解釈できます。
・サッカーの岡田監督は、あえて中国のサッカーチームの監督となった。
当時の中国は反日活動も盛んで、言葉の通じない国での監督業で成果を出すことは難しかったろうと思います。
しかしこの経験から、岡田さんはサッカー界では珍しい「中国」という掛けあわせの要素を身に着けました。
今後は、アジアで高まりつつあるサッカー熱の先頭を走られることでしょう。
投稿元:
レビューを見る
自分の為に楽しく働くことの重要性を説く
また、サイボウズという自ら経営している会社の取組を紹介
成果主義ではなく市場主義であれば、個人プレーではなくなる。書いてあることはとても共感できる。ただ、我慢して大企業にいるよりも楽しく働ける会社に転職した方が良い。
経営トップでありながら育休を三度取得
夫婦別姓を認めさせる為に裁判を起こしている