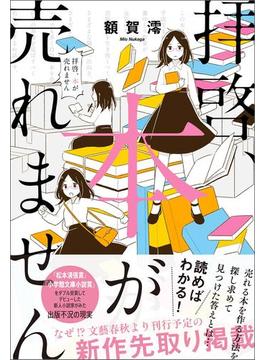電子書籍
本当に
2020/09/11 07:19
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:おどおどさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
本が売れない話をしていて、驚いた。題名だけで中身はライトなエッセイだと勝手に思っていたから。
しかし、私は本好きですよ!
しかも紙書籍。だから、今後も頑張ってほしい。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽぽ - この投稿者のレビュー一覧を見る
あー、本売れないのかぁ。残念な気持ちもありますが電子書籍や、図書館の利用など、本の人気は衰えていません。
投稿元:
レビューを見る
面白かった。非常に面白かったけれど。これでいいのだろうか。これで額賀さんの不安は払拭されたのだろうか。noteに課金ブログ書いたりとかそういうことまで踏み込まなくていいのか。「本が売れました」に届くのだろうか。「屋上のウインドノーツ」は素晴らしかったし、一ファンだからこそ、もう1歩と思ってしまう。
投稿元:
レビューを見る
タイトルに惹かれ、また最近額賀澪さんの作品に出会って印象に残っていたので読んでみた。
紙の本を取り巻く業界が縮小傾向であることは知っていたが、こんなに厳しいとは…しかし、それに抗うように闘っている人たちがいる!
今岐路に立つ出版業界、おばさんにはよく分からなかったラノベのこと、変化する文庫レーベルなどの現状がよく分かった。
額賀さんの13日に文藝春秋から出版された最新作の一章が、K Kベストセラーズの作品である本書に載っていることも大きな試みだろう。
映像世代の中学生と向き合う毎日の自分には、ありがたい一冊だった。
しかし、中学生はラノベ、ライト文学から先になかなかいかないのが、現実なんだよなぁ…250ページを超えるとなかなか手が出なくなる(西尾維新さんは読むけども)。その厚みを前にすると、厚い本一冊読むなら、薄い本何冊も読む方が、達成感あるのかな〜。現実に近い話より、非現実的な話を好むよな〜…と思いつつ、今日もポップ書き。2018.7
投稿元:
レビューを見る
平成生まれのゆとり世代作家を自認する筆者が、自分の本が売れない原因を考え、知恵を集め、次回作でそれを実行していくという作家進化型エッセイ。
楽しく読ませていただきました。
次回作、30万部売れるといいですねえ!
投稿元:
レビューを見る
新文化に紹介記事あり。
本書が出来たきっかけhttp://nukaga-mio.work/kikkake(著者blog)
180410読了。かなり読みやすった。Webコンサルタントの話が実用的で知らないことが多かった。
原田左官工業のホームページ。普通の左官屋だけどめちゃくちゃアクセス数がある。ブログを頻繁に更新してるから。主に左官の技法を画像付きで投稿。オリジナルな文章で専門性が高い。他のサイトからコピペしてちょっといじったような文章は検索エンジンがすぐに見抜いて内容のないページと判断する。
公式サイトを作ることが大事。SNSだと検索エンジンに引っかかりにくいしすぐに流れていってしまう。きちんとしたWebサイトは情報を貯めておける。良質なコンテンツは面白い文章をオリジナルで作れるかどうか。検索エンジンに評価してもらえるコンテンツを作り、サイトに訪れる人を増やすというのはサイトを育てるということ。サイトを育てるとはファンを育てるのと同じ。
サーバーを借り、wordpressをインストールして独自ドメインを取得する。
本にかかわる人の交流会
新潮文庫nexは表紙が5色刷り(4色+蛍光ピンク)
正直表紙は失敗してると思う。本屋の中で場所を検索して棚まで特定したのに平積みされてる本書に気が付かなかった。やっぱりタイトルが読みにくくて目が滑ってしまう。隣に山田詠美の吉祥寺デイズ(イラスト表紙が被っている)と内田洋子のモンテレッジォ小さな村の旅する本屋(タイトルの配置とフォントが似てる)が並んでたからかタイトルが目に入ってこなかった。あれ、ここの棚にあるはずなのに置いてないじゃんとスルーしそうになった。
投稿元:
レビューを見る
文芸作家が売れる方法をインタビューしていく、という設定がよかった。業界に近い人なら読んで損はないと思う。最後は賛否両論だと思うが、ある意味この本らしい。
投稿元:
レビューを見る
あの爽やかで切ない青春小説を次々と描きだしている「作家額賀澪」さんとは違う、リアル額賀さんの魅力を私は知っている、と思っていたけれど、いや、まだまだ甘かった。
自らを「糞ゆとり作家」と呼び、同時期にデビューした今を時めく人気作家に「お腹を壊せ」と呪をかけちゃうような、そんな方だったとは!!いやぁ、大好きな『ヒトリコ』や『君はレフティ』を次に読み返すときにはきっと額賀さんの「ニヤリ」とした黒い笑顔がちらついてしまうだろうな。
あ、でもどの小説にも爽やかなだけではないどろりとした「毒」のようなものがちらちらしていたっけ。そうかそうか。あの毒の正体が「額賀澪」の素顔だったのか。なるほどな。
これは額賀澪の本当の魅力が味わえるのはもちろんだけど、それ以上に一冊の本が店に並ぶまでにどれだけの人の手がかかわっているかがよくわかる。本を作りたい人、そして毒を吐く額賀澪を楽しみたい人におすすめ。
投稿元:
レビューを見る
お仕事小説かと思いきやエッセイだった。
普段エッセイは読まないんだけど、
作家本人が主人公の小説のような感覚で楽しめた。
本が売れる為に大切なことも大変さもよく伝わって来た。
私は本が好きなので、やっぱり出版業界には元気になって欲しい。
額賀さんの作品はデビュー2作が良くて
1作品以外全て読んでいるけど
最近ヒットがなかったから、
この取材を経た後の新作に期待!
投稿元:
レビューを見る
平成生まれのゆとり世代作家が本を売るために右往左往する話、と自虐的に始まる取材記。
小説家にはなったが、厳しい出版事情と競争の中でどう生き残るのか。模索しもがく様が、大変そうではあるが、ユーモラスでもある。キャラ立ちとでも言うか。
編集者として名高い三木一馬氏を始め、書店員、WEBコンサル、映像P、装幀家と、様々な視点から現状課題と「本を売る」手段が語られる。面白いのはその取材を作家自身がしていることかもしれない。もちろん正解はないのだが、辿り着いたところが、作家の原点と言えるのも面白い。
巻末付録で、他の出版社から出る著者の次作がまるまる1章載ってた。未校正部分もあるとのことで確かに文体の粗さは散見されたが、中身は面白く、最初の章にカタルシスを入れたのも上手い。これは読みたくなるなー。
投稿元:
レビューを見る
こんな一生懸命な本を書かれたら応援したくなっちゃうなあ。まだ「屋上のウインドノート」しか読んでいないけれど、さわやかなのに恋愛が出て来なくくて、けっこうシビアな話だったりして好感を持っていました。そんなまだ駆け出しと言ってもいい位の筆者が、どうやったら本が売れるのかを色々な人を訪ねて考えていく本です。
小説を一生書いて暮らしていきたいという彼女の願いが痛い程分かります。売れっ子の手前で右往左往している彼女は、いつ世間から必要とされなくなるか不安で仕方がないでしょう。まだ20代の彼女がルームシェアをしてつつましく生きて、小説を書いて一喜一憂している姿はまさに青春。青春を小説に賭けてですわ。
今、本を売るのに大御所の権威よりも、現場で実際に面白い本を紹介する事がとても重要になっていて、それが本屋大賞に結実していると思うのですが、サワヤ書店の松本店長が本書中で言っていた「褒めることが前提になってしまっている」という事には衝撃を受けました。そりゃそうですよね、サンプル貰ってPOPや帯に反映させるのにけなす人はいないからなんらか褒めますよね。そうすると折角現場レベルで嘘が無いお勧め本が分かるはずなのに、しがらみが色々出来て信用度が下がって来てしまうのがとても残念です。
先日読んだ本のエンドロールと本書を読んで、本好きとしては胸が熱くなるやら本の行く末が心配で泣けてくるやらいろいろな感情が入り乱れました。若い書き手さんたちに是非とも頑張って頂きたいです。もちろん額賀さんも応援しますよ!
ちなみにこれから売られる最新作の第一章が巻末に掲載されています。わくわくする始まりでしたので期待大です!
投稿元:
レビューを見る
平成生まれの、ご本人曰く‘糞ゆとり作家’の額賀澪さんが、本が売れないこの時代に、自らの生き残りを賭けてその道のプロに教えを請いにいく本書。
とにかくプロ達の本を売る事に対する情熱と工夫に感銘を受けた。
著者である額賀さんのどこにでも飛んで行くフットワークの軽さと、自虐を挟みつつも明朗さを失わないキャラクターと文章も好感度大。
「タンスの角に足の指ぶつけろ!」には噴いた。
さて、彼女がプチ呪いを送った相手とは...?
最後に未発売の小説の第1章を掲載するという面白い試みがある。
‘お試し☆額賀澪’ですね♪
章終わりの怒濤の展開に小説への期待が膨らみます。
楽しい読み物であり、お仕事インタビューであり、ひとりの新人作家の決意表明だと思った。
投稿元:
レビューを見る
ルポです、
本を売るために必死です。
でも、結論は最初から分かっていたのです。
面白かったら売れるのだと。
私は小説は9割図書館派なので申し訳なく思います。
「ゆとり世代」の活躍は
「ゆとり世代」の母ちゃんの喜びでもあります。
頑張ってほしい。
巻末に新刊の1章が掲載されてました。
ドドンと太っ腹に掲載ってことだったようですが
私はこういうのはあまり。。です。
ええーそうなの?どうなの?的なPOPのような、
読メの皆さんのレビューのほうが、
手にとろうかと思ってしまうタイプです。
表紙は大事ですね、
時代をあらわす感じもあって面白いです。
イラストレーターの中村佑介さんも
以前、自分のイラストが絶妙なデザインで
本の表紙になるのはとても気持ちがいいと仰ってました。
私はイラストを描く人が文字も自分で入れるのかと思っていたので
驚きました。
デザイナーってすごいんだ。
世の中にはいろんな仕事があるのですね。
そして、これだけ手間がかかっていれば
本は高くなりますね。
もどかしい。。
投稿元:
レビューを見る
小説かと思ったらガチで本を売るためにどうしたらいいかを取材した本だった。映像化しても売れない本もあるって悲しい…。
投稿元:
レビューを見る
本が売れない。
そんな現代に出版に関わる人々はどんな工夫をこらしているのか。本が売れるようになるコツはあるのか。
小説家の額賀さんがその答えを探す旅(インタビュー)に出る本。
読んでわかったのは何かを売れるようにするためには、売れるように「仕掛ける」のが必要だと言うこと。「良いもの」(小説で言うなら「面白いもの」)は放っておいても売れるか、といえばそうとも言い切れないのが、ものが溢れかえった現代日本の難しいところ。
よい部分を知ってもらうため、興味を持ってもらうための努力は必要なのだ。
著者がインタビューしたのはラノベのヒット作をを数々世に送り出した元編集者・三木一馬さん。
数々のベストセラーのきっかけを作った書店員・松本大介さん。
映像プロデューサーの浅野由香さん。
ブックデザイナーの川谷康久さん。
本の製作課程や広報の流れ、小説家と編集者の関係(執行官と監視官)、映像化までの流れなど、知らなかった業界のことが知れて大変面白かった。
あとリアルな現役小説家の苦悩も。
実は額賀さんの小説は未読。
「屋上のウインドノーツ」から読んでみようと思った。そしてついでに「ラノベっぽいか」どうかも自分で見きわめてみたい。笑