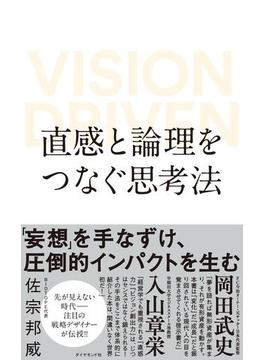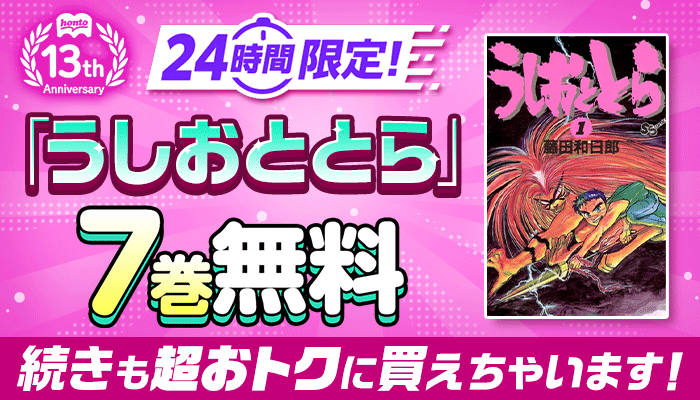1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Honto - この投稿者のレビュー一覧を見る
異なる価値観、思考法を持つ人はたくさんいますが、それらの違いを1枚のイラストでわかりやすくまとめられていて非常に良かったです。自分の中でも、何かを考えるときの新しい思考方法が加わり、世界がまた1つ変わったように思いました。
思考法の変化(デザインからビジョンへ)
2019/05/10 14:33
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:だい - この投稿者のレビュー一覧を見る
■直感と論理
デザイン思考の本質と課題
・手を動かして考える(プロトタイピング)
・五感を活用して統合する(両脳思考)
・生活者の課題をみんなで解決する(共創)
最大公約数的な解決策となり、作り手の個性や世界観の表現が制限されてしまう。
ビジョン思考
0→1(感性優位)の世界であり、妄想を駆動力に創造する
トランジション「転機・移行」の時、自分の心の声に耳を傾けるチャンスである
ビジョン思考は、妄想→知覚→組替→表現のステップがあり、それを継続的に実践していくには、スペースとメソッドが必要になる
・妄想
自分自身の内面や潜在意識と向き合い「本当の関心」と出会う
・知覚
妄想の輪郭をはっきりさせ、未来の可能性を構想する
・組替
解像度を高めて、構想の「独自性」を突き詰める
・表現
ビジョンを形にする(プロトタイピング)
・スペース
空間的余白と時間的余白
・メソッド
目・口・手からのインプットで脳の同時発火を促す
■妄想から始まる
本当に価値あるものは、妄想からしか生まれない
人間の好奇心や情報への探究心が生まれるのは「情報ギャップ」を感じることが不可欠
「情報が欠けている」という認知があって初めて「知りたい」という好奇心が生まれる
妄想を潜在的な状態に留めている限り、情報ギャップは生まれないので、前に進もうとする力も生まれない
ムーンショットアプローチ
10%の改善より、10倍の成長を目指せ!
■世界を知覚する
「個人向けにカスタマイズされた情報」に触れるほど、他人と同一化していき、人と同じような思考になる
状況判断の優劣は、情報から独自の意味を作り出す「知覚力」が左右する
センス・メイキングの3プロセス
・感知 ありのままに観る
・解釈 インプットを自分のフレームにまとめる
絵で考えて、絵に描き出すことが重要
・意味 まとめあげた考えに意味づけする
他人と共有するには「言語化」は必須
■組替の技法
新奇性を生む上で肝要なのは、妄想が持つ要素に「組替」を与え「新結合」を起こすこと
組替=分解+再構築
分解のプロセス
・既存アイデアに隠れている「あたりまえ」を洗い出す
・違和感のある「あたりまえ」をピックアップする
・「あたりまえ」の逆を考える
再構築のステップ
・アナロジー(類似性)思考による類推
・構成要素を可視化する
ある程度の知識・経験を集める
ビジュアル化する
・フォーマットを決め、一定の制限の中でまとめる
■表現する
プロトタイピング・・「表現」がプロセスの最初
「具体化→フィードバック→具体化」の繰り返しが質の完成度を高める
また「頭」より「手」を動かすことに時間をかける方が、表現の質は高まる
手で考えるを邪魔するもの
・とりあえずPCを辞める
・アウトプットせざるを得ない状況を作る
伝わりやすさ
・一瞬で伝わる「絵」を用意する
・相手の知識との「接点」を作る(比喩)
相手に影響を与える
・本気であり具体的であること
・ストーリーが描かれているか
■妄想が世界を変える
真・善・美
・妄想にとって「正しい(真実)」は何か?
・妄想はどんな「善い社会」を作るためのものか?
・妄想に「魅力(美)」を感じるのはどんなところか?
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ちょっとした時間を有効に活用しながら、思考を深める方法が、よくわかりよかったです。具体的で、読みやすかったです。
投稿元:
レビューを見る
▼穴に落ちて内省する手順
妄想→知覚*→組換→表現
*知覚:妄想の解像度を高める。
「部屋の壁やボードには、さまざまな写真や、詩のフレーズなどが無数に貼り出されており、それらを眺めたり手で動かしたりしながら、自分にピンとくるビジョンの設計図や世界観のコラージュをつくっていく。(略)ぼんやりとしていた妄想の輪郭をはっきりさせ、未来の可能性に彩られた構想を一枚の絵や設計図にまとめ上げていく。」
画像
▼ビジョン・ドリブン思考
・イシュードリブン:すでに顕在化している課題に対して、それを解決していく思考。
小さくはじめて、大きく育てる。問題を発見し、それらを潰していくことで少しずつ前に進んでいく。(前年比で比較して成長をみる→達成できなそうな予算は立てなくなる)
・ビジョンドリブン:まだ目に見えない理想常態を自発的に生み出し、そこと現状とのあいだにあるギャップから、思考の駆働力を得ていく。内発的な妄想を思考のスタートにおく。
「これをさらに推し進めるなら、「唯一の明確なビジョンをカリスマ社長が提示し、社員たち全員がその達成を目指して尽力する」という、いわゆるトップダウン型のビジョン経営すらも、時代にはそぐわなくなってくるだろう。
むしろ、経営者はごくゆるやかな不変のミッションだけを提示しておき、あとはそこに集まった個人やパートナー企業が思い思いにそれぞれのビジョン(妄想)をミッションの価値観を守る範囲で実現していく、いわゆる「ティール組織」が望ましい。不要な階層性を取り去り、個人がフラットに価値を生む「場」をつくる自律分散型の組織こそが、21世紀のビジネスの勝者となるのかもしれない。」
「成功するプロジェクトとそうでないプロジェクトの違いは、そこに「妄想」を持った人がいるかどうかでしかないということだ。目の前の世界はどんどんと移り変わっていくし、短期的には失敗や障害も出てくるだろう。その長い失望の期間に耐え得るのは、あなたの内面から掘り起こした「好き」や「関心」をおいてほかにない。
(略)
短期的な成果を期待して駆けずり回る「他人モード」を続けていては、めまぐるしい変化に振り回され、いつかは疲れ切ってしまうだろう。「自分モード」のスイッチをオンにしておきながら、背中を押してくれる「大波」を待つーそんな心構えでいるほうが毎日楽しいし、結果t機にどこかで「期待を超えた爆発」にめぐり合える可能性は高くなるだろう」
▼人の心を動かす「英雄の旅」フレーム
画像参照
投稿元:
レビューを見る
10パーセントの利益を上げるよりも、今よりも10倍の成果を上げる。他人モードではなく自分モードで考える。頭で考え始めるより、手を動かして考える。
冒頭は少し難しいかな?と思ったが、中盤以降はなるほど!と思えることばかりであった。実践例もあり、読んで良かったと感じられた一冊である。
投稿元:
レビューを見る
よく会社の後輩に妄想力をつけよう!
と行って居るのですが、それとちょっと近いことが
書いてあって、参考になった。
妄想をただの妄想のままにしておかない
方法を身に付けたいなと思った。
投稿元:
レビューを見る
解決するべき課題をいかに解決するか、というイシュードリブンな考え方ではなく、あるべき姿にいかに近づいていくか、と逆算思考するビジョンドリブン。
左脳型の思考に偏重している、という警鐘を鳴らすことは昨今のトレンドなのかよく見かけるが
本書ではそこからどう脱却するのか具体的に描かれている。
とかくPCの前に座りがちだが、まずペンと紙を手に取り、言語ではなく視覚に訴えかける形で表現しようというのは実体験からしても納得感がある。
それこそ、左脳的に一読してはい終わり、ではなく反復的に本書に書かれている試みを実践し
ビジョンを描くこと、そしてビジョンに基づき行動していくことに慣れていきたい。
投稿元:
レビューを見る
ロベルト・ベルガンティ教授のデザインドリブンを更に拡張し、かつ明確な言葉で言語化されているイメージを持ちました。知覚力を高めるには視覚情報だけに頼らないことなど目に鱗です。別方面で最近注目していたスケッチノートも、ここで点と点が繋がった気がします。
投稿元:
レビューを見る
『直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN』(佐宗 邦威著/ダイヤモンド社) vol.494
https://shirayu.com/blog/topstory/skill/7834.html
投稿元:
レビューを見る
妄想ジャーナル始めて、自宅用に壁貼りホワイトボード導入した。
1週間の中で他人のための時間と自分のための時間を意識すると、自分のための時間がいかに少ないかがわかる。意図的に自分のための時間をとって、自分の妄想を書きつけて絵にしておく。そこがない限り、現場とのギャップも可視化できないし、ギャップを埋めるためのアクションも取れない。=> 成長実感が感じられない毎日ということになる。
投稿元:
レビューを見る
おもしろい。
本書は「ビジョン思考」について説明している。
「ビジョン思考」はざっくり言えば「妄想が世界を変える」という考え方にもとづいた思考法。
妄想を駆動力にできる人、組織は強いからだ。内発的な「直感」や「妄想」からスタートして、それを駆動力にしながら具体的なアイデアを磨き上げる。
直感を駆動力にしたサイクルは以下の4つを繰り返す。
1.妄想
2.知覚
3.組替
4.表現
1.妄想について
紙×手書きが基本。「モーニング・ジャーナリング」紙に、そのときの感情であるとか、過去におきたことについて書きなぐる。できれば決まった時間に、一ヶ月は続ける。そうすると、周囲の目を気にしていた鎧がとれて、むき出しの自分が見えてくる。
2.知覚について
【感知】
人は言語脳とイメージ脳がある。イメージ脳をきたえるために、トレーニングをする。
・ペットボトルスケッチ:ペットボトルを思い浮かべてスケッチし、そのあとで、本物のペットボトルをよく観察しながら書く。視覚情報があるかどうかで、アウトプットの質がまったく変わってくることがわかる。
逆さまスケッチ:画家の作品でもいいし、マンガの画像でもいい。意味のないイメージとして認識して、描いてみるトレーニングになる。
カラーハント:「その日の色」を決めて一日過ごす。たとえば赤をその日のカラーにしたら、赤いものを探して写真を撮る。インスタグラムにハッシュタグをつけてアップしてもいい。
【解釈】頭の中にあるもやもやをスケッチする。
・ビジョン・スケッチ:妄想でも思いついたプロダクトでもいいが、ラフスケッチをする。それを清書する。その工程を繰り返す。
・1単語1イラストの視覚化トレーニング
ランダムに選んだ単語を表す絵を書く。
【意味づけ】
・クラウドハント
雲を見上げて、なにに見えるか考える
・ムードボード
毎日気になったものを写真におさめる。それらのうち特に気になった8枚をプリントアウトしてスケッチブックにはりつける。それぞれの写真のどこが気になったか言説化する。自分の関心がどういうところにありそうか、これまでアウトプットした妄想とどういう関係がありそうかなども振り返る。
日々のなかで心がうごいたものを写真に収める習慣をつけるといい。
3.組替について
組替=分解+再構築
・分解のステップ1
1.あたりまえを洗い出す
2・あたりまえの違和感を探る
3.あたりまえの逆を考えてみる
・可動式メモ術
ポストイットにメモを書く、キャンバスに貼っていく、
つねに発想の組替モードをオンにできる。
分解のステップ2
違和感を覚えたら写真をとっておく
分解のステップ3
キャンバスの中央に分解したいテーマを書く
周囲にそのテーマに付属しているあたりまえを張り出していく。
最後にあたりまえの逆をいちばん外側に貼る
再構築のステップ1
アナロジー。未知の事柄A(ターゲット)と既知の事柄B(ソース)があったときに両者のあいだの類似性Cをもとに「Aもこういう性質をもっているだろう」という推論を働かせることだ。なんとなく似ている、という感覚。
再構築のステップ2
・アイデア・スケッチ
似ているものを探してみる。「公共空間でもつけっぱなしでいられるイヤホン」というアイデアがある場合、その構成要素である「公共空間で身につけるもの」「頭につけるもの」などを手がかりにすると、「帽子」「カチューシャ」などが見つかるかもしれない。今度はターゲットに立ち戻り、「カチューシャのようなイヤホン」「帽子みたいなイヤホン」という発想。それをビジュアル化するとなおいい。
再構築のステップ3
時間やフォーマットを制限したほうがまとめる作業に有効
4.表現について
まず手書きではじめる
アウトプットせざるを得ない状況をつくる
いいアイデアを思いついたら、まずは褒めてくれるひと、新しい物好きな人、のりのいい人に話せ
・記憶力と創造性がたかまるビジュアルメモ
絵でノートをとると、文字と比べて記憶定着率が29%高い
・相手の知識との接点を持つ
聞き手にあわせて接点をカスタマイズする
表現においては他人に影響を与えることを最終目標にすべき。
投稿元:
レビューを見る
前半の例え話は、自分も独立起業の道を辿ったので「共感、わかるわかる」というより「それは知ってる」の連続だった(我ながらオッサン臭い)。
「起業ってどうよ?」「独立なんてとてもとても…」の印象持ちつつ、憧れている人には一読の価値あると思う。例え話で客体化できると怖さは和らぐと思います。
自己啓発から経営、マーケティングのロジカルな分野を、どの立ち位置の人にも理解・共感しやすいストーリーとイラストに変換するところがデザイン思考だし、本書タイトルの「つなぐ」の意図と理解しました。
後半は、著者が米国で受講したデザイン関連講義の要約といったところなのでしょう。それを日本企業向けにアレンジして現在のビジネスにされているようです(詳しく調べてないです)。
マーケティング業界で元P&Gの方々の活躍が目覚ましいのは事実で「P&Gマフィア」というタグの付く方々を追いかけたくなりました。USJを再建した盛岡さんや、日本マクドナルドのV字回復させた足立さんなど、マーケティング・スキルで名を馳せている人ばかりです。向上心と探究心が強い人たちで自分たちのブランディングもうまい人たち。
投稿元:
レビューを見る
まさに「直感」を「論理」で繋いでくれた何とも言えない感覚。
Rモードで体験していないことをLモードで習得しようとしても自分に体内にインストール出来ないと感じる部分があったし、ビジョンドリブンで進むべき意義、アナログでアウトプットしてからデジタル化することに意味と脳の働きの関係性など、LRの振幅がとても勉強になった。
投稿元:
レビューを見る
1.流行りのデザイン思考について知りたくて購入しました。
2,「やりたい」を明確に持って行動することが本書の述べていることです。
目に見えるビジネスには主に4つの世界があります。それは、カイゼンの農地、戦略の荒野、デザインの平原、人生芸術の山脈です。戦略の荒野ではレッドオーシャンの戦いを強いられ疲弊しますが、デザイン思考を取り入れることで、別の世界にいけます。つまり、マーケティングで数値を示ししてからではなく、直感を具現化しながらビジネスにするやり方です。
そのためにはプロトタイプをたくさん作って五感をフルに活用していくことが大切です。そのためには、他人に費やす時間ばかりではなく、自分と向き合う時間を確保することが必須です。この時間がアイディアを生むチャンスを生み出してくれます。そのための実践法が示してある一冊です。
3.直感を具現化するトレーニング方法はすぐに取り入れられると思いました。また、自分の生活を振り返ると、「何もしない時間」というのがまったくありませんでした。常に何かをしており、毎日疲れて寝るという日々を過ごしてました。たまには自分と向き合うために、瞑想をいれるのご良いと思い、今日からやります。
投稿元:
レビューを見る
好きな感じの本でした。純粋に楽しかった。
自分の考え方を肯定してくれるんだなとおもいつつ、トライする間隔と回数に問題があるなと実感できた。