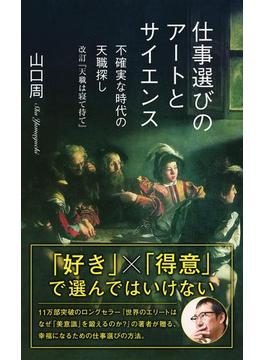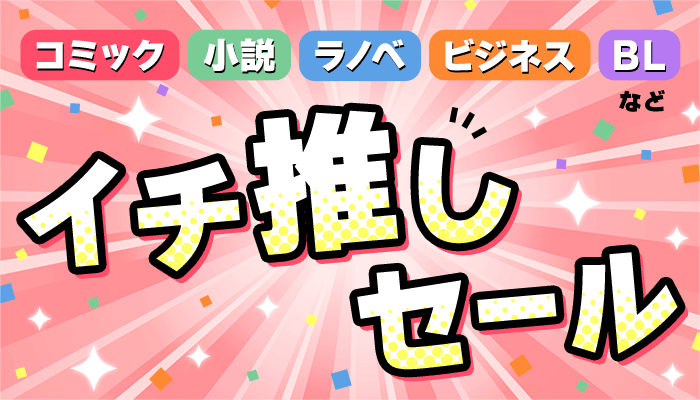絶望と光を与える本。
2020/05/16 14:32
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:まりりん - この投稿者のレビュー一覧を見る
ネタバレありです。日本社会がいかに頑固で転職者に厳しいか書いてある部分に、
本当に共感しています。
私は元から体が弱く、体に優しい職場に出会えなくて転職をせざるをないことが多く、
中途半端に小さく起業しても余計激務になるという「過剰に働きすぎ」な社会で何度も挫折を繰り返しています。
著者と同じく美術史を専攻していて西洋文化の知識・観点から日本全体を私自身の地元・両親を
振り返っても、私個人の力では、この転職者に厳しい無理解な態度を変えられない苦しさをずっと感じて生きてきました。
著者の紹介している考えは、非常に納得できますが、
欧米と比較して国土の小さな、そういう観点では弱小国で無意識に儒教や老荘思想にかぶれている(洗脳されている)日本社会・日本人たちがどれだけ変われますかね。
この本は、いささか欧米かぶれのようにも思えますが、かなりの割合で欧米にかぶれないと生きていけない社会がやってくるかもしれないので、私は著者が照らす光を受け取っておこうと思います。
もともと日本は小国であるがゆえに交易で潤っていた国ですからね。
その時に帰っていくのも仕方のない流れかもしれません。
人間、いかなる時でも、生きるためには学び続ける必要性があるという気持ちを
刺激してくれる良書だとは思います。
転職者だけでなく、経営者・雇用者側も読んだ方がいいのでは。
投稿元:
レビューを見る
本書はかなり変わってる。それはもちろん良い意味で。
元のタイトルが“転職は寝て待て”らしいので、タイトルを変えて正解だと思う。さすが元電通の人といったところか。
タイトルの意味深さ、カバーの画も相まって目を惹く。所謂店頭買いだが、かなりの良書であった。
仕事にフォーカスした哲学書と云えばそう捉えられる。哲学書をかなり読まれているようなので、いろいろな知識を知れて良かった。書き方は、曖昧さを残しつつ、自身の考えをふんだんに書かれているので満足する。おそらくこれは哲学的思考だからかもしれない。
“仕事”に関してさまざまな観点から分析している。内容を転じれば、自己分析や企業分析に活かせる。著者の豊富な(?)転職経験が盛り込まれているのが良かった。そして、なにも“転職すべき”とか“自由を求めるべき”とか固定観点一辺倒でないところもなお良い。頭いい人はこういう風に考えているのかと、思考回路が見えたような気がしないでもないのでなんか嬉しかった。
タイトルから、著書“ハッカーと画家”を想像した。こちらも良かったので、アートと関連付けた著書(一見因果関係のないものが登場するタイトル)は良いのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
「転職」について著者の経験に基づく所感をまとめた本。
内容自体は興味深く読めた。しかしタイトルの「アートとサイエンス」というのはどうなんだろう?
サイエンス要素は広義に捉えれば多かったと思うが、アート要素は殆ど無かったような……。
投稿元:
レビューを見る
タイトルに惹かれ、アートがどのように仕事選びの観点に関わってくるのか、著者の考えを知りたくて購入。
実際は、転職や仕事は、偶然が生み出す産物である事をロジカルに書いているので、アートという表現が正しいかはわからないが、著者の考え方は参考になる部分は多い。
キャリアアンカーなど、他書も紹介しているので、さらっと読むのがおすすめ。
投稿元:
レビューを見る
仕事を選ぶ際に、どのような考え方をするべきか、著者の体験も含めて説く。電通出身で、いい部分も、悪い部分も書いてあるが、その後の転職先の社名がないのは、理由があるのか、ないのかとか考えてしまう。著者は本を読んだあと、内容をエバーノートでまとめているとあり、だから、著作にいろいろと引用があるのだと納得。これから就職、転職を考えている人、今の仕事に悩んでいる人におススメ。
投稿元:
レビューを見る
仕事選び、キャリア論についての一冊。特に転職にまつわる大局観を養うには絶好の一冊であると思います。
自分の得意なことは実際にその仕事に就いてみないとわからない、「好き」と「憧れ」を混同してはいけない、仕事のおもしろさはやってみないとわからないなど、特段目新しい主張なわけではありませんが、巷のキャリア戦略の問題点について丁寧に解説されており、思わず納得、な内容です。
(個人的には)ロジカルシンキングでは人との差別化はできない、自分の中に蓄積された知識やノウハウこそが差別化の源泉であること、業界・業種によって「課題先行」「好奇心駆動」のタイプがあり必要となる能力がまったく異なる、この2点は印象に残りました。
投稿元:
レビューを見る
山口周氏の本が面白くて、もう何冊か読み進めようと思い手に取った。
「好き」×「得意」で仕事を選んではいけない。
なんてキャッチーで挑戦的なフレーズ。
じゃあなんで選ぶんだよ?
と思うが、正解はやってみなきゃ分からないよ。
らしい。
広告代理店(電通)→外資系コンサル(ボスコン)と華々しいキャリアを積んだ彼は、さぞトントン拍子にキャリアアップしていったのだろうと思ったら、実はそうではなかった。
広告代理店は、課題がクライアントから与えられ、コンサルは課題を発見する仕事である。
そもそもが異なるため、筆者は相当な苦労をした。
コンサルに入ってロジカルシンキングの思考回路を作ることを「焼き直す」とも言っている。
そんな彼は言う。
天職なんて選んでも選べない。
なぜならやってみなきゃ、好きかも得意かも分からないから。
以前学んだキャリアアンカーやプランドハプンスタンスなどが出てくる。
そう、幸運は受け止める準備をしておかなければいけない。しかし、準備することしかできない。
そして、メッセージとしては
誰かに役に立っているという実感のある労働をさせてくれる仕事を選べば幸せになるのではないか?
と発していた。
誰かを幸せにする実感は本当に大事なポイントだと私も思う。
投稿元:
レビューを見る
人間の長寿命化*事業の短命化⇨予定調和的・計画的なキャリア形成は意味をなさない.
好奇心,リスクテイク,柔軟性,対応力を持ち転職は寝て待つ.
「好き」と「憧れ」を混合しない
「機会」の増大と「機会が転機を生む」ヒット確率を上げるべく,人当たりの良い振る舞いをする
「自由」を得るには「不自由」で力を蓄えなければいけない.自由は孤独と責任との戦い
ダイヤモンドの物理的希少性はなくなりつつある,デビアス社が供給を絞りブランディングしていることで今でも宝石商売として成り立っている
「報酬」は内発的動機を外発的動機に変える.悪影響を及ぼす.
エモーショナル・サイクル・カーブ
転機:
終焉ー中立圏ー開始
キャリア・転職について考える人が手に取る本だが転職ノウハウ本とは一線を画する
芯がありそれでいてわかりやすい文体とその内容から筆者がとても理路整然とした思考ツールとバラエティ豊かな教養を纏っていることがわかる
投稿元:
レビューを見る
元気をもらった。やってること間違ってないんだと思った。チャンスの掴み方、とかいかにもなハウツーっぽくて嫌だけど、良かった。
長々と論理的な説明が続いて途中読む気なくしちゃったりもしたけどざーっと読むには良かった。
広告代理店のダメな部分は闇深さを感じた。
投稿元:
レビューを見る
いい偶然を呼び込む方法など、良いキャリアを積むための方法論。所詮勝ち組の論理かなと思いました。
もちろん自力での努力は成功の最低限の条件だが、運というか人の縁がなければ、出世はできない。
人の縁を掴むのには不平等な一定の法則があると思うが、その辺の本質は書かれていないなあと感じました。
投稿元:
レビューを見る
★本書のメッセージ
「仕事選びを予定調和させることはできない。
自分をオープンに保ち、いろんなことを試し、しっくりくるものに落ち着くしかない。」
★本の概要・感想
哲学修士→電通→戦略コンサル→ITベンチャー役員→組織コンサル とキャリアを歩んだ山口氏による、仕事選びの本。クランボルツと言っていることはほぼ一緒か。歯切れの良い物言いは相変わらず、読んでいて面白い。特に、戦略コンサルと広告代理店の行動様式がどう違うのか、という比較はオリジナリティがあって面白い。
キャリアに明確な正解や勝ち筋などは存在せず、目の前のことを死なない程度に、熱心にやっていることが大事、というのが本書の主張。本文のメッセージはシンプルであり、各章は、シンプルなメッセージの脚注にすぎないとのこと。その脚注のデータや知見がいちいち面白かった。
ただ、販促上か、タイトルはややかっこつけかな?仕事選びの「アート=技術」という意味でなら、理解できるが、著書経歴の文脈上、「アート=芸術」と解釈して本書を取る人にも多いのではないか。本書では、美意識や芸術に関するテーマと、キャリアの関係性については深く語られていないので注意。
★本の面白かった点、学びになった点
*その仕事を始める前から、「自分に合っているか」どうかなど分かるはずもない。得意は分からない
p8 勝ちパターンが明確に存在した時代の方がおかしい
p53 最初から自分にフィットする仕事を選ぶのは難しい。それにも関わらず、終身雇用をかかげ、自分にマッチしていないと考える職場や産業で働き続けている人が多いから、生産性が低いのではないか
p100 石の上にも3年は正しい側面もある。3年はやらないと、その職業の面白さは分からない部分もあるだろう
p109 あるべき姿について強すぎる観念を持つのは危険。明確なゴールイメージをもったとしても、そう思い通りにいかいことがほとんどなのだ
p131 新しいキャリアに挑戦してすぐあきらめてしまう人「プライドが高く、責任感が強い人」
→うまくやれていない自分、成果をだせていない自分をゆるせなくなってしまう。ある種の適当さが必要。そんなに高い理想を掲げて頑張り続ける必要などない
p182 山口さんもマジで苦しんでいた...「コンサルタントになって2年目くらいの時期だったと思いますが、連夜の深夜残業が続き、しかもアウトプットが評価されずに七転八倒していたころに『本当に辞めよう』と思ったのの、あまりに忙しくて転職のための準備、つまり志望動機や履歴書を作成したりするもの時間が取れず、結局目の前にやってくる氷山のような仕事の山を何とかこなしているうつに、プロジェクトも終了し、いろいろな人間関係も改善してしまった」
→学生時代の研究発表大会の運営や、卒論の執筆ん近い感覚だな
*自由を獲得するために不自由である20代
「仕事は半端ではなくキツかった。つまり、極めて不自由な生活をしていました。月曜日から金曜日は連夜の深夜残業。週末に会社に来るのが嫌で、何とか金��日に終わらせようとしたら土曜日の朝になっていた、ということが何度もありました。まさに奴隷状態だったわけですが、その奴隷状態がいまの自分の持っている自由さの礎になっていることは間違いないと断言できます。」
→Ph.Dの修業時代が一番つらく、そのあとは開放的、というのと似ているな
P 190 他業界や他業種に移ったら、「脳の回路を焼き直せ」
*転職後は必ず訪れる「2つのリアリティショック」
・まず、仕事内容や業務内容への驚きと失望
・そして、新しい組織の価値観や行動様式に対する驚きと失望
→転職して1,2か月経つと、それらに打ちひしがれる部分もあるかもしれないが...心をオープンにして、受け入れること。自分を見失わない範囲で受けれ入れることができればよい
●本のイマイチな点、気になった点
大きくはない。キャリアに関する本はいろいろと読んできた。他の本と共通するものが多いが、自然と楽しめた
●学んだことをどうアクションに生かすか
・20代は修行の時代と捉え、素直に学びつづけること
・目の前のことを一生懸命やること
・大きな理想や「~であるべき」といった考えはできるだけ持たず、可能な範囲で持続的に何かしらやっていくこと
★もそも読んだきっかけ
転職が決まったっため。また、転職後の心理について触れている章があったので。
投稿元:
レビューを見る
終身雇用は日本の伝統文化ではない
高度成長時代を元に出来上がった制度
かつては資本が貴重な時代だから労働力が過小評価
今は最も希少なのが、労働力、資本は過剰
運動量=モビリティを高めて色々と試さないとダメ
試行錯誤しても有益な示唆は得られない
好奇心、粘り強さ、柔軟性、楽観性、リスクテイク
幸運は準備の出来ている人だけに訪れる
何でもない1日を丁寧に生きる
他人と同じ答えを出す能力をいくら鍛えても競争優位を形成する事は出来ない
ストックを構築するための読書
学びの大きい本をいかに選ぶか→面白いか面白くないか
いかに効率的に読むか→眠い時には読まない、関連分野の固め打ち
自由になろうと思ったら、どこかで不自由を我慢しなければ行けない。
投稿元:
レビューを見る
オビの煽り文句「『好き』✖️『好き』で選んではいけない」というのはややミスリーディング。「好き」と「憧れ」を混同するな、「好き」による継続は才能を凌駕するが、「憧れ」では一旦環境が変わると潰しが効かないから、なるべく「好き」なものに出くわすセレンディピティを高めるよう動け、というのが著者の主張。シンプルだが良書。息子に是非読ませたい。
投稿元:
レビューを見る
これからの人たちは社会をどういう認識でとらえてくるのだろうと読んでみたけれど、なるほど、私みたいな人間にはやりにくい世の中になるなあ
投稿元:
レビューを見る
仕事選び、ということで転職に絡んだ話が中心となっているが、読んでいて分かるな、と思うことが多かった。特にいい人であることを否定しなかったり、逃げの転職もある程度認めている点は理由も含めて同意できた。
転職を現時点で考えていなくても、これからの時代を見据えてどのように動けば良いか、そのヒントを知るのに良いのではないかと、感じた。