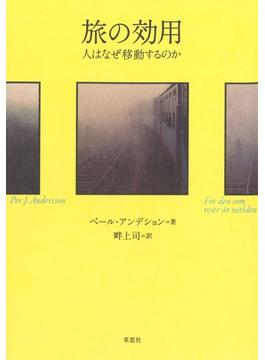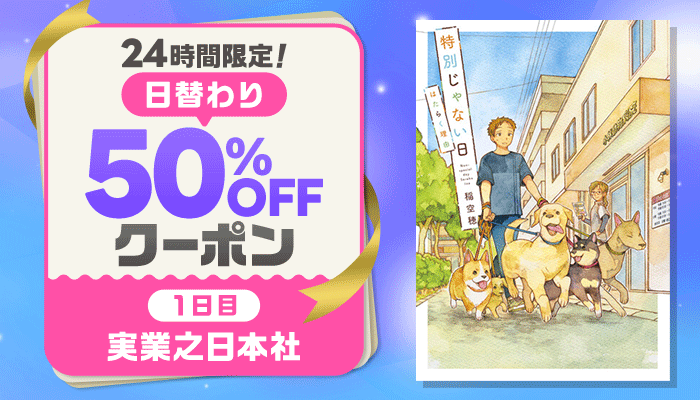投稿元:
レビューを見る
スウェーデン人ジャーナリスト、ペール・アンディション氏による旅のエッセイ集。
全編旅行記のような内容を想像していたが、アンディション氏自身が若い頃に経験した旅の様子や、旅行作家の思想についてなどの記載があり、割と盛りだくさんの内容。インドの列車旅行やヒマラヤトレッキング、そしてギリシアの島々など、決してパック旅行では体験できない旅が描かれている。
人は旅を重ねるごとに多くの事を考え、物思いに耽り、時には一冊の本として形にする。これも旅の効用の一つなのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
スウェーデンの著名な旅行雑誌創業者である著者が、鉄道、ヒッチハイク、リピーターなど様々な切り口で旅を語るエッセイ。タイトルどおり一冊を通じて旅の素晴らしさ(ある意味素晴らしくない面も含めて)を語る。私自身旅好きではあるがなぜか最後までこの本にのめり込めず、そうか、彼は北欧スウェーデン人で私はアジア人であるゆえ、彼の視点で描写されるアジアやヨーロッパの風景がしっくり来ないのかなどと考えつつ、旅とは個人的体験なのだと気づかされる。
著者いわく、「不機嫌という病を治すにはまず、自分の安全領域から外に飛び出すことだ。」コロナ禍のいま、自宅からも以前と同じように出れない状況だからこそ、ますます外に飛び出したくなった。
投稿元:
レビューを見る
旅嫌いの人は、意外なことが起こると軽いストレスを感じて神経質になることがある。それどころか興奮したり怒ったりすることもある。意外なことはもちろんどこでも起こりうるのだが、できるだけ今までどおりの生活を送りたいと思うのだ。これに反し好奇心たっぷりの旅人は、事態に即応し、異なる習慣や新たな人間関係を理解する。(p.12)
変化がなければ心は消耗する。だが新たな見方をするようになれば、新たな展望が開ける。旅をすれば感覚が研ぎ澄まされ、世間や家庭内の状況に対して注意深くなる。今まで無関心だったことにも、不意に何かを感じるようになるのだ。今まで見えていなかったことが不意に見えてくるのである。(p.13)
見方が変われば、今までずっと宇宙の中心と思ってきた場所が周辺になり、逆に、以前は縁だと思っていたところが中心になるのだ。当時の私にはそのことが分からなかった。だが私はそのニュージーランド人と出会った時、実はその後の自画像を見ていたのである。(p.18)
ミュージシャンたちは、西部で幸運をつかもうとする自由の象徴として、そしてその自由な夢の象徴として、鉄道にノスタルジーを抱きつつ歌っている。彼らは歴史の淡い光を受けていた高貴で真正な時代に、芯から憧れているのだ。(p.81)
飛行機旅行には他の面もある。私たちの世界観を歪めてしまうのだ。飛行機で旅をすれば、世界を航空路の網の目を見なすようになり、鉄道路線や車道、そして草原と湖の脇をウシがたどる道、さらには森を抜けてアルプスの峠を越える道を忘れてしまうことになる。私は今まで辺鄙なところを旅しては種々の文化が遭遇する光景をみずから体験してきたが、もし飛行機に乗れば、空間意識はしだいに狭くなっていく。地球は各々の部分が合わさって全体が構成されているのだが、現代においてはこの惑星上を行ったり来たりしているうちにそうした感覚をしだいに失ってしまうのだ。(p.111)
哲学者アラン・ド・ボトン(旅する哲学):「私たちが目にしている光景と、頭の中の考えとは、奇妙につながっている。壮大な思考を生みだすには、時には壮大な眺望、新たな考え、新たな場所が必要なのだ」(p.114)
思考にとって最良なのは、景色が穏やかなスピードで過ぎ去ることだ。列車は充分速く動いているので常に同じ景色でも飽きることはないが、ゆっくり走行している時には、もっと細かなこと、独特のことを認識できる。その認識は、果てしない雲やいつまでも変わらない大洋といった単調な光景を見ている飛行機旅や遠洋航路よりも遥かに生き生きとしている。(p.115)
カメのように、カタツムリのように
「目的地に至る過程が旅の重要部分なのだ。目標、目的地に集中しすぎると、旅に満足できなくなる」
リピーターになるというのは、広い視野を持つこと、連続性を保つこと――そして何事であれ維持することだ。(p.144)
「旅は、私たちがホモサピエンスであることと関連がある。好奇心だ。『無用な』知識を求めて努力し、知恵を拡大し、視野を広げ、世界像を拡大し、混沌を整理し、秩序を確保しようとする意思である」(p.154)
そしてウィーンに行った。ノスタルジーの旅人すべてにとって夢の都会である。リング通りを永遠に輪を描いて市電に乗る。ブルク劇場、国立歌劇場、市庁舎、そして家々、豪華さ、さまざまな付け足し。都心をことこと走る市電で何周もする。ここは第一次世界大戦前には強大なハプスブルク帝国の中心だった都会。人口5000万、17の人種、12の言語などを支配していた国の首都。
ウィーンにはヨーロッパ各地から人がやって来る。コーヒーを飲むためだったり、劇場に行くためだったり、音楽を聴くためだったり、あるいは、世の中をどう変えるべきかについて議論するためだったり。(p.205)
レストランの壁に目を向けてみよう。歴史的で絵のように美しい農機具、日々が入って灰色になった木製の農機具が多くかかっている。それはいいことなのだ。なぜだろう?現代生活が今風であればあるほど、休暇中は伝統への憧れがいっそうふくらむのだ。(p.210)
自由に動き続けているのだ。それは幸せだが、同時に物悲しい。だが彼女はこうした感情のことを、旅をしない人には語ろうとしない。もし語れば、相手は、誇張された話だと思い、彼女のことを用地で愚かな人と見なすだろうと思っているからだ。「だから、ひたすら口をつぐんでいるの」と言いながら彼女は私の顔をじっと見て、話が的確に伝わっているかどうかをたしかめている。(p.221)
「不愉快な状況に置かれても不快さを受け入れる、ということを学びました。試練が厳しければ厳しいほど、うまく行った時の安心感は強くなります。こうして、見知らぬ人への信頼は、肉体的な記憶同様、私の中に蓄積していきます。私は、世界への好奇心がますます強くなっているのを感じでいます」(p.236)
「何かを敢行するということは、あっという間に地歩を失うことを意味するが、何かを敢行しないということは、自分自身を失うということだ」(キルケゴール、p.252)
「旅をした人たちは人付き合いが良くなったし、好奇心が増し、感情が豊かになりました。また、新しい環境や新しい出会いに対応しなければならなくなっても、あまりストレスを感じなくなりました」とユーリアは語っている。(p.262)
「旅は人付き合いのトレーニング場でした。私は、何が正しくて何が間違っているか、何が良くて何が悪いか、それを旅で学んだのです。ペルーやバングラデシュといった国々で一人旅をしている最中に地元の人たちとコンタクトすると、私の世界蔵が純化されました。そして人付き合い、真理、倫理が鍛えられたのです」(p.276)
旅はおおむね、フィクションを読むのと似た働きをしてきた。過度に本好きの人たちと、過度に旅好きの人たちは共に種々の人生に接する。その結果、両者とも「そんなことはないだろう」というより「そういうこともあるだろう」と考えるようになっていく傾向があるのだ。
他方、私はしだいに、旅をしない人が些事と呼ぶような事柄でも興奮するようになってきた。旅は徐々に習慣化する。旅は、町の通りでばったり出会った人たちに対する私の見方を変えた。自宅のあるストックホルムにいて、通勤・通学する人たちをじっといていると、彼らは朝のラッシュアワー時には黙ってプラットフォームに沿っ��歩き、スマホをじっと見て夢中になっている。彼らにしてみれば、周囲は自分の気持ちと何の関係もない。そういう光景を見ると私は不意に、「自分はこの町にそぐわない」と強く感じる。(p.324)
投稿元:
レビューを見る
「旅の効用 -人はなぜ移動するのか」http://soshisha.com/book_wadai/books/2436.html 読んだ。文化人類学的な考察か、せめて社会学いやせめて統計の引用を期待したのに、視野の狭い決めつけで始まり終始旅の思い出と感想だったよ。旅先はおきまりのインド。沢木耕太郎か。よくみたら著者はジャーナリストだったよ〜涙(おわり
投稿元:
レビューを見る
旅は、我々人間に必要なものだ。
決して道楽ではない。
「旅は、私たちがホモサピエンスであることと関連がらある。好奇心だ。『無用な』知識を求めて努力し、知恵を拡大し、視野を広げ、世界像を拡大し、混沌を整理し、秩序を確保しようとする意思である」
自分の目で見て、秩序を確保する。知らない事の一つ一つのピースをはめ込んで、作り上げるジグソーパズルのように。
かの名著『ファスト&スロー』におけるシステム1、つまり感情的に反射的に素早く判断すること。動物的に危険を回避するためには必要だが、人間同士のコミュニケーションにおいては、システム1が妨げになる。システム2で理性的に判断出来ればいいが、そう簡単ではない。システム1を稼働させるのは、「不安」だ。「不安」を取り除くためには、旅をして、秩序を確保することだ。世界の全体像を知れば、不安は解消され、システム1を稼働させずに済むだろう。
そうやって人間は進化し、強さを獲得した。
だから、「旅をしたい」という欲求を押さえ付けてはいけない。
それ以外にも、「旅の遺伝子」の話、歩くことの効用、ヒッチハイクの話、旅行記の話、などあらゆる旅の話がてんこ盛りで楽しい。
投稿元:
レビューを見る
とにかくボリュームがすごい。
訳者の後書きにもあるように、そのとき読みたいテーマをランダムで選んで読んでいく方法の方が良いかもしれない。
最初から読み進めたら読み終わるのにとても時間がかかってしまった。
エッセイ・旅行記というよりは、もっと旅や人の移動について旅行記や論文から考察を重ね、パッケージのツアーに頼らない旅の魅力を伝えている。
投稿元:
レビューを見る
尾道のある本屋で買った,自分には難しかった
最初らへんは興味を持って読めたけど。
人間は本来、移動する生き物なんだなあ
旅に出たい☆
投稿元:
レビューを見る
自分の旅がいかに目的地ありきで表層をなぞったものか、考えさせられた。
次に行く旅行はスロートラベルを意識して、何事も楽しめたらいいなと思う。
世の中が便利になった今、ノスタルジックな、昔の手のかかることの体験にあえてお金を払うようになっている。今までなぜ惹かれるのか気づかなかったので、改めて認識できた。
投稿元:
レビューを見る
モノを持たなければと考えたり、モノを持って喜ぶ事はやめよう
モノはいつか壊れるし、失われる。昨日のことを悔いない生活、そして明日がどうなるか心配しない生活。
いつも今、ここだけが大切な生活。
とりあえず旅人あるあるが書かれてた本やなーっていう印象。
旅してない人の感想が知りたい。
投稿元:
レビューを見る
わたしも旅行が大好きだ。
でも、筆者が行ってきたようなことの体験とは程遠い気がする。
彼がしてきたことや、彼の知人たちの体験はとても貴重で尊い。
果たして単なる憧れや思いつきでできるようなことだろうか?
旅を通してわたしは成長していきたい。
よりもっとオープンマインドな自分になりたい。
違う自分を発見したい。
人から話を聴くこと、本を読むことから得られることはもちろんあるし、そういった時間も必要かつ価値のあるものだ。
けれども、百聞は一見にしかず。
自分の目で見ること、実際にその地に足を運んで体験することから得られるものはその何倍も意味のあることなんだと改めて思った。
投稿元:
レビューを見る
自分が求めていたような内容ではなかった。著者の旅行記を書きつつ、過去の旅行記から、人が旅行をする理由を著者なりに解説するような内容であった。もう少し客観的な内容(新書的な内容)を期待していたので、ちょっと期待外れだったかな、という印象。
投稿元:
レビューを見る
Kindleのセール本で何かいいのないかな〜とディグする習慣があるのだけど、そこで見かけて読んでみた。コロナ以降、全くもって旅をすることがなくなり早2年。徐々に解禁ムードが漂う中、改めて「なんで旅行するんだっけ?」という基本的な動機を思い出させてくれた気がする。
著者はスウェーデンの方で旅関連の著名な雑誌を立ち上げた人らしい。タイトルがだいぶ硬いので、理詰めでガチガチの議論をしているかと思いきやエッセイで読みやすい。本当にいろんな角度で旅について論考しているのだけど、大きな主張としてはツアーではなく、メジャー観光地ではなく、ゆっくり、長くといったスローライフならぬスローツアーのすすめとなっていた。自分自身は著者の考えと近くて、いわゆる観光名所よりも地元の人がどんな感じで暮らしているのかに興味を持つタイプなので主張に納得することが多かった。ただ何ヶ月も旅に出れるわけでもなく著者と比べて時間に限りがある生活ゆえに予定詰めすぎてセカセカすること多いなと思っていたので、旅慣れた場所で時間をかけてゆっくり過ごす、みたいなことが今一番したいかも。
また著者はインドに心酔しているようで自身のインド訪問時のユニークなエピソードが色々あって興味深かった。ただ旅に対するモンド映画的な態度は若干気にかかった。つまり、あくまで自分はスウェーデンという帰る場所があり、それありきで発展途上国をたまに訪れることで楽しむ的な。それは発展途上国の発展を望まないという態度に映らないでもない。旅の結果、外貨が現地に落ちるのだからいいじゃない、という論は本著でも展開されていたけど、昔からこの手の善に関する議論にすんなりと乗れない自分がいることを再認識した。
完全インドア派がますます加速しているので以下のラインを意識しながら書を捨てて旅に出たいものです。本著内で絶賛されていた「パタゴニア」を次は読もうと思う。
—————————————————————————
体験が人間を形成してくれるのだ。私たちは体験でできているのだ。体験の結実なのだ。体験する印象が増えれば増えるほど、私たちは人間として成長する。
投稿元:
レビューを見る
なかなかのボリューム。
旅行記というより放浪記。文章の癖が気になる。
旅行は帰る場所があることが前提。
交通用具が発達して、旅のスタイルも効率化されているけど、時間を気にせず旅したい。
投稿元:
レビューを見る
広辞苑によると旅は「住む土地を離れて、一時他の土地に行くこと。 旅行。 古くは必ずしも遠い土地に行くことに限らず、住居を離れることをすべて「たび」と言った。」 とされている。旅の前提は、居場所があるということのようだ。「スウェーデンの生活が安定しているからこそ、そしてスウェーデンにいれば安心だからこそ、しばらくスウェーデンを離れるのも容易なのだ。もしスウェーデン社会が荒れていたら、旅立つのは不安だろうし困難だろう。しかし、ポジティヴなことであれネガティヴなことであれ、ともかく何も変わらないからこそ、彼女は冒険家になることができ、不意に姿を消したり、不意に戻ってくることができるのである。」P173。なぜ私たちは旅をするのか?レクストレームは「旅は、私たちがホモサピエンスであることと関連がある。好奇心だ。「無用な」知識を求めて努力し、知恵を拡大し、視野を広げ、世界像を拡大し、混沌を整理し、秩序を確保しようとする意思である。」P 154。生まれつき好奇心があるから、自宅を出て遠くに行く。旅の効用は?ユーリア・ツィンマーマンの研究によれば、「旅の前までは当たり前と思っていた事柄について新しい見方をになり、物事を高く評価するようになることが判明した。旅をした人は新たな体験に対して開放的になり、精神も安定し創造的になるが、それは旅が私たちの言動を調整し、行き先の習慣を受け入れることを教えてくれるからだ。旅をする人は他人に共感するようになり、容易に妥協して他人とうまくやっていくようになる。」P 263。また著者のガールフレンドカーリンは「あなたは異文化の中に入って初めて、自分を見つめ始めることができるのよ。別の文化に反
応することによって、自分が何者か、自分がどこから来たかを理解する。異文化の人たちから奇妙だと思われることによって、あなたの自画像は正確になっていく。旅は鏡のようなものよ。そして最高のセラピー」P 266。旅とは自分の置かれた環境から出て自分を客観視する行為なのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
こっそり秋葉原を遊び場にしてた子供時代を思いだす。あえてホームシックに追い込み帰宅時の安堵感を助長させるテクニックはこの頃に身につけた。(筆者との方向性は少し違うが)
「ピダハン」然り、最後にはお決まりのようにパートナーとのあるエピソード。こういった旅物の密かな見どころ。