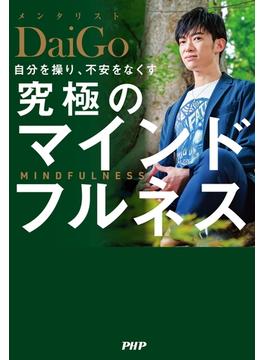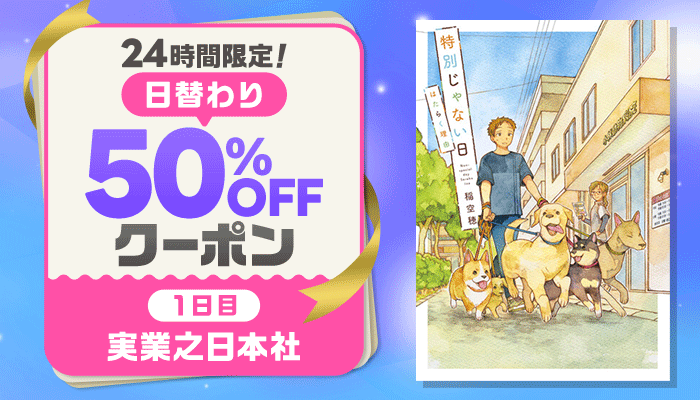すぐ使えることが多く……
2021/06/24 02:39
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
役に立ちます。目から鱗というのも……。嫉妬は、自分の好きなものがわかる、だとか……。瞑想、をしたら、不安が取り除かれる、そうなると、不安から来るストレス除去できる……その通りですよね……。
投稿元:
レビューを見る
よく成功してる人は失敗を失敗と思わないと言うけれど、それには科学的な根拠があった。
うまく自分の中で転換して原動力にすることが重要。
嫉妬も意味を理解すれば、大きな原動力となる。
この本を読めば、要は考え方、といったことがどんなに深い意味なのかがわかる。
同じ会社でイライラ仕事をしてる人に薦めたい、そんな本。
投稿元:
レビューを見る
DaiGoさんのアドバイスにより日々瞑想に勤しんでいるnaonaonao16g。果たしてその効果は出ているのだろうか。自分でもよくわからないのである。
DaiGoさんによると、マインドフルネスとは…
「自分がしていることに気付くこと。そして、気付いたことに対して判断を下すのではなく、あるがままに、明確に、その物事をとらえるということ。」
うーん…
例えば、漠然とした不安に襲われた時。
「それがいいか悪いかを考えて、悪いと判断したら、自分はすごく悪い状態なんだと、どんどん凹んでいってしまいます。そうではなくて、あるがままに、『ああ自分は不安な状態にあるな』ととらえ、何に対して不安を感じているかを明確にしていくことが、マインドフルネスなのです。」
・悩みがあり、考えても仕方のないことを頭のどこかでずっと考えていると、脳の力が低下する。つまり、バックグラウンドで通信しているアプリがあるせいでスマホの動作が重くなるようなもの。
・この同じことをいつまでもクヨクヨと考え、同じ悩みに囚われている状態を「反芻思考」といって、緑の中を歩くことで反芻思考の回数が減ると言われている。一定時間反芻思考をやめることができると、新しい方向性などを見つけてクヨクヨ悩みづらくなる。(うつ病の治療では実際にボルダリングやキックボクシングで一定時間反芻思考をやめるだけでも効果があるという研究結果が出ている。)
→なるほど、まずはバックグラウンドで通信しているアプリ(漠然とした不安)を消すという作業を始めるのね!
・漠然とした不安や焦りの正体、その原因はマルチタスク。その最たるものがスマホ。スマホを使い過ぎると、他人への共感能力が落ち、時間が無くなる感覚に陥り、不安や焦りが高じて、またスマホを触るという悪循環に。
・人間の脳はマルチタスクができないようになっている。マルチタスクにより、脳の短期記憶がダメージを受け、誘惑に弱くなり、常に刺激を求めようになる。瞑想や運動を心がけてセルフコントロール能力をあげても、スマホの使い方を間違えると効果を打ち消しあってしまう!
→なんと!例でスマホのバックグラウンドが出ていたのに、まさかの結局スマホ!でも、仕事とかで常にメッセージとか気にかける必要があるし、どうしてもマルチタスクは避けられない気がする。うーん、いったいどうすれば…
・意図的にシングルタスクの時間を作る。本を読む、映画を観る、瞑想など、30~50分くらいに分けてタイマーを設定するとか。
→なるほど。とりあえず、朝、スマホのアラームを消した後、出かけるまではスマホを見るのやめました。
・「不安脳」=⓵周囲の脅威に対して過剰に反応しやすい、②報酬に反応しづらくなる。つまり、怖がりで喜べない、のダブルパンチ。脳の筋トレのようなことをしていないと、どんどん不安に弱くなる。難しい本を読むとか、記憶力が必要なゲームやなぞなぞをやる等して問題解決を行っている脳の部分に意図的に負荷をかけるようなことをする。
→これは目から鱗。まさに不安脳ですわたし。とっつきやすいのは難しい本を読む、だけど、どのくらいのレベルの難しさがいいんでしょうね。
・不安は、「失敗したらどうしよう」という恐怖によって生じる。他人の失敗なら許せるのに自分のこととなると「失敗したら恥ずかしい、やばい」と思ってしり込みしてしまうが、人間はミスをする生き物。他者目線で失敗をとらえるといい。
・例えば、自分の身に起こったトラブルは判断が鈍るが、友達に起こっていると想定すると判断能力が上がる。なので、自分に起こったトラブルでも、友達がトラブルを抱えていると想定して、自分だったらなんと言うかを考えると答えが出てくる可能性が非常に高い。
→なるほど。これは恋愛相談とかにありがち。友達には平気で別れれば?とか言うわりに、いざ自分が同じ状況になったらそう簡単に別れられない。自分のこととなると判断できない。
・必要なのは、失敗しても凹まないとか、まったく気にならない力ではなく、失敗してもいいと思えるようになる、失敗を楽しめるメンタルを作ること。
・そのためには、①失敗を学習と捉える、②自分と他人を比べない(他人ではなく過去の自分と比べて前に進んでいる、と考える)、③正解は一つではないと考える。
・また、呼吸に注目すること、自分に優しい言葉をかけて、前に進むための励ましを与えることも効果的。
→ヨガ、瞑想、セルフコンパッション、という感じか。そして、デジタルデトックスもできたらいいわけだ。
・完璧主義者ほど失敗の確率が高くなる。SNSのフォロワー数など、人との差を感じる場面が多い。それらがとくに不満もないし、ある程度好きなこともできて、暇つぶしになるエンターテインメントがいくらでもある状況にも関わらず、なんとなくもやもやした不安を感じる状況を引き起こしている。
→これはほんとに現代社会の闇だと思う。SNSって承認欲求だけじゃない。
・なかなかすぐには自分は変えられない。ハードルをぐんと下げて、自分の生活の10パーセントくらいを変えるようなわずかな変化を積み重ねることによって自分を変えていくのがベスト。
・ようやくマインドフルネスの話。人間は、不安を感じ、危ないと思うからこそ次を考えて行動し、次を考えて準備をする。なので人間は不幸や不安を感じやすくできている。そういう性質があることを知って、今自分が感じている目の前の幸せを楽しむ。「いま、ここ」の感覚。いまに集中する能力を高めれば、自然とそれ以外のことが気にならなくなる。没頭するのに一番いいのが瞑想。
・感情に左右されなくなる、というのがすごく大事。自分が行動しているときに、自分が何をしているのかに対する気付きが起こり、客観的に自分を見られるようになって、いまベストな行動は何かを常に冷静に考えて行動できるようになる。
・例えば「怒り」を感じた時、その怒りがいいとか悪いとか価値判断をするのではなく、いまどういうことが起こっているかを客観的に観察する。そうすることで、無理に感情を抑えず、その怒りを相手にぶつけることもなくなる。
→全体を通してDaiGoさんは運動を勧めてたけど、わたしに合うのは瞑想かな。毎日ではないけれど、続いてはいるという、他人ではなく過去の自分との比較。瞑想とセルフコンパッションを、それなりに続けていこう。
投稿元:
レビューを見る
動画で発信していることの総まとめに近い感じではあるが、ひとつひとつ試してみたいと改めて感じるネタが多かった。ちょっとやってうまく感じがつかめなかった歩行瞑想をまたやり始めてみた。今度はうまくいきそうな感じがするので続けていこうと思う
投稿元:
レビューを見る
•緑の中を歩くと悩みが消える
•ミスしてもいいと思うと自分らしい行動ができる
• 友達へのアドバイスを自分にする
•他人のために何かをすると思うと強い
•毎朝楽しい行動を選ぶように心がけようと言い聞かせる
•目標を達成するのが楽しい
•強みを活かす
•人の目を気にしなくなると幸福度高まる
•コンプレックスが多いことは強みも多い
•弱さを受け入れるために悩みや失敗を紙に書く
•ストレスを避けようとするほど鬱になりやすい
投稿元:
レビューを見る
結局はアクションしなければ不安は何も解決されないということです。どのようにアクション、アプローチすべきか参考になりました。
投稿元:
レビューを見る
気づくとスマホ依存症の私。
意図的にシングルタスクの時間を作り出すためには、1つの作業に集中する時間を作る。本を読む、映画を見る、あるいは瞑想や散歩でも良いが、それぞれの時間を30から50分ぐらいに分けてタイマー設定をしておく。タイマーがなるまでは他のことをしないようにする。もちろん、メールやメッセージのチェックもやらない。
「自分が変わろう」ではなくて、「自分がこう行動することで、他人に貢献しよう」「他人に影響与えよう」と思うことで、メンタルが改善し、他人との関係を端をする。
本当に自分に自信をつけたいのであれば、目標を他人に向けた方が良い。
行動を変えていくと性格も変わる。
例えば、楽しいことをしよう、ではなく、楽しい行動を選ぶように心がけようと意識するだけで、認知能力や頭の働きがよくなる。
また、自分の力で変えられるものと、変えられないものを見分けることも大事。
二次的コントロールと言って、環境ではなく自分をコントロールすることが有用。嫌なことや辛いことがあったときにそれをなくそうとするのではなく、自分の捉え方を変えて適応しようとすること。
やりがいを感じて幸福度を上げる4つのポイント
①強みを活かして成長できているか
②自分が感謝できる人、自分に感謝してくれる人と、しっかりつながっているか。
③頑張ればある程度何とかなる、と思えるか(ただし完璧を求めない)
④他人と比べずマイペースを保てているか
なかなか変えられない自分のための10%ルール。ハードルをぐんと下げて、自分の生活の10%位を変えるような、わずかな変化を積み重ねることによって自分を変えていくのがベストのやり方。例えば、時間の使い方を変えたい場合は、10%ならぬ「1日10分間」だけ、自分のために使うようにしてみる。30分間だけ集中する。運動してダイエットしたいなら、いきなりジムに行くのではなく1日5分間だけ運動するようにすればいい。もうちょっとできそうだと思っても消して書いてはいけない。大事なことを続けること。増やす場合はほんとに少しずつ。
人間関係のストレスがなくなるメンタルチェックとしては、非常に細かい情報を思い出し、紙に書くといったトレーニングを、約6週間行うと言うものがある。過去のトラブルを中途半端に何回も思い出すから状況が悪化していくのであって、状況だけを細かに書き出すのみで、自分の感情が混じっているところは削除する。客観的に、そして自発的に過去のトラブルを分析することができるようになる。
感情に左右されなければ、そこが極楽になる。
怒りがいいとか悪いとか価値判断をするのではなく、今どういうことが起こっているかを客観的に観察する。そうすることで無理に感情を抑えることなく、その怒りを相手にぶつける必要はないと思えるようになる。
投稿元:
レビューを見る
メンタリストDaiGoさんの新刊はマインドフルネス・瞑想について体系的に解説された一冊。主に不安が不安を呼ぶ「反芻思考」に陥らないための手法が紹介されており、さまざまなテクニックを吸収することができた(今この時に集中して行動する思考を持つことが一番重要だと再認識)。感情と行動を分離するとか、お坊さんとサイコパスの共通点とかこれまで知らなかった(気付けなかった)学びも多く、文中出てくる参考図書も調べてみて面白いものが多かったので何冊か購入してみようと思った。
投稿元:
レビューを見る
非常に面白かったです。
読む前は単純にマインドフルネスの概念や具体的なやり方、効果などについて書かれてるものかと思ってました。しかし、中身を良く読んでみれば、マインドフルネスだけじゃなく、あらゆる場面での不安対策や感情のコントロールと活かし方、ファンクショナルサイコパスを身につける方法など多種多様なことが書かれていて、しかもとても読みやすかったです。私はまずセルフコンパッションとファンクショナルサイコパスを身につけるところからチャレンジしていきたいです。
投稿元:
レビューを見る
マインドフルネス瞑想の効果が詳細に書かれている一冊。
人間が連想する日々の不安を消す具体的な行動が科学的な根拠に基づき述べられていた。自分のためではなく他人のために行動することや欠点をポジティブに捉える手法などは実践していこうと思う。
投稿元:
レビューを見る
マインドフルネスは瞑想の事だと思っていたが、生き方に対する考え方を学べた。
内容も分かりやすくお薦め。
投稿元:
レビューを見る
メンタリストのDaiGo氏の著書で、ご本人の経験などを交えてわかり易く書かれており、マインドフルネス(気づき)を順を追って説明されている。
人は変わる為には心理的な作用や脳科学的な勉強をした方が効果的とのことで科学的な知見が多用されている。不安や恐怖、ストレス等の対処法も具体的に書かれており、すぐに取り入れられそうだ。
今自分が直面している諸問題は色々な要素、原因が絡みあっているようで、各々の問題に本書を活用していきたいと思う。
メンタリストの科学的知見で幸せな未来を手に入れる参考に。
★★★★✩ 4.0
投稿元:
レビューを見る
Daigoさんの本は具体的な行動と科学的根拠が明確なのですき。
行動すること。
挑戦すること。
シングルタスク。
読書そのものとは関係ないけど、忘れたくないので書いておく。読書休憩中に家族と団らん中に学生時代の話になり、自分は伝統とか保守的なことより、挑戦や自由に惹かれていたことを思い出した。ここ最近、しんどく思っていたことに、ふっと力が抜けて気付いてよかった。
2020.9.28
投稿元:
レビューを見る
他人視点で考え、自分で自分にアドバイスしてみる。
意外と人には的確なアドバイスができるけれど、いざ自分のこととなると、わからなくなる。他人視点重要。
失敗は学習。損ではない。誰かと比べるんじゃなく、過去の自分と比べてどうなのか。
嫉妬の感情は自分が欲しいものを相手が持っているときにおこる。嫉妬の感情から、自分に足りないものはこれだ。と気づき受け入れ頑張ったら、成功の道が見える。
参考になった。
投稿元:
レビューを見る
メンタリストDaiGoさんの動画サービス「Dラボ」で、この本を紹介していて、amazonで購入して読んだ。
日常的にDaiGoさんの動画を見ているので、本に書かれていることの多くは、既に聞いたことがある内容だった。
この本の中で一番勉強になり、実践していこうと思ったのは、「感情と行動を分ける」ということ。
感情は、抑えることなくありのままに受け入れる。その感情のままに行動するのではなく、今起きていることを客観的に観察して、今自分がとるべき行動は何かを冷静に見て行動できるようになりたいと思った。