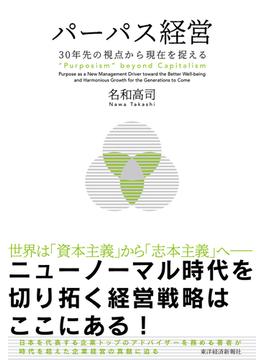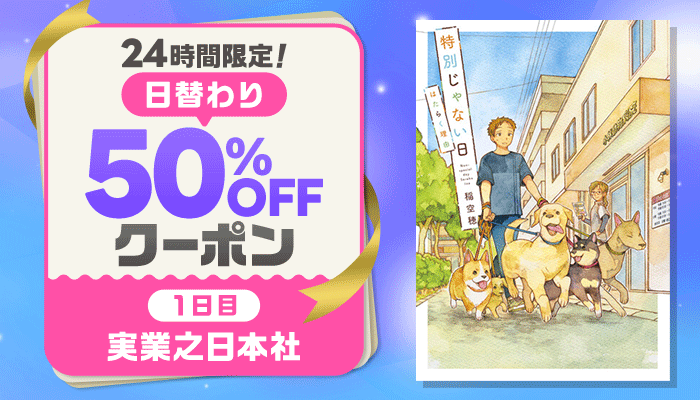0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Hoyobo - この投稿者のレビュー一覧を見る
自分はグローバル経営あるいはグローバル戦略の文脈の中で日本企業の経営を考えたくてこの書籍を購入した。この書籍の中ではグローバルズとして語られている文脈がそれにあたる。でも実際に読んでみると、他にも様々な観点で参考になる。特に創発型ネットワーク組織への進化という文脈で様々な周辺の論点が語られているが自分としては非常に学びが多かった。また筆者は大企業を中心に論じながらも中小や新興企業への視座も持っているのでそこも価値があると思う。
投稿元:
レビューを見る
SDGsバッジを見せびらかしているだけで中身がないと見透かされて見放される。
ファッションエコや、SDGs搾取は持続不可能。
かつての日本人のような、ジリリタ、三方よし、論語と算盤(道徳と経済のバランス)という気概を思い出すこと。
投稿元:
レビューを見る
資本主義における基本資産は、カネ(金融資本)とモノ(物的資本)だった。ヒト(人的資産)は、資産ではなく費用(コスト)として計上されるという欠点があった。本書で提唱する「パーパス経営」の源泉は、人の思いを中心とした「パーパス」という目に見えない資産である。これは自分は何のために存在するのか、そして他者にとって価値のあることをしたいという信念である。「パーパス」は、マネジメント用語としても、ミッション、ビジョン、バリューの上位概念として注目されている。こうした考え方は、日本の企業が昔から「志」といった言葉で、強く持っているものだ(著者はパーパス重視の経営を「志本主義」と呼ぶ)。これからは、志に基づく顧客資産、人的資産、組織資産などの無形資産をいかに蓄積していくかが経営の鍵となる。昨今、注目されているSDGsは、2030年までの目標にすぎない。そうではなく、30年先の視点から現在を捉える発想が不可欠だ。本書では、国内外の100社以上の名だたる企業の変革にかかわってきた著者が、志を追求し、成長を続けるための経営の思想と、具体的なマネジメントの方法を説き明かす。
投稿元:
レビューを見る
SDGs/ESGの波が来ている中、「そんな客観正義を示したところでステークホルダーの共感は得られないので、各企業が主観正義を打ち立てることが重要」という指摘には、納得させられた。確かに、SDGsと企業活動の紐付けやら、コーポレードガバナンスコードの全コンプライに勤しむ企業は多いが、義務感からやっているだけに見える。本来は、これを機会に、企業の志に立ち返ることが求められているのかも知れない。
一方、「ガバナンスは株主のためにやっていることで、株主資本主義から決別した今、そんなのは無用だ」という筆者の主張は極論な気がした。ガバナンスは株主のためだけにやっているわけではないし、会社は株主のものではないとしても、資金調達先として株主の存在が大きいことは事実。あと「ガバナンス態勢を構築することで、企業をリスク回避に走らせるのも問題」という主張もあるが、リスクテイクの精度向上も、ガバナンス態勢構築の目的なので、その点も踏まえて、ガバナンスを軽視しすぎている印象を持った。
投稿元:
レビューを見る
( オンラインコミュニティ「Book Bar for Leaders」内で紹介 https://www.bizmentor.jp/bookbar )
投稿元:
レビューを見る
著者の名和氏がスーパーハイキャリアで超博識過ぎて第Ⅰ部が空転しまくっている。あっちこっちに話題が飛び過ぎて説明を端折りまくり「これからはパーパスだ!」と結論ありきになっている。なので第Ⅱ部からが本番だ。ネスレやユニリーバ、ノボ・ノルディスク、堀場製作所などの具体的事例、禅など日本古来の風習や文化、マッキンゼーの回顧と一刀両断などなかなか面白い。コンセプトワードになるが「資本主義」ならぬ「志本主義」や新SDGsといった軸は明確。しかしそれが何なのかが情報量が多すぎるあまりはっきりしない。PurposeやMassive Transformtive Purposeは今の30代以下にすれば当たり前の話で、バブル世代以前でないと「売上と市場シェア至上主義の無目的な米国追従経営」は実感が湧かないであろう。部分部分は知的好奇心が刺激されて大変面白いのだが、全体からすると「で?」という感じは読後にあるのが勿体ない。
投稿元:
レビューを見る
会社のエライ人が「なわせんせい」と言ってた方の本をようやく読みました。元マッキンゼーの人なのね。
もう超ごもっともでそういう風にしたいけど、なかなか数字に追いまされてる人たちはトップが突然悟りを開いたような事を言い始めると、行動とマッチしてないと困惑するね。。
投稿元:
レビューを見る
主張すること自体はかなり観念的な要素が多かったが、そこに行き着くまでの世の中に関する基本的な情報は論点がわかりやすくカバーされていたように思う。
投稿元:
レビューを見る
小気味良い軽快な語り口で、現在のビジネスの潮流を読み解き、古今東西幅広い観点から、これから日本企業はどうあるべきかを論じている。
局所的な課題を抱えていたところだが、全体観を捉えることができ、クリアになった。
投稿元:
レビューを見る
パーパス経営によって志本主義の実現を提唱しようとしていると捉えた。「志」は行動の原動力となるため重要というのは痛感している。ただ、経営本の読み方が下手なのはありそうだが、パーパス経営を伝えるために本当に500ページも必要なのか、名和氏の言いたいことを全部詰め込んでしまっていて、論点がぼけてしまっているような気がした。実際、意図的か不明だが、ほぼ同一の表現の文章が2,3回、ページを跨いで登場してきたりして、冗長に感じる。様々な書籍の引用や事例紹介をしながら、著者の論理の補強をしており、日本語文章の書き方の上手さもあると思うが納得性は高い。ただ、両利きの経営について、要は~みたいな説明をするところで、結果的に、生半可な理解では両利きの経営は立ち行かないみたいなことが書かれていて、結局何が言いたいのか分からなかった。
投稿元:
レビューを見る
哲学的な内容もあり、少し難しいが、全体としてはなるほどと思えることが多く、なかなか読みごたえがあった。
筆者の舌鋒が鋭く、ズバズバと切り込んでくる感じが小気味良かった。
投稿元:
レビューを見る
理論的内容だが文章は読みやすい。日本的な経営とその良さを知った上での提言をわかりやすくまとめているが、良い会社における自分の成果の披露に偏っている印象も。規定演技ではなく自由演技をという点は腹落ちした。
投稿元:
レビューを見る
動的平衡を貫き通すという一途さ。
著者の言う世界観に著しく共感。
まさに『習破離』を実践しなくては。
投稿元:
レビューを見る
2023年58冊目。満足度★★★★☆
著者は東大法学部卒、三菱商事に入社後、ハーバードMBAを取得、あの大前研一氏がまだ在籍していた頃含めてマッキンゼーで約20年間コンサル業務に従事した経歴を持つ
出版時の肩書きは一橋大学ビジネススクール客員教授
本書はコロナ禍、半年間のリモートワークの生活の中で、古今東西の名著も参照しながら書き上げたもの
一言で言えば、依然としてパッとしない日本企業が本来の力を取り戻して、もっと世界で活躍するための課題提起をした大著(約500ページ)
一部箇所では正直表現がやや冗長な部分もあるが、現在も含めて日本の100社を超える先にコンサル活動をしてきた経験も踏まえて、机上の空論ではない経営書となっており、参考になる箇所は多くあった
投稿元:
レビューを見る
流し読み。500頁だが読み易いのでボリュームは感じない。前半は経営学や思想史と、パーパス=志を落とし込んで活躍している企業紹介。挙げられる参考文献が充実。
後半は日本の強みである現場のオペレーション力を仕組み化することで、可視化されていない資産である現場の力を活かす。そのための変革構想を実現していくためのHOWなど。
日本は経営力はないけど現場の力があるので、をうまく掬い取って仕組み化して経営に活かすようにしよう。あと夢を組織全体で共有できれば、自然と良い方向に向かうよね、という。(で、その辺を経営層は真面目に考えろであって、そのままただ下に落とすな)
色んな単語や何個のSとか鉤括弧の用語とか多い。