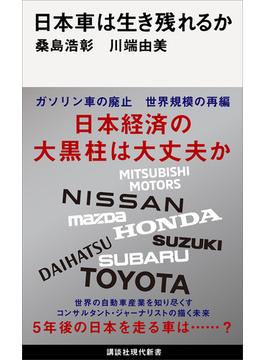投稿元:
レビューを見る
日本の自動車業界の置かれている状況を概観するにはちょうどよい本。
日本車への愛情ゆえの厳しい提言もある。さっと読めて、資料としておいておくのでもよいと感じた。
投稿元:
レビューを見る
私ごとですが先週の木曜日(6/10)に学会発表をしました。社会人生活では通算6度目となりますが、オンラインでの発表は初めてでした。技術系の同僚が会社を辞めることになり、急遽その代役として発表することになりました。
内容は将来の自動車の電動化へ向けて、それに使われることになる潤滑油(オイル)を支える添加剤の技術はどうあるべきかについての内容でした。その発表を少しでも肉付けすべくこの本を読みましたが、日本経済を支えている自動車産業は裾野が広く多くの人が携わっています。そして半導体と違ってまだ日本企業は世界で頑張っている感じを受けますが、電動化へ向けて日本車は生き残っていけるのか、というタイトルにも大変惹かれて読んだ本です。
インターネットがあっと言う間に普及したように、電気自動車もそうなるのでしょうか。10年を経過した時に、この本を読んだことを良い意味で懐かしく思い出せるように、残りの社会人生活を有意義に過ごしていきたいなと思いました。
以下は気になったポイントです。
・日本の自動車業界では往々にしてE(電動化)やA(自動化)の開発が先行して話題になりがちだが、C,A,S,Eを並列で眺めていると本質を見誤る恐れがある。最大のポイントは、Cによって、自動車がIoT(モノのインター)の枠組みの中に取り込まれていくという点である。自動車というモノがインターネットに繋がると、自動車を取り巻く環境が大きく変わることになる。パソコンがインターネットと繋がってGAFAに代表されるIT企業が生まれた、電話とネットが繋がったスマホの登場によって、アプリやサービス提供者が生まれた。これと同じ文脈で今の自動車業界は捉えられるべきである(p5)
・車が電動化するということは、完成車に部品を提供するサプライヤーを含めたサプライチェーン全体を大幅に再編する必要が生じる。これまではエンジンを大量に生産する能力を持つことで参入障壁を高くし利益を生んできた。電動化が進むに当たってどう差別化をはかるかが大きな課題となる。さらに電動化では電池のコスト、高電圧を制御する技術(パワーエレクトロニクス)が必要となる(p25)
・日本でここのブランドが生き残っている(トヨタグループ(ダイハツ、スバル、マツダ、スズキ)、ルノー(日産、三菱)、ホンダ)のは、エンジンを自社で開発する力があるから。自社のエンジン開発製造こそが完成車メーカ最大の強みであり、他社を阻む壁であり、利益の源である。これが電動化、CASE化により失われてしまうことになる(p31)
・EVの根幹となる3つの部品、動力をタイヤまで伝える駆動系として電気モータ、リチウムイオン電池、電圧を変換する制御系の装置であるパワーエレクトロニクス(D C-DCインバーター、インバータ)がある(p31)
・日本の家電産業が再編を余儀なくされた一因は、垂直統合型から水平分業型に生産の現場がシフトしていったから。垂直統合型は、製品開発から生産・販売まで全てのプロセスを1社または1つのグループで行う形態、それに対して、水平分業型とは、製品の中心となるような部品の開発・設計などは自社で行うが、それ以外の製���・販売は外部に委託する(アップルのiphoneが代表例)がある(p33)
・完成車メーカの営業利益率はトップはフェラーリ(23%)、2位は中国の吉利汽車、3位はトヨタ(8.5)だが、スバルは1台あたり35万円、日産・三菱・マツダは利益が激減していて、車を作っているだけでは儲からない時代になっている(p43)
・自動車産業界の新しいルールとして、1)自動車がIoTに組み込まれてパソコンやスマホのようになる、2)垂直統合から水平分業への変化、3)データとソフトウェアを制するものが全てを支配する、4)自走社電動化の流れはますます加速する、5)自社の手持ち技術から次の事業を興していくというスタイルから、社会の課題から次の事業を興していくスタイルへの転換(p45−47)
・自動車産業が目指すべきは、スケーラブル(拡張可能性)かつ、サステイナブル(持続可能性)な事業の創出である(p47)
・自動運転は次の3つの軸で整理する、1)人を運ぶのか、物を運ぶのか、前者は目標レベルや難易度が数段上がる、安全性と快適性の両立は難しい、2)商用か非商用か、トラック・バスといった商用向けの方が、自動運転車両を活用したビジネスモデルが想定しやすい。3)走行環境、市街地なのか高速道路などの長距離輸送なのか。アメリカでは、モノの輸送・商用・フリーウエイを中心とした長距離輸送から自動運転を始める試みが現実味を帯びてきている(p69)
・アマゾンがEVや自動運転車両に関心を抱いているのは、年間9000億ドル(9.9兆円)以上に達する莫大な配送コスト削減が目的とされている(p83)
・ドイツの自動車業界を中心した変革の方向性は、1)自社だけでは不足する機能を躊躇なく買収、合併を通じて補完する、2)オープンイノベーションの重要性、外部との研究開発協力を通じて外部のリソースを効率的に活用する、3)組織の大胆な再編成(p153)
・CASEを起点に自社や業界のイノベーション・再編に取り組む中国企業として、NIO・BYD・ジーリー・上汽集団を取り上げる(p165)BYDは、EVについては、「7+4』をせんりゃくを掲げ、幅広い分野での新エネ車対応を目指している(p177)
・日本の自動車産業の弱み、1)モノづくり信仰、2)垂直統合への強いこだわり、3)自前主義、4)電気・材料・IT系エンジニアの軽視、5)形のないものにお金を払えない(p216−229)
2021年6月20日作成
投稿元:
レビューを見る
日本の自動車メーカー、大丈夫なんだろうか… ここまでいろんなことがもうすでにされている(特に欧州・中国で)とは思っていなかった。日本の(悪い意味での)”ガラパゴス”ぶりが恐ろしい。。
投稿元:
レビューを見る
CASE connected autonomous shared service
世界的にはACES autonomous, connected, electric and shared moblity
p129 欧州自動車産業の関係者と話をすると、かつてのノキアの話がでる
p134 ボシュ Like a VoschのPV
p137 電化、自動化 コネクテッドの3つが実現して初めた交通は排出ゼロ、事故ゼロ、ストレスゼロとなる
p141 ドイツ コンチネンタル かつてはタイヤメーカ 今タイヤの売上は26% タイヤから自動車関連のハードソフトウエア全般を扱う世界屈指の自動車部品メーカとなった
p152 欧州に学ぶ、自動車産業のDXに必要な3つのポイント
自社だけで不足する機能を躊躇なく買収、合併
オープンイノベーションの重要性
組織の大胆な再編成
p179 ジーリー 吉利汽車 2010 ボルボ買収
p197 GMはリーマンショック、VWはディーゼルゲートで経営が刷新された
p202 日産 プロパイロット
日産はCASEのAやEの部分では最先端の技術を持つ しかし組み合わせて魅力あるパッケージを開発できているか?
p211 ドイツ ZF 'Zahnradfabrik 歯車工場
p219 水平分業型の産業構造の勃興により、モノづくりは工程ごとのスペシャリストに任せて、コアの部分のノウハウが必要な部分のみを自社で行うというビジネスモデルが席巻した 日本の家電業界はこの流れに遅れをとって完敗した
P223 現在の買収は、「あるときは敵、あるときは友人」というフレネミーなメンバーが同じ事業環境の中で協力する、エコシステムの一員という目で見るべきだ
p225 日本の自動車産業でのエンジニアに序列 頂点に君臨するのはエンジン製作に携わるエンジニア メカ屋至上主義の是正は急務
p229 日本自動車産業の弱み 形のないものにお金を払えない
投稿元:
レビューを見る
エクセレント!自動車産業の戦略論でありながら日本経済の再生論として出色!世界がデジタル・環境課題対応へ向かう中、日本はガラパゴス、失われた30年が続く ガソリン車販売の停止」は亡国へ
1.自動車の大変革期 ドイツは2010年から長期戦略プロジェクト
日本は長期戦略が出来ない 政治も官僚も短視眼・対症療法
2.付加価値はHardからSoftへ
EVでモジュール組立産業へ
垂直統合型産業の終わり
3.ノキアの教訓☆(128) 大ショックの話だが最も納得
ガラケー→スマートフォン
Hardから「アプリ」Softへ付加価値が移った
Apple・GoogleはOSを支配
4.どこで勝負するのか
世界の中で優位性を確立する
投稿元:
レビューを見る
ドイツのDX
M&A オープンイノベーション 組織再編成 顧客接点
ダイムラー シリコンバレー研究所 1995年 音声認識技術も自社
ボッシュ スマートシティによりゼロストレス社会実現
コンチネンタル 車両から得られたデータから分析 収益機会は渡す
アリババ
車載OS アリOS スマートハイウェイ スマートシティ
ファーウェイ
端 エッジ 管 ネット 雲 クラウド
バイドゥ
自動運転 アポロプロジェクト
NIO
EVメーカー デザイン 極上の顧客体験 ソフトウェア内製、車両製造は外注
ジーリー
ボルボ買収 ダイムラー スマート株50% 自社製車載OS
日本=ものづくり
欧州=世界観 ソリューション モノを活かすプラットフォーム 新しい未来
投稿元:
レビューを見る
1980年代に日本は、世界第二位の経済大国として、自動車、電機、半導体、鉄鋼、造船、石油化学など、各基幹産業が世界的な競争力を保持していた。
それが1990年代以降、一つまた一つと日本の基幹産業は国際競争力を失っていった。象徴的なものは「ガラパゴス携帯」と呼ばれる携帯電話である。外国の携帯電話はゴツくて使いにくいので、日本の携帯電話が世界中で売られていた。ナビも日本の製品と海外の生菌には明らかな格差があり、外国製の携帯電やナビはとても使える代物では無かった。外車のナビの性能が悪かったので日本製にわざわざ付け替えたものである。
それがスマートフォンの時代になったら、日本の製品は全く売れなくなった。僅かにソニーのエクスペリアが一部の人に利用されているのみで、圧倒的なシェアはアイフォン、やギャラクシーに奪われてしまった。
家電製品も全ての分野で日本製品が世界で売れていた。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、あらゆる電化製品の品質の保証は「メイド・イン・ジャパン」だったのだ。
それが現在ではあらゆる最終消費財で、当時の競争力を今も維持しているのはほぼ自動車産業だけになってしまった。
この自動車産業までもが、急速なデジタル化とサプライチェーンの水平分業の流れを受け、その競争力を侵食されている。
この本を読むと、自動車ももはや日本の時代では無くなっていくだろう事が、確実な予測として浮き上がってくる。日本人はモノづくりで成功すると、その成功体験から逃れられない。電気自動車になると、今までの日本車メーカーの垂直統合サプライチェーンを守れないので、本格的なEVの開発販売ではテスラや他の自動車メーカーに相当先に行かれてしまった。
自動車産業もテスラや中国の新興自動車メーカーにその地位を脅かされる時代が来た。解決策について縷々書いてあるが、海外の他メーカーの迫力に勝てるのだろうか?
世界の企業ランキングベスト100に日本企業が一つも入っていないという事態になるのはもはや時間の問題となっている。
投稿元:
レビューを見る
世の中の変化点や方向性の把握、
提供する根源的な価値とその実現方法、
どこの利益を確保しにいくのかが、
自動車業界の具体例から考えさせられる。
Dxの捉え方(世の中のニーズの変化として)、ロードマップ型技術開発の限界なども。
投稿元:
レビューを見る
caseについて書かれた最新の本。
アメリカ、中国、ドイツの会社たちがどのようにコネクテッド、オートメーション、シェアリング、ソフトウェア、エレクトロニックに立ち向かっているかが書かれている。
これを見るとドイツとアメリカ(テスラ筆頭)がリードをしているように感じる。日本は対して、エンジン志向が強くそれぞれの部品メーカーもただの下請けでコネクテッドしていく様子が見られない。
オープンイノベーションをうまく活かしながらも国策の後押しを受ける上記の国々の今後に注目だし、日本でも進むと嬉しい。
大きい会社が変わることは大変だと思うが、それらが一新し、今現在先頭に立とうとする姿(GMやフォルクワーゲン、ダイムラー)はかっこいい。
投稿元:
レビューを見る
日本の自動車産業(つまり日本)が生き残るには、「ものづくり」信仰から脱却し、社会的課題に対応する企業として存在すること。そして垂直統合から水平分業にシフトすることが必要だと説く。水平分業にシフトするとは工場を持たないメーカーであるアップルのやり方を指しているのでしょうね。
そうなんだろうけど、社会的課題と言ってもそれは「うまいお題目」ってことだし、自社の強みを生かさずどうしろって言うんだろうね。水平分業は個々の製造物の品質が担保できることが条件だと思うけど、その点には言及していない。IPhoneのような絶対的な商品力があればこその話で、そういう観点から言えば、EVよりも水素エンジンに期待したいけどねぇ。それ以前に「何をもって良しとする」かを決める政治の話が先か。日本の最大の弱点はそこだもんね。
投稿元:
レビューを見る
『日本車は生き残れるか』そのメッセージ性の強いタイトルとともに勉強になる本でした。 というのも私恐れながら自動車関連の営業担当をしており、業界勉強のためにこうした書籍から学ばないといけないと思い、読んでみました。
業界関連のメルマガも購読しているので、なんとなくの会社名やキーワードレベルでは接することが出来ていた、というところではあるけれど、まだまだ自分の不勉強が痛感された、というところと、238ページの文庫本サイズにまとめてくださった著者のお二人には感謝だなと思った書籍でした。
ほんと、このような読書レビュを記載することは、はなはだお恥ずかしいレベルでして、機械工学科出身ではあるもののクルマに関しては、申し訳ないですがほとんど興味なく、とにかく仕事のために勉強しております。(ほんと最後の謝辞の部分の川端さんのクルマ愛がすごくて申し訳なくなるレベルです…。 そうなんですよねこのクルマ愛がすごすぎて僕にはつらいという事実もあります…。)
本の概要としては、はじめにの記載で川端さんが今の日本の車産業の危機感およびCASEに関して概要を述べていただいたのち、桑島さんが欧米中国の状況をそれぞれ端的にリポートしていただいた後、最終章で「日本車は生き残れるか」の観点にて川端さんからの課題提起と提言がある、という構成。不勉強な私でもなんとかついていけるレベルにまとめていただいており、はなはだ感謝です。
それとともに、以下のメッセージが、やはり本書の中で重要な位置づけだと思いますので、この部分は先に抜粋引用しておきます。
===========
これだけは誤解のないように最初に申し添えておくが、本書の執筆は、「欧米では… それに比べて日本では…」という、欧米に比べていかに日本が駄目なのかということを語るような、いわゆる「出羽守(でわのかみ)」が目的では断じてない。そうではなく、日本の自動車産業も一刻も早く、垂直統合のモノづくり至上主義から脱却し、水平分業まで視野に入れた上で、モノづくり以上の付加価値を生み出すことで“日本経済の大黒柱”であり続けてほしいからこそ、書いておきたいと思ったものだ。
日本の自動車産業にはまだまだ戦える素地が残っている。
===========
さて、改めまして、抜粋引用となります。(自分が勉強のために抜粋するということもあり、皆様にとって有益かどうかは不明です)
===========
P47
結論めいたことを言えば、これからの時代に日本の自動車産業が目指すべきなのは、「スケーラブル(拡張可能性=ユーザーや仕事の増大に適応できる能力)、かつ、サステナブル(持続可能性のある)な事業の創出」だろう。具体的には「社会の課題を起点とし、事業のあるべき姿や目指すべき方向性を考える」、「社会に必要とされる、意味のある、欲しいと思われるサービスを作り出す」といったことだ。そのためには、自社の技術や製品にこだわらず、買収合併を含めた外部との連携を積極的に推し進めるという選択肢も重要になってくるだろう。
P120
���プティブの場合で言えば、正解かどうかはわからずとも、急速にデジタル化が進行する中で自動車産業の未来を予測し、将来的な自社の立ち位置と付加価値の源となるプロダクトを自ら考え抜き、実現のための必要な能力を身につけるため、必要ならば外部からの技術調達も厭わない――そのプロセスと姿勢こそが重要なのだ。 答えが見つからない中でも、複数のシナリオを予測し、通るべき失敗は早めにクリアし、スピードでは負けないことが彼らにとっての最優先事項なのだ。 「失敗しないこと」が最優先である時代は終わったのである。
P184
コネクテッドカーの本質は自動車と通信インフラ等との接続であり(略)すべてのアプリはOSにより実行される。したがってOSシステムの健全性、安全性はコネクテッドカーの運命を決定するカギである。ゆえに自動車メーカー自身で責任をもって開発すべきである」
P209
このまま独立路線を貫くのはやはり得策ではない。現状の中規模なポジションからの脱却を検討すべきだ。
それがプラスと判断するならば、思い切って四輪事業を資本提携先のGMに売却するくらいのオプションがあってもいい。過去のコアコンピタンスだったエンジン開発部門は、ホンダの開発を引き受ける前提で独立させ、他の自動車メーカーや船舶などのエンジン開発も請け負う。投資回収はあと20年のうちに行い、2030年に究極の高効率エンジンを開発して幕引きをはかる。四輪部門の売却で得た原資をもとに日本の二輪メーカーを束ねて事業を絶対的に強化する――というドラスティックなシナリオを描くほど思い切った改革も視野に入れるくらいの気概がほしい。
P231
デジタルの時代、コネクテッドの時代には、データをオープンに管理し、他社との連携を行うことでデータを共有し、適宜フィードバックを行うことで、よりユーザーが使いやすいプラットフォームに改良し、エコシステム全体の価値を高めていく――というビジネスモデルが一般化する。自動車産業にとっては、その一つの形態がコネクテッドになった時代のモビリティサービスなのだ。
「形のないもの」への偏見を捨てなければ、このエコシステムの中で激化する生存競争にはついていけなくなるだろう。
===========
投稿元:
レビューを見る
全て形あるものは、IoTにおける、
Tになる。それは、自動車も例外ではない。
私自身注目してきた、ドイツの
ZFという会社は、ドイツ語で歯車工場
という意味だと知った。
歯車工場が、アメリカの電気系に強い
メーカーを買ってからの躍進は、
やはり、これからも注目したい。
上のZFもそうだが、自動車しか作れない
自動車メーカーよりも、自動車パーツも作れる
パーツメーカーの動きは面白い。
ボッシュは、多面的な製品群を活かして、
ソフトウェア技術でつなぎ、スマートシティを
狙うようだ。
技術を誇るのではなく、世界観を
提示する。これがこの先、製造業に
必要なこと。
投稿元:
レビューを見る
アメリカや欧州、中国の自動車やITの最近の動きが分かり、興味深い。もはや車は移動手段ではなく、街を構成する一つのツールであり、ツール間をつないだ暮らす上での価値を高めるためにどうするかを考える自動車メーカー(すでに、メーカーと呼ぶべきではないが)が生き残ることができるのだと思う。
投稿元:
レビューを見る
2021年に書かれた本だがすでに古い
各社が社内でどんな検討をしているのかへの取材が不十分で古い公開情報から何とか本を書いたのだろう
特に日本の会社は積極的に外部発信しないので足を使わずに書けばこの程度の内容になると思われる
自分がその中にいたためよく覚えているが、国内でも有名メーカーは2015年にはCO2に対する懸念を持っていたし、その将来検討の途中でパリ協定が発行され計画がパリ協定や国際基準を満たすことを確認したりしていた
また特に残念だったのは設計会社から「製造」を委託されることで成長した会社も世界には多くあるし実際本書でも紹介されているが、そう言った会社への転換の可能性を述べることはなく、「CASE」への距離感やアプローチの多寡で評価している点
まさに自社で検討しているが生産を外部委託したところで世界のCO2が減るわけではない、消費者が喜ぶわけではない
現在流行りの外部委託は近視的に評価されているが地に足をつけた活動の強さを無視している
また、トヨタが今まさに激怒している国の取り組みの悪さに対して記載がほぼない
日本の自動車メーカーがなぜ遅れているのか、を日本固有の文化価値観で片付けては安全圏から批判しているだけである
ここまで広い視点知識があるなら国ごとの法規や規制なども記載し問題提起してほしかった