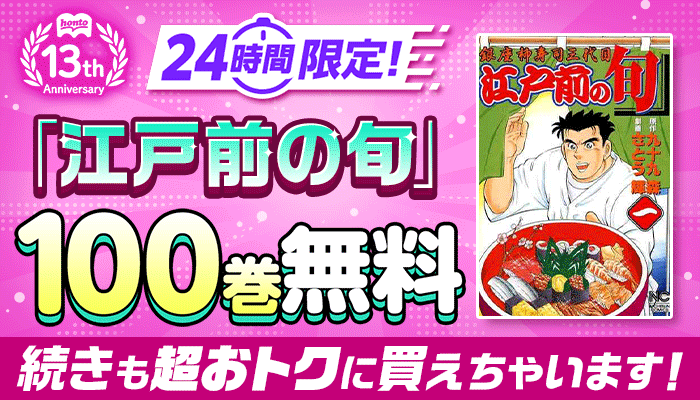投稿元:
レビューを見る
決算書から見えるものが面白い
学んだことは、
仮説をたてるということ!
決算書の特徴から、仮説を立てて、
その答えを有価証券報告書などへ探しに行く。
とっつきにくかった決算書についても、平易な言葉で書いてくれているので読みやすかったです。
ビジネスモデルを間違って理解していたなどもあり、勉強になりました。
勉強になった箇所
・貸借対象表は下から遅いもの上に行くほど早いものという作りになっている。
・どの程度の規模の投資なのかというのは、企業の本気度を図る際にも非常に重要
・Netflixなどの 作るコンテンツは固定資産に計上されている
・有価証券報告書の【事業等のリスク】
・任天堂 製造を外部の企業に委託することで、工場の運営により発生する 固定費を抑え、売上高が落ちても赤字に陥るリスクを減らしています
・東武鉄道 「なぜスカイツリーが建てられたのか」遡る事 2006年の中期経営計画に目を通してみると、「鉄道事業の収益力を高めるための成長戦略」に関する記述があります
・有価証券報告書【セグメント情報】
・出品者がお金を引き出すまで メルカリにプールされるビジネスモデルの構造上 お金が貯まりやすいモデルとなっている。メルカリは直近決算でついに黒字か
・有価証券報告書には 必ず【沿革】という項目があり
・サイバーエージェントの自己資金 配当率(DOE)、「先行投資で利益率は下がったとしても、 配当は安定して出しますよ」とか 開示することで 株主から中長期で支援してもらえるように勤めていた と読み取れます
・Adobeはフィッシュ モデルの初めての成功者と言われている
・有価証券報告書を起点に企業情報 調べる手順、ステップ1ビジネス情報を整理しよう、ステップ2財務情報をビジネス情報に紐付けよう
投稿元:
レビューを見る
P/L,B/S,C/Sの復習に加え、各企業を転換点含めた期間の幅を見た上での実践形式の問題で楽しく読むことができた。
決算書を読むことで下記のことが読み解けるよ、ということが学べる。
Netflix
コンテンツ制作に対して莫大な投資を行っている。
任天堂
2012年頃、業績が振るわず赤字になってたが資産があったため開発費等は確保できていた。
ヒット商品の有無で業績に大きなブレが生じる。
最近ではサブスク(ニンテンドーオンライン)により安定した収入がある。
東武鉄道
東武グループの展開している事業について、またそれらの営業利益打ち分けを知れる。スカイツリーって東武鉄道が持ってたんだ、、
スカイツリーは運輸事業のために建設し、見事意図通り運輸事業の収入が増えたこと。レジャー収入は徐々に下がっているが目的は運輸事業収入の改善なので大きな問題はないこと。
ワタミ
2014年を境に悪印象が抱かれて以来事業を縮小していっていること。B/Sの純資産は増えているが介護事業を、売却した影響。国内飲食事業に注力していること。
クックパッド
2016年頃、経営陣同士の方針対立があり関連会社の株式を売却し、料理事業一本に絞ったこと。
競争の激化により2020年では料理事業の利益率も減少している。
エーザイ
新薬メーカーにはパテントクリフ(特許の壁)という経営論点があり、特許切れに備えて次の新薬研究投資を欠かすことができない。
2011年の売上の急減は特許切れによるもの。
セリアとキャンドゥ
セリアの方が店舗数が多いため仕入れも一度に大量になるため割引がきき減価率が低いと考えられる。
100均という性質上、少額の割引も売上にかなり響く。
また、セリアは雑貨比率が多くキャンドゥは食品比率が多く、食品の方が原価が大きい傾向にあるため営業利益はセリアの方が高め。
ゲームウィズとジモティ
ゲームウィズはゲームをやっている最中に訪問されるため広告にそこまで力は入れず、逆にジモティは事前にサービスを知ってもらっている必要があるため広告に力を入れる。またゲームウィズは専属のライターがいるため原価率が上がり、ジモティはユーザーがコンテンツを生成するため原価率は比較すると上がりづらい。
上記の結果がP/Lに現れている。
決算書から読み取れるというよりも、事前にビジネスモデルについて理解しておく必要があるという話であった。
メルカリ
P/Lで赤字が続いているからといってダメな企業であると決めつけてはいけないという凡例。
赤字の原因は巨額の広告費であり、それに対して売上も上がっている。広告費をかけなければいつでも黒字転換できるが、企業拡大のために投資を怠っていないため赤字が続いているということが読み解ける。
大塚家具とライフネット生命保険
両者P/Lで赤字が続いている企業だが、ライフネットは長期にわたって収益を確保していくビジネスモデルのため顧客を獲得するごとにその年は損失の方が大きくなってしまう。契約数は年々増加していっているのでいい赤字である。
それに対して大塚家具は売上高が下がっており店舗数もすくなくなるという負のサイクルが出来上がってしまっており悪い赤字である。
サイバーエージェントとミクシィ
どちらもソーシャルゲーム事業を展開している企業だが、サイバーエージェントは広告事業の売上割合が大きく、メディアの媒体費がかなり大きいため売上原価が膨れている。
ミクシィはSNS事業もあるが現在はゲーム事業の割合が大きく、アップルへのレベニューシェアが大きいため販管費が膨れている。ガンホーはレベニューシェアを売上原価に入れてるらしい。
投稿元:
レビューを見る
中級者向けの一冊。有価証券報告書を読んだことのない人、管理会計を勉強したことのない人たちへオススメ。前著と一緒に読むことでさらに理解が深まると思う。
投稿元:
レビューを見る
実践編ということで、各企業の決算書を使った分析がクイズ形式で展開され、シンプルに面白くためになった。また、分析にあたり必要な考え方や、手法が紹介され、参考になる。赤字に関する考え方が変わったのが良かった。
書籍に紹介されているイラストは、筆者が分かりやすくするため準備されたものだが、この資料を決算書からどのように数字を拾い作成したのかも知れたら良かった。
投稿元:
レビューを見る
現在の名だたる企業を題材にコロナ前、コロナ後を含め決算書から企業の特徴をわかりやすく解説してくれてます。
読むなら今です。
投稿元:
レビューを見る
第一弾に続き、今回実践編も楽しく読ませていただきました。
仕事でも少しだけ見る機会のあった決算書ですが、数字の羅列ばかりで苦手な資料でしたが、ランダムウォーカーさんのおかげで、決算書にはストーリーがあり、エンターテイメントだと思えるまでマインドチェンジできたことが最大の収穫でした。
特にサイバーエージェントは興味のある企業だったので、これを機会に自分でも調べたいと思います。まずは、藤田社長のブログからチェックですね。
投稿元:
レビューを見る
流行りものの決算書解説書だが、実践的なのかと期待して購入。読んでみると内容は分かりやすく、とはいえこの本の価値は、実際に自分の会社や興味のある会社の決算資料を何度も手を動かして読むことで出てくるものに感じた。
読んだ後もちゃんと時間をとって振り返る必要のある本。
投稿元:
レビューを見る
決算書の分析の基本は「比較」です。
・1つの企業を時系列で見る「時系列分析」
・他の競合とを比較してみる「競合比較分析」
→比較する企業の共通点と相違点を整理する
有価証券報告書「事業等のリスク」
その会社のビジネスの特徴(企業特性)などが書かれている。
不安定な業績に対する任天堂の対応策
・多額の現金等を保有(1兆円近く)
危機的状況に陥った時、真っ先に確保するのは利益ではなく現金
プラットフォームビジネスに関しては、売上よりも流通総額(プラットフォーム上でいくら取引が行われたのか)の方が重要
→売上高の計算式
流通総額×手数料率=売上高
就活・転職で役立つ決算書の読み方
①事実情報・データを知る
②企業の未来を想像する
→面接で企業に投げるべき質問を抽出する
現在の姿と未来になりたい姿の差分を埋めるために人材採用を行っている
赤字だから悪い、ではなく、かならず理由も確認する必要がある
営業利益率の下がる時期=事業を創っている時期
サイバーエージェントの成長方針
大型の買収なし・上層部に外部の大物を採用しない「自分たちで創ってのばす」という一貫した経営方針で成長し続けている
事業計画を作る際に一番困るのは、変数が多いこと。→他社の決算をまねて作ってみる
有価証券報告書
上場企業は絶対提出しなければならない
どの企業も同じフォーマットだからこそ、比較しやすい
投稿元:
レビューを見る
いや面白い。会計は知的エンタメだ、はその通り。
学生からビジネスマン、投資家など様々な立場の人が有価証券報告書を立体的に読み解く方法、楽しみ方を非常にわかりやすく解説している。
投稿元:
レビューを見る
決算書(企業の決算情報全般)は、読み解ける人には宝の山だと言われる。有名企業を題材に決算書の読み方を解説した本書は「宝の地図」といったところか。
評者は職業柄「決算書が読める人」の範疇だと思うが、目の付け所や発見事項の言語化の情報など、様々なことを学ばせてもらった。大学生の娘に読むように勧めてみようと思う。
投稿元:
レビューを見る
具体的な企業例を挙げて、わかりやすく比較、分析をしている
知的好奇心をくすぐるように書籍になっていた
投稿元:
レビューを見る
決算書の読み方実践編。
前回は決算書を読む時に必要な会計の基礎を見てきた。
今回は更に、本質的に決算書が読める状態になることを目指すもの。
一通り読んだけれど、そう簡単にはいかないことがよく分かった。
今回も前回同様、学生くん・営業さん・投資家さん・銀行員さん、といった様々な立場の仲間と一緒に、様々な企業の決算書を紐解いていく。みんなとあーだこーだ言いながら意見を出し合うのはやっぱり面白い。
またクイズ形式で進行されるので、気軽な気持ちで決算書及びその企業の事業内容や経営状態を見れて楽しかったし、新たな発見もあった。
企業にとっていかに現金が大切かということがよく分かった。
投稿元:
レビューを見る
2つの決算書のどちらがどの企業かを当てる等のクイズや、その解説を通して、決算書から分かる様々な有名企業の経営方針等が分かり、タイトル通りとても楽しく決算書に触れることができた。
2022年5月に発刊された本を内容が新鮮なうちに読めたのも良かった。早めにおすすめ。
投稿元:
レビューを見る
簿記を勉強した後に読んだ。
実際の会社を例に会計の仕組みについて理解を深めることができた。
業種による特徴、同業他社でも異なる考え方など、とても興味深かった。
投稿元:
レビューを見る
前作は入門編と言うことで、業界が異なる会社や、あるいは同じ業界でも、ビジネススタイルが違う会社の財務3表を見ながら比較していくスタイルだった。
今回は実践編と言うことで、同じ業界でもビジネスさえ伝えるが、違うだけではなく、時系列分析や、競合比較をすることで、もう1歩も2歩踏み込んだ内容になっている。
これまでは、インターネットのサイトや、証券口座のサイトを通して、時系列には見る習慣がついてきてけれども、他の会社と比較してどうなのか、その会社の特徴はどうなのか、といったところを自分では踏み込めていなかった。
そこをどの数字を切り出して、どのような処理をすれば、この後やってくる、といったところまで見えてきているので、また違った見方ができると思う。
この本は、株式投資だけを目的としてるんじゃないため、株が伸びるか伸びないかといった観点では書かれていない。
その分、定性的な表現や、どうやって授業を維持していくか、と言った。一般的なビジネスや、単純な興味から入っていける面白さがある。
実は印象に残ったのは、最後のコラム、起業家は決算書をどう読むか。市場規模なぞわからないから、目の前の、課題を持つ顧客を起点に、事業計画を組み立てる上での変数に代入するために既存事業を参考にする、というもの。

![会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方 [実践編]](https://img.honto.jp/item/2/265/360/31757577_1.jpg)