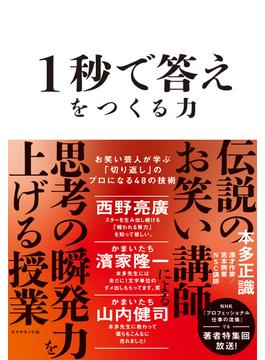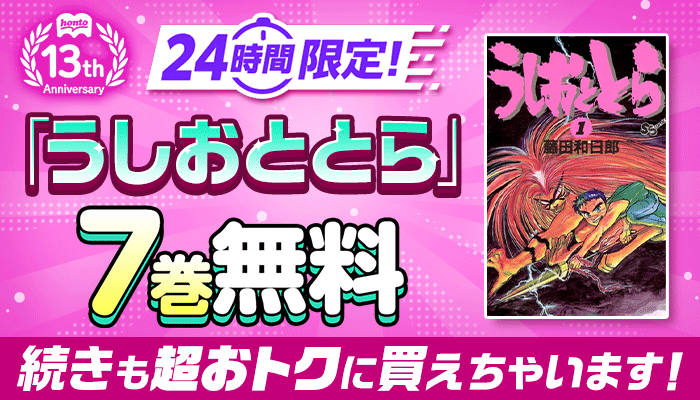投稿元:
レビューを見る
芸人に例えながらの説明で読みやすい。今まで何気なしに見ていたバラエティ番組の見方が変わりそう。
未来志向も大事だが現在志向で実行する。明日しようではしない可能性が高い。今すぐにでも実行するを決める。
私もねっニュースなど見るが、自分の興味あるニュースしか目を通さない。興味ないニュースにも意図的に目を通し、インプットをふやす。
テレビや本をただ見るだけでなく、ツッコミながら見ることで頭を使いながらの訓練になりそう。
投稿元:
レビューを見る
常識は非常に大事ですが、一方で常識だけでは、おもしろくならないので、大事なことは「常識を土台にして非常識をつくる」ということです。
さて、漫才やコントのボケで笑いが起こるのは、なぜでしょうか。
簡単に言うと、観ている人の想定を超えた意外なワードやフレーズが出てくるからです。
ですが、この「想定を超える」というのにはポイントがあります。それは、「想定は超えるが、理解はできる」範囲にとどめることです。渾身のボケで笑ってもらえるかどうかは、このポイントを押さえているかどうかで決まります。どんなに気の利いたことを言っても相手に伝わらなければ、意味不明な無駄口になるだけです。ここを見誤らないでください。
たとえば、朝の挨拶をボケの題材に考えてみましょう。
朝起きたときの挨拶は「おはようございます」です。決して「おやすみなさい」ではありません。だからこそ、朝に「おやすみなさい」と言うと「起きたばっかりやないかい!」とツッコミを入れることができます。
ですが、朝起きて「りんご!」と叫ぶボケがあるとします。こちらはなんの脈絡もないので、ツッコミようがありません。しいて言えば「なにをいうてんねん?」と疑問ツッコミになってしまい、お客さんもポカンとしてしまいます。
どういうことかというと、朝の挨拶で「おやすみなさい」というボケには、「おはようございます」というのが常識という前提があります。対して「りんご」のボケにはその前提がありません。
もちろん理解ができないボケが笑いを取るという例外もコンビのスタイル・キャラクターによっては成立することもありますが、ここではあくまで一般論として紹介しています。
このように、ボケと呼ばれる非常識に聞こえる発言について考えてみると、実は破天荒な発言が受け入れられるわけではなく、「常識」というたしかな土台があってはじめて相手に伝わる言葉であることがよくわかります。
これは、ボケに限ったことではありません。人の心に刺さることを言えたり、気の利いたことが言えるのも同じ原理です。相手の想定を超えつつ、それが相手の理解の範疇だからこそ、「すごいね」と思われるわけです。
ですから、ここで紹介した、朝の挨拶が「おはよう」なように、普段の会話においても、常識をひとつでも多く知っていると、それだけ非常識、言い換えれば、人の想像を超えつつ、理解もされることが言えるチャンスは多くなります。
これまで、うまいことが言える人は、そもそもの頭の作りが違うと思っていたかもしれませんが、この理屈を知って、自分にもできるかもしれないと思ったのではないでしょうか。
「芸は模倣から」と芸能の世界では言われます。皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。
「模倣」=「真似」と考えていいでしょう。
最初から特別なものをつくるのは余程の天才でもない限りかなり難しいことです。
それにもかかわらず、多くのお笑い芸人志望者が最初から「特別」を求めて、自分だけの答えを得ようとしてしまいます。目立ってなんぼのお笑いの世界です���ら、焦る気持ちはわかるのですが、はっきり言うと、それは間違いです。
なぜなら、どんなオリジナリティも多くの経験を積んだ先に結果として得ることができるものだからです。
ですが、授業では無理やり変えさせるようなことはしません。自分で納得して腑に落ちない限り前には進めないので「好きなことしや」としたいことを優先させます。そうしないと必ず「思うようにやっておけば良かった、やりたかった」と後悔するからです。
少し脱線してしまいましたが、話を戻します。
そのオリジナルになるために経験を積む行為が「真似」だと私は考えています。矛盾していると思うかもしれませんが、むしろ、真似をした数で、オリジナルになれるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
そのことに気がついたのには理由があります。
ダウンタウンが大人気になった頃のNSC生はネタ見せをするコンビの多くが「ダウンタウンもどき」でした。ボケは真顔でシュールに、ツッコミは勢いのある関西弁というのがひとつの形でした。ほとんどの生徒が同じことをしていたため、まったくダメなように思えました。
しかし、実際は私の予想に反して、ダウンタウンもどきの生徒の成長が非常に早いことに気がつきました。
なぜかと考えてみたところ、そういった生徒は、憧れの人の真似をすることで、お笑いのコツを掴むまでにあまり時間を必要としなかったのです。その生徒は失敗を含めて、真似によって得られることが非常に多く、他の生徒を置き去りにしてどんどん経験を積んでいきました。
加えて、興味深かったのが、真似をしていたはずの生徒が、経験を積んでいくうちに徐々にダウンタウンの型を崩して自分たちのやりやすい方に変化させていったことです。
最終的にはダウンタウンを目指していたとは思えないオリジナルネタを披露するようになっていきました。講師として「芸は模倣から」を目の前で感じることができた瞬間です。
もうお気づきの通り、真似には2つの利点があります。
利点1 成長速度が上がる。
利点2 真似をしたものは自分のやりやすいように自然と変化し、結果としてオリジナルなものになる。
成長速度は先ほどの話からもわかるように、誰かが10
年かけて見つけ出した技術や考え方も真似するだけであっという間に自分のものとして吸収できます。
もし、売れっ子芸人を目指して20歳のときから、お笑いの勉強をしたとして、ノウハウを見つけるまでに10年かかったらスタートラインに立てるのが30歳のときです。下積みは大事ですが、少しもったいないような気がします。
一方で、人のことをどんどん真似をして、技術を身につけることができたら、1年程度で基礎を学べるので21歳でスタートラインです。どちらにチャンスが多いかは言うまでもありません。
また、真似をしたからといって自分の個性が消えてしまうわけでもありません。ましてや、真似したからといって、その人と同じになれるわけでもないということもすでにおわかりいただけたはずです。
人には個性があるように、どんなことでも真似をしているうちに自分の個性に合わせて真似たことが変化していきます。
私自身も意識をしていることですが、これまでの経験に誇りを持つのは非常に大事なことだとしても、それが余計なプライドに変わってしまい「自分はこれでいく」「このやり方は自分に合わない」と決めつけてしまうのは危険です。どんなことも成功事例を参考に真似してみるのが大事ですし、同時に自分を表現するいちばんの近道でもあります。
もちろん、真似してみて合わなければ、やめればいいだけの話ですから、「最初は真似」の意識を持ってみましょう。
皆さんには好きなお笑い芸人はいますか? もしくは嫌いなお笑い芸人はいますか?
もしいるとしたら、そのお笑い芸人のどこが好き、もしくは嫌いでしょうか。
どちらでも構いませんが、こういった「好き嫌い」のような感情的な判断の「要因・原因」を知るのは非常に大切なことです。
「自分の好き嫌いの理由はわかっているから大丈夫」と思っている方もいるかと思いますが、一度立ち止まって考えてみましょう。
たとえば、皆さんがAという芸人を好きだったとします。
「その芸人が好きな理由はなんですか?」と聞かれて、「おもしろいから」と答えました。
一見、正しいように思えますが、これでは十分な理由とは言えません。
たとえば、この場合で言うと、具体的に何がおもしろいのでしょうか。
「おもしろい」というだけでは、ネタなのか、姿格好なのか
フリートークの上手さなのか、どんなことをおもしろいと思ったのかわかりません。
仮にネタだとすれば、ネタのどの部分がどうおもしろいのでしょうか。どんどん深掘りしていくと意外と答えられなくなる人が多いと思います。
売れている芸人となかなか芽が出ない若手芸人の差は、この要因・原因を考え抜く力にあります。舞台でしっかりと結果を残す若手芸人は、自分たちのネタがウケた場合もウケなかった場合も、その理由がなぜなのか徹底的に追求することが習慣になっています。そうです。分析できるのです。
要因・原因を論理的に考えることができると芸に再現性が出てきて、どんな場面でも、調子の波が少なく、常に力を発揮することができます。なぜなら、「どうして、自分たちのネタがウケたのか、もしくはスベったのか」の理由がわかるので、成功はそのままに失敗の修正ができるからです。
論理的に分析ができていないと、仮に笑いが取れたときも、「たまたま調子が良かったから」と運任せで終わってしまいます。
このように感情的なことを論理的に分析することで、若手芸人でも着実に力をつけていくことができます。
これは頭の回転を早くすることに直接繋がってはいませんが、頭の回転が速い以前に、考えることは大切なことです。速さ云々の前の土台固めとして覚えていただけると幸いです。
論理的に考える芸人として、天竺鼠の川原くんがあげられます。ナスの被り物がトレードマークの人気芸人です。彼はすぐに理解できないようなハチャメチャなネタをすることで有名で、世間一般では行き当たりばったりの破天荒な芸をしていると思われがちです。
しかし、実際は誰よりも論理派であり、舞台裏で徹底的に考え抜くタイプであるのは有名な話です。彼が生徒だった頃も意味不明なネタがほとんどでしたが、ネタの理由を聞くと、ちゃんと自分の世界「天竺ワールド」を持っていました。行き当たりばったりではなく「飛んだネタでも、どこまで理解してもらえるのか」のボーダーラインを知るためにネタをしていました。
つまり、講師である私はボーダーラインを知るための実験台にされていたのです。ひたすら「考えること」を続ける川原くんだからこそ今や人気芸人の一人になれたのでしょう。
私自身も、駆け出しの頃は、分析が甘く、なんとなくおもしろそうだからと場当たり的にネタを考えていたことがありました。そのため、仕事のクオリティに波があり、安定感を出すのに苦労しました。
そのことに気がついてから、調子の波をなくすために多くの漫才師のネタをビデオやカセットに録音してひたすら分析して、「笑いのパターン」を覚えました。大変でしたが、お笑いで飯を食っていく「プロの仕事」だと自分に言い聞かせました。
好きなものや嫌いなもののなにがその要因・原因になっているか考えてみると、これまで漠然と考えていたことにもしっかりとした理由があることに気がつくはずです。人間は誰しも感情がありますから、その感情に至る「要因・原因」がわかるようになれば、それは大きアドバンテージです。
常に論理的に「要因・原因」を考えられるようトレーニングしていきましょう。
NSCからではなくオーディションを勝ち上がって劇場の本出番を勝ち取った漫才コンビ「ミキ」。
スターダムを駆け上がる彼らを待っていたのは、「お前らの漫才はやかましすぎる」「慌ただしすぎる」「もっと落ち着いてゆくリやれ」という否定的な意見ばかりでした。
オーディション段階では肯定されていたものが、現場の劇場関係者やスタッフからは打って変わって完全に否定されました。
そんななか、私ひとりだけが、「そのままやったらええやん、それが勝ち上がってきたスタイルやねんから変える必要はない」と言っていたそうです(後にミキから聞いたことですが……)。
その後、どのように漫才のスタイルを確立していくか彼らと話をしました。そのなかで、「亜生くんに責められて困ったときに昴生くんが、ただ大声で返すだけではなく、子供のときに『バリア張った』言うて、遊んだやろ? あんなんで『雑然』とした漫才のなかに昴生くんが逃げ込める『静寂』の部分をつくったら漫才全体にメリハリつくんちゃう?」とアドバイスしました。結果、そのバリアはすぐに採用されていました。
たったひとりの肯定者の意見を聞いてくれたのも、何かの縁かもしれませんが、短所を直すよりも長所を見極めて伸ばすことの方が本人たちも楽しくできて、新しい発見もあったのでしょう。
芸人にとって「ウケない」のが悪なのではなく、「改善しない」ことが悪です。粘り強く考え続けることを本当の意味で「お笑いセンス」と呼ぶのでしょう。
知っている言葉の数が多ければ、頭の回転は速くなります。逆に知っている言葉が少なければ、なかなか頭の回転は速くなりません。なぜなら、語彙が多ければ多いほど、表現の幅も広がり、素早く正確に自分の思っていることを相手に伝えられるからです。私の知る限りでは、売れている芸人のほぼ全員が相当な語彙力を持ってい���す。
いつの時代もそうですが、「ヤバい」「エグい」などの便利な言葉の登場によって、話す側の思考が停止してしまうということがあると感じています。便利な言葉がダメなのではありませんが、多くの選択肢を持ったうえで、そう言った言葉を選ぶようにしなければ、いつまで経っても頭の回転は速くなりません。
何を聞かれても、何を食べても「ヤバいっすね」と答えている人を頭の回転が速い人だと誰も思わないはずです。
若手芸人や20代前半の生徒と話していても「エモい」や「エグい」などの表現が頻繁に出てきます。当然「ヤバい」も定番です。
お笑い芸人は相手を楽しませるのが仕事ですから、自分の発言したことを相手にストレスなく理解してもらわなければいけません。そう考えると「ヤバい」はストレスを感じやすい言葉です。なぜなら、話をしている側が思っている「ヤバい」と聞いている側の「ヤバい」では感じ方が違う可能性があるからです。
<中略>
便利な言葉は非常にキャッチーですから、つい使いたくなる気持ちもわかりますが、このようなことがあるため使うときは要注意です。
特に自分が思っているニュアンスが相手に伝わっていないのであれば、まったく意味がないので、正しい表現を考える必要があります。
当然ですが、頭の回転の速さには、状況に合わせて言葉を選ぶ力が必ず必要になります。相手との関係性、状況を加味して、使う言葉や表現で正確に伝わるか判断しながら話をする必要があるからです。
仮に自分が思いついた言葉が適切でないとしたらどんな表現がいいのか、似たような言葉や同じような表現を探さなければなりませんが、それは語彙力がなければ難しいでしょう。
ここで、「はじめに」にも登場した南海キャンディーズの山里くんの話をしましょう。山里くんは今や売れっ子芸人でバラエティから教養番組まで、彼をメディアで見ない日はないほど大活躍しています。そんな彼がブレイクする前からずっと続けていることがあります。それが「わからない言葉や知らないことがあったらすぐに調べる」です。
彼は居酒屋でお酒を飲んでいるときでも、会話のなかで知らない言葉が出てくるとわざわざ席を立ってトイレでその言葉を調べることを若手時代から現在までずっと続けています。
彼は典型的な頭の回転が速いタイプです。出演する情報番組でも見ているこちらがストレスのないような表現でスラスラと言葉が出てきます。最初は才能かと思っていましたが、しっかりと裏で努力していることが彼を今の立場へと押し上げていることがわかりました。
語彙力を上げるというのはすぐにできることではありませんが、山里くんのように着実に進んでいけば必ず力になるはずです。
焦らず、皆さんにも語彙力を上げていってほしいと思います。
「第一印象」は0.7秒で決まるという話を聞いたことがあります。プレゼンの本や面接の本を見ると、この第一印象が大事ということがよく書かれています。お笑いの世界にも「つかみ」という言葉があり、舞台に出てきてすぐにお客さんの心を掴めるかということは非常に重要視されています。
ですが、「第一印象」が悪かったからと言って気にすることはありません。それよりも大切なのは「第二印象」だということをこの場でお伝えしたいのです。このことは舞台に立つことが多くなる若手芸人によく教えています。
当然ですが、第一印象が抜群に良い人はハードルも上がります。皆さんの周りにも最初はいい人だったのに時間が経つと「最初に会ったときの期待感と違う……」と印象が変わってしまう人がいるのではないでしょうか。
第一印象が良いのに越したことはありませんが、それが、自分の実体に見合っていない見せかけでは意味がありません。それならば、時間をかけて自分のありのままを理解してもらった方が得策です。
NHK在学中にNHKの新人漫才コンクールで最優秀賞を受賞し、なんばグランド花月の本出番を獲得したコンビ「キングコング」。
絵本作家として、クリエーターとして、どんどん活躍の場を広げている西野亮廣くん。「YouTuberカジサック」として登録者数200万人以上を誇る梶原雄太くん。ともに自分の見つけた道を歩き、それぞれ階段を登り続けています。
まだ彼らが20代前半だった頃、西野くんの話を聞いて驚いたことがあります。彼がネットで炎上し、たまたま2人で話ができる時間があり、こんな会話になりました。
本多「よう炎上しとんな?」
西野「アンチが9割ちゃいますかね(笑)。それでもいいんです」
本多「なんで?」
西野「9:1、90:10、900:100ではアンチが目につきますけど、90万:10万になったら、アンチ9割のまま東京ドームで2回イベントできるじゃないですか」
本多「それだけおったら食べていけるよな」
西野「そうなんです。アンチの比率を減らさなくても、分母が増えたらアンチは関係なくなると思うんですよ」
本多「たしかに、そうやな……」
芸人という人気商売をしていて、20代でこのような考え方ができる西野くんを素直に「すごい子や」と思いました。物は考えよう、捉えようで見方がまったく変わってくるとあらためて西野くんから教えられました。
漫才志望、コント志望に関わらず、全員の生徒に教えていることがあります。
それが「話をブロックにわけて考える」ということです。どういうことか、いつもの授業通りお笑いを例に解説をします。
お笑いのコンテストには必ず、時間制限があります。1分でも2分でも、まずは限られた時間のなかでネタを披露するのが絶対条件です。
多くの若手芸人は制約された時間のなかできれいな「起承転結」の流れをつくろうとしてしまいますが、実はそうでなければいけないわけではありません。もちろんきれいな「起承転結」があるに越したことはありませんが、必須条件でもないのです。それよりも大事なことは笑いの総数をどれだけ増やせるかです。
お笑いを見たい人は話の美しさを感じたいわけではなく、単純に笑いにきているわけですから、とにかく笑える箇所をひとつでも多く作る必要があります。
そこで、私が教えているのが、「話をブロックにわけて考える」です。
たとえば、2分のネタだとしたら、5秒のフリ、5秒のボケ、5秒のツッコミの合計15秒をワンセットで考えて、ネタ全部で8ブロックの構成にすることができます。ボケとツッコミの両方で笑わせることができたら2分で最低16回も笑わせることができます。
もちろん5秒という縛りがあるわけではありませんが、目安としてそれぞれの時間を決めておくことで、思考が強制されてアイデアが出やすくなります。
「起承転結の流れがきれいな2分ネタ」と「短いブロックで構成される2分ネタ」では、後者の方がお客さんに飽きられる確率が低くなります。
起承転結型は、フリが長くなりすぎることが多く、余程言葉を削って短くしないと聞いている側も飽きてしまいます。ですが、ブロック型であれば短いテンポで話をどんどん前に進めることができるため、聞いている側もストレスを感じづらいのです。
もちろん、内容がおもしろいことが絶対必須条件なのはどちらも同じです。
なぜ、このような話をしたかというと、何度か参加させていただいたビジネスプレゼンのほとんどが起承転結型で、聞いていて飽きてしまったことがあるからです。
しかも、その多くが内容はおもしろいのにもかかわらず、前置きや説明が長くて損をしているように感じました。
もっと内容のところに時間を割いて、ガンガン強みを押し出すやり方でもいいように思います。定番の話の進め方としても「起承転結」を否定するわけではありませんが、それはときに自分の良さを消してしまうことにもなりかねないということも知っておいてください。
そんなときのために、相手に飽きられることなく話を進めるための技術として「話をブロックにわけて考える」ことを覚えていただけると幸いです。
「なんでやねん!」というワードをこれまで何度も聞いてきました。若手からベテランまで大阪を中心に今や聞かない日はないぐらいの言葉です。
NSCに入ってきた生徒たちも最初に覚えるのは「なんでやねん」かもしれません。それは言葉そのものを覚えるというよりも言い方を覚えると言った方が正確でしょうか。
プロとアマチュアの違いはこの「なんでやねん」という1ワードに詰まっていると言っても過言ではありません。
プロは自分にぶつけられたボケに対してちょうどいい温度のツッコミをします。たとえば、中くらいのボケがきたら、ツッコミも中くらいのレベルで返します。
対して、見習い中の芸人は、中くらいのボケに対して大きなツッコミで返してしまいます。大げさに見えてしまうのです。
漫才は普段の会話の延長線上にあります。ですので、大げさにすればするほど、お客さんとの距離も遠のいてしまいます。
そのことを念頭に生徒にはむやみやたらと大声で「なんでやねん!」と言うのではなく、ボケにあったツッコミをしなさいと教えています。
本書も終盤に入ってきたので、お笑い芸人たちの真髄をお教えします。お笑い芸人たちは毎回おもしろいことだけを言っているのでしょうか。答えはノーです。
多くの芸人に怒られてしまいそうですが、彼ら彼女らの発する言葉のすべてがおもしろいわけではありません。ほとんどの場合、言い方や状況に合った言葉を選ぶことで、普通のことをおもしろく感じさせているのです。
この説明だと、あたかも、お笑い芸人がつまらないことをしているように感じるかもしれませんが、普通のことをおもしろくするのが一番難しいことです。
「普通の���と=当たり前のこと」ですから、本来、笑えるわけではありません。それを技術だけで笑えるものに変えられるわけですから、やはり特別な能力と言えるでしょう。
本レッスンでは多くのお笑い芸人たちのように、皆さんの発する普通の言葉に大きな影響を持たせることをテーマに話したいと思います。
さりげない一言にも意味を持たせるために必要なのは、本レッスンのタイトルにもなっているようにフリを効かせられるかどうかで決まります。
フリが効いていればいるほど、人は正解がきたときにどんな単純なものがきたとしても心地よさを感じますし、逆に散々振ったフリに対してハシゴを外されるようなことをされるとがっかりしてしまいます。
皆さんの大好物がカレーだとして、朝の段階でご家族から晩御飯はカレーであることを予告されました。その日は1日、晩御飯が楽しみで、街を歩いてもカレーのことが頭をよぎります。仕事も頑張ってカレーを食べようと思ったら、急きょ焼き魚に晩御飯が変更になっていました。
どうでしょう。わかっていても楽しみにしていたわけですから、絶対にカレーが出てきてほしいですよね。
このときに感じるのはサプライズではなく裏切りだと思います。
そこで予告どおりにカレーが出てきたら誰もが嬉しい気持ちになるでしょう。
このようにフリを予告として活用することで、こちらがなにをするのかわかっていたとしても相手を確実に喜ばせることができます。
たとえば、フリを効かせた会話の典型例は次のような形です。
司会「Aさんはどんな人なの?」
A 「きれい好きですね」
司会「たしかに、清潔感があるもんね」
A 「はい、お風呂も2回入っています」
司会「朝と夜⁉︎」
A 「春と秋」
司会「お彼岸か!」
お笑い番組などでも見る定番の流れです。「きれい好き」のフリがあることで、聞いている側も「2回」「朝と夜?」や「1日に?」と、つい反応してしまいます。
この流れを意図的につくることができれば、芸人のように話のコントロールができるようになるでしょう。
投稿元:
レビューを見る
読書好きな方が紹介してて興味持ち、自分も読んでみた。
著者はこの本で、頭の回転は後発的に早くできるとして、話を展開していく。実際、芸人さんの実例も交えて話すことで、納得感がより高まるように感じた。 340ページとボリュームあるが、48のケースに分かれているから1個1個テンポ良く読むことができた。
印象的だった、話すテンポ、相手の動きを読んでいくといったことを、これから意識していきたい。
投稿元:
レビューを見る
お笑い芸人がNGCで学ぶ切り返し方法47をまとめた本。具体的な方法は本に譲るとして、お笑い芸人侮るなかれ。人を笑わせるのは非常に難しいと感じていたものの、具体的なプロセスを本書で公開されたことで、人を笑わすのには頭が良く、さらに地道な努力が必要である事実が分かった。本当に尊敬する職業である。
投稿元:
レビューを見る
欲しい答えをあげられる人になるために
1.想定は超えるが、理解はできる。「常識」という確かな土台。
2.自分の力を発揮できそうなところに集中する。1回の短い時間で自分を印象付ける。
3.まずは自分に求められていることに集中
4.反応、返答、考える
5.常にどうしてなんで、で論理的に考えることで調子の波が減る
6.常に自分の話を整理し、それを素早く表現する速さ
7.すべることを恐れない
8.やることを一つ決める。やらないことを決める。
9.テーマを一言でまとめる
10.専門性を高める準備と平均値を上げる準備
◎まずは相手の想定は何か、それを超えることは何かを想像する癖をつける。逆の発想、違う視点からの見方、色々。
◎いろんな先生の授業のマネ、言葉がけのマネをしてるなーってちょっと罪悪感を感じることもあったけど話し手が私に代わってる時点でオリジナルになってるからいいか。いまはたくさん学ぶ時期だと思う。ありがたや。
◎つまり抽象化。前田さんの抽象化ゲームを思い出す
◎「これなら話せるぞ」っていうネタ作り。引き出しを増やす。その引き出しになることをkeepに記録していく。
投稿元:
レビューを見る
いつチャンスが到来しても勝ち取れるような準備
想定は超えるが理解はできる言葉
その結果に対しての原因を常に考える
何を1番に伝えたいかは話す時に重要
語彙力を増やす
自分のパターンを作る
投稿元:
レビューを見る
NSCで講師をしている本多正識による一冊。
文章は論理的で、芸人の名前もちょこちょこ出てくるので、読みやすいかった。
投稿元:
レビューを見る
1秒で答えをつくる力 お笑い芸人が学ぶ「切り返し」のプロになる48の技術
著:本多 正識
お笑い芸人は「ネタそのもの」「話し方」「立ち振る舞い」「姿格好」など、どんなことでもいいので、「もう少し見てみたい」「なんか聞いてみたい」とお客さんに一瞬で思わせなければいけない。
毎回即座に頭を働かせ、その都度「笑い」や「ビジネス」の答えを作り出すことは、形は違えど、ビジネスパーソンとお笑い芸人に差はない。
本書の構成は以下の5章から成る。
①殻を破るための「頭を柔らかくする」レッスン
②状況を素早く理解するための「分析する」レッスン
③自分の必殺パターンを見つけるための「言い換える」レッスン
④端的に情報を伝えるための「言葉を操る」レッスン
⑤1秒で答えをつくるための「洗練させる」レッスン
芸人とビジネスパーソンも差はないという著者の言葉へは激しく同意する。置かれた立場や環境の違いにより捉え方は違うかもしれないが、お笑い芸人も「おもしろい」という点では、自分よがりではなくて、相手から「おもしろい」と思ってもらえてナンボである。
相手が求めることに対しておもしろさや興味等があってはじめて相手とのコミュニケーションが始まる。
コミュニケーションは聞くが9割とはいうものの、1割の話の中で本書のエッセンスから研ぎ澄まされた言葉であったりやりとりを出せるかどうか、相手との関係性も大きく変わる。
自分に相手を合わせてもらうというような高等テクニックではなく、相手を観察し事前準備し、仮説に合わせた対応を行い鍛錬する中で自分のイロを出しながら、さらなるコミュニケーションを図ることは次のステップとして必要となる。
真似る・実践する・編み出す
この繰り返しとあくまで相手を軸とした意識を持って、相手に気持ち良くなってもらうことを前提とした言葉と気持ちのやりとりが今後もさらに大切となっていく。
投稿元:
レビューを見る
結論として
すぐに実践できるトレーニングが満載で実用性の高い本だと認識しました。
本をよんで、自身に知識として蓄積させることや、自身の行動を変えたいと思っている方にお勧めです。
また内容としては頭のキレという表現をしていますが、ロジカルシンキング的な要素もありビジネスにおいても実用性をかんじます。
投稿元:
レビューを見る
相手を意識したわかりやすい伝え方、世間を知っておくべきという今に対応した考え方、共感を大切にした聴き方…お笑いと教育は繋がっていると感じた。
話の上手な先生は、長さに関わらず引き込まれていく。それはその人の話術であり、芸人さんが喋っていて面白いのと同じである。
頭の回転は情報量に比例する。
考える時に締め切りを設ける。
話を復唱する、そうですねと言うなどして、0.5秒でも良いから考える時間をつくる。
考えていることは口に出す。
難しい話は例え話にする。
5文字の言葉に1秒〜1秒半使う。
緊張をエネルギーに変える。
専門性向上、平均値向上の2種類の準備がある。
5秒のブロックをつくる。
私の場合はまずゆっくり魔を起きながら話すことを意識したい。
投稿元:
レビューを見る
お笑いの講師とあって面白い本だった。阪神巨人さんの体内時計はすごいと思った。
•頭の回転の速さは情報量に比例する。
•先延ばしグセは仕事の遅延だけでなく、考えるスピードにも影響してします。
•最初から正解が出るわけではないと割り切る。
•間をとって自分のペースを作る。見切り発車を防ぐこと。そして、話の流れをまとめる。
•返事をしながら考える。
•人生にリセットボタンはないけらど、スタートボタンは何度でも押せる。
•アドバイスは聞くものではなく、実行するもの。
•場を温めて空気を作る。
•経験を自分の引き出しとしてストックする。
•9:1の理論
•伝えたいキーワードは、丁寧に、ゆっくり、はっきり伝える。
•プロデューサー目線で、俯瞰的に自分を見る。
•コメントはベターとバットの2種類も用意しておく。
•5秒で目的、5秒で過程、5秒で結果
•考える時間を数文字で作る。
投稿元:
レビューを見る
テレビで頭の回転が良いと感じる芸人はいるが、才能ではなく、訓練で身につけることができるという本。身につけるための道のりは険しい。。
投稿元:
レビューを見る
特に目新しいことや、斬新なことが書かれている訳ではないが、内容がしっかりと入ってくる感じで、とても納得させられた。ボクサーに例えれば、基本のワンツーを毎日、如何にしっかりと繰り返し練習してきたかが最後に勝敗を別ける、そんなことなのかなぁと、勝手に解釈して自分なりに落とし込むことが出来た。
投稿元:
レビューを見る
一瞬で面白い回答や返しができる芸人の考え方について知りたくて買った本。
特に真新しいような内容はなかったが、
①自分の得意分野を認識すること
②未来を想定した前準備が大事であること
(話のストック)
③100点を目指さずある程度これは達成したい。
くらいの心持ちで挑むこと
等の大事なエッセンスは再認識することができた。
投稿元:
レビューを見る
吉本の芸人育成機関で講師をしている著者。
従来は「才能」と呼んでいた職能を、誰にでも学習可能なノウハウとしてまとめている。たしかに才能というものは存在するのだろうが、凡才にも学ぶ術はあるのだと教えてくれる。
<アンダーライン>
・能動的に反応できる頭になる➡強制的にほめる訓練
・常識を起点に非常識を作る➡常識を言い換える
・頭をアイドリング状態に保つ➡返事を「違和感センサー」にする
・予測するクセをつける➡予測は「観察」から始まる
・ハードはそのままソフトを変える➡「ハード」とは設定、「ソフト」はそのなかで使われる言葉
・緊張とは「理想の自分」と「現実の自分」のあいだのギャップを感じ、恐怖が頭をよぎった時に起きる➡余裕のある状態は、理想の自分になる道筋がはっきりと見えているとき
・「やらなくていいこと」を決めて思考をシンプルにする
★★★★★フリを効かせる
司会「Aさんはどんな性格なの?」
A 「きれいずきですね」
司会「たしかに清潔感があるものね」
A 「はい、おふろも二回はいってます」
司会「朝と夜?」
A 「春と秋」
司会「お彼岸か!」