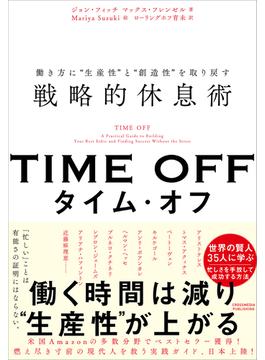投稿元:
レビューを見る
生産性の向上や人間にしか出来ない創造性豊かなアウトプットをするために必ず必要となる休息の重要性を説いた本。日本に根付いている忙しい、仕事をする時間が多いほど出来ると言う間違った認識を覆してくれる。自分も既にタイムオフの重要性を取り入れており、短時間でも密度の濃い成果を出せていると主観ではあるが実感している
日本人全員がこの本を読んでタイムオフの重要性を理解し、タイムオフが当たり前の仕事環境になる事を切に願う。。
投稿元:
レビューを見る
余暇としての学問(スコラ)
何かを求めるものではなく、学ぶプロセス自体に価値を認める。
●アリストテレス
彼(アリストテレス)の思考の大半は、純粋な思索、つまり「ただそうするためにしただけの活動であって、思索すること以外にはなにも得られない」ことであった。
それは「知りたい欲求にただ身を任せただけで、なにか有益なものを目指していたわけではない」のであり、「無益か有益か」などという価値判断を超越する営みであり、「それ」のみで善いことだと考えていた。
48
●キルケゴール
彼(キルケゴール)が問題としているのは、退屈を感じること、そのものである。
つまり、活動への欲求、絶え間ない動きへの渇望、そして静寂への恐れ、それが問題だと彼は考えたのだ。何もしないことを恐れることこそが諸悪の根源だと、キルケゴールは言っているのだ。
「退屈することは、本来穏やかで静かな性質であるはずだ。それにもかかわらず、動きを欲すること自体が大変興味深い」とキルケゴールは述べる。
160
●
学ぶこと、そして趣味に(回帰し)没頭することだけでも、素晴らしい旅の過ごし方だ。「そんなこと、どこでもできるのに」という罪悪感はいらない。ビーチで日焼けしないともったいないと思う必要もない。違う環境でやれば、心向きも違ってくる。
355
投稿元:
レビューを見る
タイムオフが人生を豊かにする。言ってることはとても良く分かるし、最近この手の著書も増えてきてるのでこれからのトレンドなのかもしれない。ただどうしても日本の企業風土に馴染む気がしない。私の職場でも最近は若い子でもワークライフバランスと言ってプライベートの充実を重視する子が増えてきたが、その子たちが職場の中核で活躍する姿は全くイメージできない。この辺のバランスが現実社会ではとても難しいなと感じる。
投稿元:
レビューを見る
ベートーベンは昼食後に自然の中で散歩することを日課としていた
パートナーとは別の部屋で寝た方が睡眠の質向上
ウォーカー博士は午後10時半から午前6時半の8時間睡眠がベスト
自分のクロノタイプに従うことが大事
孤独と一人になることはちがう。一人の時間はたいせつ
◾️近藤麻理恵
・考え事をするときに悩みを書き出し、コントロール可能かどうか区分けする
・限界を超え、スピードを落とさないといけなくなったとき、とりあえず全部置いておいて床の雑巾掛けをする。手を動かすと心が穏やかになる
・お茶を淹れて休憩時間を作る
◾️アリス・ウォータース レストラン支配人
毎日暖炉の横で朝ごはんをじっくり作って食べる
日曜日にファーマーズマーケットで食材を仕入れて何を作るか決めずになり行きでみんなでつくるのを楽しみにしてる
モーツァルトは起きてる時間ほとんど遊んでいた
オフィスやリビングに遊び心をちょっと発揮してみる
◾️マックス フレンゼル ロンドン 量子力学
普通の人は博士論文は苦痛だが、彼はギリシャに行きシロス島のエルムポリを見下ろす山で小さな家を借りて、インターネット接続があり人里離れた自然豊かだかな場所で六週間で楽しく書き上げた
起床時間は午前9時から10時
瞑想とストレッチ
山の中走ったり、レンタルスクーターで島を回ったり、美しいビーチに行って泳いだり
そのあとゆっくり朝食を作り1時間くらい本を読む
午後に60-90分で執筆 地元のカフェで
執筆の後カフェで昼食
小屋で昼寝
目が覚めたら島を散策
買い物
泳いで
ビーチを散歩
本を読む 『その男のゾルバ』ヘンリーデイヴィッドソロー 『森の生活』に触発されて
午後はパンを焼く
もう一度執筆
何もせずぼーっと過ごす
AI ディープラーニングについて勉強
ワインを飲みながら執筆
映画を見るか小説を読む
ベッドにいく
1日4時間の執筆
◾️ステファンサグマイスター 米 グラフィックデザイナー
7年ごとに1年の休暇
◾️ピコ アイヤー
『僕たちは旅をする。若くて愚かだった頃の自分にもどるためだ。時間の進み方を遅くして、じっくり吸収する。そしてまた恋に落ちるんだ』
◾️ティファニーシュライ 米起業家
週一日(土曜日など)テクノロジー(インターネット)電源を切ると人生が変わる
◾️ピート アデニー
30歳で早期退職
◾️死ぬことを忘れた島 イカリア島
投稿元:
レビューを見る
▼memo------------------------------------------------------------
▼余暇
・アリストテレス:余暇は不可欠なだけでなく、すべての人が望むべき高みなのだそうだ。仕事は必要で、余暇は高尚(ノーブル)なのだ。「全ての構想道の基本は余暇である」、「人生のすべては、仕事と余暇、戦争と平和に分けれらる」、「人は、必要なもの、有益なものを見据えて行動しなければならいない。そしてそれ以上に高尚なものはなにかということも常に考えなければならない」
・高尚な余暇は、ぼーっとすることでも、ただリラックスすることでもない。「足るを知る」時間だ。「余暇は、学問の追及や善い事(つまり音楽、詩、哲学)を気兼ねなくする時間」
・「余暇は怠けることではない」
・ラッセルの勇気ある提案はこうだ。1日4時間労働を実現するべきである。しかしこうも言っている。「それを実行した場合、残りすべての時間をぶらぶらしてほしいと言っているわけではない」と。余った時間とエネルギーで、学び、文化に貢献する。
・「シリコンバレー式 良い休息」で適切な休息と回復のための4つの主な要素を上げている。
(1)リラックス:心と体をゆっくりさせる
(2)コントロール:どのように時間を過ごすか決める
(3)マスタリー(習得する事):フロー状態になるようにやりがいのあることをする。
(4)ディタッチメント(離れること):仕事のことを忘れるくらい没頭する
・「寝る1時間前にはスマホの電源を落とす。そして、朝起きて執筆が終わってから電源をつける。」
・「スマホはたくさんのものを与えてくれる。だけど3つの発見の要素を失ってしまう。ひとりになること、不確かさ、そして退屈することの3つをね。クリエイティビティの源が奪われる。」
・タイムオフは仕事から逃げることではない。むしろ、仕事の必要不可欠な一部であり、人生のも働く事にも欠かせないものだ。
・休息倫理とは、つまるところ、自分のいちばん深いところにあるクリエイティビティと可能性を見つけ、解き放つためのものなのだ。
▼仕事
・効率性:一定時間でやれるだけの仕事をすること
生産性:価値ある結果を生み出す適切な仕事をすること
・「トップスピードを常に維持して忙しくしていなければ成功できない」という考えなど、全く信じていないところだ。
・世界はこんなにも変化したのだから。技術の発展で、自分自身と家族を食べさせる以上のものが産出できるようになったはずなのに。ずっと変われずにいるのは、僕たちの考え方だけだ。もう長い事、同じ場所で足踏みし続けている。
投稿元:
レビューを見る
充実した人生、生産的な人生を送るために、きちんと休むことを説いた本。
「休むのも仕事のうち」と教えてくれる、自分に必要な一冊だった。
投稿元:
レビューを見る
休息することが如何に大事か気づかせてくれる。様々な業種に携わる人たちのエピソードがぎっしり詰まってて読み応えがあった。具体例から休息するための実践法もあり取り入れたいと思った。
投稿元:
レビューを見る
2023 12月読破
忙しくて辛くなる前に読んで欲しい本
この本の内容は受け取り方がとても難しい本だと思った。
学生の頃などに読んでいたらこの本の根拠を元にダラダラする事に言い訳ができてしまい、仕事に力は入れられなくなってしまう危険性があると思った。
この本を読んで「休む」という考え方が変わり、人生により前向きに行動するきっかけになったと感じた。
私は去年、多忙な時期があり自分なりに休暇を取る事を心掛けていましたが、それがタイムオフという概念で、それがいかに大切か、どのように向き合うべきなのかが具体的に書かれていました。
この本を元に、タイムオフとの付き合い方を深めていき、より良い人生になるよう目指していきたいと思いました。
投稿元:
レビューを見る
結局、睡眠と、無理なく毎日やりたくなる運動、自分ひとりに向き合う時間が一番大切だな。
こんまりメソッドで、ときめかない予定を入れない。
ゆっくり走って、要はメモしなくて良い大きなことを考える。全力疾走して、走ることに集中する。
ひらめきは、仕事以外のことに集中している時に起きる。
夕焼けを見て心がホッとしたり、富士山を見て嬉しくなったり、子供を見て元気をもらったり、タイムメソッドをちりばめる。
小説家はひとりで仕事をして怒られないように、一人で仕事をする時間が必要。
自分に締切を設定して時間を確保する。
投稿元:
レビューを見る
私たちは休み方を習っていない
燃え尽き症候群の予防のために一読すると良い
成果を上げたいなら自分と向き合う時間を作る。次の3ヶ月で3つのことしかできないなら何をしたいか?
退屈すると言うのは、その人の活動や状況に意味が欠落していることからくる不安。
投稿元:
レビューを見る
素晴らしかったし、ただただ反省の時間にもなった。
休息は倫理だ。人が嫌がることをしてはいけないように、休むことにも守るべき倫理がある。働きすぎてる自分を労わるように見えて、実は自分を厳しく律さないといけない。ていうか、厳しくしてきたところが今まで間違ってたと思った。
忙しくしてることが美徳という風潮は終わりにしたい。むしろ、ちゃんとしっかり休むために自分の時間をコントロールすることが美徳であるようにしたい。休んでいいんだよ。休日にぼーっとしていいんだよ。何もしない1日があっていいんだよ。周りにも伝えていきたい。私も、忙しさのあまり心と身体を崩したから身に染みてわかる。
投稿元:
レビューを見る
創造性を発揮するには、タイムオフ、余暇が必要。
特に日本はなんとなく忙しそうにしなければならない風潮があるし、自分もその流れに乗ってしまっている節がある。働く時はきっちり働いて、煮詰まってきたら一旦手を止めるってのも思考が整理されていいなと思った。
休む時はダラダラスマホをいじるんじゃなくて、本業以外の没頭できることに取り組んだり,散歩したり,何もしないをしたり、内省したり、、、
色んなタイムオフの方法があるが、一番大事なのはまず、自分がその時何を求めているか、何が必要か、それを内省などを通じて知ることだと思った。
人間がAIより優れているのは感情を理解すること、共感力。ただ兵隊のように働くのではなく、自分の感じたこと,意思を大事にして働きたい。
投稿元:
レビューを見る
当たり前の事について広く浅く書かれた本だなと言う印象だった。
ほぼ「最近流行り書籍の紹介」と「著名人の発言の引用」。
現代人は働き過ぎ。
→「タイムオフ(戦略的休息)」を取るべき
タイムオフとは
①睡眠
→良質で十分(8時間以上)な睡眠をとる
→睡眠によって脳が整理され、新たなアイデアが生まれる
②運動
→何もしないこと=休息ではない
→身体だけでなく精神(脳機能)にも良い
③ひとりになる
→スマホやSNSによる過干渉の問題
→意識的にひとりになる
④内省する
→自分と向き合う時間を作る
→これからの時代単純作業はAIやロボに置き換わる
→クリエイティブな仕事にシフトする
→そのためには自分の好きなことをやる
⑤遊ぶ
→子どものような広く自由な発想が大事
→子供はランタン、大人はレーザー
→できない理由探しはやめる
⑥旅をする
→旅でも「有名な観光地を如何に効率よく回るか」に終始していないか
→自由に旅する
⑦繋がりを断つ
→デジタルデバイスから離れる
→ビッグテックのテクノロジーは「人の気を散らす」為に設計されている
投稿元:
レビューを見る
読書をする目的の一つに共感を得ることが挙げられる。私の悩みは私だけのものと考えてしまいがちだが、自分と同じ気持ち、同じ悩みを持っている人がいれば、それはその人にとって大きな救いになり、人生の苦痛を減らし、前向きに生きるきっかけにもなりうる。
私以外の今生きている人間、および過去にも広げ生きていた人たちの中に、同じ悩みを持っている人だって必ずいるはずで、その中の何人かは本や文献に残してくれているはずである。しかしなかなかそのような「救いの本」に出逢う確率は低い。
この本は過去に生き悩み、その答えを出すのに苦心し、その過程を本や文献に残してくれた人々の考えを多角的に分析し紹介してくれる本である。人生の約1/3を占める働くということに対し、苦を感じる多くの人には「救いの本」になりうるものだと感じた。