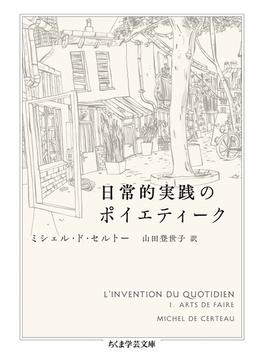読割 50
電子書籍
日常的実践のポイエティーク
著者 ミシェル・ド・セルトー , 山田登世子
読むこと、歩行、言い回し、職場での隠れ作業……。それらは押しつけられた秩序を相手取って狡智をめぐらし、従いながらも「なんとかやっていく」無名の者の技芸である。好機を捉え、...
日常的実践のポイエティーク
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
日常的実践のポイエティーク (ちくま学芸文庫)
商品説明
読むこと、歩行、言い回し、職場での隠れ作業……。それらは押しつけられた秩序を相手取って狡智をめぐらし、従いながらも「なんとかやっていく」無名の者の技芸である。好機を捉え、ブリコラージュする、弱者の戦術なのだ――。科学的・合理的な近代の知の領域から追放され、見落とされた日常的実践とはどんなものか。フーコー、ブルデューをはじめ人文社会諸科学を横断しつつ、狂人、潜在意識、迷信といった「他なるもの」として一瞬姿を現すその痕跡を、科学的に解釈するのとは別のやり方で示そうとする。近代以降の知のあり方を見直す、それ自体実践的なテクスト。
目次
- はじめに○概説○一 消費者の生産○使用あるいは消費 日常的創造性の手続き 実践の型式 マジョリティの周縁性○二 実践者の戦術○軌跡、戦術、レトリック 読むこと、話すこと、住むこと、料理すること…… 予測と政治にむけて○I ごく普通の文化○献辞○第1章 ある共通の場/日常言語○「だれも」と「だれでもない」 フロイトと凡人 エキスパートと哲学者 日常言語のウィトゲンシュタイン・モデル 現代の歴史性○第2章 民衆文化○ブラジル人の「技」 ことわざの発話行為 ロジック/ゲーム、民話、ものの言いかた 横領戦/隠れ作業○第3章 なんとかやっていくこと/使用法と戦術○使用あるいは消費 戦略と戦術 実践のレトリック、千年の狡智○II 技芸の理論○日常的な実践○第4章 フーコーとブルデュー○一 散在するテクノロジー/フーコー○二 「知恵ある無知」/ブルデュー○二つの半身 「戦略」 「理論」○第5章 理論の技○きりとることとひっくりかえすこと/理論の秘訣 「技芸」の民族学化 知られざるものの物語 思考の技/カント○第6章 物語の時間○語りの技 打つ手を物語ること/ドゥティエンヌ 記憶の技と機会 物語○III 空間の実践○第7章 都市を歩く○見る者、歩く者○一 都市の概念から都市の実践へ○操作概念? 実践の回帰○二 消えた足どりの話し声○歩行者の発話行為 歩行のレトリック○三 神話的なもの/ひとを「歩ませる」もの○名と象徴 信じられるものと記憶されるもの/住めるということ 幼児期と場のメタファー○第8章 鉄路の航海あるいは監禁の場○第9章 空間の物語○「空間」と「場所」 順路と地図 境界画定 違反行為?○IV 言語の使用○第10章 書のエコノミー○書くこと/「近代」の神話的実践 身体に刻印される掟 ひとつの身体からもうひとつの身体へ 受肉の装置 表象の仕掛け 「独身機械」○第11章 声の引用○発話行為の放逐 寓話の科学 身体の音○第12章 読むこと/ある密猟○書物による「教化」というイデオロギー 知られざる活動/読むこと 社会的エリートの産物、「原」義 ある「遍在」、この「ところかまわぬ不在」 戯れと策略の空間○V 信じかた○第13章 信じること/信じさせること○信の価値低下 ある考古学/信仰の移りゆき 「教」権から左翼勢力へ 現実という制度 引用社会○第14章 名づけえぬもの○思考しえぬ実践 語ることと信じること 書くこと 治療の権力とその分身 滅びゆくもの○決定不能なもの○重層的な場 波乱の時○原注○解説(今村仁司)○訳者あとがき○文庫版解説 日常的実践という大海の浜辺を歩く者(渡辺優)
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む