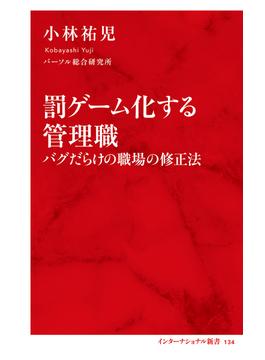投稿元:
レビューを見る
管理職指南書ではなく、管理職のもつ苦悩や会社がもたらす理不尽な課題を元に解決先や目指す方向性へアプローチしている。理想論を語る教科書ではないので、響く人は多いと想う。
投稿元:
レビューを見る
感想
爆弾の押し付け合い。それでは下のものは上を目指そうとしない。やがては会社全体の停滞へとつながる。上を目指したくなる組織を組み立てる。
投稿元:
レビューを見る
世の管理職がこんなにも辛いのであれば、うちの会社はまだ恵まれている方なのだと感じた。管理職をやりがいがある職制にするには、管理職とメンバー双方から理解を得るアプローチが必要。
投稿元:
レビューを見る
良かった。
内容は高負荷になりがちな日本の管理職の現状分析と、対処法の提言。現状分析はほぼ見知った内容なのでサラっと読み飛ばしたけど、対処法は新しい気づきがあった。
1〜3章は、現状分析。
組織がフラット化し、コンプラが強化され、働き方改革で長時間労働が規制され、人手不足になり、成果主義で年上部下も管理しないといけなくなり、という罰ゲームの話。
4章で対処法として、以下が紹介される。
1. フォロワーシップ・アプローチ
2. ワークシェアリング・アプローチ
3. ネットワーク・アプローチ
4. キャリア・アプローチ
この中で、1と4が注目されづらいが重要というのが気づき。
1は要は、部下とのコミュニケーションが管理職の負荷になっているのだから、管理職側だけではなく、部下側にも対人関係やコミュニケーションのトレーニングを受けさせろという話。意識が高い人ほど「他人は変えられないから、自分が変わる」という考えを持っているように思うけど、これとは正反対でドキッとした。
4は社員全員を幹部候補として見るから、なんでもできるスーパー管理職の幻想を持ってしまい、管理職全般に負荷をかけている。ならば、「非幹部候補」管理職という枠を作って、一定範囲のマネジメントができるスペシャリストとして育成すれば、大部分の管理職の負荷は下がるよね、という話。まあ、会社の制度として取り入れられるのは中々難しいと思うが、自身のキャリア意識として自覚的に選択すると、心理的負荷が軽減される気もする。
という感じで、個人的には新しい視点に気付けたので、良かった。
投稿元:
レビューを見る
第1章【理解編】 管理職の「罰ゲーム化」とは何か
管理職の何が大変なのか
減り続けた管理職の数と賃金
順々に消えていく「期待の若手」
死に至る管理職 管理職と健康問題
「覚悟」する男性、「退避」する女性
【理論編①】 学術研究に見る管理職の役割
第2章【解析編】 管理職の何がそれほど大変なのか
負荷を上げ続けるロング・トレンド
働き方改革の「二重の矮小化」
「年功型」と「年輪型」、頭の痛い「年上部下」問題
管理職負荷の「インフレ・スパイラル」
【理論編②】 「管理監督者」と「管理職」は何が違うのか
第3章【構造編】 ここが変だよ、ニッポンの管理職
バグの発生源はどこにあるのか?
「入り口問題」――「いつの間にか管理職候補」の不思議
なぜ管理職の市場価値が下がるのか
「出口問題」――「役職定年」という落とし穴
世代闘争から世代「逃走」へ
【理論編③】 「管理職不要論」を解体する
第4章【修正編】 「罰ゲーム化」の修正法
「罰ゲーム」に対する「筋トレ発想」という罠
1 「フォロワーシップ・アプローチ」――「同じ土俵」をいかに作るか
2 「ワークシェアリング・アプローチ」――エンパワーメントとデリゲーション
3 「ネットワーク・アプローチ」――絆の「地」をいかに設計するか
4 「キャリア・アプローチ」――「健全なえこひいき」と「行ったり来たり」の組み合わせ
第5章【攻略編】 「罰ゲーム」をどう生き残るか
「会社は何もしてくれない」ときに
「アクションの過剰」を抑えるという大原則
仕事の「ものさし」を柔らかくする
「仕事のものさし」はなぜ硬くなるのか
終章 結局、管理職になるのは、「得」なのか「損」なのか
投稿元:
レビューを見る
タイトルは刺激的ですが、日本の管理職がおかれている状況を様々なデータから分かりやすく解説してくれて目から鱗でした。
投稿元:
レビューを見る
それっぽく書かれているがツッコミどころが多い情報弱者狩り。データで正しそうに論拠を添えているが反証もなければ多角的な数値もでもない、文章も太文字が多すぎて美麗さにかけ、遠回りな解説ばかりで非常に読みにくかった。
管理職が大変なのはいつの時代も一緒であり、昔から変わらない。にも関わらず、本質的な解決策ではなく、横文字いっぱいの難しそうな対策に終始していて、他の管理職系書籍と比較して実践に活かせなそうなものは少なく感じた。
投稿元:
レビューを見る
管理職を辞退した経験があり、理由は本書に全て書かれていた。
何となく感じていたこと、引き受けたくないと思っていた理由が言語化されていて、なぜ管理職が罰ゲームと化していたのか、統計や時代背景など細かく示されていてしっくりきた。
本書のチェックリストと照らし合わせると当てはまる項目がかなりたくさんあり、勤め先の会社の管理職が罰ゲーム化されていることが再認識できた。
管理職は引き続き引き受ける気はないが、管理職の仕事が少しでも軽減できるよう協力していきたいと思う。
投稿元:
レビューを見る
サクッと読めました。
フォロワーシップアプローチとキャリアアプローチは新しくて新鮮です。
是非職場に取り入れたいです。
投稿元:
レビューを見る
身近でも「管理職になりたくない」「管理職になると給料に見合わない」といった発言がある中で、どうやったらそのような状況を改善できるかを、当事者の立場だけでなく、組織の立場で仕組み的にも検討しており、参考になった。
自身としては、まずは当事者としての取組にはなるが、仕組みとしてのやり方についての視点も得られて、勉強になったと感じた。
投稿元:
レビューを見る
とても良かった。
管理職=罰ゲームの雰囲気は自社にも漂っており、理由と解決策が知りたくて読んだ。
管理職がなぜこんなに忙しいのか?データに基づき言語化されており、また解決策のステップが大きく4つに分かれており大変わかりやすく実践的。
特に響いたのは管理職のスキルアップばかりを目標に実施する管理職研修は筋トレ、という考え方。
まさに自社は管理職ばかりをムキムキにしようとしてるわ、とはっとさせられた。大谷翔平を用いたキャッチボールの例もしっくり。
片方ばかり育てても確かに意味がない。
そのほか、管理職ネットワーク施策や部下への権限移譲など、施策情報として勉強になった。
すぐに会社を変えるのは難しいが、ツボを押すところを間違えなければ大丈夫だと信じている。引き継ぎこの本を深めながら、管理職の苦労を少しずつ緩めてあげていきたいと思った。
投稿元:
レビューを見る
まさにその通り
悩む中間管理職が読むべき本
モヤモヤしていた鬱屈とした気持ちを言語化してくれた本に感謝したい
投稿元:
レビューを見る
管理職が罰ゲームと言われる現状とその解析、そしてそう言われてしまう構造、それらが大変学びになりました。
特に日本の管理職と海外の管理職の比較は面白かったです。
(学生時代、海外のピン留め方式は日本でも普通だと思っていたのですが、いざ社会に出るとそれは普通ではないことに気がつきました)
解析のところでは、働き方改革の最優先対象は非管理職メンバーで、改革と言いつつ事実は労働時間の矮小。
よって非管理職の労働時間が減少し、少なくなった労働力をカバーするのは管理職。
更に管理職になることで責任は増し、非管理職との賃金差も小さくなっている。
ここだけ見ればたしかに罰ゲームだなと。
そんな罰ゲームをいかに神ゲーに変えていくか。
絶対の手段はないもののヒントをたくさん与えてくれた本だなと感じました。
ひとつは「脱・マイクロマネジメント」。
もうひとつは「柔軟なものさし」をもつこと。
ここの部分については今日からでも意識すべきだと思ったのでもう一度よく読みたい。
投稿元:
レビューを見る
エキスパート職やIC(Individual Contributor)という、組織マネジメント責務のない専門職もキャリアの一つとして一般的になりつつある昨今において、管理職の役割や価値とは何だろうと気になっていたこともあり手にとってみた。
管理職になって個から組織へと視点が変わったにも関わらず、「自分が周囲にどう働きかけるか」「組織を成長させるために自分がこれまで以上に頑張らないと」など、自分軸の考えから脱することができず、結果的に何もうまくいかず自信を失ってしまう人が多いように感じる。
確かに管掌範囲や目標、ステークホルダーなどの状況は変わったかもしれないけれど、役割が変わったからといってその人自身の能力が急に変わるなんてことはないと感じている。周囲を頼る、失敗を許容する(自分がやったことを含め)など、組織に身を置くことのメリットを最大限享受しつつ、組織も自分も一緒に成長していくことを目指していけると良さそう。
投稿元:
レビューを見る
近年、日本の青年たちが管理職に昇進する事を忌避する傾向が顕著になっているという話しを良く耳にします。特に、ハラスメント防止法、働き方改革、テレワークの普及など、新しいトレンドが管理職の負荷を増やし続けていると警告し、管理職の「罰ゲーム化」には、放置すると負荷が上がり続ける、まるでインフレ・スパイラルの様な構造が存在すると指摘します。今回は、課長などのミドルマネージャーの管理職の目の前に押し迫ってくる数々の「バグ=課題」について、数々の調査研究を例示しつつ、理解編、解析編、構造編、修正編、攻略編として、現実と改善策を整理していきます。管理職の役割を、情報、仕事、人、ルールの各コントロールとして整理し、管理職の現在置かれている状況を若者世代の考え方や日本型雇用の歴史的変遷も踏まえて分析します。経済における「失われた30年」について著者は、人事労務の面から「対話の欠如」が管理職問題の放置を生んだ原因であり、それが30年続いた姿が現在の日本と捉えています。また、管理者養成を研修受講などの「筋トレ」的発想では、マネージャーは養成できない事を戒め、フォロアーシップ、ワークシェアリング、(管理職同士の)ネットワーク(構築)、(管理職としての)キャリア(育成)の各アプローチを学び、実践することが管理職「罰ゲーム」の修正法として、具体例を例示します。最後の攻略編では、めざすべきは、積極的に「やらない」上司とし、「アクション過剰」を防ぐことこそが管理職として重要と提起します。