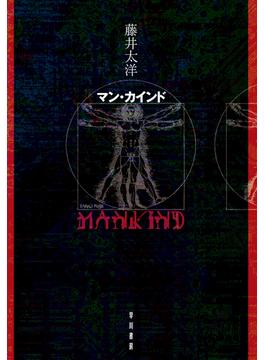投稿元:
レビューを見る
近未来リアルサイバーSFというか、まずその近しい未来の描き方がさらりと自然で、説明くさくないので、世界観に入り込みやすいのがいい。物理空間と仮想デジタル空間を融合したMixed Realityなよくアニメで観る世界(空間に向かって手をささっと動かすと仮想空間のドキュメントがばばばっと分類されてそいつを相手にシュッみたいな)が文字の中で背景のように当たり前に存在している世界を構築している時点で、物語が面白くなる素地ができているのがすばらしい。
近未来の戦争が「公正戦」と言われる事前に戦力を情報公開してライブ配信することを前提とした、まるで過去の正々堂々といざ勝負的な戦闘行為となっていたり、その報道方法も現地の中継中に記事の信頼性をチェックする機関を通して、フェイクじゃないことを実証してからじゃないとニュース配信できないようになっていたりとか、現在の状況からさもありなんというSF作家的視点がバリバリ効いている。
当の物語としての楽しみは、後半仕掛けがうすらわかり始めてくるあたりからの展開が少しやりすぎ感を感じたものの、きっちり最後まで楽しませてくれる。
ネトフリとかでアニメか実写化しないかな?
投稿元:
レビューを見る
第53回星雲賞日本長編部門受賞作品。その賞の名に恥じぬ濃密も濃密、もはや濃すぎるのではないかというレベルのゴリゴリのハードSF。2045年のテクノロジー描写が絵空事にならないようにしっかり練り込まれていてITに関心がある人はたまらないはず。一方でその辺りの土地勘が無いと情報量過多で戸惑うかも。土地勘があっても情報量は圧倒的で、とてもじゃないが「サクッと読める」ボリュームではない。じっくり味わうべし。社会批評SFとしてもアメリカの内戦という設定でアレックス・ガーランド監督のヒット映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』と共鳴しており、こんな小説が2010年代から日本で連載されていた事実が興味深い。
投稿元:
レビューを見る
公正戦闘がルールとなった近未来。人類の根本を揺るがす陰謀をめぐるサスペンスアクション。現代の技術の先にある未来の技術の姿に胸が躍った。その上で分断が進む現代の先にあるべき明るい社会の姿を夢見た。
投稿元:
レビューを見る
舞台は2045年。2030年代に横行した自動機械による殺戮応酬、非対称戦争への反省から、ORGAN(限定銃火器行使単位)という兵士部隊を運営する組織は、あらかじめの約束事に従う公正戦なるハンデを自らに課している。
そんな公正戦という概念が一般的になった世界で、独立宣言した企業都市〈テラ・アマソナス〉の排除の依頼を受け、公正戦を受諾したのが、アメリカ最大の軍事企業〈グッドフェローズ〉。公正戦の終わり、〈テラ・アマソナス〉の公正戦コンサルタントであるチェリー・イグナシオが捕虜の兵士を虐殺する。明確な戦争犯罪の真意を、その第一報を届けようとしたジャーナリストが追う。
というのが物語の導入……という認識で良いのかどうか、自分が上手く作品を理解できているのか大変心配になりますが、壮大な謎あり、緊迫感のあるアクションあり、とすごく心に残る作品でした。
ネタバラシを避けるために曖昧な言い方にはなってしまうのですが、チェリー・イグナシオの〈動機〉を知った時、〈人類とは〉と考えさせられ、そして彼らはどこへ行くのか、と考えさせられる作品でした。よく人類史の話の引き合いに出される、ゴーギャンの絵画のタイトル『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』のあの言葉が、まさに、という感じで胸に迫ってくる壮大さが魅力的でした。
投稿元:
レビューを見る
「マン・カインド」(藤井太洋)を読んだ。
これは見事!
近未来の戦争のあり方に「公正的戦闘規範」で答えを出したのかと思っていたら実はさらにその先を見据えていたのだな。
藤井太洋さんが描くちょっと先の未来って(変な言い方だけど)地に足がついた揺るぎないものに思えるんだな。
意思を強く持たないと徹夜をしていまいそうな面白さなので要注意。
投稿元:
レビューを見る
伊藤計劃トリビュートからの派生作品として、メタルギアのミームを含むのは必然として、さらにガンダムSEEDやX-MENなどに繋がり得る世界を、ドローンや仮想現実などあくまで現代技術の延長として描き出し、最終的には攻殻機動隊までも射程に入れる。たぶん色々なハッタリを効かせているのだろうけど、それを感じさせない、地に足をつけたまま遠くに連れてこられるような藤井太洋作品の良さはそのままに、今作は著者のエンタメ方面のポテンシャルがもう一段階上がった印象。
投稿元:
レビューを見る
藤井太洋(大洋ではない)、初めて読むSF作家。普通、初めて読む作家の場合は短編小説から読んで様子を見るのだが、今回はタイミング良く早川書房から新刊書が出版されたのをきっかけに思い切って読むことにした。帯を見ると、第53回星雲賞日本長編部門受賞作という華々しい勲章付き。例によって、素晴らしい作品は読む速度に加速度が付く。読み始めて早速、藤井太洋の書籍を集めにかかり、読み終わる頃までには殆ど揃えた。余りにも強烈な感動が私を襲ったので、この勢いで他の2つの長編に行くか?ちょっと待て。明後日、東京創元社から叢書短編集が出るとのこと。読むならそっちだな。
この小説の重要なテーマの一つに「公正戦」があり、既に発表した作品からこのテーマを引き継いでいるとのこと。この世から戦争が無くなれば良いのだが、どうしても戦争で決着を付けたい国同士で極めて平和的に戦う(限られた土地で、限られた人数で、限られた時間内で戦う等々の限定付きで国を代表して戦争を行う)ことができる考え方。これと比べると、いかにロシアやイスラエルが無駄な事をやっているのが判る。近未来では、ようやく戦争の愚かさを学んだようだ。また、恐らく現在からこの間は幸運にも核戦争は起こっていないようだ。
また、この作品にはいろいろな科学的要素が内包されていて、読み進めるうちにどんどん脳が活性化して読書スピードが加速度的に上昇した。特に私が気になったテーマについては簡単にコメントしたい。
〇 事実確認サービス
これを早く日本のIT産業で行って欲しい。そして早く日本の政治に適用して欲しい。なになに、そのためには「大規模言語モデル」と「量子コンピューティング」が必要なの?量子コンピューティングの方は最近良く耳にするけど、現在の進捗状況は実際どうなのかな?成功事例あるの?
〇 精子洗浄剤
不妊治療に使う薬品「精子洗浄剤」はファルキのP&Zが開発したとのこと。でも、このP&Zってアメリカの洗剤メーカーP&Gのパクリじゃないの?発音も殆ど同じ。洗剤だけに、精子まで洗っちゃうんだ。本当は洗浄じゃなくて遺伝子組み換えだけど。精子をピッカピカに磨き上げてスーパー精子にするなんて、どこまで皮肉たっぷりなの。それと、このファルキという創始者はコロナですっかり世界的に有名になったファウチのパクリ?
〇 CRISPR-Cas9
2020年ノーベル化学賞を受賞したこの技術。そりゃこの遺伝子組み換え技術を使ってDNAに新しい遺伝子を追加できるけど、SFだから入れた分だけ機能は追加できるけど、やり過ぎだよ。少しは予測できない不具合も発生するけど、ガンガン有能遺伝子を盛り込むなんて、ちょっとハメ外しすぎ。ここで、おもしろ情報を一つ。CRISPRを初めて文献に載せたのは石原良純だって?良く見たら石野良純でした。ああ、ビックリした!
一つ謎が湧き出て来た。この作品はSFマガジンにて2017年8月号から2018年8月号まで連載されたものを単行本化したものだが、2022年に第53回星雲賞を受賞してなぜ直ぐに出版されなかったのだろうか。どうして2年間も据え置かれたのだろうか。本当に謎です。
また最近、早川書房と東京創元社の仁義なき戦いが実に興味深い。似た様な題材で早川���房から8月に春暮康一の「一億年のテレスコープ」が、東京創元社から同じ8月に宮西建礼の「銀河風帆走」が出版された。そして、今回は同じ藤井太洋で早川書房から9月に本書「マン・カインド」が、東京創元社から11月明後日に「まるで渡り鳥のように」が出版される。もう、ライバル関係バッチバチやな。まあ、こういった戦いはウェルカムのウェルカム。
投稿元:
レビューを見る
ドローン戦争が活発化した「公正的戦闘規範」(短編、『公正的戦闘規範』ハヤカワ文庫)のその後を描いた作品。もちろんこちらだけでも楽しめますが、どういう歴史があむたのかは、短編を読むとなお理解が深まります。
光学迷彩とかミリタリーが好きな人には視覚化しやすく、プログラミング系やバイオ系が好きな人にも面白く感じるだろうと思います。
部隊の謎、少佐が捕虜を虐殺した理由に迫るミステリ的要素は楽しめました。
私は戦争モノはそれ自体より、起きる背景や仕組みの部分が好きなので後半が面白かったです。得意なタイプのテーマではないですが、社会の変化が見えて楽しめました。
投稿元:
レビューを見る
長編なんですけど、最初から最後までずーっとおもしろかったです。小島監督が激推しされてたとおり、メタルギア好きな人なら刺さりまくると思います。
投稿元:
レビューを見る
面白かった〜!
さすが藤井太洋、始まって50ページでデザインドベビーの話と匂わせ、「ガンダムシードとの設定かぶりか」と思わせつつ、これでもかと詰め込まれたミステリー仕立てのドンデン返し。すごい。
短編集『公正的戦闘規範』を発展させた未来、デザインドベビーをデザインした科学者と実験対象にされた男の自己中心的な思いと、デザインドベビーと知らないまま育った「マン・カインド」達の戦闘を描いた作品。
途中出てきた、指の関節を使って計算する方法、2進法なら高校の時に習ったなぁと懐かしく感じたが、それ以外の確率論やらコンピュータ系の部分はお手上げ、全く分からないまま読了。それでも筋は追えるのでよしとしよう。
『Gene Mapper』から続く遺伝子改変の物語。きちんと読み返さねば。
そして、図書館で借りた本なので、文庫に落ちたら買おう!
投稿元:
レビューを見る
傑作だった。
最初は理解できない単語の連発で戸惑ったが、話が進むにつれて少しづづ分かるようになるのが良かった。
内容は自信を持って満点を付けれます。それほど面白かった。いつか分からないほど遠い未来で実現しそうなテクノロジーに、興奮と少しの怖さを感じました。
新しい人類が誕生する場合は、自然にではなく人工的に作られる。そう確信させられるほど、本小説に魅入られてしまいました。
本屋大賞を是非取ってほしい。
万人受けする内容じゃ無いから難しいかもしれないけどね。
大おすすめです。
投稿元:
レビューを見る
最初のうち、物語中の戦闘の状況/対立関係がうまく飲み込めなくて若干混乱したけど、読み進めていくうちに頭の中も整理されてきて、そうなるともう、次の展開はどうなる?とワクワクして楽しめた。誰か映画化してくれないかな〜
投稿元:
レビューを見る
現在の技術の延長線上にある遺伝子編集でニュータイプを作るお話。作為的な進化という話はエヴァンゲリオンの人類補完計画を思い出させるが、更にその淵源を辿れば「地球幼年期の終わり」にルーツを見出すことができるだろう。
実はうちの子もIVFで生まれたのだが、文系脳の両親には似ずに読書はあまり好きではなく、理数系を得意としている。いや、まさかね。
ちょうどこれを読み始める前に映画「シビル・ウォー」を観ており、更に本書を読むのと同時並行的にアニメ「サイバーパンク:エッジ・ランナーズ」を観ていた。
本書内での政治状況や、「インプラント」などの技術についてはこれらの映像作品と共通するものがあり、これがいわゆる共時性(シンクロニシティ)というものなのだろう。
これを読んで思い出したのはヴィレム・フルッサーの「サブジェクトからプロジェクトへ」で、ディテールは忘れてしまったものの、「人体を任意にデザインすることはグロテスクに思えるかもしれないが、未来の人間はそれをするだろう」というようなことが書いてあった覚えがある。
本書のテーマからは外れるが、本書の「叙述記憶」についての叙述を読んで思ったことがあるので記しておく。
「起きた出来事を、些細な前後関係などを無視して脳が合理的なストーリーにまとめてしまう」という叙述記憶は、夢の中の時間が早く進行すると感じられることと関連しているかもしれない。夢を見ているとき(レム睡眠時)は、脳の複数の箇所が活性しているという。その間には、無意識の中で複数のストーリーが進行していると思われる。それが、覚醒に近付くにつれて、意識を駆動する脳の理性的な部分がバラバラのストーリーを合理的にまとめてしまうのではなかろうか。レム睡眠時には幾つかの出来事が短い時間の中で同時並行的に起こっているが、脳がこれを後から一本のストーリーにまとめるので、覚醒後の私たちは長い時間が経過したように感じられる、というわけである。これは検証の方法も思い付かない仮説なのだが、叙述記憶という概念は、この仮説の補強に使えるように思う。
投稿元:
レビューを見る
公正的戦闘規範 の第二内戦の後の世界が舞台。前作読んだのが7年前で、すっかり忘れているが、ORGANの説明等、舞台設定うっとうしいほど細かいので特に問題なし。近未来ガジェット満載で、戦闘用の犬型?多脚ローダーや監視ドローンだけでなく、自動運転(LEVELが場所によって変わる)、高層建築(1200mの富裕層マンション)、コンタクトレンズに内蔵された層化視(クシュヴ)、動画から記事の自動生成(これは既に現実化?)、遺伝子操作。展開もSPEED速く、最後の読後感もいい。だが
藤井太洋のSFは今ある技術の延長線上で現実化できそうな技術が売りだとおもっていたので、最後のおちには納得できない。最後だけオカルトファンタジーになってしまったので星4つ。 ここからネタバレ
マン・カインドが遺伝子操作により聖徳太子のごとく同時多数の事務処理ができるようになるというのは納得。分岐意識が脳内で多数芽生えるというのも判る。だが意識をドローンに載せるのは飛躍しすぎ。ドローンのセンサからの情報を処理する主体は人間の脳でしょ?人間の脳が死んだのにドローンに意識が残るってのは、さすがに説明必要でしょ!ドローンの処理ICが人間の脳のようにニューラルでできているとか。バイオテクで造る生体ICが主流になっている可能性もあるので、そのあたりのガジェット説明があったら星5つだったのに。
投稿元:
レビューを見る
かつてあった世界大戦における無差別で非人道的な大量殺戮の反省を経て、「公正戦闘」という国際ルールが戦争に持ち込まれた近未来。戦い、紛争、戦争というものがこの世から無くならないのであれば、せめて”フェア”な形式を定めることは出来ないかという流れのもと生まれた制度である。このアイディアひとつを取っても社会批評性が強く、技術の可能性や、テクノロジーが社会制度とどのように結びつくのか、ビジネスや国際関係と科学のつながり、その変化。そういった、現時点で存在している最新の知見を投入し、未来の戦争が描かれているため近未来ミリタリー小説が好きな方なら刺さる要素多数。遺伝子編集や身体の改造等、「身体」と「脳」といった、人間が人間である根拠を軸に、スリリングな状況と、いかにしてそれらを乗り越えるかを提示しようとしていた。
上記したもの以外にも扱っている題材は非常に多く、教育格差やドラッグの問題、差別と分断についてなど、アメリカを中心とする「いま・ここ」に横たわる問題が次々と物語の中に登場する。それらが散らかってしまったり、消化不良になることはなく、綺麗に整頓された状態で話に組み込まれており見事。ただ、藤井さんの小説の特徴なのか、文体やキャラクターへの味付けが薄く、とっかかりがなさ過ぎるのは長所であり短所でもあると思う。今ある素材をもとに未来を想像する能力や、テクノロジーの描写力については抜きん出たものがあるため、小説的な「粘り気」のようなものをもっと感じれたら良かった気がする。豊富なトピックを扱っているのに妙に薄味に感じる不思議な小説。