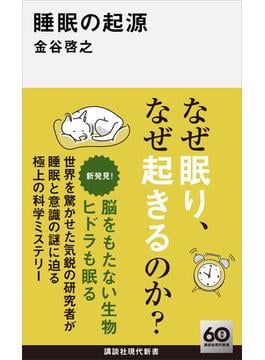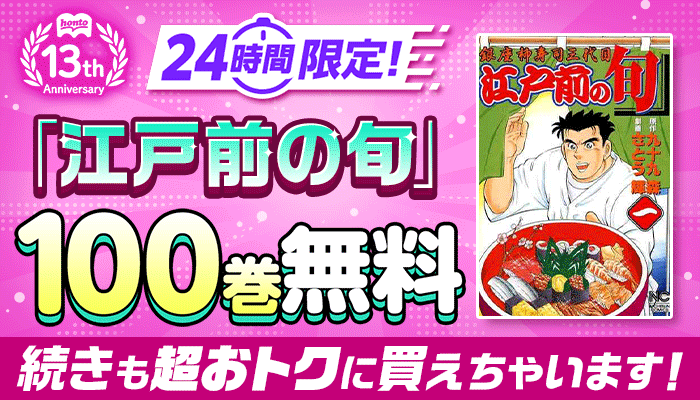投稿元:
レビューを見る
3日目朝に読了。読み始めたときの感想は福岡ハカセの「生物と無生物のあいだ」を読んだときと同じような感覚だった。心地よい。理系の文章だが、文学を楽しんでいるような感じ。科学の歴史を踏まえながら、著者自身のエピソードも盛り込んでいるからか。単に、最先端の研究の紹介ではなかった。ただそのためか、図版の量は少なかったように思う。そして、もう終わってしまうのか、というのが読後の感想。大学院でのマウスの研究についても知りたいところだ。まだまだこれからというところだろうか。今後が楽しみである。さて、意識があるかどうかは眠るかどうかで判断できるという話は養老先生の本でも読んでいた。なるほどと思った。昆虫も眠るということだから、昆虫にも意識がある。そう想像するのは楽しい。みつばちハッチは夢中で見ていた。しかし、ヒドラとなるとどうなのか。ヒドラに意識がある、それはちょっと想像しづらい。ゾウリムシもしかり。麻酔の話も確かにおもしろい。なぜ意識を失うのかは解明されていない。ということはなぜ意識が戻るのかも分からない。よくそんなものを皆使っているものだ。私はここ数年、夢をずっと記録している。それが自分の意識とどう関わっているのか、それを考えるのもまた楽しい。著者は1998年生まれのようだ。うちの息子と同い年か。我が家の長男は大学卒業後勤めた会社を2年もしないうちに辞めて、いまは無職で実家に戻っている。何やらいろいろ考えているようだが、著者のように夢中になれるものがあるというのはうらやましい。中高生に読ませたい1冊である。いや、息子に読ませたい。(同い年の著者だと伝えると、帰省中に読んでいた。)
投稿元:
レビューを見る
睡眠について、著者の経験談を踏まえてまとめた本。探求心大勢な方でありまだまだ若い。今後の活躍に期待します。
投稿元:
レビューを見る
若き大学院生による初の著書。
だが、侮ってはいけない。「睡眠の起源」と題するこの本の内容に衝撃を受ける。
人はなぜ眠るのか?という問は古くからある。著者はこの問に対し、脳を持たないヒドラでも眠るという事実を発見する。
睡眠とは脳の機能の生理的現象ではないのかと思っていたが、よくよく考えてみれば、腸、腸は第2の脳と言われるが、腸があれば、腸が脳の機能を果たすため、脳がなくても睡眠はあるといえるのだろう。
でもヒドラという生物。遺伝子はヒトより多い3万個あるという。因みにヒトは2万3千個らしい。これを聞いて、はてどう思う?
睡眠圧
睡眠のメカニズムは、起きている間に「睡眠圧」が徐々に高まり、眠気を感じ眠りに落ちる。そして眠っている間に「睡眠圧」が解消される。
「睡眠圧」の実態は、睡眠物質の存在が示唆される。
睡眠についての印象に残るフレーズ
生き物は進化の道筋のどこかで睡眠が生じたわけではないかもしれない。
生き物はもともと眠っていた。そして進化の道筋のどこかで、「起きている状態」を進化させたのではないだろうか。
生き物は一生のうちに環境の変化に合わせて体の形やサイズを変えるわけではない。世代を経ることで進化している。
つまり、生きている間は進化しない。世代を経ることで進化する。
真に興味深い考察だ。
200ページ足らずの新書であるが、著者の研究者を目ざすきっかけとなったことなど自伝的要素が適度なスパイスになっていて一気に読み進めることができた。
この本に続き更に面白い本を出してほしい。
投稿元:
レビューを見る
新生児のレム睡眠は50%
寝ている状態がdefaultで起きているのが異常?
麻酔覚醒には俺寄進が関与するが導入には関係ない
未だに全身麻酔の機序はわかっていない
投稿元:
レビューを見る
ちょっと気になって買ってみたけど面白い!
なんだかドキュメンタリーみたいで読み終えた後も余韻に浸ってしまった……
ゴリゴリ理系の話だけども事前知識がなくても読みやすく、かつ複雑な話もわかりやすく例えられていてイメージしやすい。
本筋とはズレるけど、子供の頃から研究者になりたくてアゲハチョウを研究していた等、凡人とはまったく違うエピソードしかない。これは金谷さんにしかきっと出来なかっただろうなと思う反面、サポートしてきた周囲の大人たちを見習いたい。子供がターゲットの本ではないと思うけど、何か一つを突き詰めることの楽しさ、研究の楽しさ、生物への興味を養えそうなので子供にも積極的に読んで欲しい本。
内容としては、睡眠は「睡眠圧」と「体内時計」によって調節されていて、寝ることよって睡眠圧は解消される。睡眠は脳と関係が深いと考えられていたが、脳を持たないヒドラも眠ることから、眠りに作用する遺伝子が複数あることを発見する…そもそも生物は進化の過程の「どこ」で眠り始めたのか?意識とはなんなのか?と続いていく。
本書の中で、寝ることによって睡眠圧が解消され、また時間が経つと睡眠圧が高まり眠くなると書かれていたが、私はどれだけ寝ても日中も眠い…これは睡眠圧の高まるスピードがイカレてるのか、体内時計が狂ってるのか、どっちなんだろう?抗いがたいというほどではないためナルコレプシーではないと個人的には思ってるが…。そんなことを考えながら昨日もぐっすり寝て今日も2回ほど昼寝したがまだ眠い。
投稿元:
レビューを見る
一つの事象を深く掘り下げて研究することが、どのようにして普遍的なテーマや大きな真理に結びつくのか、その過程を楽しめた。睡眠に関する知識を提供するにとどまらず、科学の探求そのものの魅力を伝えてくれました。問いから始まり、それを紐解いていく中で、生命の仕組みや進化の神秘に触れるような感覚を味わえた。知的好奇心を刺激し、思考の幅を広げてくれる。
投稿元:
レビューを見る
私たちはなぜ眠り、起きるのか?長い間、生物は「脳を休めるために眠る」と考えられてきた。それは本当なのだろうか。世界を驚かせた気鋭の研究者が睡眠と意識の謎に迫る
極上の科学ミステリー!
筆者の飽くなき情熱に感嘆しつつ、実験などで結果を出すことの難しさを実感した。睡眠という、誰にでも必要な行為であるが、分からないこともまだまだ多く、だからこそメカニズムや意味を知りたくなるのだろうと思う。医学的なことも分かりやすく書いてあって読みやすかったですが、新事実が最近判明したとかではないので、ちょっと物足りない一面もあったかな。これからの研究で解き明かされていくことを期待したい。
投稿元:
レビューを見る
生物は元々眠っていたが、進化のどこかで起きている状態を獲得したかもしれない。脳を持たない生物ヒドラも眠ることを明らかにした著者が自身の生い立ちと研究について紹介した本。
自分と同学年の研究者が書籍まで出す活躍をしていることに驚くと同時に、生物や眠りへの探究心の高さは目を見張るものがありました。あとがきにある、研究は葛藤とともにあり、最善策をとるための思考を繰り返しているという話はとても共感できました。著者が吸入麻酔薬の作用機序を明らかにし、睡眠と意識の謎を解明する日が来ることを願っています。
投稿元:
レビューを見る
愛犬ブラームスの名前の由来が「お家に来た当時金谷さんがピアノでブラームスを練習してたから」なのが良すぎる。/その他。同い年と知り横転。 /いっぱい寝よう。
投稿元:
レビューを見る
若い著者の研究者としての歩みと一途な姿勢は「バッタを倒しにアフリカへ」を思わせうらやましく感じた。脳のないヒドラの睡眠の研究から「起きている姿と眠っている姿のどちらが本来の姿か」という問いからは、今まで気づかなかった視点を得られた。
【目次】
はじめに――生物はなぜ眠るのか?
第一章 クロアゲハは夜どこにいるのか
第二章 眠りのホメオスタシス
第三章 眠りと時間
第四章 ヒドラという怪物
第五章 眠りのしくみ
第六章 眠りの起源は何か
第七章 眠りと意識
投稿元:
レビューを見る
著者の小学生時代のクロアゲハとの出会い、高校生でのプラナリアの研究、大学でのヒドラの睡眠に関する研究、大学院での麻酔と意識の研究といった活動がいきいきと語られていて面白かったです。
睡眠の起源について知りたくて読んでみたのですが、まだまだ解明すべきことがたくさんありそうで答は今回は見つからず、といった感じでしたので、星4つとしました。
理系を目指す中高生や理科系大学生にも読んでもらいたい一冊です。
【目次】
はじめに――生物はなぜ眠るのか?
第一章 クロアゲハは夜どこにいるのか
第二章 眠りのホメオスタシス
第三章 眠りと時間
第四章 ヒドラという怪物
第五章 眠りのしくみ
第六章 眠りの起源は何か
第七章 眠りと意識
投稿元:
レビューを見る
睡眠とは何か、なぜ必要か?
生物としての根源的な問い。夢、意識などとの関係から脳内のシナプスの再形成というのが定説。
だが、筆者は脳を持たないヒドラも眠ることを発見、あらためて生き物になぜ睡眠が必要であったのかを考察する。
ミステリー的な内容で専門知識がなくともグイグイ惹き込まれる内容。
結論は出ないが、生物学の魅力を十二分に伝えてくれる良作。
投稿元:
レビューを見る
幼少期から探究心が強く、小学生はアゲハチョウ、高校ではプラナリア、そしてヒドラに出会い生き物を研究しながら睡眠とは?意識とは?に迫る。
未だ解明されていないことを取り組みたい実験やどう研究していくか?など赤裸々に語ってくれているのも新鮮でとても読みがいがある。
分からないこともあるが、それ以上に作者の興味の続いていく様を読ませてもらえるのが面白い。
まだ27歳の作者、金谷啓之ひろゆき氏の今後に期待!
夢は生の状態から離れ、死に近づく状態、と言われていた、19c〜20c に精神分析学を唱えたフロイトは、心は、1. 意識 2. 前意識 3. 無意識 の3要素からなると。
1. 簡単に自覚することができる心
2. 普段は無自覚、思い出そうとしたり、注意を向けることで自覚する❤️
3. 心の奥底に隠れて抑圧された感情や願望
レム睡眠、rapid eye movement 急速眼球運動
夢を見ることが多く、より起きている時に違い脳波、筋肉は弛緩して体は動かない、睡眠全体の20%程で、後半に多い。
それ以外をノンレム睡眠という p. 35
睡眠不足時に眠らせようと抗う力を睡眠化学では「睡眠圧」という、この圧によって、ホメオスタシス(声明がある一定の状態を保とうとする性質)の性質を持つ。なぜ寝だめがダメなのかは、睡眠圧は起きている間に積み上がり、寝ることで解消。蓄積はできないから。 p. 54
オジギソウがもつ、時間をカウントするしくみ、体内時計によって葉を開閉させていたのだ。人、シアノバクテリア、遺伝子によると発見される p. 64.
細胞の遺伝情報DNAは基本的に同じ、ただ細胞ごとに
どの設計図がどのくらいコピーを取られ、どのくらい製造されるのかがことなっている。この差異によって同じ設計図を持っていても異なる働きを持つ細胞に分化する。 p. 66
⭐︎⭐︎⭐︎時計遺伝子の情報に基づいて時計タンパク質が作られる。時計タンパク質が溜まってくると、コピー担当の作業を邪魔する、設計図のコピーは永久ではなく、分解されていくため、新たな製造がストップする。
製造はストップ、分解は進むことで時計タンパク質の量は減っていく。すると邪魔が減り、コピー担当の作業が再開、時計タンパク質の製造が始まる。この1サイクルが24時間。
光によって調整され、時刻合わせ、が行われるので時差ボケが解消される。 p. 67
睡眠の二過程モデルは睡眠圧と体内時計。
睡眠圧が、眠らせようとする力
体内時計の成分は、起こそうとする力 p. 71
脳内には、1000億個以上の神経細胞があり、互いに接続して回路を形成。手の繋ぎ目を、シナプスと呼ぶ p. 139
生まれてきたとき、私たちはもともと眠っていたのか、それとも成長した後にいつしか眠るようになったのか。 p. 149
麻酔状態からの回復プロセスにオレキシンが関与している。脳内のオレキシンが欠損すると、ナルコレプシーと呼ばれる睡眠発作が起きる。オレキシンを作る神経細胞を破壊しても、麻酔は通常通り作用、導入には関与せず、麻酔からの回復が遅れる、ことが分かった。p. 173
⭐︎⭐︎⭐︎睡眠とは何かーそれは、起きている間に蓄積したものを解消する行為、なのだろう
蓄積していくもの、その実体は、未だ完全に解明されていない。だがその借金が蓄積すれば、脳や体の活動が損なわれるばかりだ。 p.177
投稿元:
レビューを見る
2025-04-01
大変に、新書。(おそらく)気鋭の若き研究者が、自分の研究に至るまでやその後をフワッと語った一般書。もう少しとがったものが読みたかったけど、まあ、それなりに。
投稿元:
レビューを見る
研究に対する情熱を感じられる、良い本だと思います。睡眠に限らず、研究分野に興味がある学生さんや、比較的時間があって、非常に興味を持つ分野がある人は、すごく共感できるのではないでしょうか。
自分も、昔から、睡眠時間をコントロールできたらすごく充実した人生を送ることができるのではないか、と思っており、睡眠というものに一定の興味を持っていたので、そういう意味で何か参考になるのではないかと思ったのが読むきっかけです。結論からすると、そういったノウハウ的な観点で実践できるような記載があるわけではないので、自分の期待からは外れていました。
その点に関しては、「世界を驚かせた気鋭の研究者が睡眠と意識の謎に迫る極上の科学ミステリー!」というポップ(?)が、一般的には、「ミステリー」=謎が解き明かされる、という期待を抱かせてしまうのではないかと思い、それを販促上狙っているとしたらミスリードなのではないかな、と思う次第です。だとしても、作者には何の罪もないので、これからもこういった研究を続けていただいて、少しでも生物の根源に関わる謎を解き明かしていただけることを願います。