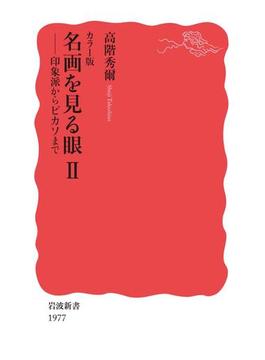0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:らら - この投稿者のレビュー一覧を見る
印象派以降について書かれています。今回新たに挿絵がカラーとなり、高階先生の素晴らしい解説とあわせてとても読みやすくなりました。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
絵画の鑑賞方法が、わかりやすく解説されていて、よかったです。抽象絵画との付き合い方など、興味深く読むことができました。
投稿元:
レビューを見る
しかし、だからと言って、印象派 絵画がチューブ入り絵具から生まれたと言うことはむろんできない。 戸外における現場での制作は、すでに一八三〇年代のバルビゾンの画家たちの時代から、絵画の野望のひとつであった。持ち運びのできる便利な絵具の発明は、それまできわめて困難であったことを容易に実現させてくれるという便利さをもたらしたに過ぎない。ただ、それによって思いのままに戸外で制作できるようになった七〇年代の若い画家たちが、眼の前の自然のな かに、それまでの絵画の知らなかった新しい世界を発見したことは事実である
ところが、モネたちは、太陽の光の下では、自然のなかのものは固有の色を持っていないということを見出した。緑の草も、時には夕陽の照り返しを受けて赤く輝くこともあれば、青い衣裳の上にオレンジ色の陽の光がこぼれ落ちることもある。それは言うまでもなく「光」の作 ちゅうちょ 用であるが、モネたちは、その「光」の作用を、躊躇なく「色」の世界に置き換えた。 例えば、この「パラソルをさす女」は、白いドレスを身にまとっている。そのドレスに、青い空や赤い野の花の輝きが微妙に反映している。そこでモネは、白い衣裳の上に、薄い青やピンクのタッチを加えるのである。
このようなことは、白い衣裳はあくまでも白いものだと信じていた当時の人びとには、容易 に理解されるものではなかった。
彼(セザンヌ)が求めたものは、眼の前の対象を形づくる本質的な構造であった。すべてが一様な光の波に還元されてしまう印象派の世界のなかから、セザンヌは、 対象を周囲の世界から区別する基本的な形態を求めた。そして、そのような確固とした形態を求めるということは、もはや単に視神経だけの問題ではない。それは後にブラックが、「眼は 形態を歪め、精神は形態を作る」という簡潔な言葉で表現したように、自然のなかにひとつの 秩序をうち立てようという精神の働きである。 セザンヌが友人のモネについて、
彼はひとつの眼に過ぎない、だが何と素晴らしい眼だろう。
と語ったという話は有名であるが、この一句にはモネの精緻な感覚に対する賛嘆と同時に、ひそかな批判をも読み取ることができる。
投稿元:
レビューを見る
後半は印象派以降、抽象画まで。
モネ『パラソルをさす女』
ルノワール『ピアノの前の少女たち』など
こちらも好みの絵の解説をじっくりと。
明るく優しい絵が多いこのふたりですが
いろいろ苦悩があってのことと
背景を知るとまた愛しく感じます。
抽象画はやっぱりよくわからないから
もう自分が好きか苦手かで。
そういう意味ではモンドリアンは好き。
シンプルで整然としたところが落ち着く。
他の画家も、ロートレックやゴッホの項など
手元に置いておいて時々勉強しなおしたい。
投稿元:
レビューを見る
古い版から文章はほとんど変更していないそうだが、ごもっともです。
修正する隙のない名文です。
日本人の大好きな印象派を抑えるうえで必読の文献。
投稿元:
レビューを見る
名画を見る眼Iの続編、名画を見る眼II。
前作のIが、マネまでであったので、IIのモネからが楽しみで読みました。
モネを数多く所蔵している西洋美術館にいらした高階さん。この人ならではの表現があり、次にモネを見るときにはその視点で見ようと思えるヒントがあったら。
パラソルの女性も作品がいくつか存在すると知れた。
出会っていなかった画家も掲載されており、新しいトキメキがありました。
投稿元:
レビューを見る
モネの「パラソルをさす女」からモンドリアンの「ブロードウェイ・ブギウギ」まで年代順に14の絵の解説です。
この他、関連する絵も一つの作品につき、2,3点全てカラーで印刷されています。
これを新書(の値段)で見ることができるのはお得感たっぷりでした。
私は、やっぱりモネの絵がいちばん好きでした。
投稿元:
レビューを見る
第Ⅱ作はモネの「パラソルをさす女」からモンドリアンの「ブロードウェイ・ブギウギ」まで。驚いちゃうのはこの間が60年しかないこと。この短期間で印象派から抽象絵画まで遷移している。抽象絵画といえども突然変異で生まれてきたわけでは無いことがよく分かる。
投稿元:
レビューを見る
モネ、ルノワールをはじめとする印象派からピカソ、シャガール、モンドリアンに至るまで、美術史の中で、大きな変革の時代を生きたアーティスト達の作品を読み解くポイントを紹介してくれる良書。
投稿元:
レビューを見る
端的に深奥までひとつの絵画で語り尽くしてくれる。印象派をまず知りたいならまずはこの一冊。ようやく美術というものを知れてきた気がします。
投稿元:
レビューを見る
外界を見る人間の眼は、習慣や約束に規制されているが、画家はこれにとらわれない新しい感覚を拓く。
まず絵画を見て読み進め、改めて観ると新しい感想を覚える新鮮な鑑賞体験。実物を見たい。
絵のリアルとは。これまでの系譜。
現実を追求した印象派が色彩分離により平面化していき、キュビズム、フォーヴィズムを経て抽象画に繋がる。色彩と造形。
投稿元:
レビューを見る
第I巻の15作品は、1434年のヤン・ファン・アイクの作品から1863年のエドゥアール・マネまでの約400年を駆け抜けてきたのに対し、第II巻の14作品は、印象派のモネから始まって造形主義や抽象画に大きく移り変わっていく、わずか100年足らずの絵画の変遷を追っています。
現代人の多くにとって魅力的で絵画として「完成」しているように感じる印象主義が、絵画としてどのような限界を抱えているのか、そして画家たちがそこからどう脱却して(あるいはそれを極めて)いったのかが分かりやすく解説されています。以前、国立西洋美術館で開催されていた「キュビズム展」と扱われている時代が同じで、おさらいする気分で読むことができました。
まるで小説を読んでいるような、筆者の豊かな表現力はこの第II巻でも健在です。
―モネの「パラソルをさす女」は、印象派の技法による人物表現のいわばぎりぎりの限界であった。色彩分割をさらにおし進めていけば、モネの人物は光の波に溺れて溶解してしまうであろう。
投稿元:
レビューを見る
印象派のモネ、ルノアールを皮切りに、難解とされる抽象絵画を分かりやすい言葉で解説している好著だ.ムンクくらいまでは記憶のある絵が出てきたが、マティス、カンディンスキー、モンドリアンになると初見のものばかりだった.絵画を全般的に把握してる著者ならではの言葉遣いで、丹念に、しかも的確な説明は非常に感銘を受けた.抽象画を手掛けた画家たちの内面に触れるコメントも多数で、絵画史の荒波を突き進んでいく快感が味わえた.
投稿元:
レビューを見る
Ⅰに比べて、著者の美術史観が確固としている。
特に印象派の影響を受けた画家たちの足跡の描き方が冴えている。
個別の画家では、スーラとモンドリアンの項がすごい。
自己の理念を越えて、アートを成し遂げた様を描ききっている。
投稿元:
レビューを見る
高階秀爾さんの訃報を知り手に取った。もともと半世紀前に出版された本のカラー版であり、とてもわかりやすい。Ⅰに次いで一気に読めた。
ここは再掲だが、各章は一枚の絵から始まる。読み終わっていると画家の一生や複数の絵も理解でき、時代背景、西洋美術史の潮流とこの絵・画家の位置付けがすっきりと頭の中に収まる。私は技術にはまったく明るくないが、画家の技術的な有能さ、社会やパトロンとどう向き合ってきたかの問題意識もわかる。
冒頭はモネ「パラソルをさす女」から始まる。印象派には多少なじみがあるのですんなり入る。ファン・ゴッホ「アルルの寝室」あたりから、見た目より意識が優先されメッセージ色が強まってくる。ムンクの「叫び」はその時代だからこそ生まれたということもわかる。最後のカンディンスキー、モンドリアンは訳が分からなさを超越した時代性もなるほどと納得。カンディンスキーはミュンヘンで実物を見ていたので、より親しみを持って読める。
改めて、歴史は大好きだが、美術はよくわからなかったという私のような身にとっては傍らに置きたい本だ。